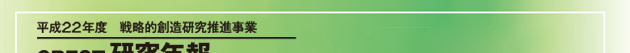 |
人間と調和する情報環境を実現する基盤技術の創出
1.戦略目標名
人間と調和する情報環境を実現する基盤技術の創出
2.本戦略目標の具体的な内容
情報通信技術が生活の隅々で利用され、あらゆる人や物が結びつき、いつでも、どこでも、だれでも恩恵を受けることができるユビキタスネットワーク環境の実現に向けた研究開発が進められている。しかし、その活用にあたっては依然として人間側から情報通信機器を使用する行動を起こし、意識し努力することで目的の情報を得るなどのユーザの労力が必要である。今後の少子高齢化社会に向けては、どんな習熟度の者でも情報通信技術の恩恵を自然に受けることができる、より人間と調和した情報通信技術の利用環境の実現が求められる。 このためには、情報通信技術が生活空間に溶け込み、情報環境と人間が相互作用を起こして、人間が必要なときに、人間にとってより適切な状態へ自然に移行する、人間と調和した情報環境知能の創出が必要となる。これにより、ポスト・ユビキタスネットワーク社会として、真に誰もが情報通信技術の恩恵を受けることができる社会が実現し、生活の安全・安心、健康さ、快適さや社会の知的生産性は飛躍的に向上すると考えられる。 本戦略目標は、情報環境が人間と適応的、親和的かつ能動的に相互作用し、個人に必要かつ最適な作用・効果を提供する環境の実現を目指すものである。 本戦略目標において、将来的な技術の利活用形態※を想定した上で、「人間行動・実空間状況の認識および取得」、「コンテンツ処理およびサービスとしての具現化」、「これらを親和的に行うためのヒューマンインタフェース」という一連の要素技術の有機的な横断・統合を目指した研究開発を実施する。 研究開発課題例として、人間の行動の背景にある認知プロセスの解明、人間の行動・意図と実空間状況を認識・解析する情報処理、人間に調和した情報サービスを能動的に提供する情報環境等が挙げられる。 ※住居、医療・福祉、自然環境、オフィス・店舗、街角、セキュリティ等における具体的な技術の利活用形態を想定して研究開発を実施。
3.政策上の位置付け(科学技術基本計画、戦略重点科学技術等との関係)
- (1)本戦略目標で実施する研究開発は、第3期科学技術基本計画・分野別推進戦略(情報通信分野)における以下のような重要な研究課題に該当する。 ユビキタス領域では、ユビキタス環境のデバイス等を活用して、社会における安全や快適性につなげる生活支援基盤の研究開発が重要とされている。具体的には、社会的弱者を含めた人間の行動支援技術が必要とされている。 ヒューマンインタフェース及びコンテンツ領域では、情報発信力・ものづくり力により生み出された知を、検索・解析、共有、蓄積、編集、構造化し、情報発信・ものづくりに結晶させていく協調活動サイクルの加速化を図るヒューマンインタフェース技術とコンテンツ技術への戦略的投資が重要とされている。具体的には、機械と人間の対話コミュニケーション支援技術等が必要とされている。また、情報分析技術、コンテキスト高次化技術等も必要とされている。 ロボット領域では、スムーズで直感的なコミュニケーションのためのロボット等の研究開発、ロボットの行動をより人間にとって親和的で、信頼性の高いものにするための人間とロボットの間を結ぶインタラクション技術、人間の状況や活動履歴を蓄積し、それを踏まえて人間と自然に対話できるようにする技術が重要とされている。さらに、人間の行動観測や意図解釈等により、ロボットの行動をより人間に親和的にするための技術が必要とされている。 また、ライフサイエンス分野の「生命プログラム再現科学技術」にもあるように、生命機能単位をITを駆使してシステムとして再現する技術は人間と情報の接点を親和的にする鍵となりうる。 加えて、科学技術基本計画の理念として、「健康と安全を守る ~安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて~」を掲げるとともに、社会的課題を早急に解決するためには、「専門化・細分化されてきている知を、人文・社会科学も含めて横断的に統合しつつ、進めることが重要」であることが指摘されており、安全・安心・快適な生活環境を実現させるためには、実フィールドを想定し、さまざまな科学技術をすり合わせ・統合する技術開発が必要である。
- (2)長期戦略指針「イノベーション25」5章「イノベーション立国」に向けた政策ロードマップの早急に取り組むべき課題の中で「生活者の視点に立脚したサービス分野の生産性向上に向けた取組の強化」が挙げられている。「生活者のニーズを取り入れ、場所やモノに関する情報をいつでもどこでも誰でも入手可能とする基盤を構築」を活用促進するためには、本戦略目標で実施される研究開発が重要である。
- (3)本戦略目標は「経済財政改革の基本方針2008(骨太の方針2008)」の革新的戦略技術の項で提唱されている「ITをいかしたユビキタス技術やロボット技術を一層活用して、高齢者や障害者が暮らしやすい社会づくりを進める」ことに資する基礎研究を推進するものである。具体的には、本戦略目標の成果となる技術群は革新的技術である「生活支援ロボット技術」に応用することができる。 また、安全安心の観点からは「国民の安全・安心を確保する技術を更に発展させ、成長の制約要因を除去し、我が国産業の国際競争力強化を図るとともに、これら技術を核に世界に貢献する。」ことが掲げられている。
4.当該研究分野における研究振興方策の中での本研究事業の位置づけ、他の関連施策との切り分け、政策効果の違い
ヒューマンインタフェースの分野では、総務省の「ネットワーク・ヒューマン・インターフェースの総合的な研究開発」において、平成16年度から5ヶ年計画で、ネットワークロボット技術等の研究開発を実施している。当該研究は行動・状況認識やロボットコミュニケーション技術に関する要素技術の研究開発である点で本目標とは重複しない。 ロボット分野では、科学技術連携施策群「次世代ロボット-共通プラットフォーム技術の確立-」及び経済産業省「次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト」が実施されている。前者は、ロボットが空間や環境を構造化するための研究開発であり、後者はロボットが確実性を持って自律的に活動するため機能の高度化に必要な知能化技術の研究開発であるため、情報空間と人間の接点についての研究開発を対象とする本戦略目標とは関連が薄い。 情報検索技術及びコンテンツ処理技術の分野では、以下の4つが関連する施策として挙げられる。
- (1)科学技術連携施策群「情報の巨大集積化と利活用基盤技術開発」では、大量の情報の中から信憑性が判断できる有益な情報を高速に見つけ出すことを可能にし、様々な情報サービスの基盤となる情報集積活用基盤技術を構築するものである。
- (2)文部科学省科学研究費補助金の特定領域研究「情報爆発時代に向けた新しいIT基盤技術の研究」があるが、当該研究は、情報検索や自然言語処理等、主としてウェブ上の情報の急激な増加に伴う収集や分析に焦点が当てられており、個々の要素技術の基礎研究である。ウェブ上であることと、一研究者の自由な発想に基づいている点で技術フェーズも異なる。 また、経済産業省の「情報大航海プロジェクト」では、新しいマーケットを開拓することを主眼におき、様々なサービスにおける情報の活用技術の開発が行われている点で、より人間に親和的な情報環境を実現する戦略的な基礎研究を行う本戦略目標とは異なる。
- (3)科学技術振興機構(JST)が平成20年度戦略目標「多様で大規模な情報から『知識』を生産・活用するための基盤技術の創出」の下、戦略的創造研究推進事業(さきがけ)で平成20年度より実施している「知の創生と情報社会」は、大規模データを基に知識を獲得・処理するための技術を実現し、それを社会の効率化、問題点の解決、あるいは人間の知的作業の質や量の向上に活用できるようにすることを目指している一方、本戦略目標は人間と情報空間(情報通信機器)の応答を親和的・適応的にするための技術群についての研究開発を行うものであり、目的は異なるが、状況の分析に基づく提示情報の決定の面で成果を活用するなど相補的関係の下、協調して実施することが可能である。
- (4)平成17年度戦略目標「安全・安心な社会を実現するための先進的統合センシング技術の創出」 の下、JSTが戦略的創造研究推進事業(CREST)にて、「先進的統合センシング」を実施しており、ここでは、主に危険物・有害物質やビル・橋など建造物等、人間等の物理的な異常等を高感度・高精度に検知し、その情報を迅速に伝達することが可能な先進的統合センシング技術の創出を目的としている。一方、本戦略目標は主として、人間の意図や状況のセンシングを対象としている点で異なる。
なお、生命現象の内部をブラックボックスとしてその入出力を模倣するバイオミメティック(生体模倣)を指向する研究(遺伝的アルゴリズム、ニューラルネットワークなど)はこれまで実施されてきていたが、現実の生命システムの内部の計測・操作を主体とした研究は実施されていない。本戦略目標は、適応的な相互作用を実現するために、これらの研究も対象となりうる。
5.この目標の下、将来実現しうる成果等のイメージ、他の戦略重点科学技術等に比して優先して実施しなければならない理由、緊急性、専門家や産業界のニーズ
本目標の達成により、現状ではユーザが情報機器を使いこなしながら周辺機器を制御し、自分自身の嗜好に応じた環境に調整している状態を脱し、人間の望みに機器が自律的に応答し、より快適な状態へと自然に移行する情報環境基盤の創出が期待される。 また、人間の知的生産活動が、情報環境によって支援され、より創造的な活動の実現が期待される。 人間から働きかけなくとも(キーボードやマウスを使わずに)、ネットワークで繋がったセンサやGPS、ICタグなどが、ユーザや環境から情報を取得し、携帯端末機器や街の至る所に設置された情報通信機器が、子供からお年寄りまでユーザの意図と行動を陽に陰にサポートすることによって、実社会において安全・安心、健康で快適な生活環境の実現に貢献することができる。 例えば、次のような協調的情報提供サービスが創出される。
- 人間の意図と行動を陽に陰にサポートさせることによる生活の質の向上
- 異常状況(不審者を含む)の自動認識等による社会のセキュリティ確保
- 高齢者等の自律支援(移動、作業能力、感覚機能の強化)
- 在宅医療・健康管理サービス
- 子供や高齢者の安全見守りサービス
- 個人の学習プロセスに合わせて情報が提供される学習支援サービス
6.本研究事業実施期間中に達成を目指す研究対象の科学的裏付け
人間行動などのセンシングにおけるセンサ技術はニーズが牽引する形で研究開発が行われており、医療・福祉・介護用用途のセンサも研究開発が活発化している。また、注目すべき研究開発の動向として、センサなどによる実世界の監視データを扱うデータストリーム処理技術が挙げられ、センシング情報を取り扱う技術についても今後の発展が予想されている。<「科学技術・研究開発の国際比較 2008年版 (電子情報通信分野)」(平成20年2月JST研究開発戦略センター)【センサ技術】> この分野の要素技術としては、人物分離、全身動作解析等の画像認識技術、生体データ等の情報を計測するセンサ技術等について技術の発展が期待されている。 近年の科学技術が目指すのは、人間とより多様に、より柔軟にストレス無く関わる機械であり、コミュニケーション技術やインタフェース技術は、そのような技術の根幹をなすものである。従来の単なる言語情報等、表層的な人間理解を超えるものとして、意図や感情推定等を含めた人間理解や視覚・聴覚・触覚等のセンサ機能に加えロボット等の身体性も利用したマルチモーダルコミュニケーションについての研究が進められているが、この分野ではHuman Robot Interaction 等の国際会議においてトップクラスの研究成果を発表しているように我が国の研究水準は高い。ヒューマンインタフェースの向上に関しては、我が国でも米国に次ぐ成果が上がっている。視覚メディアとして撮影した画像を元に対象を色々な方向から見ることを可能にする自由視点映像技術は今後のデジタルメディアのインタラクティブ化を加速すると期待され、東京大学、京都大学、名古屋大学などが活発な研究開発を進めている。音声認識では、音声対話コンソーシアム(ISTC)をはじめとした国内研究機関の連携が進んでいる。<「科学技術・研究開発の国際比較 2008年版 (電子情報通信分野)」(平成20年2月JST研究開発戦略センター)【ヒューマンインタラクション】、【コミュニケーション】> この分野の要素技術としては、非定常雑音、複数話者の音声認識技術、センシング情報等からのユーザ情報・意図把握やユーザの意図に適応する技術等の発展が期待されている。 さらに、我が国は、本戦略目標の下で研究開発される技術と併せて用いることが想定される最適情報を映し出すディスプレイ技術、及び情報空間上の情報を実世界へ反映させる上で重要なロボット技術について、世界をリードしており、これらを次世代の情報環境の実現に活かすことが可能となることで副次的に、国際的に大きな優位性をもたらすと考えられる。 本戦略目標を達成するためには、現在それぞれの分野で個別に取り組まれているそれぞれの要素技術を一体的な連携体制のもとで研究開発することが効率的であるとともに、さらには複数の実問題への取組事例の中から得られた知見を蓄積し汎用化した上で基盤技術の創出を導くことが望まれるため、ノウハウ提供が難しい企業等での実施は困難な課題であり、国が主体となって推進することが重要である。
7.この目標の下での研究実施にあたり、特に研究開発目標を達成するための留意点
研究開発の推進にあたっては、各研究課題が個別に要素技術を開発するのではなく、研究総括の下、課題間においても系統的に統合・検証できるような研究手法・体制が望まれる。例えば、各研究課題間で研究用に収集した多種多様なセンシングデータ等の統合・共有を図る仕組みや、人間と調和する情報環境を構築するためのプラットフォーム技術等の共通基盤構築も視野に入れて取り組む。 また、平成17年度戦略目標「安全・安心な社会を実現するための先進的統合センシング技術の創出」、及び平成20年度戦略目標「多様で大規模な情報から『知識』を生産・活用するための基盤技術の創出」の下で実施される研究領域との連携が望まれる。
| 研究領域 | 研究総括 | ||||
| 共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築 | 東倉 洋一 (国立情報学研究所 教授・副所長) |
||||
|
|||||