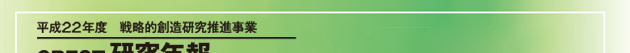 |
ナノデバイスやナノ材料の高効率製造及びナノスケール科学による製造技術の革新に関する基盤の構築
1.名称
ナノデバイスやナノ材料の高効率製造及びナノスケール科学による製造技術の革新に関する基盤の構築
2.具体的な達成目標
本戦略目標は、将来のナノテクノロジーの本格的な実用化時期に必須となる「ナノ製造技術」の基盤を次の一連の研究により提供することを目的とする。
- (1)ナノデバイスやナノ材料を高効率に製造する技術群、例えば、ナノ構造の設計技術・創製技術・転写技術、ナノ材料の高再現性・大規模生産技術、ナノ自己組織化を適用した製造技術、ナノ構造の評価・検査技術などを支える基礎基盤の構築、および、これらのナノ製造を実現する装置の創製。
- (2)構築したナノ製造技術の基盤の応用による具体的実施例の提示。
- (3)ナノ製造に関る現象のナノスケール科学による解明。
- (4)様々なデバイス、システム、材料などの製造技術基盤のナノスケール科学による革新。例えば、広義の工具と被加工物との相互作用をナノスケールで理解し、制御することによる再現性や均一性の向上、ナノスケール科学に基づく製造工程の高度化・環境負荷の低減など。 上記達成目標の具体例を以下に示す。 ・ トップダウン加工と自己組織化との組合せによるデバイスの創製 ・ 超高解像度印刷技術の基盤確立と応用 ・ ナノエッチング技術の基盤確立と応用 ・ ナノインプリント技術の様々な材料への適用と応用 ・ 革新的な光リソグラフィ技術やレーザ加工技術の開発 ・ 超並列ビーム/プローブを用いた加工・検査技術の開発 ・ ナノ表面改質による革新的接合技術の基盤確立 ・ ナノ構造を実現する有機合成技術の基盤確立 ・ 新しいMEMS・NEMSプロセスの創製と応用 ・ ナノコーティング技術の基盤確立 ・ ナノメータの精度を実現する超精密機械加工技術の基盤確立 ・ 次世代ナノ加工・検査装置の開発 ・ ナノ材料プロセスの高速化や再現性向上 ・ ナノ材料の大規模生産法の基盤確立 ・ ナノ構造の欠陥修復技術の基盤確立 ・ バイオ材料の精密配置技術の確立とバイオチップへの応用 ・ ナノ流体チップを用いたナノ材料やバイオ材料の創成 ・ 様々なナノ加工技術の統合による新しいデバイスの創成 ・ 自己組織化のメカニズムの解明と制御 ・ ナノスケール科学による製造の効率化・低環境負荷化 ・ 広義の工具と被加工物との相互作用のナノテクノロジーによる解明
3.目標設定の背景及び社会経済上の要請
本戦略目標の設定の背景には、ナノテクノロジーの急速かつ着実な進展、およびその成果の産業応用・社会還元への強い期待が存在する。このため、現行のナノテクノロジー関連の戦略目標に基づく諸研究(ナノテクノロジー・バーチャル・ラボラトリーなど)の成果をイノベーションに繋げるために、ナノテクノロジー重点化開始から5年を経た現在、提示すべき戦略目標である。 ナノテクノロジーの重点化により、様々なナノ材料やナノデバイス、ナノ加工技術、ナノプロセス技術が開発されている。しかしながら、これらは実験室の試行段階であり、高速・大規模に再現性よく実現することとは、技術的に大きな隔たりがあるため、将来、ナノテクノロジーの本格的実用化を迎える際に、最も深刻な問題の一つになると考えられる。本戦略目標は、第一に、その隔たりを埋めうる新しい技術群を支える基礎基盤を、ナノスケールの現象理解に基づいて創出することである。 一方、ナノテクノロジーに基づく製品として、顔料やカーボンナノチューブ混練樹脂のように、それ自体がナノスケールの材料であるものと、材料や製造工程といった付加価値を生み出す鍵となる要素にナノテクノロジーが用いられるものがある。本戦略目標は、第二に、ナノスケール科学の適用による製造技術基盤の革新で、これらのナノテクノロジー製品を生み出す基盤を構築することである。 諸外国において、ナノ製造技術は、ナノテクノロジーの根幹をなす技術として重点的に研究され始めている。「ナノ製造技術」は、米国では2005年の最重点投資課題であり、欧州ではフレーム・ワークプログラム7の重点課題として取り上げられている。したがって、本戦略目標の提示は国際競争力維持の観点からも緊急性を有することは明らかである。国内のナノテクノロジー研究者は、これまでの重点化施策によって、ナノ加工、ナノ計測、ナノプロセス、ナノ材料などに関して十分なシーズを蓄積しており、これらのシーズを「ナノ製造技術」として高度化/統合する準備は整っている。また、本戦略目標の提示によって、総合技術である「ナノ製造技術」を構築するに必要な分野融合と知識統合とが必然的に生まれると考えられ、それを土壌に、新しいナノテクノロジーの着想や展開が生まれることも期待する。
4.目標設定の科学的裏付け
本戦略目標設定の第一の科学的裏づけは、これまでのナノテクノロジー研究によって、ナノ製造技術の基盤構築に関する解決すべき課題が明確化されてきていることである。現在、ナノ加工技術・ナノプロセス技術として、極限フォトリソグラフィー、ナノインプリント(ナノ転写加工)、ナノインク描画、走査プローブ加工・計測、ナノレーザ加工・計測、自己組織化、バイオプロセス、マイクロリアクタなどが研究されている。また、超高密度LSI、ナノバイオチップ、MEMS/NEMSなどのナノデバイス・システム、および様々なナノ材料が研究されている。その結果、数多くの有望な着想やシーズが生み出されたが、その実用化や発展における解決すべき重要課題の1つが、これらの高効率・大量製造法の基盤を構築することであることが明らかになってきた。 本戦略目標設定の第二の科学的裏づけは、ナノ計測技術の発展によって、様々な現象のナノスケールでの科学的理解が可能になっていることである。例えば、高機能走査プローブ顕微技術、極微量物質同定技術、超高感度表面吸着物質測定技術、極微小力測定技術、ナノ位置決め/測定技術などが発展してきた。これらのナノ計測技術によって、様々な製造過程で現れる現象をナノスケールで科学的理解できるようになってきており、例えば、ナノインプリント時のモールドと樹脂との相互作用、自己組織化のメカニズムなどが解明されようとしている。 このように、科学技術的側面から、本戦略目標を設定する時期が来ていると判断できる。
| 研究領域 | 研究総括 | ||||
| ナノ科学を基盤とした革新的製造技術の創成 | 堀池 靖浩 ((独)物質・材料研究機構 名誉フェロー) |
||||
|
|||||