- JST トップ
- /
- 戦略的創造研究推進事業
- /
 CREST
CREST- /
- 研究領域の紹介/
- 生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出/
- [マルチセンシング] 2022年度採択課題
[マルチセンシング] 2022年度採択課題
大木 研一
多感覚の統一的知覚を担う座標変換回路の解明
グラント番号:JPMJCR22P1
研究代表者
大木 研一

東京大学
大学院医学系研究科
教授
主たる共同研究者
| 磯村 拓哉 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター ユニットリーダー |
研究概要
我々は多数の感覚を統合し、統一された世界像を知覚する。例えば目前の物体を掴むとき、手に触れる物体と見ている物体の同一性を当然のように知覚する。本研究ではこのような多感覚間の統一的知覚を生み出すメカニズムを、頭頂葉と側頭葉における多感覚領野での座標変換回路の解明と、その自由エネルギー原理に基づく予測・検証を通じて、実験と理論の両面から解明する。
大野 和則
社会的シグナルを介したイヌのスーパーセンシングの解明
グラント番号:JPMJCR22P2
研究代表者
大野 和則

東北大学
タフ・サイバーフィジカルAI研究センター
教授
主たる共同研究者
| 久保 孝富 | 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 准教授 |
| 永澤 美保 | 麻布大学 獣医学部 教授 |
| 藤原 幸一 | 名古屋大学 大学院工学研究科 特任教授 |
| 山川 俊貴 | クアドリティクス(株) 研究開発部 研究員 |
| 藤原 幸一 | 北海道大学 電子科学研究所 教授 |
研究概要
ヒトが無意識のうちに発する社会的シグナルを介して、ヒトの内的情動を推定するスーパーセンシングの研究開発が必要とされている。本申請は、イヌの持つ、ヒトが無意識に発する社会的シグナルを介して内的情動に気付くスーパーセンシングのメカニズムの計測と解明に挑む。患者や飼い主の内的情動の変化に気付きやすい、ファシリティードッグや一般家庭犬を利用してメカニズムの解明に取り組む。
高橋 英彦
幻覚スペクトラムの操作と可視化
グラント番号:JPMJCR22P3
研究代表者
高橋 英彦
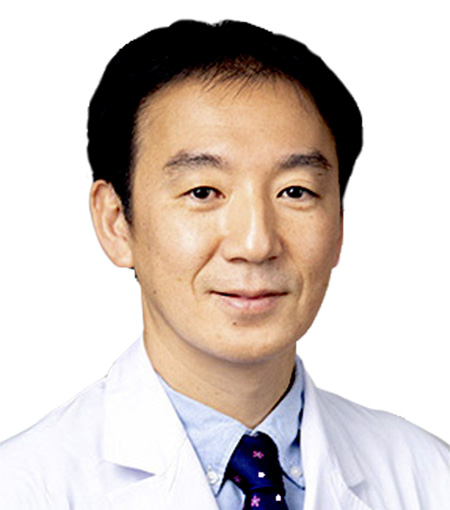
東京科学大学
大学院医歯学総合研究科
主任教授
主たる共同研究者
| 神谷 之康 | (株)国際電気通信基礎技術研究所 脳情報研究所 客員室長 |
| 原 正之 | 埼玉大学 学術院(大学院理工学研究科) 教授 |
研究概要
脳の予測に基づくイメージ生成の制御度に応じて①生理的な予測に基づく情報補完②錯覚③病理的な幻覚を連続的に「幻覚スペクトラム」と捉える。外界の物体・身体・自己イメージも予測による補完情報の大小に応じた連続的なものと捉える。XRやロボット技術を駆使して、健常者や精神・神経疾患を対象に幻覚スペクトラムの操作と脳情報のデコーディング技術を用いて、幻覚スペクトラムの脳情報表現の可視化を目指す。
春野 雅彦
サイバー社会における多重世界予測符号化の解明
グラント番号:JPMJCR22P4
研究代表者
春野 雅彦

情報通信研究機構
未来ICT研究所
室長
主たる共同研究者
| 安藤 英由樹 | 大阪芸術大学 芸術学部 教授 |
| 二本杉 剛 | 大阪経済大学 経済学部 教授 |
| 蜂須 拓 | 筑波大学 システム情報系 助教 |
研究概要
個人がいくつもの仮想世界を異なるアバターとして行き来し、多重世界で活動するサイバー社会が現実となりつつある今、ヒトが、脳や身体に負担を掛けることなく多重世界のメリットを享受し、自己変革をも可能とする多感覚情報通信技術の開発が望まれる。本研究は、計算論的神経科学、VR技術、触覚デバイス、行動経済学を背景に持つ研究者が協働することで、多重世界予測符号化の脳内メカニズムを解明し、その応用を目指す。
平田 豊
空間識の幾何による重力覚解明と感覚拡張世界創出
グラント番号:JPMJCR22P5
研究代表者
平田 豊

中部大学
理工学部
教授
主たる共同研究者
| 荒井 迅 | 東京科学大学 情報理工学院 教授 |
| 川合 伸幸 | 名古屋大学 大学院情報学研究科 教授 |
研究概要
自己の姿勢や運動状態の知覚を空間識と呼ぶ.空間識は主に,前庭覚,視覚,体性感覚からの異種感覚情報を統合することにより形成される.地球上で進化・発達した動物は,鉛直下向1Gで不変な重力を参照基準軸とし,その脳内推定値である重力覚を基に空間識を形成する.本研究では,異種多感覚統合による重力覚ならびに空間識形成の神経機構を新たな計算理論により定式化し,空間識を操作する方法を確立する.
和氣 弘明
神経-免疫連関による感覚認知システムの統合的理解
グラント番号:JPMJCR22P6
研究代表者
和氣 弘明

名古屋大学
大学院医学系研究科
教授
主たる共同研究者
| 榎本 和生 | 東京大学 大学院理学系研究科 教授 |
| 長谷部 理絵 | 自然科学研究機構 生理学研究所 特任准教授 |
| 的場 修 | 神戸大学 次世代光散乱イメージング科学研究センター 教授 |
研究概要
本研究では免疫系が感覚受容と相互作用する分子―回路メカニズムを末梢と中枢のレベルで明らかにし、その連関を捉える。まず末梢神経系における感覚―免疫連関を分子動態を中心に各発達段階で明らかにし、これをマウスで検証する。さらに、提案者らが開発したホログラフィック顕微鏡による感覚伝送を可能し、要素抽出を行う。









