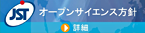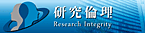2018 MRS Fall Meeting & Exhibitへ出展しました。
JST保有のマテリアル・デバイスに関する厳選技術を紹介しました。
知的財産マネジメント推進部は、ライセンスによる技術移転を見据えて2018年11月27日(火)~29日(木)にアメリカ・ボストンで開催された「2018 MRS Fall Meeting & Exhibit」に出展しました。JSTが保有する特許等の中から、マテリアルに関連する厳選した技術を紹介しました。
MRS(Material Research Society)は1973年に創設された、世界最大の材料学会です。年に2回、約1週間にわたる学会と、3日間の展示会が開催されています。90以上の国・地域から会員が集まり、その分野は化学、物理学、工学等多岐にわたります。
■ 2018 MRS Fall Meeting & Exhibit 出展概要
- 【会期】
- 2018年11月27日(火) 11:00~17:30
2018年11月28日(水) 11:00~17:30
2018年11月29日(木) 10:00~13:30
- 【会場】
- Hynes Convention Center, Level2
900 Boylston Street, Boston, Massachusetts 02115, USA
617.954.2000
- 【公式WEBサイト】
- 【来場者登録】
■ 出展技術のご紹介
| No. | 技術の名称 | 代表発明者 ・所属 |
技術の概要 | 国際公開番号/ 登録番号(日本) (各種公報) |
関連資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属有機構造体ナノシート Simple “Nanosheets” Synthesis New method to synthesize thin “Nanosheets” for various materials |
内田幸明 (大阪大学) |
従来のナノシートの製造方法として、層状化合物を形成し、層間に嵩高いゲストを挿入して単層を剥離する方法(トップダウン的手法)や、CVD法、ゾル-ゲル法等のボトムアップ的手法が知られていた。しかし、前者は層状化合物を形成できないものには適用できないことから適用可能な材料が限られ、また製造時に高温を必要とする工程が含まれるため、エネルギー面で不利な場合が多い。一方、後者は得られるナノシートの厚みが数百nm程度であり、より薄いものを得るのが困難であったり、また装置面での制約があった。 発明者らは、より薄く、より簡便なナノシートの製造方法を検討したところ、「超膨潤ラメラ相」を利用することによって、数nmのナノシートをより簡便に製造する方法を見いだした。この方法により、様々な材料をナノシート化することが可能となり、種々の材料の機能向上を図ることができると期待される。 |
WO2018016650/ 特許第6978783号 |
|
| 2 | 多孔フィルム、トリブロックポリマー Unique Block Copolymers New block copolymers containing catechol segments capable of supporting inorganic nanoparticles |
藪浩 (東北大学) |
カテコール基含有ポリマーは接着性や還元性などの機能を有することから、多様な応用が期待されている。 発明者らは、カテコール基に加え、疎水性基と親水性基とを側鎖に含むブロック共重合体を合成した。このブロック共重合体は、有機溶媒に溶解し、キャスト、乾燥することで、親水性セグメントと疎水性セグメントとがミクロ相分離をすることで多層構造体を形成することができる。また、このブロック共重合体のカテコール基が金属イオンと強く相互作用し、金属イオンを還元するため、その構造体中に金属粒子を導入することができる。これにより電気伝導性や、磁性を有する高分子組成物を製造することができる。このブロック共重合体の多層構造中に金属粒子を導入することで、材料に異方性を付与することができ、燃料電池材料、電子部品材料、磁気記録材料といった応用が期待される。 |
WO2015129846/ 特許第6270179号 |
|
| 3 | 多核金属錯体を用いた結晶性化合物 A New Conceptual Ionic Crystal NCIS: Non-Coulombic Ionic Solids Formation of Crystals from a Multinuclear Metal Complex |
今野巧 (大阪大学) |
イオン性固体は通常陽イオンを持つ原子と陰イオンを持つ原子がクーロン力によって引き合い、固体を形成している。 発明者らは、多核金属錯体のリガンドを工夫することでクーロン力に支配されていない全く新しいイオン性固体を発明した。これらの固体内部のイオンや水分子の配置や分布などの構造によってそれぞれ多様な物性を持ち、誘電特性、等方的に収縮する電歪特性、金属イオンの超流動性、急速なイオン交換特性を示す。センサー、カリウムイオン電池としての応用やイオン交換体への利用が期待されている。 |
WO2018056237/ 特許第7185228号 |
|
| WO2018079831/ 特許第7105449号 |
|||||
| 4 | 白金表面上部分無電解金メッキによるナノギャップ電極 Electroless Au Plating on Pt Room temperature operable 0.7nm Au nanogap electrodes by electroless Au plating on Pt |
真島豊 (東京工業大学) |
室温でも安定で、ギャップ間隔を精密に制御可能で、ゲート電極による電界変調が可能なAuナノギャップ電極を提供する。 白金電極母構造表面に無電解金メッキを行い電極先端に半径5nm程度の金粒子を堆積させ、0.7nm以下のギャップ間隔を有するナノギャップ電極を作成する方法を発明した。白金上無電解金メッキの核生成密度の制御により、部分金メッキから均質金メッキまでを制御することに成功した。また無電解金メッキの自己停止機能により、ナノギャップ電極のギャップ間隔をより精密に制御することが可能になった。 |
WO2012121067/ 特許第5942297号 |
|
| WO2013129535/ 特許第5674220号 |
|||||
| WO2015033600/ 特許第6283963号 |
|||||
| 5 | 酸素透過膜を用いた炭化水素改質方法及び炭化水素改質装置 H2 Generator Innovative method to realize both High Energy Efficiency and Facility Miniaturization |
高村仁 (東北大学) 松本広重 (九州大学) |
家庭用燃料電池の普及には、高純度水素ガスを大量・高効率に製造・供給できる技術が不可欠である。 本発明は、安定供給が望めるメタンを主成分とする天然ガスから高純度水素を製造する新しい方法として、「酸素透過性セラミックスによる部分酸化法」と「プロトン伝導体による水素分離法」を融合した天然ガス改質技術に係わるものである。 酸素が酸素透過性セラミックスを透過するためには酸素ポテンシャル勾配が存在すればよく、天然ガス改質に必要となる純酸素を、従来技術に比較して極めて効率よく供給しうる新技術である。 |
WO2007046314/ 特許第4255941号 |
|
| WO2003084894/ 特許第4277200号 |
|||||
| WO2007060925/ 特許第4977621号 |
|||||
| 6 | 熱電変換材料 Energy Harvesting Device Thermochemical Cell based on Host-Guest Chemistry generating electricity from Room-Temperature Heat |
山田鉄兵 (九州大学) |
熱を電気に変換する熱化学セルデバイスは従来からあったものの、室温付近では変換効率が低く、温度差が小さくなると十分な出力感度が得られなかった。 発明者らは、デバイスの電解液中に包接化合物を添加し、室温環境においても感度が高いデバイスを発明した。このデバイスは5~10度の温度差を検知できるため、ウェアラブルデバイス等へのセンサー応用や、低温廃熱から電力を取り出すエネルギー変換システムの実現が期待される。 |
WO2017155046/ 特許第6511708号 |
|
| 7 | カルボン酸をアルコールに変換する金属触媒とそれを用いる膜電極 Power Storage Facilities Environmental Friendly Power Storage with Electrochemical Cells using Natural Carboxylate |
山内美穂 (九州大学) |
エネルギーキャリアとして、水素、アンモニア、メチルシクロヘキサンなどが知られている。 発明者らは、余剰電力をカルボン酸からアルコールに変換して蓄電するための触媒、およびそのために用いられる装置を発明した。カルボン酸およびアルコールは水溶液であってもよく取り扱いが容易であり、安定、安全、安価に蓄電することができる。また、適切な燃料電池を用いればアルコールをカルボン酸に変換できるので、カーボンニュートラル・エネルギーサイクルを構築することができる。 |
WO2017154743/ 特許6875009第号 |
|
| 8 | CO2をトラップする電気化学有機金属錯体 Novel CO2 Reduction Method Capturing of CO2 from low concentration gas by using an Electrocatalysts |
石谷治 (東京工業大学) |
従来の二酸化炭素を有用物質に変換する方法は効率が悪く、二酸化炭素の純度が低いと利用できないといった欠点があった。 今回発明者らは、二酸化炭素を効率的に捕捉し一酸化炭素やギ酸へ変換する触媒を発明した。本発明を用いると、濃度が1%二酸化炭素であっても100%二酸化炭素であっても同程度の転化率で反応できる。火力発電所の燃焼ガスなどの濃度の低い二酸化炭素が大量に発生する場所での利用が期待される。 |
WO2016136433/ 特許6615175第号 |
※掲載技術にご関心がある方は、是非下記お問い合わせ先までご連絡ください。
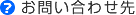
〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ
国立研究開発法人科学技術振興機構
知的財産マネジメント推進部 知財集約・活用グループ
TEL:03-5214-8486 FAX:03-5214-8417 E-mail: ※お問い合わせの内容によっては、回答に時間を要する場合があります。
※お問い合わせの内容によっては、回答に時間を要する場合があります。