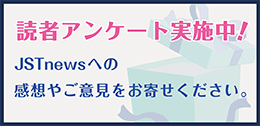JSTnews
JSTnews 2025年10月号
JSTnewsは、国立研究開発法人科学技術振興機構(略称JST)の広報誌です。
2025年10月号
- 特集
- がん細胞由来のエクソソームを尿から捕捉
手軽なリスク検査で健康な社会を実現へ
トポロジカル物質で次世代材料を探求
電子物性に着目し、便利な製品づくり
P.03特集 1― がん細胞由来のエクソソームを尿から捕捉 手軽なリスク検査で健康な社会を実現へ

細胞が放出する顆粒状の物質である「エクソソーム」は、細胞間の情報伝達などさまざまな役割を持つことがわかってきた。東京科学大学生命理工学院の安井隆雄教授は、尿中に含まれるエクソソームを捕捉し、そこに含まれる特定のマイクロRNAを解析してがんのリスクを検査する技術を開発。小野瀨隆一代表取締役(CEO)とスタートアップのCraifを共同創業し、この技術を事業化した。同社が開発・販売する「マイシグナル」は、医療機関や一般企業、ドラッグストアへの導入だけでなく、個人向けのオンライン販売も進むなど、健康社会実現への貢献が期待される。
P.08特集 2― トポロジカル物質で次世代材料を探求 電子物性に着目し、便利な製品づくり

身の回りのものを研究し、新たな性質を持つ物質を作ることは、社会をより便利にする製品の登場につながる。対象の性質を調べたり、新たな物質を探求したりする学問を「物性物理学」といい、近年はトポロジーという概念の導入により研究が盛んに行われている。理化学研究所創発物性科学研究センターの藤代有絵子理研ECL研究ユニットリーダーは、トポロジーの幾何学的な性質を生かした電子物性の研究を通じ、次世代へつながる材料の開発を目指している。
P.12連載― イノベ見て歩き 第24回
ケアリーバーの孤立を防ぐ仕組みづくり アプリ開発と自立支援体制構築の両輪で

社会実装につながる研究開発現場を紹介する「イノベ見て歩き」。第24回は、児童養護施設などを退所した社会的養護経験者(ケアリーバー)が、支援者と安全につながりながら自立できる仕組みづくりを目指す同朋大学社会福祉学部の宮地菜穂子准教授と、プロジェクトでアプリ開発を担当する中京大学工学部の曽我部哲也准教授に話を聞いた。
P.14NEWS & TOPICS

- 開催予告
- サイエンスアゴラ2025開催
20周年の節目を迎え、未来の担い手が集う場に - 研究成果
- 植物が寄生線虫を認識する仕組みを解明
- 研究成果
- 超軽量で強靭な「人工ヘチマスポンジ」

ISSN 1349-6085
編集発行/ 国立研究開発法人科学技術振興機構 総務部広報課
住所/ 〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ
電話/ 03-5214-8404 FAX/ 03-5214-8432
E-mail/ jstnews