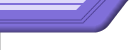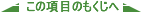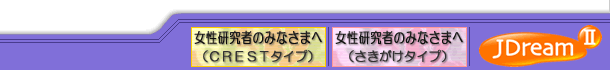C.さきがけ
応募に際しては、以下の1.〜12.の全てに加え、「II.応募・選考要領 A.共通事項 1.〜3.」、「V.応募に際しての注意事項」及び「VI.JST事業における重複応募について」をご確認下さい。
1.さきがけの研究推進の仕組み
戦略的創造研究推進事業全体の概要については、「I.事業の概要」をご参照下さい。「さきがけ」の研究推進の仕組みは以下の通りです。
(1)「さきがけ」の概要・特徴
a. 国が定める戦略目標のもとに設けられた研究領域において、研究総括の研究マネージメントのもと、選定された研究者の発想に基づいて研究を実施します。
b. 研究領域ごとに、研究提案(研究課題)を募集し、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て選考・選定します。
c. 選定された研究者はその研究構想の実現に向けて、個人で研究課題を実施します。
(2)さきがけ大挑戦型の概要(平成21年度新設)
実現の可能性の観点からは明確な見通しが得難いが、成功した場合には飛躍的、画期的な成果が期待できる研究(ハイリスク研究)を積極的に採択します。このため、従来のさきがけの選考プロセスに加え、幅広い視点から、ハイリスク研究としての提案の可能性・期待性の審査を行います。
さきがけは、これまでも研究者個人の独創的で挑戦的な研究を推進してきましたが、大挑戦型の新設により、さきがけの特徴であるチャレンジングな研究をさらに推進していきます。
実現の可能性の観点からは明確な見通しが得難いが、成功した場合には飛躍的、画期的な成果が期待できる研究(ハイリスク研究)を積極的に採択します。このため、従来のさきがけの選考プロセスに加え、幅広い視点から、ハイリスク研究としての提案の可能性・期待性の審査を行います。
さきがけは、これまでも研究者個人の独創的で挑戦的な研究を推進してきましたが、大挑戦型の新設により、さきがけの特徴であるチャレンジングな研究をさらに推進していきます。
a. 通常のさきがけ選考に加え、大挑戦型としての審査も受けることができます。希望する場合は、研究提案書の様式1に明記するとともに、様式7を提出していただきます。なお、審査により通常のさきがけ(以下、通常型と呼ぶ)で採択される場合があります。
b. 研究者は研究期間中に目指す「挑戦目標」を掲げ、当該研究領域において、研究総括の下で他の研究者と交流を持ちつつ挑戦目標の達成に向けて研究を行います。挑戦目標を達成することにより、科学技術の飛躍的、画期的な発展への手掛かりが得られることを期待します。
c. 研究推進においては、研究の進捗に応じて研究費の変更(研究費総額で最大2倍程度までの増額)が認められる場合があります。また審査により、研究開始から5年目の年度末を限度として研究期間を延長できる場合があります。
d. 中間、事後評価では、ハイリスク研究に挑戦したことを前提とした評価を行います。しかしながら、研究の進展に可能性が見えない課題は、中間評価の結果を受けての中止もあり得ます。あるいは中間評価時以外にも、研究総括の判断による期間途中での研究計画の縮小や中止もあり得ます。
(3)研究総括
研究領域の責任者として、研究課題の募集から研究活動の様々な支援まで、研究領域の運営において中心的な役割を果たします。研究者が研究の進捗状況を発表し、ディスカッションする領域会議の開催や研究実施場所の訪問等の活動を通じて、指導や助言を行います。また研究上のニーズや評価により研究費の調整を行います。
研究領域の責任者として、研究課題の募集から研究活動の様々な支援まで、研究領域の運営において中心的な役割を果たします。研究者が研究の進捗状況を発表し、ディスカッションする領域会議の開催や研究実施場所の訪問等の活動を通じて、指導や助言を行います。また研究上のニーズや評価により研究費の調整を行います。
(4)研究実施体制
a. 研究者が個人で研究を進めます。
b. JSTは、原則、研究者が研究を実施する研究機関と委託研究契約を締結します。
c. 採択された研究者は、兼任*1、専任*2、出向*3のいずれかの形態で、研究期間中JSTに所属します。勤務条件等については「11.採択された研究者の勤務条件等」をご参照下さい。
※ 応募に際しては、必要に応じて、所属研究機関や共同研究機関等への事前説明等を行ってください。
*1兼任:大学、国公立試験研究機関、独立行政法人、財団法人、企業等に所属している方で、JSTの所属を兼務して、参加する場合です。
*2専任:研究機関、企業等に所属されていない、あるいは所属機関を退職して、JSTの雇用する研究者として参加する場合です。
*3出向:企業・財団法人等に所属している方が、JSTへの出向の上、参加する場合です。
※ 研究期間中の所属機関の変更など必要に応じて、参加形態を変更することは可能です。
(5)研究実施場所
研究内容や研究環境を考慮しつつ、研究者ならびに研究を実施する機関とご相談の上、決定します。所属機関以外で研究することも可能です。
研究内容や研究環境を考慮しつつ、研究者ならびに研究を実施する機関とご相談の上、決定します。所属機関以外で研究することも可能です。
(6)研究計画
採択後、研究者は研究課題の研究期間全体を通じた全体研究計画書を作成します。また、年度ごとに年度研究計画書を作成します。研究計画には、研究費や研究体制を含みます。
採択後、研究者は研究課題の研究期間全体を通じた全体研究計画書を作成します。また、年度ごとに年度研究計画書を作成します。研究計画には、研究費や研究体制を含みます。
(7)研究契約
各研究課題の推進にあたり、JSTは研究者が研究を実施する研究実施機関と研究契約を締結します。
各研究課題の推進にあたり、JSTは研究者が研究を実施する研究実施機関と研究契約を締結します。
(8)知的財産権の帰属
さきがけの研究で得られた発明等の帰属は以下のようになります。
さきがけの研究で得られた発明等の帰属は以下のようになります。
a)国内の研究機関で研究する場合
ア)兼任の研究者の場合
研究により生じた特許等の知的財産権は、委託研究契約に基づき、産業技術力強化法第19条(日本版バイドール条項)に掲げられた事項を研究機関が遵守すること等を条件として、原則として研究機関に帰属します。
研究により生じた特許等の知的財産権は、委託研究契約に基づき、産業技術力強化法第19条(日本版バイドール条項)に掲げられた事項を研究機関が遵守すること等を条件として、原則として研究機関に帰属します。
イ)専任・出向の研究者の場合
研究実施機関との契約によります。
研究実施機関との契約によります。
b)海外の研究機関で研究する場合
海外の研究機関とJSTの共有となります。JST持ち分については、原則として研究者とJSTの共有となります。
海外の研究機関とJSTの共有となります。JST持ち分については、原則として研究者とJSTの共有となります。
(9)研究支援体制
研究領域ごとに、JSTが研究活動を支援します。JSTは、研究総括の助言に基づいて研究実施場所や体制、研究の広報やアウトリーチ、特許出願などを含め、研究に必要な支援活動を行います。
研究領域ごとに、JSTが研究活動を支援します。JSTは、研究総括の助言に基づいて研究実施場所や体制、研究の広報やアウトリーチ、特許出願などを含め、研究に必要な支援活動を行います。
(10)課題評価
a. 研究総括は、研究の進捗状況や研究成果を把握し、領域アドバイザー等の協力を得て、研究課題の中間評価および事後評価を行います。研究期間が3年間の課題では、研究終了後、速やかに事後評価を行います。また、研究期間が5年間の課題では、中間評価は研究開始後3年程度を目安として、また事後評価は研究終了後速やかに行います。
b. 研究期間が5年間の研究課題について、中間評価の結果は、以後の研究計画の調整(縮小、中止)、研究費の増額・減額に反映します。大挑戦型の場合は、中間評価以外にも研究総括の判断により、研究計画や研究費の見直し等の措置を行うことがあります。
c. 研究終了後一定期間を経過した後、研究成果の発展状況や活用状況、研究者の活動状況等について追跡調査を行います。追跡調査結果等を基に、機構が選任する外部の専門家が追跡評価を行います。
(11)研究領域評価
記(10)課題評価とは別に、研究領域と研究総括を対象として領域評価が行われます。戦略目標の達成へ向けての進捗状況、研究領域の運営状況等の観点から評価が実施されます。
記(10)課題評価とは別に、研究領域と研究総括を対象として領域評価が行われます。戦略目標の達成へ向けての進捗状況、研究領域の運営状況等の観点から評価が実施されます。
(12)海外の研究機関での研究実施
次の2つの条件を満たす場合に、海外の研究機関等で研究を行うことも可能ですが、研究総括の承認を必要とします。
なお、海外での実施を希望される場合は、海外での実施を希望する理由を研究提案書(様式6)に記載してください。
次の2つの条件を満たす場合に、海外の研究機関等で研究を行うことも可能ですが、研究総括の承認を必要とします。
a. 研究者の研究構想を実現する上で必要不可欠と判断され、海外の機関でなければ研究実施が不可能であること。
b. 当該機関とJSTとの間で、少なくとも下記の2つの条件を満たす契約を締結できること。
ア.当該の海外研究機関への間接経費の支払いが、研究費の30%を超えないこと。
イ.当該の海外研究機関とJSTとの間で、知的財産権の共有ができること。
2.応募者の要件
研究者となる方本人から提案してください。応募者の要件は以下の通りです。
(1)自らが研究構想の発案者であるとともに、その構想を実現するために自立して研究を推進する研究者。
(2)研究室を主宰する立場にある等により、提案課題に専念できない研究者は対象外となる場合があります。
(3)日本国籍を持つ研究者、または、応募時に日本国内の研究機関において研究を行っている外国人研究者。※所属機関における常勤、非常勤の身分あるいは有給、無給の別は問いません。
(注)研究代表者と研究総括が利害関係にあるとされる場合には、研究提案書を選考対象から除外することがあります。詳しくは「6.選考の方法等」を参照してください。
3.対象となる研究提案
(1)平成21年度研究提案募集では、「IV.戦略目標」に記載の11の戦略目標のもとに定められた、13の研究領域(平成19、20年度発足の研究領域および平成21年度発足の新規研究領域)に対する研究提案を募集します。5年型、大挑戦型の対象領域については、以下の表を参照して下さい。「III.「研究領域の概要」および「研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針」」をよくお読みになり、研究領域にふさわしい研究提案を行って下さい。
なお研究提案の応募は、「CREST」および「さきがけ」の全研究領域を通して1件のみ可能です。
なお研究提案の応募は、「CREST」および「さきがけ」の全研究領域を通して1件のみ可能です。
(2)様々な科学技術に革新的発展をもたらし、新技術・新産業の創出につながる先導的・独創的な研究で、国際的に高く評価され得るものを期待します。
ただし、他の研究プロジェクトや研究課題等の一部だけを遂行するような研究提案は対象となりません。
ただし、他の研究プロジェクトや研究課題等の一部だけを遂行するような研究提案は対象となりません。
| 研究 領域 発足 年度 |
研究領域 | 研究総括 | 募集対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年型 | 5年型 | 大挑戦型 | |||
| 平成 21年度 (新規研究領域) |
情報環境と人 | 石田 亨 (京都大学大学院情報学研究科 教授) |
○ | ○ | ○ |
| 太陽光と光電変換機能 | 早瀬 修二 (九州工業大学大学院生命体工学研究科 教授) | ||||
| 光エネルギーと物質変換 | 井上 晴夫 (首都大学東京 大学院都市環境科学研究科長) | ||||
| 脳神経回路の形成・動作と制御 | 村上 富士夫 (大阪大学大学院生命機能研究科 研究科長) | ||||
| エピジェネティクスの制御と生命機能 | 向井 常博 (佐賀大学 理事・副学長) | ||||
| 平成 20年度 |
iPS細胞と生命機能 | 西川 伸一(独立行政法人理化学研究所発生・再生科学総合研究センター 副センター長) | ○ | ○ | ○ |
| 光の利用と物質材料・生命機能 | 増原 宏(奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 特任教授/台湾国立交通大学 講座教授(応用化学系及分子科学研究所)) | ||||
| ナノシステムと機能創発 | 長田 義仁(独立行政法人理化学研究所基幹研究所 副所長) | ||||
| 脳情報の解読と制御 | 川人 光男(株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)脳情報研究所 所長/ATRフェロー) | ||||
| 知の創生と情報社会 | 中島 秀之(公立はこだて未来大学 学長) | ||||
| 平成 19年度 |
革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス | 佐藤 勝昭(東京農工大学大学院工学府 特任教授) | ○ | × | × |
| 数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索 | 西浦 廉政(北海道大学電子科学研究所 教授) | ||||
| 生命現象の革新モデルと展開 | 重定 南奈子(同志社大学文化情報学部 教授) | ||||
4.研究期間
(1)研究期間
「3.対象となる研究提案」の表を確認して下さい。
「3.対象となる研究提案」の表を確認して下さい。
a. 平成20、21年度発足領域では3年間または5年間とします。
応募時に、3年と5年の2種類から選択して下さい。応募後は、研究期間を変更することはできません。
応募時に、3年と5年の2種類から選択して下さい。応募後は、研究期間を変更することはできません。
b. 平成19年度発足領域では3年間とします。
(2)本年度採択される研究課題の研究期間は、3年間の課題では、最長で平成25年(2013年)3月末まで、5年間の課題では、最長で平成27年(2015年)3月末までとなります。
(3)大挑戦型では、当初設定の研究期間にかかわらず、ハイリスク研究であることを考慮した上で、研究総括の判断により研究期間を延長・縮小する場合があります。原則として研究期間は3〜5年としますが、研究の進捗や進展の見通しによっては、1年で終了することもあれば、最長で5年目の年度末まで延長できる場合もあります。
5.研究費
(1)一研究課題あたりの研究費
a. 3年間の課題では、全研究期間で総額3〜4千万円程度です。
b. 5年間の課題では、全研究期間で総額5千万円〜1億円程度です。
(2)各年度の予算計画は研究計画に基づいて設定してください。
(3)研究総括は、研究課題採択後、研究者と相談の上、全研究期間の研究計画、初年度の予算等を定めた年度研究計画を決定します。次年度以降は同様に、毎年、当該年度の研究計画を決定していきます。なお、研究総括の評価や研究の展開状況により研究費が増減することがあります。大挑戦型では、研究の進捗により、研究費総額で最大2倍程度までの増額が認められる場合があります。
(4)研究費は、JSTと研究機関が結ぶ研究契約に基づき、研究機関で執行していただきます。研究費の30%を上限とする間接経費は、JSTが別途措置して研究実施機関に支払います。また、必要に応じて研究費の一部をJSTで執行することもできます。
(5)研究費(直接経費)の使途については、以下の通りです。
a)研究費(直接経費)とは、さきがけの研究の遂行に直接必要な経費であり、以下の使途に支出することができます。
 物品費:新たに設備・備品・消耗品等を購入するための経費
物品費:新たに設備・備品・消耗品等を購入するための経費
 旅費:研究者のさきがけの研究に直接関わる旅費。あるいは、研究計画書に記載された研究参加者が、さきがけの研究に直接関わる本人の研究成果を国内で発表する際の旅費。
旅費:研究者のさきがけの研究に直接関わる旅費。あるいは、研究計画書に記載された研究参加者が、さきがけの研究に直接関わる本人の研究成果を国内で発表する際の旅費。
 謝金等:さきがけの研究に直接関わる研究補助者の人件費。
謝金等:さきがけの研究に直接関わる研究補助者の人件費。
 その他:研究成果発表費用(論文投稿料など)等
その他:研究成果発表費用(論文投稿料など)等
b)以下の経費は研究費(直接経費)として支出できません。
 さきがけの研究の研究目的に合致しないもの
さきがけの研究の研究目的に合致しないもの
 間接経費としての使用が適当と考えられるもの
間接経費としての使用が適当と考えられるもの
c)その他、研究費からの支出が適切か否かの判断が困難な使途がある場合は、JSTへお問い合わせ下さい。
(「Q&A」もご参照下さい)
(「Q&A」もご参照下さい)
(注)JSTでは、研究費の柔軟で効率的な執行を研究機関に対して要請するとともに、国費を財源とすることなどから、一部の項目について委託研究契約書や事務処理説明書等により、一定のルール・ガイドラインを設けるなどして、適正な執行をお願いしています。
6.選考の方法等
スケジュールは「II.A.2.募集・選考スケジュールについて」をご参照下さい。
(1)研究領域ごとに、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て、書類選考、面接選考の2段階選考を行います。大挑戦型では、次頁の図に示すように、通常の2段階選考に、さきがけ大挑戦型審査委員による多角的な視点での審査を加えた3段階選考を行います。3次選考は、大挑戦型審査資料(さきがけ - 様式7)のみを用いた書類審査(マスキング審査)の 形で行われ、各研究領域での採択枠は設定せず、研究課題の挑戦性に重点を置いて審査します。必要に応じて、その他の調査等を行う場合があります。また、外部評価者の協力を得ることもあります。この選考結果に基づき、JSTは研究者および研究課題を選定します。
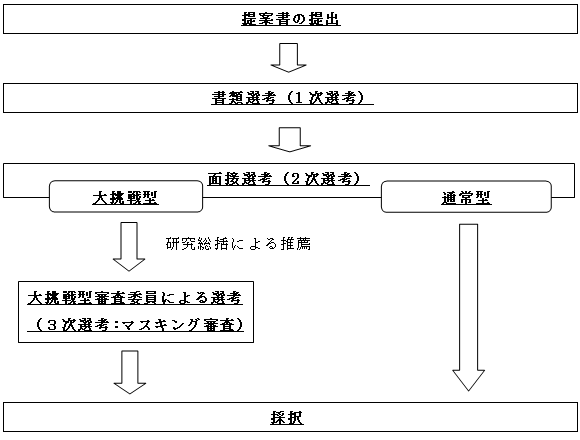
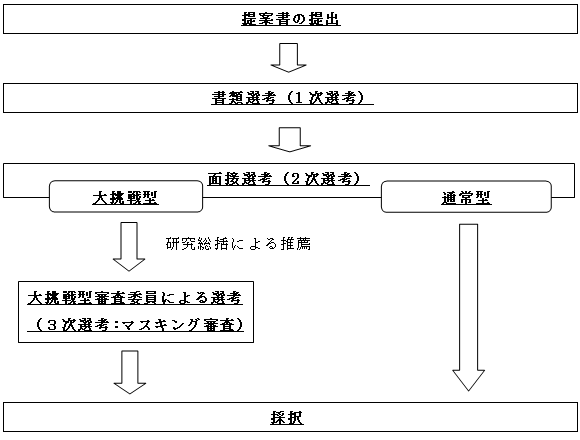
(2)JSTの規定に基づき、公正で透明な評価を行う観点から、研究提案者等に関して、下記に示す利害関係者は
評価に加わらないようにしています。
a. 被評価者と親族関係にある者。
b. 被評価者と大学、国研等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同一の企業に所属している者。
c. 緊密な共同研究を行う者。
(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メンバー、 あるいは被評価者の研究課題の中での研究分担者など、被評価者と実質的に同じ研究グループに属していると考えられる者)
(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メンバー、 あるいは被評価者の研究課題の中での研究分担者など、被評価者と実質的に同じ研究グループに属していると考えられる者)
d. 被評価者と密接な師弟関係あるいは直接的な雇用関係にある者。
e. 被評価者の研究課題と直接的な競争関係にある者。
f. その他JSTが利害関係者と判断した場合。
(3)加えて平成21年度発足の研究領域に関しては、研究総括が研究提案者と下記の関係にあるとされる場合には、
研究提案書を選考対象から除外することになりますので、そのような可能性がある場合には事前にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:03-3512-3530(E-mail rp-info@jst.go.jp)
a. 研究総括が研究提案者と親族関係にある場合。
b. 研究総括が研究提案者と大学、国研等の研究機関において同一の研究室等の最小単位組織に所属している場合。
あるいは、同一の企業に所属している場合。
c. 現在、研究総括と研究提案者が緊密な共同研究を行っている場合。または過去5年以内に緊密な共同研究を行った場合。
(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メンバー、あるいは研究課題の中での研究分担者など、 研究総括と研究提案者が実質的に同じ研究グループに属していると考えられる場合)
(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メンバー、あるいは研究課題の中での研究分担者など、 研究総括と研究提案者が実質的に同じ研究グループに属していると考えられる場合)
d. 過去に通算10年以上、研究総括と研究提案者が密接な師弟関係あるいは直接的な雇用関係にあった場合。“密接な師弟関係”とは、
同一の研究室に在籍したことがある場合を対象とする。また所属は別であっても、研究総括が実質的に研究提案者の研究指導を行っていた期間も含む。
(4) 選考に係わった領域アドバイザー等の氏名は、採択課題の発表時に公表します。
(5)面接選考の実施および選考結果の通知
a. 書類選考の結果、面接選考等の対象となった研究提案者には、その旨を書面で通知するとともに、面接選考の要領、日程(※)、追加で提出を求める資料等についてご案内します。
(※)面接選考の日程は決まり次第、
ホームページにてお知らせします。
b. 面接選考では、研究提案者ご本人に研究構想の説明をしていただきます。その際、全研究期間を通した希望研究費総額も示してください。なお、日本語での面接を原則としますが、日本語での実施が困難な場合、英語での面接も可能です。
c. 書類選考、面接選考の各段階で不採択となった研究提案者には、その都度、選考結果を書面で通知します。
d. 最終選考の結果、採択となった研究提案者には、その旨を書面で通知するとともに、研究開始の手続きについてご案内します。
7.選考の観点
(1)さきがけの各研究領域に共通の選考の基準は、以下のとおりです。
a. 戦略目標の達成に貢献するものであること。
b. 研究領域の趣旨に合致したものであること。
c. 提案者自身の着想であること。
d. 独創性を有していること。
e. 研究構想の実現に必要な手掛かりが得られていること。
f. 今後の科学技術に大きなインパクト(新技術の創出、重要問題の解決等)を与える可能性を有していること。
g. 研究が適切な実施規模であること。
大挑戦型では、次の基準を加えます。
h. 実現の可能性の観点からは明確な見通しが得難いが、成功した場合に飛躍的、画期的な成果が期待できること。
(2)上記のほか、研究領域毎の独自の選考の観点や方針について、「III「研究領域の概要」および「研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針」」をよくお読み下さい。
(3)研究費の「不合理な重複」ないし「過度の集中」にあたるかどうかも、選考の要素となります。詳しくは、「V.応募に際しての注意事項 2.」をご参照ください。
8.採択予定件数
13研究領域で130件程度とします。
平成20、21年度発足領域(研究領域の発足年度は3ページ参照)では、研究期間5年の課題を当該領域の採択件数の2割程度採択します。大挑戦型では、通常型の採択に加えて1領域あたり若干名を採択する予定です。
平成19年度発足領域では全て研究期間3年の課題となります。
9.採択された研究者の責務等
(1)研究の推進および管理
研究の推進全般、研究成果等について責任を負っていただきます。また、研究計画書の作成や定期的な報告書等の提出を行っていただきます。
研究の推進全般、研究成果等について責任を負っていただきます。また、研究計画書の作成や定期的な報告書等の提出を行っていただきます。
(2)資金の執行管理・運営、事務手続き、研究補助者等の管理、出張等について責任を負っていただきます。
(3)研究成果の取り扱い
研究総括等に研究進捗状況を報告していただきます。また、国内外での研究成果の発表や、知的財産権の取得を積極的に行っていただきます。研究実施に伴い、得られた研究成果を論文等で発表する場合は、戦略的創造研究推進事業の成果である旨の記述を行っていただきます。併せて、JSTが国内外で主催するワークショップやシンポジウムに参加し、研究成果を発表していただきます。
研究総括等に研究進捗状況を報告していただきます。また、国内外での研究成果の発表や、知的財産権の取得を積極的に行っていただきます。研究実施に伴い、得られた研究成果を論文等で発表する場合は、戦略的創造研究推進事業の成果である旨の記述を行っていただきます。併せて、JSTが国内外で主催するワークショップやシンポジウムに参加し、研究成果を発表していただきます。
(4)研究総括主催による合宿形式の領域会議(年2回)に参加し、研究成果の発表等を行なっていただきます。
(5)JSTと研究機関等との研究契約、その他JSTの諸規定等に従っていただきます。
(6)JSTは、研究課題名、構成員や研究費等の所要の情報を、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)および政府研究開発データベース(「V.応募に際しての注意事項」参照)へ提供することになりますので、予めご了承ください。また、研究者等に各種情報提供をお願いすることがあります。
(7)戦略的創造研究推進事業の事業評価、JSTによる経理の調査、国の会計検査、その他各種検査等に対応していただきます。
(8)研究終了後一定期間を経過した後に行われる追跡評価に際して、各種情報提供やインタビュー等に対応していただきます。
10.研究機関の責務
(1)研究機関には、研究契約書及びJSTが定める研究契約事務処理の説明書に基づいて、研究費の柔軟で効率的な運用に配慮しつつ、適正な経理事務を行っていただきます。また、JSTに対する所要の報告等、およびJSTによる経理の調査や国の会計検査等に対応していただきます。
(2)委託研究契約に基づき、産業技術力強化法第19条(日本版バイドール条項)が適用されて研究機関に帰属した知的財産権が、出願および設定登録などされる際は、JSTに対して所要の報告をしていただきます。
(3)研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づき、研究機関における研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります。また、その実施状況の報告等をしていただくとともに、体制整備等の状況に関する現地調査が行われる場合には対応下さい(「V.応募に際しての注意事項」参照)。
11.採択された研究者の勤務条件等
(1)勤務条件
原則としてJSTの諸規定によりますが、勤務時間、休憩および休日については研究実施場所ごとに定めます。
原則としてJSTの諸規定によりますが、勤務時間、休憩および休日については研究実施場所ごとに定めます。
(2)研究者に対する報酬、社会保険の適用
a. 兼任について
兼任研究者とは、既に大学等の研究機関に雇用され、JSTを兼務し研究を推進する研究者を指します。JSTが研究者に支給する報酬については、JSTの規定に基づき、毎月一定額をお支払いします。社会保険については、ご所属の研究機関での加入となります。
兼任研究者とは、既に大学等の研究機関に雇用され、JSTを兼務し研究を推進する研究者を指します。JSTが研究者に支給する報酬については、JSTの規定に基づき、毎月一定額をお支払いします。社会保険については、ご所属の研究機関での加入となります。
b. 専任について
専任研究者とは、研究者としてJSTに雇用された研究者を指します。
JSTが研究者に支給する報酬は、JSTの規定に基づき、年俸制となっています。年俸には給与・諸手当及び賞与等のすべてが含まれています。また、社会保険については、JST加盟の健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金および雇用保険に加入していただきます。
専任研究者とは、研究者としてJSTに雇用された研究者を指します。
JSTが研究者に支給する報酬は、JSTの規定に基づき、年俸制となっています。年俸には給与・諸手当及び賞与等のすべてが含まれています。また、社会保険については、JST加盟の健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金および雇用保険に加入していただきます。
c. 出向について
出向する研究者には、給与および事業主負担額(健康保険、厚生年金保険、退職給与引当金等)に兼務率を乗じた額がJSTから出向元に支払われます。給与は出向元を経由してお支払いします。兼務率は出向元との相談で決めますが、JST80%以上の兼務が望まれます。
社会保険の適用については、出向元の健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金および雇用保険を継続することになります。ただし、労働者災害補償保険については、JSTが適用事業主になります。
出向する研究者には、給与および事業主負担額(健康保険、厚生年金保険、退職給与引当金等)に兼務率を乗じた額がJSTから出向元に支払われます。給与は出向元を経由してお支払いします。兼務率は出向元との相談で決めますが、JST80%以上の兼務が望まれます。
社会保険の適用については、出向元の健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金および雇用保険を継続することになります。ただし、労働者災害補償保険については、JSTが適用事業主になります。
12.研究提案書(様式)の記入要領
研究提案書の記入要領(PDF:196KB)に従い、研究提案書を作成してください。