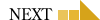�X�D�����Q�P�N�x��茤���҃x���`���[�n�o���i���� �p & �`
�i���Ƃ̖ړI���j
�p�P�@�{���Ƃ̖ړI���ڂ��������Ƃǂ��Ȃ邩�B
�`�P�@��茤���҂��x���`���[��Ƃ̑n�o�Ɏ����錤���J�����ʂ�Ƌ��ɁA�N�ƉƂƂ��ĕK�v�Ȏ����E�\�͂��K�����A�x���`���[���N�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���܂��B
�@�A���A�{���Ƃɂ����āA�s�꒲���y�ь����J���̐i���ɂ��A�N�Ƃ��������I�����ʓI�Ɋ�Ɖ��ł����i�����o����A����茤���҂��Y�ƊE���Ŋ���ł���ƌ����܂��ꍇ�́A���̎�i��I�����邱�Ƃ��l�����܂��B
�@�܂��A��w���̋N�Ǝx���g�D�i�x���`���[�E�r�W�l�X�E���{���g���[���j�̍X�Ȃ�@�\�����ɂȂ��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�p�Q�@�{���ƂŋN�Ƃ�����Ƃɑ�����T�͂���̂��B
�`�Q�@���߂ɉ����Ē�����Ɠ����琬������Г��̋��Z�@�ցA������Ɗ�Ր����@�\�ւ̏Љ���s���܂��B�{���ƂŋN�Ƃ�����Ƃ����̓��ʂȎx���ł͂���܂��AJST���J�Â���e��W����ɏo�W���邱�Ƃ��\�ł��B�܂��A�N�Ƃ����x���`���[�ɑ��Ă͊e�Ȃ��s���Ă���e��x�����x�̗��p���\�ł��i�������A�ʓr�e���x�ɉ���������ƂȂ�܂��j�B
�i�Ώە���j
�p�R�@�K���ȕ��삪�Ȃ��ꍇ�͂ǂ�����悢���B
�`�R�@�������e���画�f���A
�T�W�y�[�W�̃R�[�h�\�̒�����ł��K���ƍl�����镪��i�啪��A������j��I�����Ă��������B
�i����̗v�����j
�p�S�@���厞�_�ł͑�w���ɏ������Ă��Ȃ���茤���҂�����ł��邩�B
�`�S�@���厞�_�ł͕K��������w���ɏ������Ă���K�v�͂���܂��A��茤���҂͌����J�����Ԓ��ɂ����đ�w���ɂi�r�s�N�ƌ������Ƃ��ď����ł���҂݂̂Ƃ��܂��B�Ȃ��A�����J�����Ԓ��̎�茤���҂̌�ւ͏o���܂���̂Œ��ӂ��Ă��������B
�p�T�@�����@�ւ̗����͕K���K�v���B�܂��A�ǂ̃��x���̗������K�v���B
�`�T�@�{�ȋ��ʌ����J���Ǘ��V�X�e���ie-Rad�j�ɂ��\����A�i�r�s�N�ƌ���������������@�ցi��w���j�̏��F���K�v�ɂȂ�܂��B�{�����J�����{�ɓ������ẮAJST�Ƒ�w���Ƃ̊ԂɈϑ������J���_�K�v�ƂȂ�܂��B
�p�U�@���݃|�X�h�N�Ƃ��ď������Ă����w���Ƃ͈قȂ��w���ɂ����Ė{���Ƃ����{���邱�Ƃ͉\���B���̏ꍇ�A�\���͂ǂ���̑�w������s���̂��B
�`�U�@�o���̑�w���̗�����������̂ł���Ή\�ł��B�������A�������̎��{�����ւ̓��ӂȂǂɂ͋C��t���ĉ������B�\���͖{���Ƃ����{���邱�ƂɂȂ��w������s���Ă��������B
�p�V�@��茤���҂Ƃ͉��܂ł̂��Ƃ��B�܂��A��Ƃ�ސE���|�X�h�N�ƂȂ��Ă���ꍇ�͉��܂ł��B
�p�W�@�u�i�r�s�N�ƌ������̏����@�ցv�Ƃ͉����B
�p�X�@��w���͉��厞�ɂi�r�s�N�ƌ������ƂȂ��茤���҂ƌ_��K�v������̂��B
�`�X�@���厞�ɂ����Ă͎�茤���҂Ƃ̌_��͗v���ł͂���܂���B�������A��茤���҂Ƃ̘A���ʼn��傷��K�v������܂��̂ŁA����ɍۂ��Ď�茤���҂̎��O�����Ă����Ă��������B�{���Ƃւ̐\���ɂ�e-Rad�𗘗p���Ă��������܂����A���̎��_�ł܂��i�r�s�N�ƌ������ƂȂ��茤���҂��@�ւɏ������Ă��Ȃ��ꍇ�́A�N�Ǝx���S���҂���s���Ă��������B
�p�P�O�@�N�Ǝx���g�D�����������ɎQ�����Ă��悢���B
�`�P�O�@���������ւ̎Q���͑z�肵�Ă��܂���B�N�Ǝx���g�D�̎�ȋƖ��́A�i�r�s�N�ƌ������ւ̎{�݁E�ݔ��̒�A�i�r�s�N�ƌ��������s���s�꒲���⎖�ƌv��쐬�ւ̎x���Ȃǂ̋Ɩ��ł��B
�p�P�P�@�\���ɂ����āA�N�Ǝx���g�D�̎Q���͕K�{���B
�`�P�P�@�N�Ǝx���g�D�̎Q���͕K�{�ł��B
�p�P�Q�@�N�Ǝx���g�D�ɂ͂ǂ̂悤�ȑg�D���Ȃ��̂��B
�`�P�Q�@�u
�i�S�j�\���҂̗v���i�Q�j��w���ɑ���v���@�B�v�̗v�������A��w���̓����g�D�ł��B���̑g�D�𒆐S�ɁA�i�r�s�N�ƌ������̌ٗp�A���ƌv��쐬�̎x���A�������{�ꏊ�̒A�o���A�Ǎ��ʂ̎x�����A�����J���v���W�F�N�g�̐i�����x�����A�����J����x���`���[�n�o�̉ߒ��̒��ŁA�i�r�s�N�ƌ��������u�A���g���v���i�[�v�Ƃ��ė{�����A�Љ�ɔy�o����g�D�ł��B
�@��w���ɂ���ĈقȂ�܂����A�u�a�k�i�x���`���[�E�r�W�l�X�E���{���g���[�j�A�C���L���x�[�V�����{�݁A�Y�w�A�g�{���A�m�I���Y�{�������S�����Ă��܂��B
�p�P�R�@�x���`���[��Ƃ̑n�o�ł͂Ȃ��A������Ƃ̐V�K���ƂƂ���ꍇ�͉���̑ΏۂɂȂ邩�B
�`�P�R�@�N�ƂƂ́A�V������Ђ������i�n��j���Ƃł��̂ŁA����̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B
�p�P�S�@��w���̌����҂��O���[�v�ʼn��傷�邱�ƁA�܂��c�́A���Ԋ�Ɠ�����̒�Ă͉\���B
�`�P�S�@�ł��܂���B�i�r�s�N�ƌ������ƂȂ��茤���ҁi�l�j�ƋN�Ǝx���g�D�̐ӔC�ҁi�l�j�̘A���ʼn��債�Ă����������ƂɂȂ�܂��B����ȊO�̕��͕��S�J���҂Ƃ��ĎQ������A���邢�͂q�`���̎x���҂Ƃ��ċ��͂��Ă����������ƂɂȂ�܂��B
�p�P�T�@���厞�_�œ������Ȃ��Ɛ\���ł��Ȃ��̂��B
�`�P�T�@���厞�_�ŁA�i�r�s�N�ƌ������ƂȂ��茤���҂��֗^���A�x���`���[��Ƒn�o�̊j�ƂȂ錤�����ʁi���������j�����邱�Ƃ������ł��B�w������̌������ʂ��͈͂Ƃ��܂��̂ŁA�K�������������̔����҂ł��邱�Ƃ͋��߂܂���B
�@�Ȃ��A�{���Ƃɂ����ẮA�������Ƃ́A�������i���������ꂽ�������͏o��ς݂̓����j�A���p�V�Č��A���쌠�i�v���O�����A�f�[�^�x�[�X���j�A�琬�Ҍ��A��H�z�u���p���ɂȂ�܂��B
�p�P�U�@�x���`���[�N�Ƒn�o�̊j�ƂȂ錤�����ʂƂ͉����B
�`�P�U�@�{���Ƃɂ����ẮA�i�r�s�N�ƌ������i��茤���ҁj���֗^�����������ʂ���ɉ��p�����A�J���������s�����ƂɂȂ�܂��B���̂��߁A�Œ�ł���b�����͏I�����Ă���A���̐��ʂ��������Ƃ��ďo�肳��Ă���K�v������܂��B���̍ہA�u�i�r�s�N�ƌ������i��茤���ҁj�̊֗^�v�ɂ��܂��ẮA���Y�������̔����҂Ɏ�茤���҂̖��O�������Ƃ��A�֘A�̘_�����ɂ���Ă��̊֗^���F�߂���̂ł���Ό��\�ł��B�Ȃ��A�\�t�g�E�F�A���J������ꍇ�́A���̊�{�����ƂȂ�_�����ɂ��܂��B
�p�P�V�@�����Ƃ��Ď��R�Ȋw����Ƃ��邪�A�Љ�Ȋw����ł��\�����\��
�`�P�V�@���R�Ȋw����̌����J�����ʂ̗��p�E�W�J�𐄐i���A�Љ�I�E�����I���l�̑n�o��ڎw���A�Љ�̋�̓I�Ȗ��̉����Ɋ�^������̂ł���ΐ\�����\�ł��B
�p�P�W�@�G�t�H�[�g�Ƃ͂Ȃɂ��B
�`�P�W�@�����Ȋw�Z�p��c�ɂ�����G�t�H�[�g�̒�`�w�����҂̔N�Ԃ̑S�d�����Ԃ�100���Ƃ����ꍇ�A���̂������Y�����̎��{�ɕK�v�ƂȂ鎞�Ԃ̔z�����i���j�x�Ɋ�Â��܂��B�Ȃ��A�u�S�d�����ԁv�ɂ͌��������̎��Ԃ݂̂��w���̂ł͂Ȃ��A���u�t��w���̎����⏕�A�@�퐮�����̋��瓙�̋Ɩ��ɏ]�����鎞�Ԃ��܂߂������I�ȑS�d�����Ԃ��w���܂��B
�@�Ȃ��A�G�t�H�[�g�͓K�ɊǗ�����K�v������܂��B
�p�P�X�@�i�r�s�N�ƌ������ɑ��āg�G�t�H�[�g�̂U���ȏ���[�Ă邱�Ɓh�Ƃ͂ǂ̂悤�ȈӖ����B
�`�P�X�@�g�G�t�H�[�g�̂U���ȏ���[�Ă邱�Ɓh�Ƃ́A�{���Ƃ̌����J���Ɩ��ɏ]�����鎞�Ԃ��G�t�H�[�g�̂U���i60���j�ȏ�m�ۂ��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�u�S�d�����ԁv�̎c��S���i40���j�ɁA���ɑ����x���Ŏ��{���̌��������̎��Ԃ��܂߂�ꍇ�A�{���ƂƂ̏d���̓K�ۂɂ��Ă��ꂼ��̋@�ւɖ₢���킹��K�v������܂��B�����x���ɂ��ꂩ��\������ꍇ�����l�ł��B
�@�Ȃ��A�R���ł́A�{���Ƃɏ[�Ă�G�t�H�[�g������茤���҂̋N�ƈӗ~��������w�W�Ƃ��čl�����܂��B
�p�Q�O�@�w���͐\���ł���̂��B�܂��A�Q���ł��邩�B
�`�Q�O�@���厞�_�ł͔��m�ے�����݊w���ł���A���m�̊w�ʂ��擾�����҂ɑ�������\�͂�L����ƔF�߂��A�����J���J�n�܂łɑފw�������͋x�w����Ȃǂɂ��A�i�r�s�N�ƌ������Ƃ��Ė{���Ƃɐ�O�ł�����������҂ł���ΑΏۂƂȂ�܂��B���̏ꍇ�A����\�����ɕ����Ďw�������̐��E�����o���������܂��B�Ȃ��A�{���Ƃł́A�i�r�s�N�ƌ������̐l������S�T�O���~���x�^�N��z�肵�Ă���܂����A���m�ے�����ɍݐЂ��Ȃ���Q������ꍇ�́A��w���̋K��ɑ������z�Ƃ��Ă��������B
�@�܂��A�i�r�s�N�ƌ������Ɠ�����w���ɏ������锎�m����ے��̊w���ł���A�i�r�s�N�ƌ������̌����J�������T�|�[�g�����C�̃��T�[�`�A�V�X�^���g�i�q�`�j�Ƃ��ĎQ�����邱�Ƃ��ł��܂��B�{���Ƃł́A�w���̋N�ƈӗ~�����コ����Ƃ����ϓ_���A�q�`�ƂȂ锎�m����ے��̊w���̎Q���𐄏����܂��B
�@�Ȃ��A�K�v�ɉ����Ċw�������C�Ƃ��ĎQ�����A���̊w���ɑ��ĎӋ����x�������Ƃ��ł��܂��B
�p�Q�P�@�O���ŋN�ƁE�V��Аݗ����Ă��悢���B
�`�Q�P�@�{���Ƃł́A�n�o���ꂽ�x���`���[��ʂ��đ�w���̌������ʂ̓��{�Љ�E�o�ςւ̊Ҍ���}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���܂��̂ŁA���{�����ł̋N�ƂƂ��Ă��������B
�p�Q�Q�@�O���l�͐\���ł���̂��B�܂��A�{���Ɩ��̉p��́H
�`�Q�Q�@��茤���҂́A�����J�����Ԓ��͓��{�����ɋ��Z���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A���{�����ł̋N�Ƃ������Ƃ��Ă��܂��̂ŁA���{��ł̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�L���Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ�܂��B�����̗v�������A��w���ɏ�������҂ł���A�\�����邱�Ƃ͍����x������܂���B�������A�N�Ƃɂ����Ă͍ݗ����i�̕ύX�Ȃǂ��K�v�ȏꍇ������܂��̂ŁA�N�Ǝx���g�D�ɂ����ď\���Ɍ����̂����\�����Ă��������B
�@�Ȃ��A�{���Ɩ��̉p��͈ȉ��̒ʂ�ɂȂ�܂��B
�@Science and Engineering Entrepreneurship Development program for Vigorous researchers�iSEED-V�j
�i�\�����ނ̋L�����@�j
�p�Q�R�@�\�����ނɒʂ��y�[�W��t�����ƂƂȂ��Ă��邪�A�ǂ̗l������ǂ̗l���܂Ńy�[�W��t���̂��B
�`�Q�R�@�u�l���P�v����u�l���W�v�܂ł̊e�y�[�W�̉������ɒʂ��y�[�W���L�����Ă��������B
�p�Q�S�@�e�l���ɂ��ċL�����闓���������̂ŁA�t�H�[�}�b�g��ύX���Ă��悢���B
�`�Q�S�@�l���̃t�H�[�}�b�g�͕ύX���Ȃ��ł��������B�e�l���ɐ����������L�ڂ���Ă���܂��̂ŁA���͈̔͂ł���y�[�W�̑����͉\�ł��B
�p�Q�T�@�e�l���̗��O�́i���j�����́A���ލ쐬�̍ہA�폜���Ă��悢���B
�`�Q�T�@�����x������܂���B
�p�Q�U�@�u����\�����v�i�l���P�j���́u�i�r�s�N�ƌ������v�u�N�Ǝx���S���ҁv�̘A����́A�ǂ̂悤�ɂ���悢�̂��B
�`�Q�U�@��茤���ҋy�ыN�Ǝx���S���҂֎����A������ہA�����P�O���O�O���`�P�V���R�O���̊ԂɁA�d�b�AFAX�A�d���[�����ł̑Ή����\�ȘA������L�����Ă��������B
�p�Q�V�@�����J���̓��e���画�f���āu�ϗ��ʂւ̔z���v�i�l���R�j�͖��W�ȏꍇ�ł��L�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B
�`�Q�V�@���W�ȏꍇ�͂��̎|���L�����Ă��������B
�p�Q�W�@�u�i�r�s�N�ƌ������f�[�^�v�i�l���T�j�A�u�N�Ǝx���S���҃f�[�^�v�i�l���U�j�A�u���T�[�`�A�V�X�^���g�i�q�`�j�f�[�^�v�i�l���V�j�u���S�J���҃f�[�^�v�i�l���W�j�́A�S�Ă̎҂ɂ��č쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B
�`�Q�W�@����̏ꍇ�������A�i�r�s�N�ƌ������A�N�Ǝx���S���ҁA���T�[�`�A�V�X�^���g�i�q�`�j�y�ѕ��S�J���҂̑S�Ă̎Q��҂ɂ��č쐬���Ă��������B
�i�\�����ނ̍쐬�E��o���j
�p�Q�X�@�\���l�����_�E�����[�h�ł��Ȃ����ǂ�������悢���B
�`�Q�X�@�Ȋw�Z�p�U���@�\�@�헪�I�C�m�x�[�V�������i���@��w���x���`���[�E���x���`���[�S���ɂ��A��������A�d���[�����ɂĐ\���l���������肵�܂��B
�p�R�O�@�\�����ނ̒�o��A�L�ړ��e�ɕύX���������̂ŏC�����������ǂ�����������B
�`�R�O
�i�d�q�\���j
�@�{�ȋ��ʌ����J���Ǘ��V�X�e���ie-Rad�j�ɂ��d�q�\���ɂ����āA�u�z���@�֎�t���v�ƂȂ����ꍇ�́A�C���͂ł��܂���B�Ȃ��Ae-Rad�ɂ��d�q�\���A�\�����ނ̒�o���@���̏ڍׂɂ��ẮA���V�X�e���̌����җp�}�j���A�������Q�Ƃ��������B
���̃}�j���A���́A���L�z�[���y�[�W�́u�����Ҍ����y�[�W�v���_�E�����[�h�ł��܂��B
http://www.e-rad.go.jp/
�i�X�����ށj
�@��o���ԏI����̐\�����ނ̍����ւ��́A�ł����f�肵�܂��B
�p�R�P�@���ڎ��Q����o���邱�Ƃ͉\���B�܂��d�q���[���A�e�`�w�ɂ���o�͉\���B
�`�R�P�@�\�����ނ̒�o�́A�{�ȋ��ʌ����J���Ǘ��V�X�e���ie-Rad�j�Ɍ����Ă��܂��B���Q�AFAX���͓d�q���[���ɂ���o�͎t���܂���B�Ȃ��A�X�����K�v�ȏ��ނ́u�ȈՏ����v�܂��͑�z�ցi�o�C�N�֊܂ށj�Œ�o���Ă��������B
�p�R�Q�@�\�����ނ̎�̏��͂��炦��̂��B
�`�R�Q�@�\�����ނ̎�̏��͂���܂��A�{�ȋ��ʌ����J���Ǘ��V�X�e���ie-Rad�j��ł̃X�e�[�^�X���u�z���@�֎�t���v�ƂȂ��Ă���A�m���Ɏ��ꂽ���ƂɂȂ�܂��B
�p�R�R�@�\�����ނ̏��������킩��Ȃ��̂ŁA���ڕ����ɍs���Ă��悢���B
�`�R�R�@���ځAJST�ɂ��z�������������Ƃ́A���������������B�����ⓙ�ɂ��ẮA�Q�S�y�[�W�ɋL�ڂ��Ă���܂����[���AFAX���͓d�b�ɂ�肨�肢���܂��B
�i�R���j
�p�R�S�@�R���̌o�߂������Ă��炦��̂��B
�`�R�S�@�R���ɂ��ẮA�������̊ϓ_�������J�ōs���܂��B�܂��A�R���o�߂ɂ��Ă̖₢���킹���ɂ͉������܂���̂ŁA���炩���߂��������������B
�p�R�T�@�ʐڐR���̓����͌��܂��Ă���̂��B�ʐڐR�����邩�ǂ����̘A���́A��������̂��B
�`�R�T�@�ʐڐR���̓����́A�����_�ł͖���ł��B�܂��A�ʐڐR���͕K�v�ɉ����Ď��{����邱�ƂƂȂ��Ă���A�Ώێ҂݂̂ɒʒm����邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B
�p�R�U�@�ʐڐR���́A�i�r�s�N�ƌ������ƂȂ��茤���҂ƋN�Ǝx���g�D���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B���̎Q���҂ł͂��߂Ȃ̂��B
�`�R�U�@�ʐڐR���́A��茤���ҋy�ыN�Ǝx���g�D���Ȃ���Ȃ�܂���B�N�Ǝx���g�D�ɂ��ẮA�\���Ȑ������\�ł���A�K�������ӔC�҂ł͂Ȃ��S���҂ł����\�ł��B
�i�����J���̎��{���j
�p�R�V�@�����J�����Ԓ��̎��앨�̔Еz�͉\���B
�`�R�V�@���[�U�[�ɕ]�����Ă��炤���߂ɁA���앨��Еz���邱�Ƃ͉\�ł����A�`�Ԃɂ��Ă͗\�߂i�r�s�ɂ����k���������B
�p�R�W�@�����J�����Ԓ��̓������̏o��A�ێ��A�ۑS��p���͂ǂ��Ȃ邩�B
�`�R�W�@�{�����J�����Ԃɂ����錤�����ʂɊ�Â����V�K�����̏o��E�o�^�E�ێ��E�ۑS�ɕK�v�Ȕ�p�́A�����Ƃ��ĊԐڌo���x�o���Ă��������B�܂��A���L������w�ɋA�����Ă�������ɂ��ẮA�i�r�s���^�c����u�����o��x�����x�v�i���j�����p�ł��܂��̂ŁA�����k���������B
�@�Ȃ��A�������̈ێ���p��{���Ƃ̌o���x�o���邱�Ƃ͏o���܂���B
�@�܂��A�N�ƌ�̎��Ɖ^�c�ɕK�v�ƂȂ錴�����E�V�����̏��n�A���{�������Ɋւ��Ă͐V��Ђƌ����ۗL�҂Ƃ̊ԂŒ��������_��Ɋ�Â��ʓr�Ώ����Ă��������܂��B
�p�R�X�@�����o��O�ٗ̕��m�ւ̑��k��p�͎x�o�ł���̂��B
�`�R�X�@�ʏ�A���k��p�͏o���p�Ɋ܂܂�܂��̂ŁA�Ԑڌo���x�o���邱�ƂɂȂ�܂��B�������A���������̔�p�́A�N�ƂɌ����������̈�Ƃ��āA���ڌo��u���̑��v����x�o�ł��܂��B
�p�S�O�@�����J�����Ԃ̓r���ŋN�Ƃ����ꍇ�A�p�����Ďx��������̂��B
�`�S�O�@�����J�����Ԓ��ɋN�Ƃ����ꍇ�A�e��̐���������܂��̂ŁA���O��JST�ɑ��k���Ă��������B
�i�o��j
�p�S�P�@���ڌo��͂P�疜�~���x�Ƃ��邪�A�P�疜�~���Đ\�����邱�Ƃ͉\���B
�`�S�P�@�P�疜�~�͖ړr�ł��̂ŁA������e�ɑ��ēK�ł��������Đ\�����邱�Ƃ͉\�ł��B�������A�̑����ɉ�����e�Ⓖ�ڌo��̊z�������Ă����������Ƃ͂��蓾�܂��B
�p�S�Q�@�����J�����Ԃ��S�N�ȏ�ł��悢���B�܂��A�����J�����Ԃ̉����͂ł��邩�B
�`�S�Q�@�����J�����Ԃ͕����Q�P�N�x���n���Ƃ���Œ��R�N�x�ł��B
�p�S�R�@�Ԑڌo��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��Y������̂��B
�`�S�R�@�Ԑڌo��́A�{���Ƃ��l�����������҂̌������̉��P�⌤���@�֑S�̂̋@�\�̌���Ɋ��p���邽�߂ɕK�v�ƂȂ�o��ɏ[�����Ă��������B��̓I�ɂ́A�{���Ƃ̌����̐��s�Ɋ֘A���ĊԐړI�ɕK�v�ƂȂ�o��̂����A�ȉ��̂��̂�ΏۂƂ��܂��B
�P�j�Ǘ�����ɌW��o��
�|�{�݊Ǘ��E�ݔ��̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|�Ǘ������̕K�v�o��
���i�w����A���Օi��A�@��ؗ��A�G��A�l����A�ʐM�^����A�Ӌ��A�����O����A��c��A�����
��
�Q�j��������ɌW��o��
�|���ʓI�Ɏg�p����镨�i���ɌW��o��
���i�w����A���Օi��A�@��ؗ��A�G��A�l����A�ʐM�^����A�Ӌ��A�����O����A��c��A�����A�V���E�G����A���M����
�|���Y�����̉��p���ɂ�錤�������̐��i�ɌW��K�v�o��
�@�����ҁE�����x���ғ��̐l����A���i�w����A���Օi��A�@��ؗ��A�G��A�ʐM�^����A�Ӌ��A�����O����A��c��A�����A�V���E�G����A���M����
�|�����֘A�o��
�|�������̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|���������Ǘ��{�݂̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|�����Ҍ𗬎{�݂̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|�ݔ��̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|�l�b�g���[�N�̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|��^�v�Z�@�i�X�p�R�����܂ށj�̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|��^�v�Z�@���̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|�}���ق̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
�|�ُ�̐����A�ێ��y�щ^�c�o��
��
�R�j���̑��̊֘A���鎖�ƕ���ɌW��o��
�|�������ʓW�J���ƂɌW��o��
�|�L�ƂɌW��o��
��
���̂ق��A�@�ւ̒��������ۑ�̐��s�Ɋ֘A���ĊԐړI�ɕK�v�Ɣ��f����o��ΏۂƂȂ�܂����A���ڌo��Ƃ��ď[�����ׂ����̂͑ΏۊO�Ƃ��܂��B
�p�S�S�@�\�t�g�E�G�A�̊J����ړI�Ƃ��Ă��邪�A�Ĉϑ�������J����̂قƂ�ǂ��߂邪�悢���B
�`�S�S�@�ΏۂƂȂ�Ĉϑ���́A�����Ƃ��āA�e�N�x�̐\���z�̂T�O�����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�p�S�T�@���S�J���҂ɐl��������Ƃ͂ł��邩
�`�S�T�@�{���Ƃł͕��S�J���҂ւ̐l����͎x�o�ł��܂���B
�`�S�U�@�i�r�s�N�ƌ��������K�v�Ƃ����ꍇ�A�����J����̒�����Ӌ����Ƃ��ă|�X�h�N��w���ɐl��������Ƃ͂ł��܂��B
�@�܂��A���̏����������m�ے�����̊w���ł���A��C�̃��T�[�`�A�V�X�^���g�i�q�`�j�Ƃ��ĎQ���ł��܂��B�P�ۑ蓖��A�q�`�͂P���܂ł������Ƃ��܂��B
����C�̂q�`�Ƃ��Ă̌ٗp�E�Ϗ��̏�����
�E�����J���]�����ԁi���������̊w���ւ̎w����u�`��u���̎��Ԃ͏����j�̑S�Ă�{���Ƃ̌����J���ɏ[�Ă邱�Ɓi�u��C�v�ł��邱�Ƃ̒�`�j�B
�E�l����́A�����@�ւ̋K��ɏ����������̂ł��邱�ƁB���̌`�Ԃ͌ٗp�i���^�̎x�����j�������͈Ϗ��i�Ӌ��̎x�����j�̂�����ł��\��Ȃ��B
�E�l����́A��������z���x�Ƃ��ĔN�ԂQ�O�O���~��ڈ��Ƃ��A�N�ԂP�W�O���~�������Ȃ��z�ł��邱�Ɓi���̊z�͌l���S�̎Љ�ی����y�ѐŋ��̍T���O�̂��̂ł���j�B�Ȃ��A�Љ�ی��̎��Ǝ啉�S���͂��̊z�̘g�O�ł���B
�E��C����҂ɐ�������z���x���x�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��邽�߁A���w����A���o�C�g��ȂǑ��̎���������҂ɂ��Ă͉ߓx�̎x���ƂȂ邱�Ƃ���ΏۂƂ��Ȃ��B
�E���̐l����͖{���ƂƂ��Ă̗\�Z�ł���A�w�Ƃ��̂��̂�{���ƈȊO�̌�����Ɋւ�銈���Ȃǂɑ���l����[���͖ړI�O�i�s���j�g�p�Ƃ݂Ȃ����ꍇ������̂Œ��ӂ��K�v�ł���B
���@���m�ے��i����j�̊w����
���C�̂q�`�Ƃ��Čٗp�E�Ϗ����邱�Ƃ��\�ł��B
�p�S�V�@�u���{�v�揑�v�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��B
�`�S�V�@�{�N�x���{�\��̌����J���y�ыN�Ƃ̂��߂̋Ɩ����e����̓I�Ɏ��܂Ƃ߂����̂ŁA�ȉ��̍��ڂ��܂ނ��̂ł��B�ڍׂ͍̑��ۑ茈���ɐ��������Ă��������܂��B
�@�ʋƖ��̐���
�@���{���ځA���{���e�A���{���@�A���{�ꏊ�A���ʖڕW��
�A���{�v�����
�B���{�̐�
�O���A�Ĉϑ����̑����͊W���܂�
�C�l����i�i�r�s�N�ƌ������A�q�`�j�A�����J���o��i�N�Ǝx���o��܂ށj�g�p�̖���
�D���̑�
�i�����J����̌o���Ǘ��j
�p�S�W�@������̌����J���v��𗧂Ă�悢�̂��B
�`�S�W�@�����J���J�n�����́A�W���P���Ɖ��肵�āA�����J���̐��s�ɕK�v�Ȋz���L�����Ă��������B
�p�S�X�@�����J����́A�N�x���z���Ďg�p���邱�Ƃ͂ł��邩�B
�`�S�X�@�����Ƃ��āA���̌����J����̎g�p�́A���̉�v�N�x�i�S���P���`���N�R���R�P���j���ɏI���Ă����������Ƃ��O��ł��B
�p�T�O�@�o��ԁi�x�o��ڊԁj�̗��p�͂ł��邩�B
�`�T�O�@�����J����ɂ��ẮA���ڌo��̂T�O���ȓ��ł���Η��p�͉\�ł��B�A���A��C�q�`�ւ̌ٗp��A�Ϗ���ɂ��Ă͐�������z���x���蓖�Ă��邱�Ƃ���|�Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A�P�N�ԂɊ��Z���ĂP�W�O���~������邱�Ƃ͂ł��܂��� �B
�@�N�Ǝx���Ɩ���ɂ��ẮA�_����z�i���ڌo��j�̊e��ڂ̗\�Z�̂R�O���i�e��ڂ̗\�Z�̂R�O�����T�O���~�ȓ��ł���T�O���~�j�ȓ��̊z�ł���A�x�o��ڊԂ̗��p���\�ł��B
�p�T�P�@���S�J���҂Ɍ�����i�{�l�̐l����͕s�܁j���o���邩�B
�`�T�P�@���S�J���҂͂i�r�s�N�ƌ������Ɠ���̑�w���ɏ������Ă���҂łȂ���Ȃ�܂���B���̏�ŁA�i�r�s�N�ƌ������̔��f�ƁA�i�r�s�N�ƌ������̏����@�ւ̏��F�̂��ƂŌ�������x�o���邱�Ƃ��ł��܂��B
�p�T�Q�@�N�Ǝx���o���Ĉϑ�����o���邩�B
�`�T�Q�@�N�Ǝx���̈ꕔ���O���@�ւɈϑ����邱�Ƃ͉\�ł��B�A���A�s�꒲���A�����������̔�p�͂i�r�s�N�ƌ������̔��f�Ō����J�����x�o����悤�ɂ��Ă��������B
�i�t�H���[�A�b�v�E�]���j
�p�T�R�@�����J���̐i�����̕��̒�o�����A�`�ԓ��ɂ��ẮA�����A��������̂��B
�`�T�R�@�����J�����Ԓ��̖��N�x�A�O���L���ҁA�o�c�y�тo�n�ɂ��t�H���[�A�b�v�y�ѕ]�������{����܂��B���̂��߁A�i�r�s�N�ƌ������y�я����@�ւ́A�����J���̐i���i�����J�����ʁj�y�ђ��������J����p�̎x�o�i�g�p���ʁj���ɂ��Ă̕����A�y�ыN�Ǝx���S���҂͎x���Ɩ��̐i�����A�����J�����Ԓ��ɖ��N�x��o���Ȃ���Ȃ�܂���B�����̕��̒�o�����y�ь`�ԓ��ɂ��ẮA�̑���̎�������������Ő����v���܂��B
�p�T�S�@�o�c�y�тo�n�̈ʒu�t���y�і����͉����B
�`�T�S�@�o�c�y�тo�n�Ƃ́A�����I�������x�ɂ�����{���Ƃ�K�����~���Ɏ��{���邽�߂ɁA�i�r�s�̔z�u����O���L���ғ��ō\������錤���J���^�c�E�x���g�D�̊j�ƂȂ�A�{���Ƃ̓K�ȉ^�c�A�ۑ�̐R���E�]���E�t�H���[�A�b�v���̈�A�̋Ɩ��̐��s�Ǝ��܂Ƃ߂��s���܂��B�Z�p�E�N�Ƃ̗��ʂ���\���҂����{���錤���J���������x�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ������x�ł��B�Ȃ��A�o�n�͖{���Ƃ̉^�c�A�ۑ�̐R���E�]���E�t�H���[�A�b�v���̎��܂Ƃ߂��s���܂��B
�p�T�T�@�����J�����Ԃ̏I����ɒB������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͉����B
�`�T�T�@���̎��Ƃɂăx���`���[��Ƃ̑n�o�Ɏ����錤���J�����ʂ�Ƌ��ɁA�i�r�s�N�ƌ��������N�ƉƂƂ��ĕK�v�Ȏ����E�\�͂��K�����A�\�����ނɋL�ڂ��ꂽ�ړI�E�ڕW��B�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@��̓I�ɂ́A�N�ƂɎ��邱�ƁA���邢�͋N�Ƃ��������I�����ʓI�Ȏ�i�������o���ꂽ�ꍇ�͂��̎�i�Ŋ�Ɖ����邱�ƁA��Ɖ��Ɍ����đ����x���łi�r�s�N�ƌ������������J�����p�����邱�Ƃł��B
���Ⴆ�A�u�s�����̊O�I���̉e���Ŏ������B������ƂȂ�A�N�Ƃ�������A�����̊�Ƃ̌o�c������̘H�𗘗p���Ăi�r�s�N�ƌ���������Ɖ���}����������I�����ʓI�Ƃ݂Ȃ����ꍇ�v�Ȃǂ��z�肳��܂��B
�i�����҂̔��蓙�j
�p�T�U�@�����J�����Ԓ��̔������o�肷��ꍇ�A�����҂̔���͂ǂ̂悤�ɂ��čs���̂��B
�`�T�U�@���ۂɔ����Ɋ֗^�����҂������҂ƂȂ邱�Ƃ������Ƃ��܂��B���������҂�����ꍇ�́A�����҂̔���y�т��̊�^���ɂ��ē����ҊԂŋ��c�̂����i�r�s�N�ƌ������ɔ��f���Ă��������܂��B
�i�����J�����ʓ��̕y�є��\�j
�p�T�V�@�����J�����ʂɂ��ĕ����쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�A����͂����B
�`�T�V�@���̎��Ƃɂ�蓾��ꂽ�������ʋy�ђ��������J����̎x�o�ɂ��ẮA���N�x�y�ь����J���I���㑬�₩�ɁA�K�v�ȕ��s��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�Ȃ��i�r�s�́A�̂��������ʂ��A�i�r�s�N�ƌ������̏����Č��\�ł�����̂Ƃ��܂��B
�p�T�W�@�����J�����ʂ̌��\�ł́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B
�`�T�W�@�����J���I����ɁA����ꂽ�����J�����ʂ��A�K�v�ɉ����A�N�ƂɎx��̂Ȃ��͈͓��Ŕ��\���Ă����������Ƃ�����܂��B
�p�T�X�@�V���A�}���A�G���_�����Ɍ����J�����ʂ\����ꍇ�A���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͉����B
�`�T�X�@���O�ɂi�r�s�ɒʒm���A���\�ɂ����Ă͖{���Ƃɂ�鐬�ʂł��邱�Ƃ�K�����L���ĉ������B
�@�܂����\�ɂ������ẮA�N�ƂɎx��̂Ȃ��悤�A�����o�蓙�̉\���ɂ��Ă͎��O�ɏ\���������������A�K�v�ł���Ώo��葱���ς܂��Ă������̑Ή������肢���܂��B
�i���̑��j
�p�U�O�@�Ĉϑ���Ƃ̌_��ɐD�荞�ނׂ��v���͂��邩�B
�`�U�O�@�Ĉϑ��_��̍ۂɂ́A�m�I���Y���̋A���ƗD����{�A�擾���Y�̋A���A���`�����Ɋւ������Ƃ��Ĉϑ������J���_��i�@�ւƂi�r�s�Ƃ̌_��j�ɏ������戵�������肢���܂��B
 �@
�@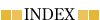 �@
�@