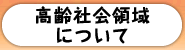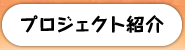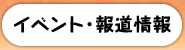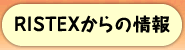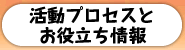ほっとコラム
人生の最終段階における意思決定をめぐる社会の動向
~お任せ医療から自己決定へ~

領域アドバイザー 袖井 孝子
お茶の水女子大学 名誉教授
1. 在宅死から病院死へ
かつての日本社会では、圧倒的多数の人が自宅で家族に見守られてその生を終え、死後は地域の人々の助けを得て、葬儀を執り行うのが普通だった。在宅死と病院死の比率が逆転するのは、1970年代半ばのこと。病院死が増加した理由は、1961年に国民皆保険制度が確立し、医療費の個人負担が軽減されたことが大きい。老人医療費の無料化(医療費の個人負担分の公費負担)が実現した1973年以降は、高齢者は自宅にいるよりも入院したほうが金がかからないために、高齢者の入院が増加した。
他方、病院側も高齢者を入院させておけば国や自治体から自動的に医療費が支払われる。長期入院する高齢患者が急増し、国民医療費が飛躍的に高騰した結果、この制度は10年後に廃止された。しかし、病気になれば入院するのが当たり前という考え方が人びと間に浸透し、命の終わりが家庭から医療機関に移り、医師の統制下におかれるようになった。
2. 医師主導型医療から患者主導型医療へ
すべてを医師に任せるというパターナリスティック(権威主義的)な医療に対する批判が高まるようになったのは、それほど旧いことではない。アメリカにおいて、生も死も医療者ではなく当事者が決めるという考え方が広く受け入れられるようになったのは1990年代以降にすぎない。とりわけ患者の自己決定権法(the Patient Self-determination Act)が施行されるようになった1991年以降は、治療方法や予想される結果およびリスクなどについて予め患者に説明し、同意を得るインフォームド・コンセントや生命の危機に瀕するような状況に陥った際に、どのような医療を受けるかあるいは拒否するかを予め文書に記しておく事前指示書が普及するようになった。
3. 自己決定能力を欠く人の意思をどう確認するか
近年、医療における患者の自己決定権を重視するという方向は、日本でもかなり受け入れられるようになった。終末期医療に関して、予め自分の希望を記しておくエンディング・ノートも多数発行されている。しかし、患者に意思決定能力を欠く場合には、どうするのかについては、今のところ明確な合意が得られてはいない。
なかでも長寿化に伴いその数を増している認知症患者の自己決定権をどこまで尊重できるのかは未解決の問題である。多くの場合、家族が決定を下しているが、家族自身、それで良かったのかと迷い悩むことが少なくない。
自己決定能力を欠く人にとって最善の利益を実現するような医療を提供するには何をなすべきか、医療者だけでなく、将来、認知症になる可能性のあるすべての人にとっても、早急に解決しなければならない大きな課題である。