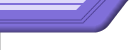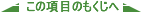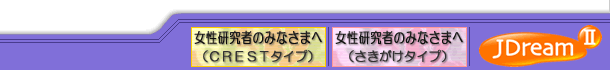○戦略目標「異分野融合による自然光エネルギー変換材料及び利用基盤技術の創出」の下の研究領域
太陽光と光電変換機能
研究総括:早瀬 修二(九州工業大学大学院生命体工学研究科 教授)
研究領域の概要
本研究領域では、次世代太陽電池の提案につながる研究を対象とします。化学、物理、電子工学等の幅広い分野の研究者の参画により
異分野融合を促進し、未来の太陽電池の実用化につながる新たな基盤技術の構築を目指します。
具体的には、色素増感系、有機薄膜系、量子ドット系高性能太陽電池の研究や、従来とは異なるアプローチによるシリコン系、
化合物系太陽電池の研究を対象とします。同時に、まったく新しい原理に基づいた太陽電池の創出につながる界面制御技術、
薄膜・結晶成長、新材料開拓、新プロセス、新デバイス構造などの要素研究も対象とします。次世代太陽電池の創出という視点を重視し、
理論研究から実用化に向けたプロセス研究にわたる広域な研究を対象とします。
研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針
太陽電池は将来のエネルギー供給源として大きく期待されています。現在シリコン系太陽電池、化合物系太陽電池が実用化され、
大きな市場を形成しつつあります。今後、更なる高効率化や原料ソースを多様化しなければならないという観点から、高効率、長寿命、
低コストを達成する次世代の太陽電池に対する期待がますます強くなってきています。現在、色素増感系、有機薄膜系、量子ドット
系太陽電池等の次世代太陽電池の実現を目指した研究が個別に行われていますが、高効率化、長寿命化、低コスト化を達成して実用化に
つなげるためには、既存の研究に斬新なアイデアを加える必要があり、また、まったく新しい原理に基づいた太陽電池の創出のためには、
理論(計算)−新材料合成―デバイス作製プロセス―新デバイス構造―デバイス解析に関する研究が融合し、一つの目的のために
結集しなければなりません。本領域では、次世代太陽電池の創出という大目的のために必要な要素研究を重視します。高効率化、長寿命化、
最適材料の探索など現在の太陽電池が直面している諸課題を、既存の研究分野・研究テーマの延長ではなく、原理に立ち返った独創的
アプローチで解決するような目的基礎研究型、課題解決型の研究を推進します。この目的を達成するために、物理、化学、電子工学、
光学、その他の多くの学問分野の研究者を結集します。さらに、異分野研究者の参入を積極的に図ることで、材料研究とデバイス物理研究の
融合、太陽電池研究と有機発光デバイス研究の融合、無機太陽電池研究と有機太陽電池研究の融合等によるインタラクティブイノベーションを目指します。
高効率化を図るためには光制御―光吸収―(エキシトン拡散)―電荷分離―電荷収集のすべての過程に高効率化が必要です。
例えば、有機系太陽電池(含色素増感太陽電池)の効率を飛躍的に高めるためには、近赤外、赤外領域の光電変換効率を飛躍的に向上する必要があり、
このためには酸化物半導体や長波長色素、有機半導体の伝導帯準位やHOMO-LUMOコントロール、電子収集ロスの少ないハイブリッド、タンデム構造の
提案、電荷収集プロセス、光閉じ込め構造の提案、およびこれらを作製するためのプロセス研究等が必要になります。電荷分離効率を上げるためには、
画期的な界面制御技術、界面解析技術、結晶化技術、新材料開拓が必要です。既に実用化されているシリコン系、化合物系太陽電池の領域においても、
高効率化のための新しい手法、例えば、界面制御技術、結晶化技術、新デバイス構造、塗布による新プロセスなどは本領域の対象とします。
さきがけは個人研究であり、若手・中堅を中心とした個人の研究者の斬新な発想と、リスクをものともしない熱意を持って太陽電池に新しい時代
を開く提案を期待し、そのような熱意を持った研究者が全く新たな次世代の太陽電池の創出という一つの目的に向かってお互いに議論しながら、
有効に結びつきながら研究できるように運営します。