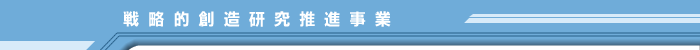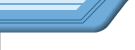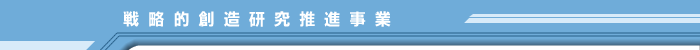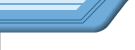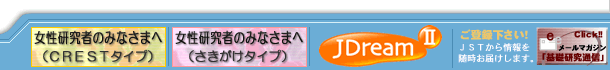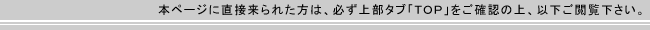
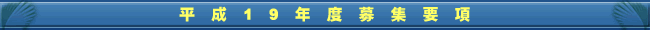 |
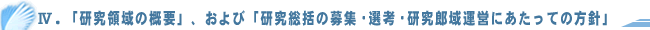 |
|
【さきがけタイプ】
○戦略目標「光の究極的及び局所的制御とその応用」の下の研究領域
 「物質と光作用」 「物質と光作用」
研究総括:筒井 哲夫(九州大学先導物質化学研究所 教授)
|
|
|
|
研究領域の概要
本研究領域は、「光機能を物質から取り出す」、「光を用いて物質の本質を調べる」、「光を用いて機能物質を創成する」という観点で、有機物、無機物、生物関連物質などの凝集体(固体、薄膜、分子集合体、液晶、ゲルなど)に対する光の作用について新しい角度から多面的に追究する研究を対象とするものです。
具体的には、物質が演出する多様な電子状態と光との相互作用に関係する化学と物理を対象とします。それらを応用した将来の革新的なフォトニクス・エレクトロニクス技術につながる光機能材料・電子機能材料の創出、光デバイス・電子デバイスの原理探索や作製技術確立、生物関連物質の利用技術開拓、超高純度物質の合成とその物性計測、デバイス応用のための利用環境下での物質の安定性と信頼性の追求などの研究も含まれます。
|
|
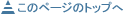
|
|
研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針
有機物、無機物、生物関連物質などは、数ミリエレクトロンボルトから数エレクトロンボルトにわたる束縛エネルギーに支配されて、単一分子から、各種分子集合体、酵素、生体膜、などに至るまで階層性を持った多様な凝集体を形成している。一方光は紫外から赤外までの波長において、まさに同じエネルギー領域でこれらに作用し、多種多様な現象が観測され、また豊富な機能が生み出されます。このような物質と光作用に由来する現象の本質的な理解と機能の開拓は、21世紀の環境共生型科学技術の一つとしての革新的なフォトニクス・エレクトロニクス技術の創出につながるものです。
物質が演出する多様な電子状態と光との相互作用には、例えば、光化学反応、光電子移動、光電変換、光の発生・検出・変調、光による構造形成や形態変化などがあります。このような諸現象をフォトニクス・エレクトロニクス技術として結実させるためには、物質の構造物性並びに発現する現象の本質的な理解が不可欠です。また、工学的な利用を念頭におくならば、システムの簡潔さ、発現する機能の安定性と高い効率性も忘れてはならない要素です。
本領域では、さまざまな分野の若手を中心とした個人の独創的な発想に基づいたこれまでにない研究を対象としますが、単なる新奇な思いつきではなく、長期的な視野での光関連科学技術の発展につながる基礎的で深みのある研究提案を期待します。また化学者と物理学者、物質創成専門研究者と構造物性専門研究者、物性研究者とデバイス応用研究者のような、異なる専門分野の相補的協力関係が、本領域における研究実践の中から生まれることも大いに期待しています。
|
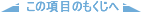 |