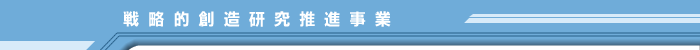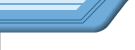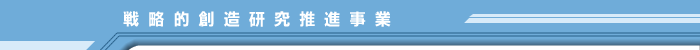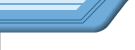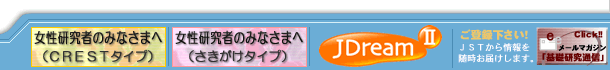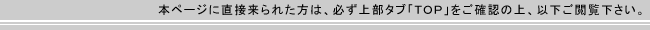
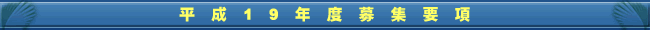 |
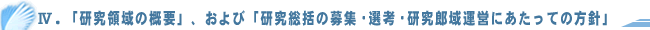 |
|
【さきがけタイプ】
○戦略目標「プログラムされたビルドアップ型ナノ構造の構築と機能の探索」の下の研究領域
 「構造制御と機能」 「構造制御と機能」
研究総括:岡本 佳男(名古屋大学エコトピア科学研究所 客員教授)
|
|
|
|
研究領域の概要
この研究領域は、ナノサイズの材料や構造を、原子・分子レベルでの制御を基礎に造り上げる科学技術に、これまでにない新しい考え方や手法を導入し、欲しい構造を欲しいタイミングで欲しい場所に積み上げて造ることを目指す挑戦的な研究を対象とするものです。
例えば、原子・分子レベルでの制御によりナノサイズの物質、組織、空間などを創製し、必要な分子構造、空間構造、テンプレート構造、デバイス構造などを、様々なスケールで起こる現象と結びつけて設計し構築するプロセス、およびその応用を目指した機能探索などの研究が含まれます。
|
|
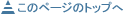
|
|
研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針
ナノサイズの材料や構造を制御して構築するための研究は、従来の材料科学でも広く行われてきました。しかし、「欲しいものを、欲しいタイミングで、欲しい場所に」構築し、新しい機能を得るという意味においては体系化された技術はほとんどみられません。また、原子や分子が実用的なスケールの構造体まで「階層を越えて」組織化し、機能を発現させる手法の重要性は、今後ますます高まることでしょう。
そこで、この領域では「プログラムされた」及び「ビルドアップ型」という概念を意識した独創的な研究提案を募ります。「プログラム」とは、「欲しいものを、欲しいタイミングで、欲しい場所に」構築するための原理を指します。また、「ビルドアップ型」とは、構造体の形成手法のうち、原子や分子を積み上げて構築していくタイプのものを意味します。
ビルドアップ型ナノテクノロジーの難しさは、分子や原子、あるいはその原子や分子を組織化してナノ構造体を構築する基板に対して人間の意図を伝え、実用的なアウトプットを得るプロセスの体系化にあります。この体系化は、一朝一夕にできるものではありません。分子や原子の相互作用の研究も必要ですし、そのナノ構造を構築する基板に情報を付与する研究も必要です。理論的な考察も必要でしょう。
こうした様々なアプローチの中にある独創的なアイデアに飛躍の機会を提供することで、ナノ構造の構築とその機能発現につながる技術の多様性を確保し、将来体系化された技術となりうる新しい技術の芽を見いだすことをこの領域設定の目的とします。独創性のポイントは、ナノ構造の構築手法でも、構築したものから発現する機能であっても構いませんが、ナノ構造の構築プロセスの制御が、系の特性に本質的な影響を及ぼすものを対象とします。研究で掘り下げる部分は限定されていても、その研究が、ナノスケールから実用的なスケールまで、様々なスケールで起こる現象を結びつける連続的なプロセスを意識した視野の広い研究提案を期待します。多様性確保の観点から、リスクの高いチャレンジングな研究を積極的に採択したいと思います。 |
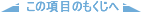 |