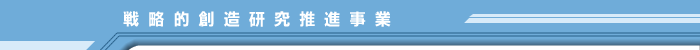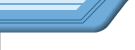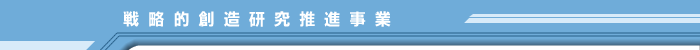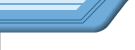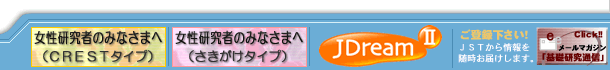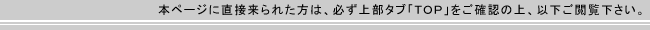
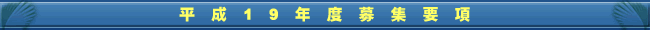 |
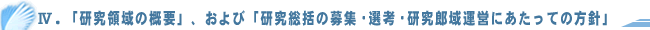 |
|
【CRESTタイプ】
○戦略目標「異種材料・異種物質状態間の高機能接合界面を実現する革新的ナノ界面技術の創出とその応用」の下の研究領域
 「ナノ界面技術の基盤構築」 「ナノ界面技術の基盤構築」
研究総括:新海 征治 (九州大学大学院工学研究院応用化学部門 教授)
|
|
|
|
研究領域の概要
本研究領域は、異種材料・異種物質状態間の界面をナノスケールの視点で扱う研究分野が集結することによりナノ界面機能に関する横断的な知識を獲得するとともに、これを基盤としたナノレベルでの理論解析や構造制御により飛躍的な高機能を有する革新的材料、デバイス、技術の創出を目指すものです。
具体的な研究対象としては、エレクトロニクス、エネルギー変換用デバイスにおける有機材料と金属・半導体などとの界面、環境浄化触媒や機能制御膜などにおける表面・界面、ナノバイオ医療用の生体材料と人工物との界面などが対象となります。さらには、物質・材料の生成プロセスを利用した、または、ソフト構造体を鋳型とした無機系物質のナノ構造体の創製なども機能界面の利用という視点で研究対象に含まれます。また、ナノスケール材料の生体安全性に関する知見の蓄積、例えば、ナノ粒子の細胞膜上での挙動なども主要な研究の方向性の一つです。
|
|
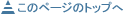
|
|
研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針
本領域で実施する研究における界面(表面)の定義としては、一般的な材料間、物質状態間の2次元界面(表面)のみには限定せず、0次元(ナノ粒子、ベシクル、細胞表面など)、1次元(ナノチューブ、分子集合型ナノファイバーなど)、3次元(多孔質結晶の空孔など)などの超構造体が提供する界面(表面)も対象とします。また、革新的なナノ界面材料やデバイスの創製に直接関わる研究だけではなく、これに資する理論計算やシミュレーション解析、分析・計測についても募集対象とします。
ただし、界面におけるナノレベルの原子・分子の精密操作・微細加工など装置開発を主目的とする研究は原則として募集対象とはしません。これは同時期に設定されている他の類似プログラムとの重複を避けることを考慮したためです。
平成18年度は、金属固体表面、有機−無機ハイブリッドなどの界面現象や界面機能に関する課題が主として採択されました。これに対して有機材料およびバイオ材料に関する課題は一件も採択に至りませんでした。この主たる原因はこれらの分野からの申請の"質"そのものが劣っていたためではなく、「"界面"において生み出される現象や機能は何か」というCREST課題の本質に迫る申請がなかったからです。
平成19年度も「ナノ界面」をキーワードとして無機、有機、高分子、超分子、コロイドなどの幅広い分野からの申請を期待しています。異分野間での研究交流や共同研究を活発化させる目的から、今年度は「ナノ界面」の要素を巧みに取り込んだ強力な申請が「有機材料およびバイオ材料」分野からも出ることを期待しています。
|
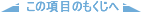 |