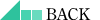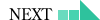公募受付締め切り日 平成20年4月18日(金)17時
5.審査
この事業では、段階的選抜方式により、一次選抜及び二次選抜を実施します。(一次選抜(事前審査)を通過した課題に対しては、約一年間の活動実績に基づく二次選抜が実施されます。)二次選抜では、一次選抜を通過した課題の研究開発の進捗状況やその成果等を基に選抜評価を実施し、評価の高い課題から順番に選抜します。JSTは、選抜された課題に支援を集中します。選抜された課題は、引き続きJSTの支援の下、質の高い大学発ベンチャーの起業に向けて、研究開発及び起業準備を遂行してください。
(2) 審査の方法
申請内容等の審査は、外部有識者により実施されます。
申請者から提出された申請書類等の内容についてPD・POおよび外部有識者(学識経験者、産業界、ベンチャービジネスの経験者等)を活用して選抜評価(書類審査及び必要に応じ面接審査)を行い、それらの評価結果を基に、PD・POが取りまとめを行い本事業の目的に照らして優秀と認められる採択候補課題を選定します。
なお、審査は非公開で行われますが、申請課題との利害関係者は、当該課題の審査から排除されることになっています。
また、評価者として審査に携わる有識者は、審査の過程で取得した一切の情報を、評価者の職にある期間だけでなく、その職を退いた後についても第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義務をもって管理すること等の秘密保持を遵守することが義務づけられています。
審査の経過は通知いたしませんし、お問い合わせにも応じられません。
申請内容等の審査は、外部有識者により実施されます。
申請者から提出された申請書類等の内容についてPD・POおよび外部有識者(学識経験者、産業界、ベンチャービジネスの経験者等)を活用して選抜評価(書類審査及び必要に応じ面接審査)を行い、それらの評価結果を基に、PD・POが取りまとめを行い本事業の目的に照らして優秀と認められる採択候補課題を選定します。
なお、審査は非公開で行われますが、申請課題との利害関係者は、当該課題の審査から排除されることになっています。
また、評価者として審査に携わる有識者は、審査の過程で取得した一切の情報を、評価者の職にある期間だけでなく、その職を退いた後についても第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義務をもって管理すること等の秘密保持を遵守することが義務づけられています。
審査の経過は通知いたしませんし、お問い合わせにも応じられません。
(3)一次選抜の手順
一次選抜では、書面審査及び面接審査を次の手順により実施します。
一次選抜では、書面審査及び面接審査を次の手順により実施します。
① 形式チェック
提出された申請書類について、応募の要件(申請者の要件、申請金額、研究開発期間、重複申請の制限等)を満たしているかについてチェックします。 応募の要件を満たしていないものは、以降の審査の対象から除外されます。
提出された申請書類について、応募の要件(申請者の要件、申請金額、研究開発期間、重複申請の制限等)を満たしているかについてチェックします。 応募の要件を満たしていないものは、以降の審査の対象から除外されます。
② 書面審査
外部有識者による書面審査を実施します。書面審査を通過した申請者は面接用の追加資料を提出します。
外部有識者による書面審査を実施します。書面審査を通過した申請者は面接用の追加資料を提出します。
③ 面接審査
必要に応じて、外部有識者による申請者に対する面接審査を実施します。 なお、面接審査に出席しなかった場合は、辞退と見なされます。
必要に応じて、外部有識者による申請者に対する面接審査を実施します。 なお、面接審査に出席しなかった場合は、辞退と見なされます。
④ 最終審査
書面審査及び面接審査における評価を踏まえ、PD・POが取りまとめを行い、採択候補課題を選定します。
書面審査及び面接審査における評価を踏まえ、PD・POが取りまとめを行い、採択候補課題を選定します。
⑤ 採択課題の決定
最終審査結果を踏まえ、JSTは採択の要件確認を実施の上、採択課題を決定します。その際、採択の要件確認のために必要な下記の書類を別途提出して頂きます。
最終審査結果を踏まえ、JSTは採択の要件確認を実施の上、採択課題を決定します。その際、採択の要件確認のために必要な下記の書類を別途提出して頂きます。
・起業家及び分担開発者の本事業への参加同意書(所属機関の発行する同意文書。開発代表者と異なる所属機関に所属している場合にのみご提出いただきます)
・側面支援担当者の本事業への参加同意書(所属機関の発行する同意文書)
・本申請課題が他制度による助成対象課題と重複していないことの説明書
・原権利の実施許諾同意書(原権利保有者の発行する同意文書)
(4)一次選抜の観点
一次選抜(形式チェックを除く。)では、提案された課題の研究開発成果の内容が実用化され、大学発ベンチャーを起業できる内容となっているかどうかを技術面及び起業面から審査します。選抜の観点は、以下のとおりです。
一次選抜(形式チェックを除く。)では、提案された課題の研究開発成果の内容が実用化され、大学発ベンチャーを起業できる内容となっているかどうかを技術面及び起業面から審査します。選抜の観点は、以下のとおりです。
① 書面審査
a. 技術の新規性及び優位性
提案する技術に新規性があるかどうか。優位性または応用展開性があるかどうか。
提案する技術に新規性があるかどうか。優位性または応用展開性があるかどうか。
b. 技術目標とその解決策の妥当性
最終的な技術課題と目標値、解決策は妥当であるかどうか。
最終的な技術課題と目標値、解決策は妥当であるかどうか。
c. 事業化の可能性
ターゲット市場、競合者、市場動向を鑑みて、提案する製品・サービスに事業化の可能性があるかどうか。
ターゲット市場、競合者、市場動向を鑑みて、提案する製品・サービスに事業化の可能性があるかどうか。
② 面接審査
a. 技術の新規性及び優位性
提案する技術に新規性があるかどうか。優位性または応用展開性があるかどうか。
提案する技術に新規性があるかどうか。優位性または応用展開性があるかどうか。
b. 技術目標とその解決策の妥当性
最終的な、並びに1年後に達成すべき技術課題と目標値、解決策は妥当であるかどうか。また、その実施体制は整っているかどうか。
最終的な、並びに1年後に達成すべき技術課題と目標値、解決策は妥当であるかどうか。また、その実施体制は整っているかどうか。
c. 事業化の可能性
ターゲット市場、競合者、市場動向を鑑みて、提案する製品・サービスに事業化の可能性があるかどうか。
ターゲット市場、競合者、市場動向を鑑みて、提案する製品・サービスに事業化の可能性があるかどうか。
d. 業務計画の妥当性
事業化に向けての1年間のマネジメント業務計画は妥当かどうか。また、その実施体制(支援体制を含む)は整っているかどうか。
事業化に向けての1年間のマネジメント業務計画は妥当かどうか。また、その実施体制(支援体制を含む)は整っているかどうか。
(5)一次選抜の結果の通知等
① 書類審査の結果、面接審査の対象となった課題の申請者に対し、面接審査の開催要領・日程等について通知します。
② 最終審査の結果については、採否にかかわらず、申請者に通知します。
③ 採択課題については、課題名、開発代表者名、起業家、側面支援機関名をホームページ等で公表します。
(6)二次選抜の手順(予定)
二次選抜は、研究開発着手から約1年後に、次の手順により実施されます。
二次選抜は、研究開発着手から約1年後に、次の手順により実施されます。
① 事前資料の提出
面接審査の前に、1年間の進捗状況を含む成果報告を提示していただきます。この資料は、事前資料として外部有識者に提示されます。
面接審査の前に、1年間の進捗状況を含む成果報告を提示していただきます。この資料は、事前資料として外部有識者に提示されます。
② 面接審査
外部有識者による一次選抜通過者に対する面接審査を実施します。
外部有識者による一次選抜通過者に対する面接審査を実施します。
③ 最終審査
面接審査における評価を踏まえ、PD・POが取りまとめを行い、二次選抜の採択候補課題を選定します。
面接審査における評価を踏まえ、PD・POが取りまとめを行い、二次選抜の採択候補課題を選定します。
④ 採択課題の決定
最終審査結果を踏まえ、JSTは二次選抜通過課題を選定します。
最終審査結果を踏まえ、JSTは二次選抜通過課題を選定します。
(7)二次選抜の観点(予定)
二次選抜では1年間の研究開発の達成度と事業化の見通しについて評価をします。
二次選抜では1年間の研究開発の達成度と事業化の見通しについて評価をします。
a. 技術の優位性
二次選抜の時点においても、課題の技術内容が新規性に優れているか。また、競合技術と比べて優位性を保っているかどうか。
二次選抜の時点においても、課題の技術内容が新規性に優れているか。また、競合技術と比べて優位性を保っているかどうか。
b. 研究開発の達成度及び次年度以降の計画
1年目の技術目標は達成できたか。技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応し、最終目標を達成するための次年度以降の計画は適切に見直されているかどうか。また、実施体制が機能しているか。
1年目の技術目標は達成できたか。技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応し、最終目標を達成するための次年度以降の計画は適切に見直されているかどうか。また、実施体制が機能しているか。
c. 実用化、事業化の見通し
事業環境分析が適切になされているか。この事業は新規に市場参入する可能性は高いかどうか。または、核となる技術を応用展開した事業の多様性が期待されるか。
事業環境分析が適切になされているか。この事業は新規に市場参入する可能性は高いかどうか。または、核となる技術を応用展開した事業の多様性が期待されるか。
d. 業務計画の妥当性
1年目の業務計画が遂行できたかどうか。技術の開発状況や事業環境分析結果に対応し、最終目標を達成するための次年度以降のマネジメント業務計画は適切に見直されているかどうか。また、実施体制が機能しているか。
1年目の業務計画が遂行できたかどうか。技術の開発状況や事業環境分析結果に対応し、最終目標を達成するための次年度以降のマネジメント業務計画は適切に見直されているかどうか。また、実施体制が機能しているか。