事業成果
これからの建築、土木を変える新技術
世界初、温度依存性のない鉄系超弾性合金2022年度更新

- 企業:株式会社古河テクノマテリアル
研究者:東北大学 大学院工学研究科 准教授 大森 俊洋 - 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)
- 産学共同フェーズ シーズ育成タイプFS
- 「大地震後の建造物の機能維持に向けた鉄系超弾性合金単結晶大型部材の開発」(2019-2020)
制震構造に使える超弾性合金
巨大地震後の建物や橋梁の残留変形(地震終了後に構造部材などが元の形に戻らないこと)を抑制する制震構造をつくるために、近年、超弾性(※1)合金を利用する研究が活発化している。本研究グループは、強度の温度依存性がほとんどない、極低温(絶対零度-273.15℃近く)から200℃まで超弾性が現れる鉄系超弾性合金の開発に成功。激しい温度変化にさらされる月や火星などで利用できるほか、超弾性合金を用いた建築・土木分野の制震構造システムの開発につながる成果を得た。
この研究成果は、2020年8月14日付の米科学誌Scienceに掲載されている。
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abc1590
※1 超弾性
大きな変形を与えても力を除けば元の形状に戻る性質。

図1 開発した鉄系超弾性合金
高温だと元に戻らない既存の超弾性合金
形状記憶特性のひとつである超弾性を持つ金属は、超弾性合金と呼ばれてTi-Ni(チタン-ニッケル)合金が歯列矯正ワイヤーやメガネフレームなどに使われている。しかし、超弾性合金は温度が高くなると変形強度が高くなり、変形した後に元に戻る性質が得られなくなる欠点があった。Ti-Ni合金では、温度が1℃高くなると強度(応力)が約6MPa高くなり、材料組成を調整しても実用的に超弾性を利用できる温度範囲はおおよそ-20℃~100℃に限られる。さらに「高コストで、加工・切削が難しく、複雑な形状には応用できない」という弱点があった。そこで、Ti-Ni合金の欠点を補う新たな超弾性合金として鉄系弾性合金の開発が進められてきた。
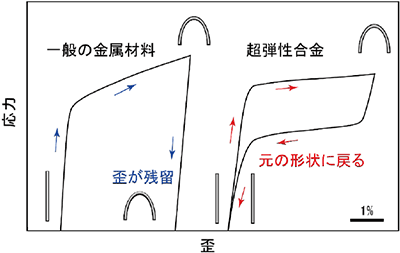
図2 一般の金属材料と超弾性合金の歪と強度(応力)の関係の模式図
地球外の温度範囲もカバーする超弾性合金開発
今回、新たに見出した鉄系超弾性合金(鉄を主成分とし、マンガン、アルミニウム、ニッケル、クロムを含む合金)は、図3に示す通り、温度が変化しても強度(応力)がほとんど変化しない特徴を持っている。また、図4でわかるように応力変動が50MPa(メガパスカル)以下に収まる温度範囲は、実に幅広い。実用されているTi-Ni合金では室温近傍の約8℃の範囲に限られるが、この鉄系超弾性合金では極低温からの約400℃にわたる。これは、地球上での温度範囲はもちろん、月や火星での温度範囲もカバーするものである。また、組成の調整により、通常の超弾性合金とは異なる傾向である、高温ほど強度が低下する性質を得ることができる。
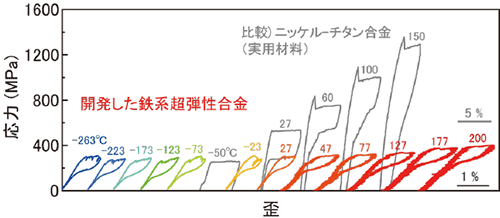
図3
開発した鉄系超弾性合金の−263℃から200℃における超弾性。実用されているTi-Ni(チタン-ニッケル)合金よりも、温度変化の影響を受けない
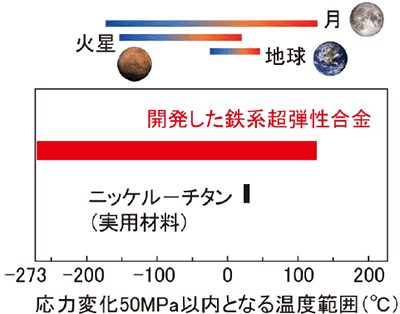
図4
開発した鉄系超弾性合金、実用化されているTi-Ni(チタン-ニッケル)合金の利用温度範囲の比較。応力変化が50MPa以内となる温度範囲を示した。図の上部は地球、月、火星の温度範囲
FSで見出した熱処理条件をもとに大型化に臨み、建築・土木、宇宙開発分野に貢献
今回開発した鉄系超弾性合金は、安価な原料で構成されるため、大型部材として利用しやすい。したがって地震による建造物の被害を軽減させ、地震後の継続利用を可能とする制震システム等へ展開されることが期待できる。兵庫県南部地震以降、巨大地震時でも建造物の崩壊を免れるようになったが、残留変形により、余震で被害が拡大したり、継続利用が困難で改築を余儀なくされたりする問題がある。超弾性合金を建物や高速道路の橋脚の一部に利用することで、地震により大きな変形を受けても原点復元力が働き残留変形を抑制することができる。また、鉄系超弾性合金は、外気温の変化に力学特性が影響を受けにくい点で汎用性が高く、地域や季節による温度変化で利用が制限されないという特長も備えている。今後、熱処理による単結晶化技術を確立して大型部材化と超弾性の性能評価を行い、建築・土木分野における制震構造への適用を目指す。
また、世界初となる極低温から200℃までの広い温度範囲で超弾性を発現する合金としても注目される。日本、米国などで構想・計画される月・火星や小惑星探査において、温度変化の激しい地球外の環境でも弾性を示す性質を有する鉄系超弾性合金は、衝撃吸収材料や振動吸収材料としての利用が考えられる。
- ナノテクノロジー・材料の成果一覧へ
- 事業成果Topへ
- English