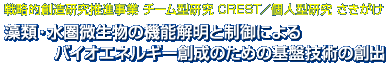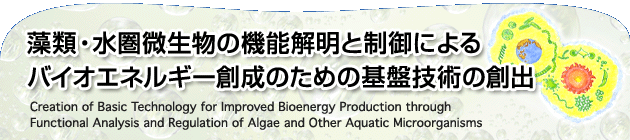研究総括
藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出

研究総括: 松永 是
(東京農工大学 工学研究院 特別招聘教授)
(早稲田大学 理工学術院総合研究所 上級研究員・研究院教授)
生物を用いて太陽光からエネルギーを生産することは、人類の長年の夢でした。すでにトウモロコシやサトウキビから酵母によって作られるエタノールがバイオ燃料として実用化していますが、食料との競合が問題とされています。そのため、作物の非可食部や廃材の利用の研究が広く行われてきましたが、近年、藻類・水圏微生物を利用したバイオ燃料の生産が注目されています。これらの生物はエタノールに変換可能であるばかりでなく、バイオディーゼルや炭化水素を生産することも可能です。生産の場についても、陸上に限らず、表面積の7割を占める海洋の利用は重要な選択肢です。
本研究領域では、海産、淡水産の生物を用いてバイオエネルギー生産を行うための基盤技術の創出を目指します。バイオ燃料(例えばバイオディーゼル、軽油(アルカン、アルケン)、エタノール、メタン、水素等)の産生、もしくはこれらにつながる脂質、糖類等の産生に資する研究を対象とします。さらに、バイオ電池による電気エネルギーへの変換も含みます。また、バイオ燃料の副生成物として、シリカ、アルギン酸等の工業原料物質、アスタキサンチン、β-カロチン、DHA、EPA等の生理活性物質等が想定されます。
藻類等によるバイオエネルギー創成の研究は、これまでも行われてきましたが、本研究領域では、近年急速に発展したオミクス分野の知見や技術を駆使して、藻類等の機能を解明し、その制御を通してポテンシャルを大幅に向上させることにより、革新的な技術の創出を目指します。研究内容としては、例えば、ゲノム情報に基づくプロテオームやメタボローム解析結果を基にしたメタボリックエンジニアリング、メタゲノム解析による未知有用遺伝子の探索、遺伝子組み換えによる機能改変などが挙げられます。また、これらの先端技術を組み入れた、バイオ燃料高生産株の探索・培養から燃料の分離・抽出方法の開発に至るまでの一連の研究も含まれます。なお、将来的な実用化を念頭において、コスト計算、CO2収支、LCAや海洋利用を見据えた藻類の生態学等を考慮することも重要です。
藻類等によるバイオエネルギー創成のための研究には、マリンバイオテクノロジー、藻類学、微生物学、情報生物学、海洋生物学、生化学、遺伝子工学、植物生理学、化学、化学工学等、多岐にわたる分野の研究者による有機的協力が不可欠です。本研究領域の目的を達成するためには、上記諸分野の研究者の有機的な協働と共に、新進気鋭の研究者の独創的な発想を活かした挑戦的なテーマによる成果も期待されることから、実施体制としては、CRESTとさきがけの2つのタイプで行います。
領域運営にあたっては、CRESTとさきがけの相乗効果を高めるために、両者を一体的、統合的に推進する体制で行います。研究の進捗に応じて、相互の研究成果の情報交換を密にし、CRESTとさきがけの異なる推進体制間におけるコラボレーション(研究協力)等も積極的に推進したいと考えています。
本研究領域の成果により、効率がよく、低コストのバイオ燃料生産系を構築するための基盤技術が開発されることが期待されます。この技術を活用することにより、原油等の化石燃料の使用が削減されることが期待されます。また、物質代謝系技術の確立は、プラスチック原料を含む化成品等の製造技術などへとつながることから、化学産業の石油依存度を変える可能性があります。さらに、このような研究を通じて、医薬品、機能性食材等の原料となり得る新規有用物質の創成が可能となります。これらの技術は、大規模実用化実験をへて、領域終了後5年から10年をめどに達成されることが期待されます。
アドバイザー紹介
- 石倉 正治
- 昭和電工株式会社
事業開発センター グリーンプロジェクト 開発グループ リーダー - 井上 勲
- 筑波大学 名誉教授
- 大倉 一郎
- 東京工業大学 名誉教授
- 大竹 久夫
- 早稲田大学 客員教授
大阪大学 名誉教授 - 大森 正之
- 東京大学 名誉教授
- 嵯峨 直恆
- 弘前大学 食料科学研究所 所長・特任教授
- 竹山 春子
- 早稲田大学 理工学術院 教授
- 田畑 哲之
- (公財)かずさDNA研究所 所長
- 民谷 栄一
- 大阪大学 大学院工学研究科 教授
- 横田 明穂
- 奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授
株式会社植物ハイテック研究所 取締役研究開発本部長 - 横山 伸也
- 公立鳥取環境大学大学院環境情報学研究科 特任教授
領域運営アドバイザー
- 和気 仁志
- 東京農工大学先端産学連携研究推進センター 特任教授/統括リサーチ・アドミニストレーター