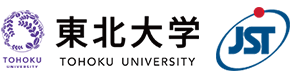ポイント
- 細胞性粘菌は低酸素環境下において動きを活性化させ、酸素を求めて遊走する性質(走気性)を持ちます。
- 既存の仮説に反し、ミトコンドリアや酸化ストレスは細胞性粘菌の走気性には関与しないことが明らかになりました。
- 本研究成果は、全く未知の酸素応答機構の存在を示唆する重要な知見であり、将来的にはヒト細胞を含む真核細胞の生命現象の解明と予測につながるものと期待されます。
酸素環境は多くの真核細胞の生命現象を左右し、生理学・病理学的な事象に深く関わっていますが、その機構は完全には解明されていません。
東北大学 流体科学研究所の船本 健一 准教授、廣瀬 理美 氏(大学院 医工学研究科 博士後期課程 修了生、現・マサチューセッツ工科大学 博士研究員)、リヨン第1大学のJean-Paul Rieu(ジャン=ポール・リウ) 教授、Christophe Anjard(クリストフ・アンジャル)教授らの共同研究チームは、真核細胞のモデル生物である細胞性粘菌Dictyostelium discoideum(和名:キイロタマホコリカビ)が、細胞周囲の酸素濃度勾配に応じて酸素が豊富な領域に向かって遊走すること(走気性)を発見し、その機構の解明に向けて研究を行ってきました。
従来の培養皿を用いた細胞実験方法に加え、任意の酸素環境と化学刺激環境を生成できるマイクロ流体デバイスを用いた実験や、細胞の遊走の数理モデルを用いた解析により、細胞性粘菌の走気性は、誘引物質と考えられていた酸化ストレスや酸素代謝を担う細胞内小器官ミトコンドリアの働きに依存しない現象であることを明らかにしました。
これらの発見は、真核細胞の酸素応答における未知の機構の解明に向けた重要な知見であり、生命現象の解明と予測につながるものと期待されます。
本成果は、2023年6月15日付(現地時間)でオープンアクセス誌「Frontiers in Cell and Developmental Biology」に掲載されました。
本研究は、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業 さきがけ「複雑な流動・輸送現象の解明・予測・制御に向けた新しい流体科学(研究総括:後藤 晋)」における研究課題「間質環境の再現と制御による細胞動態の操作技術の創成(研究代表者:船本 健一、JPMJPR22O8)」および「次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2114)」、日本学術振興会の「若手研究者海外挑戦プログラム」、東北大学 流体科学研究所の公募共同研究による支援を受けました。
<プレスリリース資料>
- 本文 PDF(601KB)
<論文タイトル>
- “The aerotaxis of Dictyostelium discoideum is independent of mitochondria, nitric oxide and oxidative stress”
- DOI:10.3389/fcell.2023.1134011
<お問い合わせ先>
-
<研究に関すること>
船本 健一(フナモト ケンイチ)
東北大学 流体科学研究所 准教授
Tel:022-217-5878
E-mail:funamototohoku.ac.jp
-
<JST事業に関すること>
安藤 裕輔(アンドウ ユウスケ)
科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
Tel:03-3512-3526 Fax:03-3222-2066
E-mail:prestojst.go.jp
-
<報道担当>
東北大学 流体科学研究所 広報戦略室
Tel:022-217-5873
E-mail:ifs-kohogrp.tohoku.ac.jp
科学技術振興機構 広報課
〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地3
Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432
E-mail:jstkohojst.go.jp