日米研究連携シンポジウム
COVID-19を乗り越えるイノベーション:人を中心に据えたデータ統合で強く柔軟な社会を目指す
開 催 場 所
3階講堂 キャンパスマップ
ZOOM オンライン
アメリカ
2022年11月9日(水)8:00 pm - 11:00 pm (米国西部時間)
日本
2022年11月10日(木)1:00 pm - 4:00 pm (日本時間)
シンポジウム概要
歴史上、COVID19パンデミックのような全世界的危機の後に芽生えたイノベーションの例は複数存在します。日米のトップ科学者が、この未曽有の危機をイノベーションの機会として取り組む最先端科学の挑戦について話し合います。また、次世代の若手科学者が、日米共同で取り組む未来社会創造と次世代個別化医療の挑戦課題について、事前に積み上げた議論の成果を発表します。
プロシーディング
シンポジウム終了後に、プロシーディングはここからダウンロードできます。
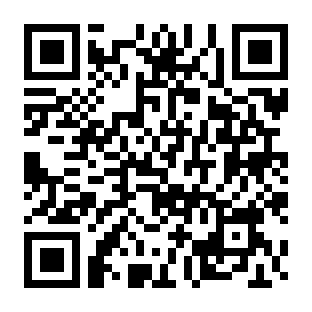
参加申し込み
オンラインと会場でのハイブリット開催
参加無料 シンポジウム開催前に、当イベントコーディネーターより参加者へZOOMアクセス情報を個別にメールにてご連絡いたします。
基調講演

スタンフォード大学
マイケル・シュナイダー スタンフォード大学医学部教授
「マルチオミクスとウェアラブルデータを関連付けた長期的ビッグデータ研究による健康管理」
COVID-19パンデミックでは、重度・軽度だけでなく、長期・短期の症状が現れるが、その機序はまだ解明されていない。また、これらの影響の個人差は、遺伝子だけでなく、生活環境、例えば、食事、睡眠、ストレスなどにも影響を受ける可能性がある。本講演では、これまで米国で得られた研究成果を紹介するとともに、今後、生活環境の異なる国間での比較研究、特に日本との共同研究への期待を述べる。
略歴: 1982年にカリフォルニア工科大学で化学・生物学博士号取得。1982年スタンフォード大学研究員、1986年イェール大学分子生物学講師を経て、2009年スタンフォード大学医学部教授に就任。現在はスタンフォード大学医学部遺伝学研究科長を務めるとともに、同大学の遺伝学・オーダーメイド医療研究センターのセンター長を務める。

藤田医科大学
橋本直純 藤田医科大学呼吸器内科学講座教授 (元名古屋大学医学部 准教授)
「名古屋Stanfordコホート研究のフィージビリティスタディと個別化医療への期待」
2022年1月から3月まで、COVID-19の患者をはじめとするボランティアの参加を得て、名古屋大学でスタンフォード大学との日米生活環境比較予備調査が行われた。このフィージビリティスタディで明らかになった、いくつかの予備的知見と、ウェアラブルデバイスを使ったコホート研究への期待と課題を発表する。
略歴: 2002年、名古屋大学大学院医学研究科内科系専攻で医学博士号取得。2002~2004年アメリカミシガン大学病理学講座ポスドク・フェロー、また、2004~2007年名古屋大学医学系21世紀COEプログラム「神経疾患・腫瘍の統合分子医学の拠点形成」ポスドク・フェロー、2007~2013年名古屋大学医学部附属病院呼吸器内科助教、2013~2015年名古屋大学医学部附属病院呼吸器内科病院講師、2015~2018年名古屋大学医学部附属病院呼吸器内科講師を経て、2018~2022年名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座呼吸器内科学分野准教授。2022年9月藤田医科大学呼吸器内科学講座教授に就任。
招待講演

慶応義塾大学
福永興壱 慶応義塾大学医学部教授
「コロナ制圧タスクフォースの成果と今後の展開」
2020年5月から、日本人集団の感染者の重症化因子を解明し、新型コロナウィルスから国民を守るために様々な研究分野から日本を代表する科学者が横断的に結集して開始されたコロナ制圧タスクフォース。現在6000を超える検体(2022年7月時点で約6000の血液検体)が集められ、その解析により重症化のバイオマーカー(DOCK2)等が明らかにされてきている。このタスクフォースの活動で得られた成果を紹介するとともに、海外研究機関との国際共同研究への期待や課題を述べる。
略歴: 1994年、慶應義塾大学医学部卒業後、米国ハーバード大学医学部Brigham and Women’s Hospital留学3年間を経て、2007年~2010年埼玉社会保険病院(現埼玉メディカルセンター)内科医長、2010年4月より慶應義塾大学医学部呼吸器内科特別研究助教に就任、その後、2018より同大学准教授、同年8月より2019年5月まで同大学、アレルギーセンターのセンター長を兼任し、2019年6月、慶應義塾大学医学部呼吸器内科教授に就任、また2021年9月より、同大学病院副病院長を兼任。現在日本で結成されたコロナ制圧タスクフォースの責任者も努める。
話題提供

名古屋大学
天野 浩 名古屋大学教授 2014年ノーベル物理学賞受賞者
「深紫外発光LEDを活用したウィルスの不活化とその展開」
略歴: 1989年に名古屋大学大学院で工学博士号取得。1988年名古屋大学工学部助手、1992年名城大学理工学部講師、2002年名城大学理工学部教授を経て、2010年名古屋大学大学院工学研究科教授に就任。2015年に名古屋大学 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター 未来デバイス部、 未来エレクトロニクス集積研究センター長に就任。赤﨑勇名城大学終身教授・名古屋大学特別教授、中村修二カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授と共に「高輝度、省エネルギーの白色光源を可能とした高効率青色発光ダイオードの発明」にて2014年ノーベル物理学賞を受賞。現在は名古屋大学で次世代半導体およびエネルギーデバイスのテクノロジー開発に従事。
京都府立大学
塚本 康浩 京都府立大学学長
「パンデミックの中で生まれた新抗体科学とその展開」
略歴: 1998年に大阪府立大学大学院で博士課程獣医学専攻修了。1997年カナダ・ゲルフ大学獣医学部客員研究員、2005年大阪府立大学准教授を経て、2008年京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授に就任。2020年に京都府立大学学長に就任。2008年に京都府立大学発ベンチャー「オーストリッチファーマ株式会社」を設立、ダチョウの卵から抽出した抗体を用いて新型インフルエンザ予防のためにマスクを開発。2009年には「ダチョウによる新たな抗体大量作製技術を用いた鳥インフルエンザ防御用素材の開発」の功績で文部科学大臣賞を受賞。以後もダチョウ抗体を利用したさまざまな研究に取り組む。開会挨拶

東海国立大学機構機構長

京都府立大学学長

国立研究開発法人
科学技術振興機構(JST)
顧問

スタンフォード大学
教授、
麻酔科前科長
閉会挨拶

麻酔科創薬医療機器開発研究所
所長

名古屋大学大学院医学系研究科長・医学部長
総合司会

メディカルイノベーション推進室室長(MIU)、
名古屋大学大学院医学系研究科教授
【事前開催】オンラインウェビナー・ワークショップシリーズ
JST-Stanfordイニシアティブプログラム-デジタルデータ・イノベーション・ウェルネス
「日米連携企画を構想しよう!- 多様性と包摂を学ぶ国際企画」
シンポジウムに先立ち、スタンフォード大学と名古屋大学のCIBoGとDII(卓越大学院プログラム)の支援のもと、若手研究者を対象としたオンラインセミナー・ワークショップシリーズを実施しました。4回のオンラインウェビナー・ワークショップ、チュートリアルセッション、特別セッションの計6回のオンラインイベントを企画しました。この企画は、JST-Stanfordイニシアティブ(*)の一環として実施されたものです。世界各国から参加した優秀な若手研究者が、以下の6つのテーマに分かれ、将来の国際共同研究のためのプロポーザル、具体的な解決策を議論・創造しました。また、すべてのグループに対して、国際的に著名な専門家がメンターとして指導にあたりました。
- Digital Twin
- Super Aging
- Web 3.0
- Self Medication
- Disaster & Health
- Wearable & Digital
グループディスカッションを通じて得られた各グループの成果は、シンポジウムにてピッチトーク形式で発表されます。この取り組みを通じて出来た仲間と日米をベースに更なる様々な国際連携へのファーストステップを踏み出すきっかけになればと期待しています。
本プログラムの修了者には、主催者より修了証が授与されます。
チュートリアルセッション
9/3/2022
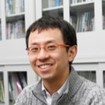
黒田 啓介
名古屋大学

田岡 紀之
名古屋大学

西村 俊彦
スタンフォード大学
第1回オンラインウェビナー・
ワークショップ
9/17/2022

ロナルド・パール
スタンフォード大学

満倉 靖恵
慶應義塾大学

秋元 秀昭
Yazaki Innovations, Inc.
第2回オンラインウェビナー・ワークショップ
10/1/2022

マイケル・シュナイダー
スタンフォード大学

近藤 博基
名古屋大学

伊地知 天
Creww, Inc.
第3回オンラインウェビナー・ワークショップ
10/15/2022

天野 浩
名古屋大学

マイケル・チュー
ITIC

鳩山 玲人
Sozo Ventures
特別セッション:
シリコンバレー起業家Q&A
10/22/2022

熊谷 芳太郎
ŌURA

パヴァン・オンゴール
MFV Partners

満倉 靖恵
慶應義塾大学
第4回オンラインウェビナー・ワークショップ
10/29/2022

塚本 康浩
京都府立大学
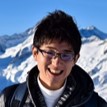
松井 佑介
名古屋大学

鬼澤 美穂
incri
メンター
6つのテーマにはそれぞれ、世界的に著名な専門家が指導にあたり、議論を促し新しいアイデアを鼓舞するメンターとして貢献していただきました。

友池仁暢
NTT物性科学基礎研究所
リサーチプロフェッサー
"Digital Twin"

チェン-エン コー
国立台湾大学
名誉教授
"Super Ageing"

パヴァン・オンゴール
MFV Partners
投資家
"Disaster & Health"

山口泰人
参天製薬
"Self Medication"

市嶋洋平
エクサウィザーズ
社長室 マネージングエディター
兼 新規事業開発担当
"Web 3.0"

満倉 靖恵
慶應義塾大学
教授
"Wearable & Digital"
(*)JST-Stanfordイニシアティブとは?
JSTとスタンフォード大学がハブとなり、日本と米国西海岸の大学・研究機関・企業群との間に研究交流の基盤を作ることを目的に、2021年に開始された活動です。 2021年12月にJST国際部とスタンフォード大学麻酔科の間で締結された研究協力に関する覚書に基づき、スタンフォード大学医学部麻酔科創薬医療機器開発研究所と科学技術振興機構国際部ワシントン事務所が事務局となり、毎週の定例会議を通じて、年に複数回、合同シンポジウムや研究会を企画・実行しています。日米からトップ科学者を招聘するとともに、その科学者の取り組む研究開発のステークホルダーを順次合同シンポジウムや研究会に招待し、意見交換を通じて相互の取り組みを理解し信頼関係を構築しています。
2021年2月に開催されたJST-スタンフォード大学合同シンポジウム「COVID-19にイノベーションで立ち向かう」での議論を端緒として、2021年5月から「感染症耐性のある社会を目指すイノベーション」をテーマに、名古屋大学、京都府立大学、スタンフォード大学の研究者が研究協力について毎週議論を重ね、2022年1月から3月に「日米生活環境比較予備調査」を行い、感染症の重篤化等に影響を及ぼす要因の同定のための日米生活環境比較調査のフィージビリティスタディを行いました。こうした個別具体的な研究交流の積み重ねにより、信頼関係で結ばれたコミュニティが持続的に形成され、日米の間の研究交流基盤となることを目指しています。
この取り組みには、JSTやスタンフォード大学が保有する様々なネットワークとの連携が含まれます。例えば、スタンフォード大学が継続的に連携する神奈川県、慶応大学、京都府立大学や、JSTが連携するNational Science Foundation(NSF)やGlobal Federation of Competitiveness Councils(GFCC)等とも連携し、個別に育ててきたネットワークの間の触媒効果を設計しつつ進めます。今後も、この活動に賛同いただける機関を日本と米国の大学・研究機関・企業群の中から募り、JST-Stanfordイニシアティブを発展させていく予定です。





