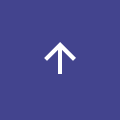海外事例 イタリア分子癌研究所(イタリア)
分野を超えた強固な研究者コミュニティの形成
― イタリア分子癌研究所(IFOM)ポスドク協会の取り組み ―
本事例は、プログラムフレームワークの上記のコンピテンシーに関連しております。
イタリア分子癌研究所(IFOM:Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS)は、国際的に活躍する研究者に対して、癌生物学の研究を強力に推進する環境を提供している。
今回お話を伺ったのは、IFOMの博士課程事務局で学生アドミニストレーターを務める住江美緒氏。住江氏は研究所内の博士研究員(ポスドク)のコミュニティ形成を主導するIFOMポスドク協会(旧称)の非常任理事でもある。組織としてのIPAは、ソフトスキル講座、セミナー、ピアネットワーキングのためのイベントを通して、ポスドクのキャリア開発に重点的に取り組んできた。
またIPAは研究所のポスドクを対象に、あらゆるキャリア開発において重要な、関連分野の同僚研究者との強固なネットワーク構築も支援している。現在IPAは再編成の途上にあるが、博士研究員や博士号取得者を支援するための新たな独自のネットワークが間もなく発足予定である。
機関について
ミラノに本部があるイタリア分子癌研究所(IFOM:Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS)[参考1]は、癌生物学の理解を目的として設立された研究機関である。この研究所は、国際性豊かな研究環境を提供するだけでなく、最先端のインフラをも備えている。またIFOMは研究組織でありながら、海外の4つの教育機関と提携し、研究プロジェクトに従事する博士課程学生も受け入れている。
IFOMポスドク協会(IPA:IFOM Postdoc Association)[参考2][参考3]は、研究面のみならず、キャリア形成や生活面も含めたポスドク支援を目的とする所内組織である。IPAは、研究者のネットワーク作りや学習の機会を提供するさまざまなイベントを開催し、その充実を図っている。また、ソフトスキルの向上と、アカデミアの枠を超えた多くのキャリアの選択肢を模索することに重点を置いている。
インタビュイーについて

住江美緒(Mio Sumie)氏はIFOMの博士課程事務局のステューデント・アドミニストレーターである。住江氏はIFOMポスドク協会(IPA)の非常任理事でもあり、日本に関連したIFOMの国際事業を担当している。
研究機関について

IFOM ETS本部。画像提供:IFOM

IFOMでは高度な設備とインフラに加え,優秀なスタッフが各種の溶液,抗生物質,細胞培養,その他あらゆる実験材料の滅菌処理や保管を通して研究者をサポートしている。画像提供:IFOM
イタリア分子癌研究所は、同国で初めて設立された、癌の発生・形成を専門に研究する機関です。設立以来長きに渡って国際性豊かな環境作りに取り組んでおり、現在ではスタッフの26.5%が海外出身者で占められています。高度な技術とインフラによって多くの共同研究プロジェクトが進められており、それが研究を強力に後押しする気風を育んでいます。
IFOMでは博士課程の学生を対象に、提携先の学術組織に所属しながら研究プロジェクトを進めることが可能な、全額負担型の奨学金プログラムを設けています。このプログラムの提携機関は、ミラノに所在する欧州分子医学校(SEMM:the European School of Molecular Medicine)のほか、オープン大学(ミルトン・キーンズ、イギリス)、ゴールウェイ大学(ゴールウェイ、アイルランド)、パーズマーニ・ペテル・カトリック大学(ハンガリー、ブダペスト)を合わせた4つです。博士課程のプログラムを多様化するため、IFOMはこうした運営面での協業に積極的に取り組んでいます。提供されるプログラムには、広範なテーマに基づくものもあれば、より専門的な特定領域に相当するものもあります。
また、オープン大学との提携により、IFOMに所属している学生はVitae Research Development Framework(RDF)を利用できます。RDFは、博士課程での研究プロジェクトの進捗状況を把握し、次に何を行うかの意志決定を十分な情報に基づいて行うためのツールです。今のところ、この制度はオープン大学の博士課程に在籍する学生に限定されていますが、将来的にはポスドク研究者も対象となる可能性があります。
IFOMポスドク協会(IPA)
IFOMでは博士課程において学生をするだけでなく、博士研究員(ポスドク)の受け入れも行っています。そうしたIFOM内の研究者コミュニティの間でネットワーク形成の機会を提供するために活動しているのが、IFOMポスドク協会(IPA:IFOM Postdoc Association)です。IPAはIFOMで働く全てのポスドクのための団体であり、研究者が精力的に活動できる雰囲気の醸成と、コミュニティ間の交流促進に努めています。現在IPAは組織を再編成している最中ですが、将来的に活動範囲や重点的に取り組む分野をより広げていく可能性があります。
IPAの掲げる目標は、おおよそ以下の4つに集約されます。
- 異なる研究室のポスドク間の交流の促進
- ソフトスキル講座の開催
- 研究室主宰者(PI)以外のキャリアについて、様々な視点の提供
- 世界各地のポスドク組織とのネットワーク構築
以前のIPAは、毎年研究所内のポスドクから選出される最大10人のボランティアからなる理事会を組織して活動していました。会長と副会長、執行委員会によって代表される理事会では、役割分担が男女平等になされていました。また、その構成員はIFOMで働く多様な研究者のコミュニティから選ばれていました。IPAの改革に伴って運営体制が変わる可能性はありますが、インクルージョンとダイバーシティを維持しようとする組織の伝統は引き続き維持されるでしょう。
IPAは、サイエンティフィック・ディレクターが推薦する特別会員にも支えられています。特別会員の役割は、多くの研究者が不慣れとしている事務的な業務を補助しながら、コミュニティにとって不可欠な支援を提供することです。住江氏も、IPAを支援している特別会員の一人です。
研究者が相互に連携し、知識や技術を共有しながら学ぶことができるように、IPAはさまざまなイベントを開催しています。毎月開かれる理事会では、具体的な企画や運営についての話し合いが行われます。活動資金はすべてIFOMの管理部門による事前承認を受けており、IPAはその範囲内で柔軟に活動し、研究者からの要望や毎年開催するイベントなどの活動にあてています。
IPAの活動
〜ピア・エンゲージメントとネットワーキングのためのイベント開催

ヒト人工多能性幹細胞に関する研究について講演するチンツィア・カンチェリエリ博士。IPAでは、ポスドクが同僚に短い講演を行い、研究プロジェクトについて話し合うこのようなセッションを数回開催している。画像提供:IPA
IPAの取り組みについて、IPA理事会の元メンバーであるヘマ・マレ・エングラ博士は「ポスドク・研究者生活の中で、共通の関心をもつ人たちを常につなぐための組織として不可欠です。教育の機会や人脈形成の面で、また創造性やモチベーションといった面でも非常に役立っています」と述べています。
IPAが主催するさまざまなイベントは、同僚と貴重なつながりを作り、互いに学び合うことを主眼にしています。
人気のあるイベントの一つが、2人のポスドクを招いて行われる「Pizza Talk」です。このイベントでは、現在取り組んでいる、もしくは過去の研究プロジェクトについて、ゲストに短いトークを披露してもらいます。講演後には全員参加のディスカッションがあり、自分の研究と演者のそれとの関連を探ったり、ピザや飲み物を楽しみながら交流したりします。Pizza Talkはカジュアルな雰囲気を維持するよう配慮がなされており、研究所に入所して日が浅いポスドクや主任研究員が気軽に参加できるようになっています。
多くの研究グループでは、研究室主宰者、ポスドク、また博士課程の上級学生などの若手研究者の間で、定期的にコミュニケーションの機会がもたれています。それらを「縦」のネットワークとするならば、Pizza Talkは「横」のネットワークを広げるためのプラットフォームを提供しているといえるでしょう。このイベントの最終的な目標は、交流を通じ有意義な協力体制を異なる研究グループ間で構築できるよう手助けすることにあるのです。
アカデミアに限らない多様なキャリアパスの探求

Science and Proseccoで講演者と交流するIFOMの研究者たち。画像提供:IPA
IPAが運営しているもうひとつのイベントに、毎年ないし隔年開催される「Science and Prosecco」があります。このイベントでは、著名な研究者や国際的な企業、欧州の著名な組織に所属する人たちとの双方向的な対話の機会が設けられます。経験を積んだ研究者が別のキャリアパスを模索するのを支援し、学術界や研究室主宰者だけがポスドクのキャリアパスではないことを伝えるのを目的としているのです。
この催しでは、サイエンス・コミュニケーター、研究助成金管理者、起業家、実業家など、多様な分野から講師を招きます。参加者は、博士課程の学生やポスドクのキャリアについて視野を広げることができます。ときにはIPAの在籍経験者についてキャリアを紹介し、現役の研究者たちと交流してもらうこともあります。また、IFOMの新しい研究室主宰者を紹介する場ともなっています。
そのほか、定期的に開催されている企画としては「IPA Meets」があります。これはIPAによるネットワーキングの取り組みの一つで、ポスドクを対象に第一線で活躍する科学者との交流の機会を提供することに重点を置いています。また、外部講師によるセミナーが行われることもあります。
ソフトスキル向上のための選択講座
IPAの大きな目的のひとつは、研究以外の領域でも役立つソフトスキルをポスドクが身につけられるよう支援することです。ポスドクがキャリア形成で優位になるうえで重要なスキルとしては、コミュニケーション、ライティング、プレゼンテーション、マネジメントが挙げられます。そのためIPAはポスドク向けに、サイエンス・コミュニケーションや助成金申請書類の書き方、デジタル機器を用いたプレゼンテーションや特許申請といった、いくつかの選択科目を開講しています。こうした講座の多くは博士課程の学生にも門戸を開いており、研究者キャリアの早い段階でのスキル開発に大きく役立っています。
ポスドク側のニーズや関心に応えるため、適宜IPAは研究者から提案を募り、開催可能な講座をリスト化しています。これにより、参加者の必要性に合致したプログラムを提供し、活動的な学習環境を維持しているのです。
IFOM、IPA、そして日本から得られるチャンス

IFOMウェルカムオフィスは、外国人研究者に多岐にわたるサポートを提供している。またIFOMとIPAは、研究への興味関心の醸成のため、留学生を対象にいくつかのプログラムを用意している。画像提供:IFOM
IFOMは多方面に及ぶ国際協力体制を敷くと同時に、個人の経験や知識の共有を重要視しています。IFOMの提携機関には、京都大学、理化学研究所横浜キャンパス、東京大学計量生物学研究所(IQB)といった日本の大学・研究機関も含まれます。これらに所属している博士課程の学生、ポスドク、研究者は、IFOMの研究室や実験室を短期間訪問し、そこでの活動を体験することが可能です。これは二国間協定の一環として行われており、IFOMから選ばれた奨学生も、日本の大学の研究環境を体験することができます。
学部学生もこうした取り組みの参加対象となっています。Science and Proseccoのようなイベントに参加し、現地の奨学生と交流しながら、IFOMの研究環境を肌で感じる機会を得られるのです。
海外で学ぶ際にほとんどの人が文化的・社会的な変化に直面しますが、それらに最初からうまく対応することは難しいものです。IFOMのウェルカムオフィスは、イタリアに移住する外国人ポスドクを支援するため、広範なサポート体制を敷いています。研究者や教員も、海外出身者がイタリアの文化・慣習に慣れることができるように努めています。
IPA在籍者からの声

IPA主催の卓球大会は、研究者間の交流、コミュニケーション、親睦を深めるための活動のひとつである。画像提供: IPA
創設以来、IPAは世界各地で成功を収め、充実したキャリアを歩む卒業生を多く輩出してきました。彼らは、IPAが企画したさまざまなイベントや講演によって自身の創造性が刺激され、モチベーションが高まり、自分の研究分野以外のスキルも広げることができたと考えています。
住江氏によれば、当初研究者たちはIPAに対して懐疑的で、参加にためらいもあった、といいます。ただ時間が経つにつれ、彼らは自分たちの声を拾う場所をもつ重要性に気づき、研究室の外にいる仲間と交流できる機会を作るため、互いに協力したのだ、とのこと。2年に渡る議論の末にIPAが設立されたことからもわかるように、一朝一夕にこのような体制を作ることはできません。結果として、IPAはIFOMの研究者にとって必要不可欠なコミュニティとして成長を遂げたのです。
また、IPAの活動の企画・運営を通じて、イベント開催、講座の実施、プロジェクト管理などについて実地経験を積むことができたと語る人もいます。その一人で、IPAの前会長であるウンベルト・レストゥッチャ博士は「IPAで過ごした間に、私は科学・社会イベントの企画、科学的講座の実施、プロジェクト管理などに携わりました。これによって自分のスキルを広げることができました」と回想しています。
IPAに興味のある若手研究者へ
住江氏は、IPAに将来参加したいと願う若手研究者へのアドバイスとして 「大きな声で考えること」と「適切な問いを続けること」の2つを送ってくれました。卓越した研究者たちが集まるIPAは、スキルを磨き、アカデミアに限定せず将来のキャリアを探求するために役立つ、いきいきとした環境となっています。オープンマインドな姿勢のもと、自身が関心をもつ分野で新たな展開を探り、仲間と情熱的に議論すること。それこそが、IFOMとIPAがもたらす多くのチャンスを最大限に活かすのに必要な、熱意を発揮するのにつながるでしょう。
研究機関の情報
イタリア分子癌研究所(IFOM)は、イタリア癌研究協会(AIRC)の支援のもと運営されている、非営利の研究機関である。IFOMではその研究の目的を、癌の発症とその原因となる分子プロセスの理解に置いている。
現代科学の高い水準に応えるため、IFOMはミラノ周辺に所在する主要な国立研究機関の科学者の協力を得てきた。そして社会的、経済的、あるいは文化的な資源を共有可能な研究環境を整備してきた。複数の研究機関のネットワーク構築はイタリアでは初めての試みだったが、その結果としてIFOMは分子腫瘍学と機能ゲノミクスの分野で国際的に高い競争力を有する研究センターとなった。
ロンバルディア州議会から卓越した研究センターとして認証を受けたことで、IFOMはさらに発展を遂げた。
現在、基礎研究分野での確固たる基盤を確立したIFOMは、科学的知見を臨床での診断・治療へ迅速に活かすための橋渡し研究に注力している。これと並行して、IFOMは強固な国際協力体制を築き、日本とインドの卓越した研究機関とのパートナーシップを結んできた。これらの協定により、IFOMは世界のがん研究機関のなかでも重要な位置を占めるようになりつつある。
本記事の参考資料、関連するサイト
- [参考1]イタリア分子癌研究所(IFOM:Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS)
- [参考2]IFOMポスドク協会(IPA:IFOM Postdoc Association)
- [参考3]IPA設立に関連する記事(論文)
本記事で紹介する取組一覧
| 取組名 | コンピテンシー |
|---|---|
Pizza Talk |
|
Science and Prosecco |
|
IPA Meets |
取材日:2022年12月
取材協力:カクタス・コミュニケーションズ株式会社