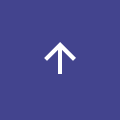海外事例 インド工科大学ボンベイ校(インド)
インド発のイノベーション創出に向けて
—インド工科大学ボンベイ(IITB)の起業家教育と研究エコシステム構築—
- 01ネットワーキング
- 02表現力
- 03コミュニケーション
- 04チームワーク
- 05リーダーシップ
- 07チームマネジメント
- 08プロジェクトマネジメント
- 10問題解決力
- 11創造力
- 13汎用技術・知識
- 16キャリア開発
本事例は、プログラムフレームワークの上記のコンピテンシーに関連しております。
「テクノロジー大国」「起業大国」であるインドにおいては、それを支える人材育成のための国家的取組が早くから打ち出されてきた。なかでもインド工科大学は、起業マインドと高い技術力を併せもつ優秀な人材を多く輩出し、起業人材育成のインキュベータとして世界でも高い評価を得ている。新たな産業の創出につながる革新的なアイデアを持った若者を育成するためのエコシステムについて、その環境整備を推進するIITB機械工学部研究開発部門長のアトレイ博士にお話をうかがった。
機関について
インドのムンバイにあるインド工科大学ボンベイ校(Indian Institutes of Technology Bombay: IITB)[参考1]は、工学分野の教育・研究で世界をリードする名門公立大学で、インド各地から優秀な学生や研究者が集結している。
研究者育成の取組について
IITBは、新しいアイデアや研究、学門が興る風土を醸成することを目指し、インキュベーションと教育の2本柱に力を入れている。そのミッションをまさしく体現するのがIITBのDesai Sethi School for Entrepreneurship(DSSE)[参考2]とSociety for Innovation and Entrepreneurship(SINE)[参考3]である。DSSEは、イノベーション創出に意欲的な学生を対象として、メンタリングと様々なプログラムを提供している。SINEは起業家精神を養い、テクノロジー系スタートアップを育成するビジネスインキュベーターであり、新たな技術シーズを活用した起業をサポートし、研究からベンチャー起業への転換を実現するための様々な支援を行っている。
インタビュイーについて

ミリンド・アトレイ(Milind D. Atrey)博士[参考4]はIITBの機械工学部の教授であり、熱工学を専門としている。博士課程の学生として IITBに入学し、博士号取得後は、英国のオックスフォード・インストルメント、インドの原子力エネルギー省等、世界各地で研究を行った。14年間にわたって産業界や研究分野での経験を積んだ後、2005年にIITBの教授に就任し、以来17年間にわたってIITBで教鞭をとっている。SINEの担当教授を務め、現在はIITBの研究開発(R&D)部門長を務めている。
IITBの研究エコシステム

創立以来、IITBは才能溢れる起業家や研究者を輩出してきた。画像提供:IITB
IITBには多くの学生や若手研究者が集い、技術研究の推進という共通の目標に向かって、日々邁進しています。IITBは優れた学士課程プログラムを有することで広く認知されるようになりましたが、組織として重要な位置を占めるのは研究活動です。IITBには12,000名の若手研究者が在籍しており、その多くは大学院や博士課程に所属しています。大学の研究開発に対する彼らの貢献は計り知れません。
博士課程に入学した学生は、初日にガイダンスを受けた後、十分な時間をかけて各研究室の環境を見定め、しっかりと吟味した上で、研究指導を受ける教員を選択します。こうしたシステムは、他の組織ではあまり取り入れられていません。
所属する研究者が最先端の機器やテクノロジーにアクセスできるように計らい、研究プロジェクトのスムーズな進行をサポートするのも、研究開発部門長の責務です。しかし、学生や若手研究者の研究キャリアを高めるためには、最先端の機器へのアクセスを確保するだけでは十分ではありません。研究の発展を支援し、イノベーションの創出に向けて後押しする「エコシステム」が不可欠です。そこでIITBは、学生や若手研究者と、第一線で活躍する各国の研究者や卒業生とが積極的に交流することを奨励しています。こうした交流イベント等を通じて出会った研究者同士が、IITBで独自の研究をゼロからスタートさせることもしばしばあります。
IITB卒業後のキャリア
博士課程の学生は、自らのキャリアは学界か研究分野に限られていると考えがちです。しかし実際は、研究分野以外でキャリアを構築できる民間の研究・調査会社は各国に存在し、そうした会社に就職するという選択肢もあります。
IITBでは、多くの場合、学生は23歳で博士課程プログラムに入学しますが、在籍中にさまざまな経験を積むことで、卒業時にはより幅広い視野で自らのキャリア・ゴールについて考えられるようになります。
インドでは民間の研究会社や研究産業が日に日に成長しています。近い将来、そうした組織や企業が、博士課程の卒業生を学部生と同じように採用するようになるでしょう。
共同研究を通した研究資金獲得
IITBは、インド政府が指定するInstitute of Eminence(卓越した組織)の一つに選ばれており、インド23都市にある全IITのなかでも屈指の名門校です。IITBの研究成果の重要性は広く認識されており、インド科学技術庁、バイオテクノロジー省、教育省等の政府省庁といった外部組織から十分な研究資金を得ることができています。
IITBは、外部機関との連携も積極的に行い、共同研究を通じた研究資金も数多く獲得しています。例えば、IITBはインド宇宙研究機関(Indian Space Research Organization: ISRO)と宇宙関連テクノロジーの開発分野で様々な協力を行っています。同様に、石油・天然ガス省も、IITBとの提携に意欲を示しています。新たなテクノロジーの開発には膨大なリソースが必要であり、研究者は多大な時間を割く必要があります。そうして膨大なリソースを費やしたとしても、IITBで行うことができるのは技術成熟度レベル(TRL)と呼ばれる、新技術の開発がどの程度商業化に近いかを検証する、コンセプトレベルの検証に過ぎないことが多いのが現状です。新たな技術を商業利用できるレベルにまで引き上げるためには、業界の多様なプレーヤーと協力関係を築く必要があります。
ほんの20年前は、製造やテクノロジー系の企業の多くは、学術研究機関への投資には消極的でしたが、状況はどんどん変わってきています。現在では、シーメンスやタタ、マヒンドラ、そして、グーグルやフェイスブック等の巨大ソフトウェア企業が、様々なプロジェクトでIITBとの提携に興味を示しています。
こうした提携は、インドが自国内での完結する自立した技術開発を志向するようになって以降、増加の一途を辿っています。様々な企業が、各分野を専門とする教授に協力を仰ぎ、プロジェクトに対するコンサルティング・サービスという形でアドバイスを受けています。
こうした外部のスポンサーシップやコンサルティングの提供等で、IITBは平均で年間30億インドルピー(約5億円)の研究資金を得ています。これは、全研究資金の15~20%に相当します。なお、残りの約80%の研究費は、政府から提供されるものです。
学際的研究における共同研究の役割
IITBが学際的研究を進める上で、産業界との提携は非常に有用です。研究開発部門では、企業からアプローチを受けた際には、機械工学、工学、土木学、化学工学等、関連分野の代表者を交えて、共同プロジェクトの目的について協議するようにしています。
また、プロジェクトに興味のある研究者同士が互いに協力して研究することも奨励しています。こうして生まれた共同研究プロジェクトは、必然的に学際的な色彩を帯び、問題解決の近道となります。
IITBでは、ナノテクノロジー、デジタル・ヘルス、AI、マシン・データ分析等の分野で新たに研究拠点を創設しました。これらのセンターでは、様々な分野の研究者が協働して学際的な研究を行っています。
IITBの主な取組:研究開発部門によるイノベーション創出のための環境整備
IITBの研究開発部門は、研究者に居心地の良い「コンフォート・ゾーン」から踏み出して起業家的なアプローチを採ることを奨励しています。開発中のテクノロジーの特許をとって、若い研究者が革新的なプロジェクトで起業できるようサポートも行っています。少し前までは、「新たな知見は無償で提供するべきだ」という信念を持ち、新規技術の特許申請を躊躇う研究者も少なくはありませんでした。しかし近年、新技術の特許を取得して、その技術をスタートアップ企業に投資することの価値を正しく理解する研究者が増えてきています。
IITBと産業界との提携は、新規技術開発プロジェクトの展開に不可欠です。研究開発部門の主な仕事の一つは、そうしたプロジェクトの研究管理業務です。
研究開発部門では、プロジェクト提案の承認、契約書の完成、会計管理、採用、知的財産管理等、研究管理の全てのステップをオンラインで処理しています。IITBには、こうした研究管理プロセスを全て記録する統合ポータルがあります(補足:アトレイ博士らは、現在、このポータルをドイツのSAP社が提供するERPシステムと統合して、さらに堅牢なシステムを構築中)。
その他の業務としては、IITBで独自の研究室を立ち上げる新任教授のために、研究環境を整備することが挙げられます。IITBに新たに着任する教授は、世界中から集まった、各分野でトップレベルの研究者で、将来を嘱望されています。彼らが研究をスムーズにスタートさせ、情熱を維持できるよう、IITBは研究立ち上げのための資金の提供を行っています。加えて、研究開発部門は、IITBで開発された技術の特許申請等、知的財産の保護に関する業務も担当しています。
また、研究開発部門は、IITBの研究から生まれた最新の成果やテクノロジーをまとめたAnnual Reports[参考5]を作成しています。企業に共同研究プロジェクトを提案する際、ウェビナーと併せて、本レポートを資料として活用しています。
他には、IITBの研究者と産業界のパートナーとが交流し、アイデア共有や情報交換ができる場として、非公開カンファレンスの運営も行っています。
DSSEによる起業カルチャー育成プログラム
近年、インドの学生や若手研究者の間で、新しいテクノロジーの創出や起業に対する関心が高まりつつあります。そうした若者に役立つのが、Desai Sethi School for Entrepreneurship(DSSE)で行っている起業家精神を学ぶ副学位プログラムです。このプログラムでは、革新的なプロジェクトやスタートアップを実際に見学することができる他、技術の知的財産権、マーケティング、コミュニケーション、資金確保等について学ぶことができます。プログラムに参加した学生の約10%が起業家となります。
起業には、ビジネス展開、経理、次世代テクノロジー、リソース管理等の様々な側面がありますが、研究者にとってはそのどれもが困難を伴うもので、一筋縄ではいきません。
また、IITBは、起業は男性優位だという先入観をもつ人が未だに多いという現状を打破すべく、女性も起業家精神について学ぶことを奨励しています。
SINEによるイノベーション創出を促す組織風土の醸成
Society for Innovation and Entrepreneurship(SINE)への参加を希望する研究者は、新しい技術の具体的なアイデアを持ち、そのコンセプトを実証するとともに、同じ目標に情熱を持って向かう仲間を見つけ、チームを作る必要があります。
また、起業のアイデアはテクノロジーに関連したものである必要があります。SINEの学生及び若手研究者には250万インドルピー(約400万円)の研究資金が与えられるほか、オフィス、リソース、必要に応じた卒業生や教授によるメンタリング、IITBが有する全てのテクノロジー・エコシステムの利用が可能となっています。さらに、TechfestやE-Summitの他、E-Cell[参考6](起業を目指すIITBの学生主体の団体)が主催する様々なイベントへの参加を通じて、世界に新規技術を紹介する機会も得ることができます。イベントには、将来性のあるスタートアップを見つけて投資するベンチャー・キャピタリストも数多く参加しています。こうしたイベントへの参加は、投資家に対して存在感をアピールする絶好の機会となります。
アトレイ博士はSINEの担当教授を務めていた当時、若手研究者に適切なリソースの提供やサポートを行い、技術開発を支援していました。こうした活動を通じてSINEを様々な学部や教授とつなげることにより、SINEはIITBのイノベーションを促進する組織文化の一端を担う存在となりました。
 起業家精神を養い、学生によるスタートアップを育成するIITBのSINE。画像提供:IITB SINE
起業家精神を養い、学生によるスタートアップを育成するIITBのSINE。画像提供:IITB SINE
SINEとDSSEの人気と評価

DSSEで起業に興味を持つ学生に対し、メンターとして指導する教授。画像提供:IITB
一般的に、学生や若手研究者は、座学よりも実践的なアプローチを必要とするプロジェクトから学ぶことが多いと言われています。DSSEでは、まさにそうした実践的なアプローチを奨励しています。
IITBでは学生や若手研究者がユニークかつ多様なプロジェクトに参加しており、それが研究開発及び起業エコシステムを駆動する原動力となります。その好例が、IITBの学生と研究者のグループが開発したレース・カーです。このレース・カーの開発には、電気、機械、土木等、工学に関する様々な分野の学生が開発に参加し、国際コンクールで様々な賞を獲得しました。また、1年目の学生と研究者を対象とした、学生主導のプログラム“Ideas Program”は、はんだ付け、3Dプリンティング、製品組み立て、データ収集等の多様なスキルを身につけるためのトレーニングを提供しています。
こうしたプロジェクトが実現する背景には、プロジェクトに興味を持った若い研究者が、必要なリソースを得ることができる環境があります。IITBにおいては、DSSEとSINEこそがその役割を果たす組織であり、研究者にとってなくてはならないサービスといえるでしょう。
SINEは現在までに約175のスタートアップのインキュベーションを行ってきました。昨年だけでも、IITBは250件の知的財産申請を行っています。
IITBでは、研究や起業の過程で生じた知的財産を保護するためのシステムやプロセスが整備されています。エネルギー効率向上技術を提供するスタートアップ企業として成功をおさめているAtomberg社も、IITBにルーツを持ちます。また、ドローンの開発企業として名をあげ、国境警備軍の監視機能を担うまでに成長したideaForge社も、IITBでインキュベートしたスタートアップです。
-

IITBの機械及び電気工学分野の60名以上の学生が開発した一人乗り電気レース・カー。写真のレーシング・チームは、英国で開催されたFormula Student 2014レースに参加した。画像提供:IITB
-

IITBの学生衛星開発プログラムに参加した学生と研究者。画像提供:IITB
起業カルチャーとイノベーション創出についての今後の展望
インドの産業界は、インド発の新たなテクノロジーへの投資にますます力を入れるようになってきています。インドの研究者が行っている研究の重要性は広く認知されるようになりつつあり、そうした人材の採用を検討する会社や、アカデミアとの共同プロジェクトを開始する会社は、増加傾向にあります。
産業界からアカデミアに提供される資金が増えるほど、研究成果が商用化・実用化される可能性も高まり、一層社会に貢献できると期待されます。
研究規模を拡大し、商用化にまで至る技術を今よりも増やすためには、IITBのキャンパス内で、新技術の技術成熟度レベル(TRL)を引き上げるためのシステムの整備が必要です。そうしたトランスレーショナルリサーチセンターをIITBに創設することができれば、起業家や研究者にとって大きなメリットになるでしょう。
また、テクノロジー分野の学生や若い研究者はしばしばテクノロジー以外の分野の知識が不足していることから、ビジネス、マネジメント、流通、経済分野のバックグラウンドを持つ学生との協力を通じて、スキルの向上を図ることも大切です。研究は社会に資するものであるべきで、そのためにはマネジメントやデザイン、人文分野等の広い知識が必要となります。
イノベーション創出のための研究のあり方
研究に対して抑えられない情熱を感じるのであれば研究の道にぜひ進むべきですが、決して消去法で選んではいけません。
研究者はもっと多様な組織、業界と協働すべきであり、社会に直接関わる問題について、専門家の立場から研究を行い、研究で見い出したソリューションを社会全体に行き渡らせるために、様々な組織、研究所、産業界、またはスタートアップ企業等とも協働する必要があると考えます。
本記事の参考資料、関連するサイト
- [参考1]IIT Bombay: Indian Institute of Technology Bombay: IITB
- [参考2]Desai Sethi School of Entrepreneurship(DSSE)
- [参考3]Society for Innovation and Entrepreneurship(SINE)
-
[参考4]Prof. Milind D. Atrey
Atrey博士のホームページ。ご経歴や研究業績等
-
[参考5]Annual Reports
IITBの年次報告書
-
[参考6] E-Cell IIT Bombay
トップページにE-Summit等のイベントについての案内が掲載
本記事で紹介する取組一覧
| 取組名 | コンピテンシー |
|---|---|
| 研究開発部門における取組 | |
プロジェクトの研究管理業務 |
|
研究立ち上げのための資金の提供 |
|
特許申請等、知的財産の保護に関する業務 |
|
非公開カンファレンスの運営 |
|
| Desai Sethi School for Entrepreneurship(DSSE)における取組 | |
起業家精神を学ぶ副学位プログラム |
|
| Society for Innovation and Entrepreneurship(SINE)における取組 | |
研究資金 |
|
オフィス、リソース、必要に応じた卒業生や教授によるメンタリング、IITBが有する全てのテクノロジー・エコシステムの利用 |
|
E-Cellが主催する様々なイベント |
|
取材日:2022年2月
取材協力:カクタス・コミュニケーションズ株式会社