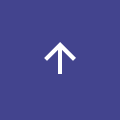海外事例 フランス国立科学研究センター(フランス)
特定のテーマに特化した短期プログラムと“ユニット”単位のトレーニング・プラン
—フランス国立科学研究センター(CNRS)の専門能力育成—
本事例は、プログラムフレームワークの上記のコンピテンシーに関連しております。
CNRSは科学誌Natureによる2021年の世界国立組織ランキングで2位に輝く等、世界的な研究機関ランキングトップ5の常連である。CNRSの高い生産性を支えるのは、CNRS独自の研究テーマ別短期プログラムthematic schoolsと、研究室単位で行われるUnit Training Planの存在だ。研究者及び他のスタッフと緊密な連携をとりながら、研究者のスキル向上やキャリア開発をサポートしているCNRS人事部門のクリスティアン・イネム氏とヘレン・レバス氏、国際協力部門のエドゥアルド・ベサーヴ氏に、CNRSにおける研究者を対象としたプログラムについてお話をうかがった。
機関について
フランス国立科学研究センター(Centre national de la recherche scientifique: CNRS)[参考1]は、フランスの国立研究機関であり、ヨーロッパ最大の基礎科学研究機関で1,144の研究室及び3万3,000名の研究者を抱える。
研究者育成の取組について
毎年、研究者のトレーニングや能力開発を行っており、同組織が重点をおく取組の一つが、thematic schools(テーマ別スクール)[参考2]と呼ばれる、特定の研究テーマに特化した短期プログラムである。このthematic schoolsでは、扱う研究テーマに関連した最先端のトレーニングを受けることができる他、専門家と交流し、共同研究を行う機会も得ることができる。
また、CNRSでは各研究室が所属する研究者を対象として、ラボワークに必要なスキルと併せて、個別のキャリア開発プランを考えるUnit Training Planと呼ぼれるトレーニング・プランを提供している。CNRSは、これらのプログラムや他のトレーニングを通じて、研究者が科学的な知識及び最先端の研究スキルや技術を身につけ、キャリアアップが実現可能になるよう支援している。
インタビュイーについて
クリスティアン・イネム(Christiane Ename)氏及びヘレン・レバス(Hélène Lebas)氏は研究者育成とトレーニングに深く関与し、エドゥアルド・ベサーヴ(Edouard Besserve)氏はCNRSの国際協力部門で活躍している。
- クリスティアン・イネム氏は、CNRSの人事部門の研究者トレーニングおよびキャリアパス課(SFIP)の課長を務めている。

- ヘレン・レバス氏は、CNRSの人事部門で研究者の能力開発サービスを担当している。

- エドゥアルド・ベサーヴ氏は、CNRSのアジア及びヨーロッパ研究部門と国際協力部門の副部長を務めている。

研究者のキャリア構築をサポートする短期トレーニング・プログラム

CNRSの物理学をテーマとしたthematic schoolの参加者。School of Les Houches (Ecole Des Houches)内の一室。画像提供:CNRS
どんな仕事でも、円滑に業務を進めるためにはトレーニングが必要ですが、特に日進月歩で変化する科学分野では、トレーニングは欠かせない要素です。しかし実際には、ほとんどの大学や研究機関は、研究者に対して、上司や先輩にあたる研究者からの研究に関する指導しか行っておらず、それ以外のトレーニングを必須プログラムとして組み込んでいる組織はほんの一握りです。CNRSは、そうしたプログラムを持つ数少ない研究機関の一つといえます。
CNRSは研究者の能力開発プログラムにいち早く取り組み、これまで長きにわたって研究者をサポートしてきました。CNRSにおける研究者の能力開発プログラムには、トレーニング、評価、キャリアアップ、ボーナスや表彰等が含まれます。レバス氏とエネミ氏は、研究者の人事評価やボーナス、昇進の手続きの他、個別のサポートを提供するチーム(以下、チーム)に属しており、ベサーヴ氏が所属する国際協力部門も同チームをサポートしています。チームは、ワークショップを通して専門的な研究プロジェクトを構築するためのツールを研究者に提供し、研究者が研究目的やプロジェクトについて検討する手助けをしています。
CNRSは毎年、全ての科学分野を網羅する102のテーマ別短期トレーニング・プログラム thematic schools を開講しています。thematic schools は、研究者自身の発案によって実施されます。先ず、トレーニングのテーマとしたい研究アイデアを持つ研究者が、自分の研究チームのメンバーと話し合い、トレーニング・プロジェクトを提案します。次に、提案されたプロジェクトにマッチする分野の担当者が書類を審査し、thematic schoolsの研究テーマにあったトレーニング・プロジェクトを採択します。最終的に、毎年102のプロジェクトが採用されます。採択するプロジェクトが決定した後、チームが予算の割り当てを決定します。興味のあるCNRSの研究者やスタッフは無料でトレーニング・プロジェクトに参加でき、希望するあらゆる科学分野でトレーニングを受けることができます。トレーニングを通じて、研究者は、論文を発表したり、研究パートナーを見つけたりすることができますし、場合によっては他のプロジェクトと協働して、最終的にはプロジェクト同士が融合して一つになることもあり得ます。それぞれの研究テーマの分野の専門家を招いて話を聞くこともあります。thematic schoolsの終了後も、プロジェクトを通じた仲間との交流は続きますので、更なる研究の発展が期待できます。実際、thematic schoolsはこれまで、素晴らしい成果をあげてきました。
CNRSは過去7~10年間のthematic schoolsの記録をオンラインで提供しており[参考3]、これまでのトレーニングのテーマやポイント、テーマに関連した大学や研究機関等を閲覧することができます。
トレーニングはあくまで仕事の一部
CNRSが実施するトレーニングは、thematic schoolsだけではありません。CNRSはフランス政府から年間900万ユーロの予算を受け取り、人事部はその予算を3万3,000名のメンバーに割り当てます。予算のうち100万ユーロはthematic schools用に確保しており、残りの予算は他の様々なトレーニングに使用されています。
フランスでは、全ての企業でスタッフのトレーニングにかかる費用が給与の一部として組み込まれています。CNRSでも、研究者や他のスタッフがトレーニングを受ける時間は勤務時間とみなされます。おおまかな見積りでは、CNRSの給与のうち1.5%から1.7%がトレーニング費用にあたります[参考4]。
未来を見すえた研究者トレーニング

CNRSは研究室を一つのユニットとしてとらえ、各ユニット特有のニーズやユニットで必要なスキルに応じたトレーニング・プランを開発している。画像提供:CNRS
CNRSのキャリア・ウェブサイト[参考5]では「トレーニングとは、自分のキャリアにおけるactor(当事者)であるということだ」と宣言して、様々なトレーニングを重視する姿勢を強く打ち出しています。CNRSにおけるactor(当事者)、つまりCNRSのスタッフ、研究者、トレーニングを提供するエージェント、管理職全てが、自分の担当部署で必要なトレーニングについての発言権を持つということです。CNRSでは、CEOや人事管理職を含むさまざまなactor(当事者)に対して、それぞれの立場の目的にあったオリエンテーションを提供する戦略的トレーニングを年間複数回にわたって行っています。
CNRSのトレーニングの第一の目的は、未来の研究者を育てるということです。これには研究者にとって新しい、未知の分野のトレーニングも含まれます。第二の目的は、専門能力開発や人間としての成長で、これには研究者としてのキャリア・ゴールを明確にすることも含まれます。第三の目的は、トレーニング内容自体を発展させることです。例えば、CNRSは5年前にデジタルおよびコンピュータ・サイエンスのトレーニングの必要性を予見し、以来、eラーニング・セッションの開発に取り組んできました。3年前は理解してもらうことが困難だったeラーニングの必要性は、パンデミックによりその有効性が実証されました。
研究室と研究者個人、双方のニーズの満たすUnit Training Plan
CNRSは、トレーニング・プログラムのデザインにあたってユニークな方法をとっています。Unit Training Planは、ユニットのリーダーが設計するユニット特有のトレーニング・プランで、「ユニット」は研究室に限らず、部署、大学の研究者以外のスタッフからなる特定のチームの場合もあります。Unit Training Planは、トレーニング内容について説明するパートと、ユニットの管理者や監督者がそのプロジェクトを遂行する上で必要なものとして要求したスキルを身につけるために、実際にトレーニングをするパートからなります。提出されたUnit Training Planを70名のトレーニング・カウンセラーがチェックし、人事部にトレーニング案及び予算の見積もりを提出します。
ワークライフバランスを実現する柔軟なトレーニング日程
CNRSは大規模にトレーニングを行っていますが、ワークライフバランスを考慮して、トレーニングは通常の勤務日に行うよう指導しています。フランスの組織は、トレーニングを仕事の勤務と同等とみなします。CNRSでは、約半数のメンバーが、平均で最低年間2日間のトレーニングに参加しています。
管理職がリクエストした必修のトレーニングもありますが、その他のトレーニングは参加者が日にちや時間を選ぶことができます。こうした選択肢の広さは、ワークライフバランスに重きをおくCNRSの姿勢の表れです。
eラーニングと対面トレーニングを組み合わせて効果を最大化

Saint-Flourで開催されるCNRSの数学分野のthematic schoolは、世界的に有名な夏期プログラムの一つである。画像提供:CNRS
チームはこれまでに、研究者向けの様々なトレーニングを展開し、大きな成果をあげてきましたが、今後はさらに内容を充実させていきたいと考えています。具体的には、研究者の能力開発トレーニングに、eラーニングを対面トレーニングと組み合わせた時間的にフレキシブルなプログラムの開発等です。また、研究者がキャリアや研究の進展に応じて必要とするスキルを身につけられるように、より幅の広いトレーニング・プログラムを提供することも重要です。
CNRSでは研究者の20~21%、エンジニア及び他のスタッフの69~70%が毎年何らかのトレーニングに参加しています(国主催のトレーニング、thematic schoolsトレーニング、及び地域ごとのトレーニングを含む)。CNRSでは、そうしたトレーニングの追跡調査を定期的に行っています。thematic schoolsに限れば、トレーニング参加者の80%が研究者で、期間は平均5日間です。しかし、全般的に見れば研究者のトレーニング参加率は高くありません。これは、研究室で過ごす時間こそがトレーニングになると考える研究者が多いことが一因だと考えられます。CNRSは他にも、研究者を対象とした研究室運営やパートナーシップの確立等、研究スキル以外のトレーニングも提供しています。
講師同士が教え合うシステムも構築中
CNRSでは年度ごとにキャリア・プランを作りますが、次年度に向けた計画の一部として内部臨時講師(internal occasional trainers)プログラムを開発中です。トレーニング・セッションの講師は、外部企業またはCNRSのメンバーが務めますが、CNRSのメンバーが講師を務める場合、彼らを内部臨時講師と呼んでいます。この内部臨時講師システムはCNRSですでに10年以上にわたって継続してきましたが、内部臨時講師はトレーニングする側としての正式な指導を受けていませんでした。そこで最近、600名の内部臨時講師を対象にアンケートを行ったところ、教育方法についての現行の4日間のトレーニング以外の指導も受けたいと希望していることがわかりました。これを受けてCNRSは、内部臨時講師が自分の得意分野に関するeラーニング・セッションをデザインできるツールを提供し、講師同士で教え合えるようなシステムを構築する予定です。
トレーニング=研究機関としてのビジョンを達成するための戦略
CNRSは、トレーニングは組織がビジョンを達成するための戦略として活用すべきだという理念を持っています。そのためには、ビジョン、戦略、そして研究者の能力開発やトレーニングの目的を明確にする必要があります。目標達成のためにどのようなスキルが必要か、組織に欠けているスキルは何かを理解できてはじめて、そのギャップを埋めるためにどうしたらよいかが見えてきます。
ギャップを埋めるために必要なものは、必ずしもトレーニングではありません。情報やコミュニケーションが必要な場合もありますので、柔軟な対応が求められます。さらに、トレーニングは誰でもできるものではないということも、常に頭に入れておかなければなりません。トレーニングが必要な分野のプロフェッショナルや、トレーニングの必要性を理解する研究者の存在が不可欠です。該当する分野の科学的な知識をもち、研究テーマがトレーニングに値するかどうか判断できる専門家との協力が必要になります。
また、研究者にトレーニングの必要性を理解してもらうことも重要です。研究に関する従来通りの指導以上のトレーニングを受けることに消極的な研究者も、依然として多いのが現状です。先ずは、数は多くはないかもしれませんが、興味を示す研究者にトレーニングの機会を提供することが重要です。彼らがトレーニング・プログラムに満足し、その意義を感じれば、他の研究者にもその評判が伝わり、より多くの研究者がプログラムに参加するようになり、また評判が広がって参加者が増えるという好循環が期待されます。
本記事の参考資料、関連するサイト
- [参考1]Centre national de la recherche scientifique: CNRS
-
[参考2]GUIDE DE PRÉPARATION ÉCOLE THÉMATIQUE CAMPAGNE 2023
thematic schoolsのガイドブック(フランス語)
-
[参考3]Écoles thématiques
thematic schoolsの紹介ページ。アーカイブも公開(フランス語)
-
[参考4]FORMATION PLAN NATIONAL D’ORIENTATION 2020-2023
CNRS職員研修ガイドライン(フランス語)
-
[参考5]CAREERS CNRS
本記事が紹介するCNRSのキャリア支援の方針や取組等の概要(英語ページもあり)
本記事で紹介する取組一覧
| 取組名 | コンピテンシー |
|---|---|
thematic schools |
|
Unit Training Plan |
|
研究室運営やパートナーシップの確立等、研究スキル以外のトレーニング |
取材日:2021年11月
取材協力:カクタス・コミュニケーションズ株式会社