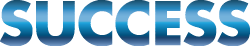インタビュー

変わる糖尿病ケアの未来
JST支援が日本発ヘルステックを後押し
株式会社Provigate
CEO 関水 康伸 氏
糖尿病患者の血糖モニタリングシステム「glucoreview®」を開発し、低/非侵襲性の在宅検査機器とアプリを組み合わせた行動変容を支援するサービスの社会実装を目指す株式会社Provigate。技術開発および創業から今に至るまでの軌跡、その過程で活用した制度、今後の展望について、CEOの関水康伸氏にお話を伺いました。
糖尿病患者の血糖測定における負担軽減を目指したバイオセンサー開発

Q、まずは会社概要をご紹介ください。
関水 当社は糖尿病およびその予備群の方を対象に、在宅型の血糖測定センサーと専用アプリの開発を行う東京大学発のスタートアップです。「グリコアルブミン(GA)」という1週間の平均血糖を示すバイオマーカーを週に一度測定し、その結果をアプリで確認。利用者が自ら行動目標を設定・実行し、その成果をGAの変動で確認できる仕組みを提供しています。糖尿病の進行・重症化防止に欠かせない、食事・運動・服薬の行動変容を支援することを目的としています。
Q、創業のきっかけについてお聞かせください。
関水 2013年、JSTの「START(研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム)」の起業実証支援にて、東京大学工学系研究科の坂田利弥先生を中心に、涙糖(涙に含まれるグルコース)を計測するセンサーが開発されました。翌年、事業化のお話を頂いたのですが、血糖モニタリングはレッドオーシャンゆえ当初は起業に消極的でした。しかし、坂田先生にお会いするとすぐに意気投合、2014年には『Nature Biotechnology』の特許被引用ランキングで4位になったほか、当該技術をライセンスした米国のスタートアップが7億ドル以上で買収されるなど、素晴らしい実績をお持ちでした。 技術オリエンテッドの事業開発では、市場規模が小さいと一つの技術シーズの成否が事業化の成否も左右しますが、糖尿病は世界人口の約1割が抱える病です。すでに各国で大きな社会問題になっており、多様なアプローチを探れる分野です。日本の優れた技術が国内では活用されにくいという現状へのもどかしさもあり、坂田先生とならグローバルな視点で新しいイノベーションが起こせると確信し、2015年に創業しました。
涙糖からGAへ。バイオマーカーの転換でブレークスルー

Q、涙糖センサーから、現在の血糖センサー開発に至った経緯をお聞かせください。
関水 創業から5年間は苦戦の日々でしたが、血中タンパク質の一種「アルブミン」にグルコースが結合したグリコアルブミン(GA)が、涙液や唾液にも入っており、しかも血液GAと極めて高い相関を持っていることを2016年に突き止めました。涙糖は採取条件によって濃度が大きく変動する課題がありましたが、GAは濃度測定ではなく分子内の透過度を%で示すテストなので、検体種を選ばず正確です。特に唾液は容易に採取することが可能ですので、誰でも手軽に血糖状態を把握できるGAセンサーの開発に着手したのです。QバイオマーカーをGAへ変更したメリットついて、詳しく教えてください。
関水 今日の糖尿病医療では、数か月の1度の通院・採血にて、1~2か月の平均血糖を示すHbA1c(ヘモグロビンA1c)値を見る方法が一般的です。しかし、例えば通院前の数日間、食事や運動に気を配ってもすぐに数値に反映されないため、モチベーションの維持・向上には不向きです。他方、在宅型の自己血糖測定(SMBG)は瞬間の血糖値をスナップショットとして把握できますが、血糖変動の全体像を知るためには1日数回の指先採血が必要ですので、痛み・手間・コストが障壁になっています。また、持続血糖測定(CGM)は7mmほどあるワイヤー状のセンサーを皮下に埋め込むため万人向けではなく、2週間毎に付け替えるためにコストも高いといった問題がありました。 一方、GAの場合は、直近1週間程度の平均的な血糖状態をたった週1回の在宅検査で把握できるうえ、数日から1週間程度の行動変化の結果が反映されます。加えて、GA値は血糖値のように食事のたびに大きく変動せず、なだらかに推移するため、測定のタイミングは自由です。平均血糖をシンプルに示すので「今週は旅行で炭水化物が多く、少し上がったから来週は改善しよう」といった自己評価がしやすい点も行動変容のモチベーション維持につながります。さらに、通院や採血の負担を大幅に軽減できるうえ、経済的負担の軽減にも寄与します。遠隔医療にも効果的で、公衆衛生のゲートキーパーであるクリニックの経営安定化・生産性向上にもつながることが期待できます。JSTの支援が創出した事業パートナーとの出会いと資金調達の誘因

Q、起業・研究開発を進めるうえで活用したJSTの支援と、その効果について教えてください。
関水 創業には資金が必要になりますが、人とのご縁も大切です。坂田先生とはJSTの「START」で出会いました。JSTには当社の事業に関心のある企業や投資家をご紹介いただき、それが出資につながったケースもありました。人的ネットワークの拡大において、JSTがまさに架け橋となっています。また、2020年に出資型新事業創出支援プログラム「SUCCESS」の出資を受けましたが、これが本当に大きな支えになりました。
Q、「SUCCESS」の効果は、どのようなものだったのでしょうか。
関水 正直、「SUCCESS」がなければ、とっくに潰れていました(笑)。公的機関からの出資は民間VCの投資判断の有力な根拠となりますが、「SUCCESS」のおかげで民間投資家からの出資が拡大したのは事実です。まだ海外の投資家からの出資は得ていませんが、JSTが出資している旨を海外VCに話すと、驚かれるとともにプラスに評価されます。また、2024年には「SUCCESS」の追加出資がされ、さらなる信頼性向上と「呼び水効果」を生みました。他の公的助成金とは異なり、「SUCCESS」は使用用途が限られていないことも大きな魅力です。
グローバル視点で挑むディープテックの未来

Q、JSTの支援プログラムについての感想をお聞かせください。
関水 この10年で日本のディープテック企業を取り巻く環境は格段に良くなりました。とりわけ、JSTのプログラムが劇的に進化していることが大きく影響していると思います。2012年に「START」が始まり、大学の基礎研究と起業家、投資家を結ぶ仕組みが作られました。「START」には、単なる学術振興ではなく、積極的に科学技術を基盤とした新産業を創出するという意図が感じられます。さらに、2014年に開始された「SUCCESS」のように、シード期から成長期まで継続的に支援するプログラムが整備されたことで、スタートアップをより確実に育てる体制が整ったのではないでしょうか。
Q、若手研究者やスタートアップを考えている人たちにメッセージをお願いします。
関水 国内では今もなお、数々の画期的な発明が誕生しています。しかし、それを実用化し、世界に広げるイノベーションは米国で起こるという歴史が長く続きました。これは、大学の知財を産業に結びつける制度に関して、日本は米国に比べて20年ほど整備が遅れていたことが一因です。JSTのプログラムをはじめとする国の支援は、この課題を克服し、日本の優れた科学技術をイノベーションにつなげるための重要な原動力となっています。 またディープテック分野において、以前は資金調達や情報収集が難しかったのですが、今は制度も充実しています。国内市場だけを考えるのではなく、海外進出を視野に会社設立の段階からグローバル投資家を入れることも重要だと考えています。JSTなどの制度を賢く利用し、産学連携を推進させ、一緒に成功に向けて頑張る起業家仲間が増えると嬉しいです。
Q、今後の目標を教えてください
関水 現在「glucoreview®」は指頭血の郵送検査にてパイロット展開していますが、さらにその先には、在宅検査機器の小型化・量産化を進めつつ、より負担の少ない涙や唾液での測定実用化を目指しています。将来的には、アナログ在宅検査・デジタルAIアプリ・人的サービスをベストミックスで組み合わせたハイブリッドな医療サービスとしてグローバルに普及させ、医療現場の効率化や医療費削減を通して世界に貢献したいと考えています。 「糖尿病は自己責任」「糖尿病の人は習慣を変えられない」という誤ったスティグマが根付いていますが、発症には体質などの個人差がありますし、行動変容に必要なのは強い意志ではありません。必要なのは、糖尿病のある方や予備群の方を孤独にさせることなく、適時適切なフィードバックと周りのサポートが受けられる体制を経済合理的に実現することです。テクノロジーによって糖尿病に対する社会の偏見を無くすことを通し、誰もが幸せで、持続的な社会を築く一助となること。これが当面の目標です。
- 株式会社Provigate
-
〒113-0023 東京都文京区向丘2丁目3-10 東大前HiRAKU GATE 5F
- 主な事業内容
- 家庭用血糖モニタリングデバイスおよびアプリの開発