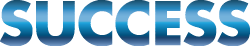インタビュー

カイコが作り出す「経口ワクチン」を開発
資金調達で苦戦していたとき「SUCCESS」出資が風向きを変えた
KAICO株式会社
代表取締役 大和 建太
氏
「カイコ-バキュロウイルス発現系」の応用による難発現タンパク質生産を強みとする九州大学発のバイオベンチャー、KAICO株式会社。「九大独自のカイコ系統×KAICOのゲノム技術」を活用した、医薬用タンパク質の合成・経口ワクチンの開発を軸に、環境保全や地域創生にもつながるビジネスモデルを構築中です。カイコ(蚕)の可能性を最大限に引き出し、革新的な医薬品開発に挑む同社の代表、大和建太氏にお話を伺いました。
カイコを「製糸工場」から「タンパク質工場」に

Q、まずは、会社概要についてご紹介ください。
大和 当社は「カイコで世界を変えていく。」をミッションに掲げ、独自の技術でカイコをバイオリアクター、すなわち「タンパク質の製造工場」として活用しています。具体的には、バキュロウイルスというカイコのみに感染する特殊なウイルスに、バイオ医薬品やワクチンに必要なタンパク質の遺伝子を組み込み、カイコ体内で大量生産させる仕組みです。現在、この技術を応用した経口ワクチン(食べるワクチン)の開発・普及に注力しており、安価で効率的な医薬品提供を目指しています。
Q、なぜカイコに注目したのでしょうか。
大和 九州大学農学部では、養蚕の品種改良を起点に100年以上前からカイコの飼育・遺伝子研究を行っており、世界最多の800種以上の系統を保有しています。ご存じの通りカイコは絹糸を作りますが、実は家畜化された唯一の昆虫であり人間のお世話がないと死んでしまいます。かねてから製糸業衰退に伴う養蚕農家の廃業への危機感や、種の保存にかかる研究費確保の面から、絹糸以外の用途を探す研究が進められていたのです。 その中で大学院農学研究院長・日下部宜宏教授が着目したのが、養蚕では致命的な「バキュロウイルスに罹りやすい系統のカイコ」を用いて、効率的にタンパク質を作る技術でした。医療用タンパク質の合成には大腸菌や哺乳類の細胞を培養する方法がありますが、カイコを使えば従来合成が難しかった分子の大きなタンパク質(酵素、抗原、抗体タンパク質など)を高品質で生産することができます。加えて、カイコ1頭から約1,000人分のワクチンを作れるほか、2畳ほどのスペースで約2万頭を飼育できるため、大量生産と省コスト化が可能です。
出会いが紡いだ商業化への可能性と、偶然が生み出した「食べるワクチン」

Q、創業の経緯をお聞かせください。
大和 私は文系出身で民間企業に勤めていたのですが、40代を目前に「もっと社会に貢献できる面白いことに挑戦したい」と入学したのが、九州大学のビジネス・スクールでした。在学中、新しいビジネスシーズを探していた際に日下部先生と出会い、このユニークな技術に、直感的に大きな可能性を感じたのです。JSTの「START(研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム)」の起業実証支援を利用して、まずは技術を熟成させつつ事業化の準備を進め、3年後の2018年にKAICO株式会社を創業しました。Q、経口ワクチンを開発中とのことですが、その経緯についてもお聞かせください。
大和 創業当初は製薬会社と共同での医薬品開発を試みましたが、カイコの技術に興味は持っていただけても協業には至らず、結局、自社製品を開発することになりました。試行錯誤の中、ブタ用の注射型ワクチンの研究中に、たまたまカイコの蛹(さなぎ)を実験用マウスに食べさせたところ、その体内で抗体ができたのです。通常、タンパク質は消化されてしまうので、特別な処理をしない限りワクチンの効果は出ないはずなのですが、この偶発的な発見が「食べるワクチン」の開発へとつながりました。 その後、新型コロナウイルスのパンデミックにて、注射型ワクチンの課題(医療従事者や冷凍保存の必要性、強い副反応など)が浮き彫りになり、途上国にも届けられて誰もが簡便に摂取できる錠剤型の経口ワクチンの必要性を強く実感。これが研究を加速させる決定打となりました。現在は、ブタ用の粉末型経口ワクチンの実用化がベトナムで始まっており、すでに飼料添加物として現地での登録が完了しています。今後は人用のワクチンへと段階的に広げていく予定です。単なる資金提供を超える「SUCCESS」の「お墨付き」効果

Q、JSTの出資型新事業創出支援プログラム「SUCCESS」の効果はいかがでしたか?
大和 「カイコで医薬品を作る」という前例のない研究開発だったため、当初はなかなか民間の投資家や企業に信用してもらえませんでした。しかし2020年、「SUCCESS」に出資され、国の機関からのいわば「お墨付き」をいただいたことで、他のVCからの出資を呼び込む大きなきっかけとなりました。「SUCCESS」が私たちの研究の信頼性を確認する際の技術リファレンスとして機能したことで、カイコ技術の生物化学的な部分の理解が難しかった投資家からも出資していただけるようになったのです。「SUCCESS」は単なる資金提供以上の大きな意味がありました。
Q、その他、JST支援の効果としては、どのようなものがありましたか?
大和 「START」では事業化ノウハウを持つ事業プロモーターとマッチングしていただいたほか、JSTの担当者からは資金調達の際のストーリー作りからピッチ資料の改善に至るまでさまざまな助言をいただきました。また、JSTの支援先である他の大学発ベンチャーとのつながりを作っていただき、さらに『BioJapan』のような大きな展示会に出展する機会を与えていただくなど、事業成長に不可欠なネットワーキングや情報発信の面でも大いに助けていただいております。JSTの支援は、大学発ベンチャーを成功へと導くための、心強い伴走者だと感じています。
事業拡大が社会貢献につながる。大学に眠る技術シードを社会へ

Q、今後の展望について教えてください。
大和 ブタ用経口ワクチン事業には、年間1,500万頭以上のカイコが必要となります。かつて日本の養蚕は基幹産業・主要輸出品であり、明治時代には年間約2,000億頭も生産されていましたが、価格安定制度も廃止となった現在は年間約2,550万頭と最盛期のわずか0.01%ほどにまで落ち込んでいます。 そこで私たちは、量産化に向けて各自治体や民間企業と連携し、新たな養蚕業の創生を目指しています。例えば、カイコの餌である桑の木を耕作放棄地に植樹したり、廃校を活用して高齢者や障がいのある方の雇用機会を創出したりすることで、環境保全や地方創生に貢献できます。また、生糸や化粧品の原料となるシルクは繭(まゆ)の部分を利用し、中の蛹は廃棄処分されていましたが、当社は蛹を利用しますので、SDGsにも寄与します。「養蚕農家を守るため、安定した取引価格を維持できる『医薬品』を作る」という目的から始まった事業ですが、事業拡大がさまざまな社会貢献へとつながるため、私自身、今後の展開が楽しみです。 2026年には、まずは注射型からになりますがノロウイルスのヒト用ワクチンの臨床第1層試験を行う予定です。昆虫を使用したワクチン・医薬品は前例がないため、長い道のりにはなりそうですが、実用化に向け一歩ずつ進んでいくつもりです。
Q、これから創業を考えている起業家に向けて、メッセージをお願いします。
大和 若い起業家の方々には、まずは自分のアイデアで挑戦してほしいと思います。一方、ある程度の社会人経験を積んだ方は、ぜひ大学発ベンチャーという選択肢も考えてみてください。長年の会社勤めで培ったコミュニケーション能力や調整力は、大学や教授との協業において大きな力になります。大学には、まだ世に出ていない優れた技術シーズが数多く眠っています。大切なのは、「研究者が持つ素晴らしい技術をどう社会で活かすか」という視点です。自分に突出した技術や才能がなくても、自身の経験と大学の知財を組み合わせることで、新たな価値を生み出せる可能性があるのです。大変なことも多いですが、そのやりがいは何倍にもなって返ってくると思います。
- KAICO株式会社
-
〒819-0388 福岡県福岡市西区九大新町4-1 福岡市産学連携交流センター
- 主な事業内容
- タンパク質受託発現、試薬・診断薬・医薬品原料の製造・販売、動物用経口ワクチン、飼料添加物の開発・製造・販売、ヒト用経口ワクチンの開発