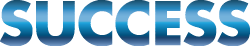インタビュー

対話型診断AIが人の可能性を引き出す
「人とAIの共進化」が切り拓く次世代社会
株式会社エキュメノポリス
代表取締役CEO/CTO 松山 洋一
氏
「ディープ“ヒューマン”テック」という独自の視点で人とAIの共進化を目指す株式会社エキュメノポリス。2022年に早稲田大学 GCS研究機構 客員准教授 松山洋一氏が立ち上げた大学発のベンチャー企業。2023年にリリースした世界初の対話型英会話能力診断サービス「LANGX Speaking」はその革新性が高く評価され、大学・高校・中学、さらに中央省庁・自治体・企業への導入が進んでいます。CEO/CTOの松山氏に創業の裏側から事業の展望までを語っていただきました。
世界初!診断型AIエージェントが、英語教育に革新をもたらす

Q、まずは、会社概要についてご紹介ください。
松山 当社は「人とAIの共進化社会の創出に向かって」をビジョンに創業した早稲田大学発スタートアップです。世界的にAIエージェント市場が急速に拡大するなか、当社が注力しているのが、対話による診断技術に特化したAIエージェント。AIとの会話からユーザーの潜在能力やニーズを深く掘り下げ、そのデータをもとに診断やカウンセリング、トレーニングを提供し、学習や業務の目標達成を支援するものです。その第一歩として、2023年に世界初となる対話型の英会話能力診断サービス「LANGX Speaking」をリリースしました。
Q、「LANGX Speaking」の詳細を教えてください。
松山 従来の英会話力判定法には主に3つの課題がありました。まずは専門家による面接の場合、かかるコストと属人性が高い点が挙げられます。そして既存の自動判定テストは、発音や文法など一部の能力しか測定できない点が課題でした。 「LANGX Speaking」は、AIとの自然な対話によって、会話の「インタラクション能力(やりとりの力)」を含む総合的な英会話力の診断ができることが特長です。発話内容に加え、表情や声の調子といった非言語情報も分析し、レベル判定・強みと弱みのレポート・学習アドバイスを即座に提供します。低コストで正確なレベル判定が可能になり、しかも楽しみながらユーザーの英会話力を伸ばすことができます。長らく日本の英語教育は「コミュニケーション能力」を育む指導方法や教材が不十分でした。当社が開発した「LANGX Speaking」は、その一助になるサービスだと自負しています。
Q、「LANGX Speaking」の開発経緯を教えてください。
松山 開発のきっかけは、早稲田大学からの依頼です。早稲田大学は長年にわたり英会話授業のクラス分けを筆記テストで判定していたため、会話力の正確な測定ができず、レベルに合わないクラスに配属されてしまう学生が多数いることが課題になっていました。お話をいただいてから約3年の開発期間を要しましたが、2023年春から「LANGX Speaking」が年間約1万人の受講者のクラス分けと期末のフィードバックに利用されています。導入後は毎年2~3割発生していたレベルのミスマッチがほとんどなくなり、離脱者の減少にも成功しています。この実績がきっかけとなり、現在は東京大学をはじめ複数の大学に導入されたほか、文部科学省や千葉県・岐阜市等の自治体とも連携して中高での実証実験を進めています。
従来の研究ファンドにはない自由な裁量。創業の基盤を支えた「START」

松山 米国でのAI研究を経て、古巣の早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構で研究成果の事業化を目指すなか、2019年にJST「START(研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム)」の起業実証支援に採択されました。 「START」の最大の魅力は、まとまった資金とその用途が比較的自由である点です。この支援があったからこそ、拠点となる研究室を構えることができ、宮村(現CSO/CFO)と渡邉(現COO)をはじめ、世界中から様々な才能が集い、外部の専門家も巻き込みながらシーズ技術のPoC(概念実証)ができました。また、ハンズオン支援により専門家から起業のいろはも教えていただきました。
Q、他にも活用した制度はありますか。松山 2020年、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」に、早稲田大学として採択されています。このファンドで英会話のインタラクションや能力判定といった技術の開発を進めることができました。JST「START」でAIインフラ構築の研究を行い、NEDOで英会話の領域を深化させる形で予算と研究員を使い分けて特許を取得しました。この2つの支援で会社の原型をつくり、2022年に創業しました。私のキャリアにおいても忘れがたい二大プロジェクトです。 その他、総務省・国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)「Beyond 5G 研究開発促進事業」をはじめ、複数の国の支援を活用させていただいています。
「SUCCESS」を契機に強みを再認識、プラットフォーム化と多領域展開へ挑む

Q、JST「SUCCESS」の活用についてお聞かせください。
松山 2023年後半はシード期とアーリー期の狭間で、技術・製品に自信はあれどもリリース開始から日が浅いこともあり販売実績が乏しく、民間VCからの資金調達に苦戦していました。転機となったのが、2024年の「SUCCESS(出資型新事業創出支援プログラム)」からの出資でした。「SUCCESS」は、単なるデューデリジェンスにとどまらず、技術の本質的な価値を専門家の目で評価する制度です。審査の過程で、論文を深く読み込んだJSTの担当者から核心をつく質問を受け、「診断型AIへの特化」が我々の強みだと気づくことができました。これは巨大資本とも張り合える領域ですし、イグジットまでの明確なビジョンを描けるようになった結果、VCの投資も決まりプラス・スパイラルの起点となりました。「SUCCESS」出資による「呼び水効果」も大きな要因でした。
Q、今後の展開について教えてください。
松山 事業面では、これまで個別に開発していた技術やサービスを、プラットフォームとして統合するフェーズへと移行しています。2025年にJSTの研究成果最適展開支援プログラム「A-STEP」実装支援(返済型)にも採択されましたので、「EQU AI Platform」の開発を加速させ、英会話にとどまらない言語教育のDX推進と実社会でのコミュニケーション能力の向上に貢献していきます。現在は、外国人が日本で働く場合に直面する日本語の壁を取り去る「LANGX Japanese」を開発中です。さらにビジネススキル診断やヘルスケアといった新たな領域での展開を目指しています。 組織面ですが、現在従業員数が30名を超えています。半数以上が外国籍で多様性が当社の特色です。しかし、同時に組織再編や意思決定プロセス改善の必要性が生じてきています。そもそも研究室がベースの体制ですから、今後企業として成長していくためには必ず乗り越えなければならない壁だと思っています。研究・事業開発との両輪を回しながら、基盤づくりを進めていきます。
「ディープ“ヒューマン”テック」「文理融合」で、“人”が進化する次世代社会を創造

Q、エキュメノポリスが目指す社会貢献とビジョンをお聞かせください。
松山 当社の技術の中核はAIですが、単に技術を追求するのでなく、「次の社会はどうあるべきか」を考え、その実現に技術をどう活用するかが大切です。単なるAI企業ではなく社会そのものを見据える企業でありたいと、社名を「エキュメノポリス(惑星規模の世界都市)」としました。これからの時代、人とAIの共存・共栄・共進化は必定です。その共生を誰よりも上手く実現できる企業を目指しています。 また、注力する分野は、教育、医療、人事といった、「人」の成長や幸福に関わる領域です。ディープテックを通じて、人間の可能性と豊かさを深める「ディープ“ヒューマン”テック」こそ、当社らしい社会貢献だと考えます。 もう一つ、「文理融合」も重要です。AIが高度化するほど人文社会学的な知見が不可欠となり、伝統的知識と先端技術の融合が新しい社会価値を創出します。次世代社会の設計には人間の叡智が必要です。テクノロジーを使いこなしながら、人間性を高めていくことこそが、豊かな未来を築く道だと確信しています。
- 株式会社エキュメノポリス
-
〒162-0042 東京都新宿区早稲田町27 早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究センター301
- 主な事業内容
- 会話AIエージェントプラットフォーム開発、およびそのアプリケーションの開発