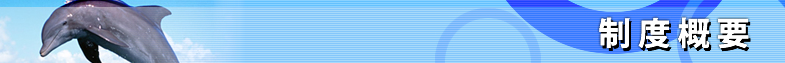
目的、狙い
具体的には、社会課題解決等に向けた研究成果の社会実装のアイデアに関して、研究を推進するとともに、企業訪問等を通じたニーズの詳細把握や、知的財産を形成※することで、企業等との共同研究に繋がる成果を得ることを目指します。
育成フェーズによる支援終了時にはステージⅡ(本格フェーズ)において実施が可能な産学共同の研究体制を構築していることを期待します。また、ステージⅡ(本格フェーズ)への移行を希望する研究開発課題を対象に、移行可否を決定するステージゲート評価を実施し、研究開発課題の絞り込みを行います。切れ目なく産学共同で研究開発を継続し、技術移転を進めることで、将来の科学技術イノベーションの創出や、SDG s 等の国際的な目標達成への貢献、社会的・経済的な波及効果の創出に繋がることを期待します。
また、多様な研究成果の実用化や継続的な研究開発に向け、若手研究者の産学連携への参加促進も目的としています。若手研究者からの積極的な応募も期待しています。自然科学と人文・社会科学の融合による総合知を活用する提案も期待します。
なお、2025年度においても、「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、デジタル実装を通じて地域が抱える課題の解決に資する研究開発の提案も期待します。
(注) 研究を推進するとともに、企業ニーズ把握、共同研究相手先の企業探索のため企業訪問や知財形成等の産学共同研究に向けた活動も実施いただきます。研究者自ら積極的に取り組むことが必要です。
※国において、旧来の知的財産権に加え「スタートアップ・大学による活用」「標準化」「データ利活用」等の重要性も踏まえた知的財産推進計画が公表されています。
「知的財産推進計画2024」(知的財産戦略本部 2024年6月4日)
支援の概要
| 課題提案の要件 | 提案者 | 研究開発体制 | 支援規模 | 資金タイプ |
|---|---|---|---|---|
|
●大学等における新規性・優位性のある基礎研究成果(技術シーズ)が存在すること。 ●社会課題解決等に向けて目指す、技術シーズの社会実装のアイデアが示されていること。 |
研究責任者: ●提案内容の元となる技術シーズの創出にかかわった者であること。 ●日本国内の大学等に常勤の研究者として所属していること。 ●研究倫理教育に関するプログラムを予め修了していること。 ●応募にあたって、各種ガイドラインの遵守等について誓約できること。 |
●単独あるいは複数の大学等のみからなる研究開発チームであること。 ●研究責任者の課題提案を実現する上で最適な体制であること。 |
金額: 上限1,500万円(年額) ※初年度は研究期間を踏まえて上限額設定
※間接経費を含む、税込
期間:最長2.5年 |
グラント |
JSTによるマネジメント
●企業探索、マッチングについても支援。
●最終年度にステージⅡ(本格フェーズ)へ移行のための事前評価(ステージゲート評価)を受けることが可能。
事業推進体制・研究開発体制
ステージゲート評価
ステージゲート評価では、ステージⅡ(本格フェーズ)の評価と同様に企業等との技術移転計画もあわせて評価します。ステージゲート評価にあたっては、公募要領の「4.2.3 研究開発体制、研究開発機関の要件」の要件を満たしていることが前提となります。また、ステージゲート評価は、研究開発開始から3年度目に実施し、同じ採択年度の研究開発課題の中からステージⅡ(本格フェーズ)に移行する課題を選定します。3年度目に研究開発が継続していない研究開発課題は、原則、ステージゲート評価を受けることができません。
ステージゲート評価により育成フェーズからステージⅡ(本格フェーズ)への移行が決定した研究開発課題は、切れ目なく産学共同で研究開発を継続し、実用化に向けて技術移転を加速していただきます。また、ステージⅡ(本格フェーズ)への移行の他に、最長1年間のフィージビリティスタディを実施する場合があります。
なお、ステージゲート評価では研究開発課題の絞り込みを行い、ステージⅡ(本格フェーズ)への移行、またはフィージビリティスタディが決定した課題のみ公表します。
対象分野と各P0について
本分野は、IoT、AI、ネットワーク等のICT技術とそれを支える計算機・センサ・デバイス基盤技術、設計・加工・組み立て・造形等によるものづくり技術、さらにはロボティクスを含めたサイバーフィジカルシステムについて、その高度化、効率化、スマート化、安全性・信頼性向上などに関する提案を幅広く対象とします。
また、異分野との連携・協働による融合領域に資する提案も対象となります。
●選考にあたってのPOの方針
AI、次世代高速通信、自動運転、半導体の開発が加速する中で、社会で必要とされる新技術も刻々と変化しています。本分野では、従来の延長線上にある技術だけでなく、様々な新技術の利活用や融合をはかり、現代社会の課題解決を目指す提案を募集します。また、未来社会の課題を予想し、その解決や展開を創造するような提案も歓迎します。
選考に当たっては、社会的なインパクトの大きさ、知財や論文発表を根拠とする独創性、社会実装に適したシンプルな取り組みが示されている提案を重視します。産学連携に高い意欲を持つ若手研究者・女性研究者による提案も尊重します。
ICTや電子デバイス、ものづくりは、日本の発展を支える裾野の広い分野です。10年以内の社会実装を本気で考える提案を期待します。
本分野は、大学等における材料に関するシーズ研究を応用し、実用化を通じて社会課題の解決につながる革新的な材料の開発を目指します。対象分野には、機能・構造材料、ナノテクノロジー、再生可能エネルギーに関する材料技術、資源循環技術、代替素材技術、カーボンニュートラルを実現する低環境負荷プロセス技術、および効率的な材料開発を支えるマテリアルDXが含まれます。これらの分野に関する幅広い提案を歓迎します。
特に、ステージI(育成フェーズ)では、出口を見据えた基礎・基盤研究を重視します。この段階では、社会実装を視野に入れつつ、学術的に高い水準を維持することが求められます。学術から応用への発展を目指し、革新的な研究成果が新たな知見を生み出すとともに、次世代の材料科学技術を牽引するものとなることを期待しています。また、異分野との連携や協働による研究提案も引き続き歓迎します。
●選考にあたってのPOの方針
マテリアル分野は、幅広い産業課題や社会課題を解決に導く分野横断的な基盤技術であり、革新的材料の開発は、我が国製造業のGDPの3割以上を占めるマテリアル産業の国際競争力を維持する上で中核的な役割を担います。特に、「マテリアル革新力強化戦略」においても、新たな価値を創出する取り組みの重要性が強調されています。
本分野では、固定観念にとらわれない斬新なアイデアに基づく革新的な材料開発の提案を募集しています。具体的には、材料の新機能の発現やその高機能化、ナノからマクロレベルにわたる構造制御、機能と構造の相関性を基にした新しい材料設計、従来の材料技術を超える革新的な材料技術の開発、データ科学やAIを活用したデータ駆動型の材料開発、そして社会実装を見据えた材料合成プロセスの開発など、多岐にわたる提案を歓迎します。
ステージI(育成フェーズ)では、新たな現象の発見時にその新機能の科学的根拠を明確にし、基礎的な理解を深めることが求められます。同時に、研究成果が社会実装へと繋がる具体的な道筋を示すことが重要です。一方、ステージII(本格フェーズ)では、企業との共同研究を通じて実用化の可能性をさらに検証し、その技術移転を目指します。
どのステージにおいても、材料が実装された際の社会的および経済的なインパクトを評価する視点を重視しています。これらの研究活動を通じ、社会課題の解決を意識した基礎研究課題を設定する大学や研究機関の研究者を積極的に支援していきます。
本分野は、高機能バイオ素材、バイオプラスチック、持続的一次生産システム、生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品、デジタルヘルス、バイオ生産システム、バイオ関連分析・測定・実験システム、バイオ創薬に資する基盤技術など、アグリ・バイオ分野に関する基礎研究(育成フェーズ)と産学共同による実用化に向けた検証(本格フェーズ)の提案を幅広く対象とします。
また、異分野との連携・協働による融合領域に資する提案も対象となります。
●選考にあたってのPOの方針
アグリ・バイオ分野の研究開発は、食糧問題、健康問題、環境問題などグローバルな課題の解決に繋がることが期待され、持続可能な開発目標(SDGs)のゴール達成に必要とされる技術・製品開発が含まれます。これらの研究開発は、独創的な基礎研究からスタートする一方、社会のニーズを捉えて研究開発の方向性を考え、明確にゴールを設定していくことが重要です。
本分野では、単なる基礎技術の組み合わせでなく、斬新なアイディアをもとに新規技術や製品を開発し、産業へ繋げようとする意欲的な提案を期待します。戦略的な知財化と産学共同研究を展開させることが、社会実装に繋がると期待しています。特に、本格フェーズでは、アグリ・バイオ分野での市場規模を意識した経済的なインパクトに繋がることが期待できる提案を歓迎します。
また、異分野融合での提案も期待し、今後の産学連携に意欲的に挑む若手研究者や女性研究者を積極的に採択します。