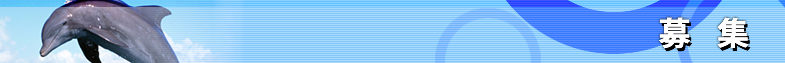
2025年度 産学共同 ステージⅡ(本格フェーズ)の募集概要
産学共同 ステージⅠ(育成フェーズ)/ステージⅡ(本格フェーズ)の2025年度募集は
5月12日(月)11:59に受付を終了しました。
5月12日(月)11:59に受付を終了しました。
募集・選考スケジュールについて(予定)
募集締切後のおおよその選考スケジュールは以下の通りです。
- 書類選考2025年5月下旬~6月中旬
- 面接選考2025年7月中旬~8月上旬
- 課題選定2025年9月
- 研究開発開始2025年10月1日
※書類選考の結果は、面接選考の対象となった課題提案のみ、応募時のe-Radにおける課題ID(8桁)をA-STEPウェブサイトの募集ページに掲載します。
※面接選考の結果については、採否にかかわらず、研究責任者にe-Radを通じて通知します。
支援の概要
| 目的・狙い | 社会課題解決等に向けて、大学等の基礎研究成果(技術シーズ)を、大学等と企業等との共同研究により、実用化に向けた可能性を検証し、中核技術の構築に資する成果の創出と、その成果を大学等から企業等へ技術移転することを目指す。 |
| 課題提案者 | 大学等の研究者と企業等 |
| 研究開発期間 |
最長4.5年 ステージゲート評価から移行した場合は最長4年 |
| 研究開発費 |
上限2,500万円(年額、間接経費含む、税込) 初年度は研究期間を踏まえて上限額設定 |
| 資金の種類 |
マッチングファンド
・JST からの研究開発費の支出に関して、詳しくは2025年度公募要領「6.3.4 マッチングファンド形式における企業等の参画に係る留意事項について(本格フェーズのみ)」をご覧ください。
|
募集期間
2025年3月18日(火)~5月12日(月)11:59
採択予定件数
~15課題程度
※件数は課題提案の状況や予算により変動します。
※件数は課題提案の状況や予算により変動します。
評価者
2025年度公募 産学共同における評価者について
一覧はこちら
一覧はこちら
お問合せ先
本事業そのものに関する問い合わせはJSTの担当部署にて受付けます。e-Radの操作方法に関する問い合わせは、e-Radヘルプデスクにて受付けます。
当ホームページと公募要領および府省共通研究開発管理システム(e-Rad)をよく確認の上、お問い合わせください。
なお、選考状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。
※問い合わせe-mailアドレスの[at]は@に置き換えてご利用ください。
当ホームページと公募要領および府省共通研究開発管理システム(e-Rad)をよく確認の上、お問い合わせください。
なお、選考状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。
※問い合わせe-mailアドレスの[at]は@に置き換えてご利用ください。
|
事業に関する問い合わせ 及び 応募書類の作成・提出に関する手続き等に関する問い合わせ |
科学技術振興機構 A-STEP産学共同募集担当窓口 |
E-mail:a-step[at]jst.go.jp |
| e-Radの操作方法に関する問い合わせ |
e-Radヘルプデスク |
府省共通研究開発管理システム 0570-057-060(ナビダイヤル) 9:00~18:00 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く |