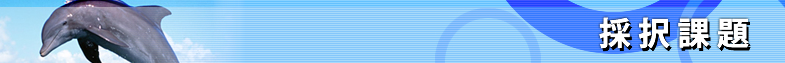
IoT、ウェアラブル・デバイスのための環境発電の実現化技術の創成

研究開発テーマの設定趣旨
●テーマの概要
あらゆるモノがインターネットにつながるIoTを実現するためには、あらゆるモノに電源が必要です。電源配線敷設や充電・電池交換が技術的にあるいはコスト的に困難なケースも少なからずあり、代替となる低コストで普遍的な電源技術の確立は急務となっています。そのような代替電源技術の1つが、環境中に存在する光、振動、温度差、電波などの様々なエネルギーを電気エネルギーに変換する、環境発電技術です。
IoT関連技術のなかでも、近年、技術開発が急速に進んでいるものの1つがウェアラブル・デバイスです。ウェアラブル・デバイスは、スポーツ、健康管理、医療、見守り、作業効率化、エンタテインメントなど様々な用途への展開が始まっていますが、充電や電池交換の手間が普及の障害となっています。環境発電技術の活用によってウェアラブル・デバイスの無給電化が実現すれば、上記用途を始め、人間以外(家畜、ペット、野生動物、さらには植物、無生物)へのウェアラブル・デバイス適用などによる、新たな産業の創出が期待されます。
ウェアラブル・デバイス向けの環境発電技術には、発電性能だけでなく、超小型、低コスト、軽量、フレキシブルなどの特性が求められます。さらに、テキスタイルへの実装、洗濯耐久性、生体適合性などが要求される場合もあります。このような多様な要求を満たす環境発電技術の開発成果は、ウェアラブル・デバイス以外のIoT用途への展開も可能でしょう。サイバーフィジカルシステムを社会実装するうえで、各種センサや通信デバイスの省電力化に伴い、超小型、低コスト、軽量でフレキシブルなどのポテンシャルを有している環境発電技術は重要な基盤技術となることが期待できます。
本研究開発では、ウェアラブル・デバイス向けの超小型、低コスト、軽量、フレキシブルな次世代環境発電技術の実現化技術を創成することにより、新たな産業創出の礎となる技術確立を目指します。
●公募・選考・研究開発テーマ運営にあたってのPOの方針
本研究開発では、環境発電技術の飛躍的な性能向上に資する研究開発をベースとしつつ、それと同時に、ウェアラブル・デバイスへの適合性を高めた実用的なデバイス化に向けた実用化の基盤となる技術を創成します。そのためには、環境発電技術に関する確固たるシーズを持つ大学などと、実装面での技術・経験に長けたデバイスメーカとの緊密な協力が必須となります。さらにこれら2者に加えて、ウェアラブル・デバイスの活用を検討されている製品製造業者、サービス事業者の参画を得て、要求仕様の提示やフィードバック評価を得ながら、方向性を修正しつつ実用化を見据えた研究開発を推進する研究開発体制を推奨いたします。
課題の実施にあたっては、研究開発チーム間の連携、情報共有を推進します。機密保持には配慮しつつ、課題間で成果などを可能な限り共有し、テーマとしての成果最大化を図ります。必要に応じて採択課題間の協力を要請しますので、対応していただきます。
核となる環境発電技術の開発を実施する大学などは、環境発電技術に関する確たるシーズを持っていることが必要です。たとえば、JSTの「CREST」・「さきがけ」あるいは、科学研究費補助金などでの研究実績、査読付き論文、特許出願実績などを示してください。このシーズをもとに、飛躍的な発電性能の向上に取り組んでいただきます。さらに、ウェアラブル・デバイスへの適合性向上への取り組みも歓迎いたします。また、発電デバイスと蓄電デバイスの一体化や、電源回路の工夫による発電性能の画期的な向上などの研究も歓迎いたします。デバイスメーカとの緊密な協力により、研究開発を実施してください。
将来、環境発電技術の製品化を目指すデバイスメーカは、ウェアラブル・デバイスへの実装技術を有する必要があります。ウェアラブル・デバイスの開発実績は必須ではありませんが、活用可能な自社技術を示してください。研究開発の内容としては、ウェアラブル・デバイスへの適合性を高めるための周辺技術の開発や、大学などが開発した環境発電技術のウェアラブル・デバイスへの実装技術の開発などが想定されます。また、一般に、環境発電デバイスは、外部環境からエネルギーを取り込む機構と、それを電気エネルギーに変換する機構の組み合わせからなりますが、その一部機能を分担して環境発電技術の性能向上に関する研究を行うことも可能です。蓄電デバイスや電源回路についての考え方は前述のとおりです。大学などとの緊密な協力により、研究開発を実施してください。
将来、ウェアラブル・デバイスを活用した製品、サービスの提供を目指す事業者は、ウェアラブル・デバイスの適用・活用が可能な、製品あるいはサービスを提供している必要があります。これら製品、サービスに対するユーザニーズや発電環境に関する知見あるいは調査に基づき、大学など及びデバイスメーカに対して、研究開発の方向性を示すための要求仕様の提示やフィードバック評価を行うことを期待します。
ウェアラブル・デバイスを活用したサービスとしては、人に対するもの、動物に対するものなど、いろいろと考えられますが、今回の公募においては、特にスポーツを対象とした提案を歓迎します。アスリート向けに特定競技の技量向上を支援するものから、基礎体力の増進やリハビリテーションへの活用など、様々なサービスが考えられます。2020年の東京オリンピック・パラリンピックへの関心の高まりも視野に入れたデモンストレーションなどを実施可能な計画を歓迎します。
発電量、大きさ、コスト、重さ、フレキシビリティなどについては、一律の基準は設けません。目指すウェアラブル・アプリケーションを示したうえで、それを実現するための研究開発の目標設定をしてください。発電量については、環境中から得られるエネルギー量や実装しようとする構造などを踏まえて、既存技術に基づく現時点での想定値及び研究開発によって達成しようとする目標値を示してください。機器の消費電力については、製品化の時期には既存技術の10分の1程度になっていると想定しますが、もし、より消費電力を低減できる見通しがあれば、そのような想定にもとづいて目標設定をすることも可能です。目指すウェアラブル・アプリケーションについては、ボタン電池などの既存技術を利用する場合と比較してメリットがあることを示してください。
研究開発の成果は、特定のウェアラブル・アプリケーションに適用されるだけでなく、広く社会的あるいは経済的なインパクトをもたらすことが期待されますので、そのようなビジョンを示してください。
テーマの評価
追跡評価
プログラムオフィサー(PO)及びアドバイザー
| 役 職 | PO・アドバイザー | |
| 氏 名 | 所属機関・役職 | |
|
プログラム オフィサー |
竹内 敬治 |
株式会社 NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー |
| アドバイザー | 桑野 博喜 | 東北大学 未来科学技術共同研究センター 教授 |
| アドバイザー | 佐々木 健 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 |
| アドバイザー | 篠原 真毅 | 京都大学 生存圏研究所 教授 |
| アドバイザー | 前中 一介 | 兵庫県立大学大学院工学研究科 教授 |
| アドバイザー | 森 孝雄 |
物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA) ナノマテリアル分野 熱エネルギー変換材料グループ グループリーダー |
| アドバイザー | 吉田 郵司 | 産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究センター 副研究センター長 |
課題
※下線はプロジェクトリーダー(課題の取りまとめ役)を指します。
| 課題名 | 課題概要 | 企業責任者 ※ | 評価結果 | 完了報告書(概要版) |
| 研究責任者 ※ | ||||
| ジャイロ効果を利用したウェアラブル発電システム | 人や移動体の振動から電力を生成する発電機を開発し、健康増進や作業補助に利用します。小型軽量な装置で大電力の発電を行うため、高速回転するロータを振動させて、ジャイロ効果により低周波、低加速度の振動から大きな慣性トルクを取り出します。ウェアラブルサイズの装置で1Hz程度の振動から、10mW~1Wの電力を得ることを目指します。本装置を靴、ベルト、衣服、ザックなどに装着してランプ、携帯電話、生体センサ、微弱無線などを駆動させます。 |
谷口 博昭 (精技金型株式会社) |
(平成29年度実施)
(令和2年度実施)
|
|
|
保坂 寛 (東京大学) |
||||
| スポーツを対象としたウエアラブル圧電型振動発電モジュールの開発 | 圧電型振動発電素子をセンサとして利用することで、自立動作可能なセンサ素子の開発を行います。特に高い運動エネルギーの供給が可能であり、今後運動機能の計測ニーズが高まると予想されるスポーツシューズへの応用を想定したセンサ機能内蔵振動発電モジュールの開発を行います。軽量・高出力と共に高い柔軟性と耐久性を備えた素子の設計・試作に加え、得られた情報の活用について体系的な検証を行います。 |
田中 隆 (パナソニック株式会社) |
(平成29年度実施)
(平成30年度実施)
|
|
|
神野 伊策 (神戸大学) |
||||
| 3次元圧電単結晶スプリングを用いた振動発電の研究開発 | 『圧電結晶を用いた3次元スプリング構造』により、ウェアラブル・デバイスに適した小型、軽量でかつ柔軟性に優れた振動発電デバイスを実現します。圧電体をスプリング構造にすることで、人の動作に共振する低周波共振に対応しながらも、デバイスサイズの大幅な小型化を図ることが可能となり、その柔軟性により必ずしも共振現象によらない、人の動作による変形を利用した発電をも可能にする革新的な振動発電デバイスを実現します。 |
井上 憲司 (株式会社Piezo Studio) |
(平成29年度実施)
(平成30年度実施)
(令和元年度実施)
|
|
|
吉川 彰 (東北大学) |
||||
| バイオ燃料電池を搭載したウェアラブルヘルスケアデバイスの創成 | 環境や身体に安全な酵素を利用し、体液に含まれる糖分、乳酸から電力を取り出す“バイオ燃料電池”を開発します。さらに、その出力値をもとに体液中の成分をセンシングする自己駆動型ヘルスケアデバイスの開発を行います。これにより、アスリートの疲労管理や真夏時の熱中症見守りなど、電池交換を不要とし、また、薄くて軽く装着感を感じさせない、ウェアラブルヘルスケアデバイスの実現を目指します。 |
小出 哲 (株式会社タニタ) |
(平成29年度実施)
(令和2年度実施)
|
|
|
四反田 功 (東京理科大学) |
