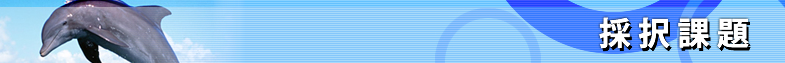
○2023年度 実装支援(返済型)
実装支援(返済型) 採択課題1件(2024年7月1日発表)
| 開発課題名 | 技術シーズを創出した大学等の研究者 | 開発実施企業 | 概要 |
| UAV空撮・AI画像処理を用いたマラリア撲滅手法の開発 |
宇宙航空研究開発機構(JAXA) 研究統括付 研究員 長谷川 克也 |
SORA Technology株式会社 |
世界3大感染症の1つであるマラリアは、マラリア原虫により引き起こされる急性熱性疾患である。マラリア原虫を保有した雌のハマダラカ(蚊)の成虫に刺されることで、人へ感染する。アフリカを中心に熱帯・亜熱帯地域で主に流行しており、世界保健機関によると、2022年の感染者数は約2億4,900万人、死亡者数は約61万人と推計される。感染後は合併症発症や重症化のリスクもあり、感染を未然に防ぐことが重要である。 マラリア対策として、ハマダラカは主に夕方から夜間に活動することから、屋内向けには蚊帳の設置や室内残留型殺虫剤の噴霧が行われてきた。しかし、日中に屋外で人を刺す種や、殺虫剤耐性を持つ種のハマダラカの出現を踏まえ、新たなマラリア対策が求められている。そこで近年注目されているのが、ハマダラカが成虫になる前に個体数を減らす「幼虫源管理(LSM))」である。蚊の幼虫(ボウフラ)が繁殖しやすい水たまりに駆除剤を散布することで、ボウフラを効率的に駆除できる。一方で、そのような水たまりの特定には多くの人的・時間的リソースが必要となるため、現状ではあらゆる水たまりに駆除剤を散布している。その結果、高いコストと高い環境負荷がかかり、普及が限定的だった。 このような課題を解決するため、SORA Technology株式会社は、長時間・長距離飛行に強みがある固定翼型のUAVを用いて、水たまりを効率的に発見し、その中からボウフラ発生リスクが高い水たまりを抽出して駆除剤を散布する、効率的なLSMサービス「SORA Malaria Control」の事業化を目指している。 本開発では、UAVの空撮で得られた地表面の情報から、水たまりの位置と特徴(大きさ、温度、深さなど)を抽出した上で、ボウフラ発生リスクの高い水たまりのみを検出するAIを開発する。加えて、AIで検出した水たまりへの移動経路・駆除剤散布量の提案などを通じて、散布作業者を支援するLSMアプリを開発する。 また、長谷川研究員らの研究成果である、空撮画像を用いた高精度の道路網抽出・渋滞情報取得プログラムを活用し、道路網が未発達な地域においても、駆除剤散布作業者へ最適な移動経路の提案を行えるようにする。これらにより、ボウフラ発生リスクの高い水たまりの特定から駆除剤散布までを迅速化し、ボウフラ駆除の効率向上を目指す。 本開発により、LSMにおける課題であった人件費および駆除剤のコストと環境負荷を低減させ、効率的なマラリア対策の普及、ひいてはマラリア撲滅に貢献する。将来的には、蚊や水が媒介するマラリア以外の疾患対策としての展開も期待される。 |
実装支援(返済型) 採択課題1件(2024年6月28日発表)
| 開発課題名 | 技術シーズを創出した大学等の研究者 | 開発実施企業 | 概要 |
| 都市インフラの自動検出・マッピング手法の構築 |
東京大学 生産技術研究所 特任研究員 前田 紘弥 (発明当時) |
株式会社アーバンエックステクノロジーズ |
主要な都市インフラの1つである道路の管理は、地方自治体(市区町村・都道府県)を始めとした行政などによって行われている。全国約120万キロメートルの道路の大半を管理する市区町村では、予算も限られる中、長距離の道路を少人数で管理している。このような状況でも、点検を通じて路面異常(道路の損傷や路面標示のかすれ)、道路附属物破損など、さまざまな不具合を確認し、傷や路面標示のかすれ)、道路附属物破損など、さまざまな不具合を確認し、予算の範囲内で補修・修繕している。これまで多くの地方自治体では人間による目視点検が行われてきたが、長い道路を管理するには担当職員が不足しており、一方で専用測定車による点検は高精度だが高額という問題があった。そこで、AIによる不具合検出が活用され始めたが、不具合の内容によっては事故防止のために早急な補修が必要となることから、不具合のリアルタイム検出が望まれていた。 このような課題を解決するため、東京大学の前田特任研究員(発明当時)らは、計算量を従来に比べて大幅に削減しつつも、検出精度を担保するAI(深層学習モデル)を開発し、演算能力に限りのある汎用デバイス(スマートフォンやドライブレコーダーなど)でも路面異常のリアルタイム・高精度検出を実現した。 この技術を基に、株式会社アーバンエックステクノロジーズは、検出アプリを起動したスマートフォンを自動車内のダッシュボードに設置して道路を走行するだけで、走行中に得られた画像から路面異常を自動検出し、Web上で一元管理可能なサービスを開発した。すでに複数の地方自治体での導入実績があり、さらなる事業展開を目指している。 本制度の支援により、生成AIなどの手法も活用しつつ、AIの検出対象を拡張させることで、路面異常だけでなく道路附属物破損なども自動検出・管理可能なサービスを開発する。合わせて、異常発生位置とWeb上のマッピング位置のズレを補正する、位置情報の高精度化技術も開発する。 また、街中のさまざまな製品に本サービスを搭載し、そこから自動収集される画像より道路附属物破損などの情報を自動検出することで、地方自治体職員が巡回せずに情報を得られる仕組みの構築も目指す。 以上の取り組みにより、デジタルサービスで点検できる対象が増え、都市インフラ管理の人材不足解消と点検業務の効率化に貢献できる。また、取得した画像には、道路附属物破損だけでなく、さまざまな街の変化が捉えられている。将来的には、道路附属物破損に伴う地図更新、さらには不動産情報の検出による空き地判定などへの展開も期待される。 |
実装支援(返済型) 採択課題1件(2024年4月26日発表)
| 開発課題名 | 技術シーズを創出した大学等の研究者 | 開発実施企業 | 概要 |
| FPGA向けAIアクセラレータの開発 |
東北大学 未踏スケールデータアナリティクスセンター 教授 中原 啓貴 |
Tokyo Artisan Intelligence株式会社 |
さまざまな作業・点検の効率化に向けて、画像処理においてニューラルネットワークを基盤としたAIが活用されている。具体的には、画像処理後にニューラルネットワーク処理で特徴を抽出し定量化することにより、画像に写る特定の人・物を認識・検出することができる。例えば、鉄道会社では沿線の環境変化やレールの変状などの目視点検にAI搭載カメラを導入し、その補助に利用され始めている。 しかし、高精度に検出するためには、特徴抽出に多くのパラメーターが必要となり、AIを作動させるためのメモリー量や消費電力が肥大し、その結果コストも増大する。一方で、パラメーター数を減らすと検出精度が劣化するというジレンマがあり、適用できるアプリケーションが限定的であった。 東北大学の中原教授(発明当時は東京工業大学)らは、バッチ正規化回路注を不要とするニューラルネットワーク回路を実現することで、消費電力およびコストを抑えつつ、高精度検出を可能にした。 Tokyo Artisan Intelligence株式会社は、この技術を活用した映像処理AIシステムを開発しており、すでに鉄道の点検支援ツールなどとしての納品実績があり、今後、映像処理AIのさらなる事業展開を目指している。 本開発では、これまでの研究成果を活用して、FPGA向けAI処理専用カスタムアクセラレータ)を開発する。具体的には、顧客ごとのカスタマイズ性を担保するために認識処理工程をカスタムアクセラレータで、その前後にあたる画像処理および後処理工程を、顧客のアプリケーションに応じて書き換えできるFPGAで処理する。 これにより、消費電力およびコストを低減しながらも、高い検出精度を保つAIを利用することが可能になる。また、カスタムアクセラレータの導入により顧客ごとのカスタマイズが自由にできることから、将来的には、大量のデータ処理が求められるインフラ点検や工場における人体接近検知の自動化への展開も期待される。 |
実装支援(返済型) 採択課題1件(2024年3月21日発表)
| 開発課題名 | 技術シーズを創出した大学等の研究者 | 開発実施企業 | 概要 |
| レプリカ法による光学研磨不要な超軽量高精度CFRPミラーの開発 |
愛媛大学 大学院理工学研究科 教授 粟木 久光 |
株式会社テックラボ |
テレビなどの映像表示に用いられる液晶ディスプレイ(LCD)の製造装置では、LCD用ガラス基板を載せたステージをXY方向に動かしながら露光する。テレビなどの大画面化と生産効率向上のために、世代を追うごとに基板とLCD製造装置の大型化が進んできた。大型ガラス基板の露光には、大型ステージ上でのレーザー干渉計による精密な位置決めが必要で、それに対応する精密かつ大型のバーミラーが必要となる。現在、70キログラム以上の重量があるガラスやセラミック製のミラーが用いられており、ステージ移動に大きな負担がかかる。このため、LCD製造時間の短縮には、ステージの移動速度の向上を可能とするバーミラーの軽量化が必要不可欠である。 軽量化に向けて、熱膨張率が小さく軽量であるというCFRPの特徴を生かした、CFRP製ミラーの実現が望まれてきた。そのためには、炭素繊維や繊維束に起因してCFRP表面に凹凸が生ずるプリントスルー(繊維模様が表面に表れる現象)と、大型化に伴って影響が大きくなる全体的なたわみを解決する必要があった。 株式会社テックラボは、CFRP表面に均一な樹脂層を形成することでプリントスルーを覆い隠すことにより、光学研磨が不要で高精度な鏡面を実現する「レプリカ法」という製法を発展させてきた。 レプリカ法ではプリントスルーのような局所的な凹凸は滑らかにすることができるが、大型LCD製造装置に用いられる3メートルを超えるバーミラーで生じるたわみなどのミラー全体の凹凸までは滑らかにすることが難しい。この課題を解決するため、熱膨張ゼロの素材の型枠を使ってCFRP全体を平坦にする成形技術を新規に開発する。 さらに、愛媛大学の粟木教授らの研究成果である、CFRP表面を薄板ガラスで積層する技術とレプリカ法を組み合わせ、プリントスルーを抑制し、超高精度な鏡面を持つ3メートルサイズの大型バーミラーを開発する。 本開発により大型バーミラーの軽量化が実現されることで、ディスプレイの大型化などにより堅調な成長が見込まれるLCD製造市場で、製造時間の短縮など、生産効率向上への貢献が期待される。将来的には、LCD製造装置と同様に超軽量・高精度・大型化が求められる半導体製造装置や人工衛星搭載の望遠鏡用のバーミラーへの展開も期待される。 |