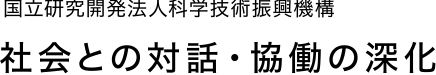科学コミュニケーションについて知りたい
インタビューシリーズ「科学と社会の関係深化のために」
Vol.07
科学と社会の関係深化のために
ネット社会で面と向かって対話することの価値
長神 風二
(東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 特任教授)
東北大学で、住民の理解を得ながら、大規模コホート研究などの先端生命科学を進めるための活動を行う長神風二氏。長神氏は、かつて日本科学未来館や科学技術振興機構に在籍していた頃にサイエンスアゴラを企画提案して立ち上げ、以来、アゴラ以外の場も設えながら、生命倫理や情報社会、エネルギーのあり方など、多様な課題を社会に提示し、意見交換を実践してきた。そして今、宮城を拠点に自らも震災を経験した一人として地域の人びとと向き合う中で、対話の仕方に新たな着眼を得ているようだ。

決定プロセスの不透明さがコミュニケーションの障害に
2001年から科学コミュニケーションに携わってきましたが、この間、科学と社会の関係が良くなったのかと問われると、正直、疑問符がつくと思います。それはなぜなのか? きっと、科学コミュニケーションの場の設定が、何かを「決定するところ」に関係していないからだと思います。では「何を決定するところに」か? 日常のあらゆるシーンでの決定にです。
政策や方針、予算など、多数に影響を及ぼすことがらについて、科学の視点を持った人びとの意志や考えをぶつけて決定するプロセスが、社会の中に作られていません。また、その決定がうまくいくように、科学的な事象に関心を持って役立ててもらうための示し方も見えていません。
生活を楽しむ一側面になるような科学の示し方は試されてきましたが、それはいわば「余興」と言えば語弊があるかもしれませんが、生活においてシリアスでない部分の科学コミュニケーションです。そして、それ以上のものにならなかったなあ、というのが、僕がこれまでを振り返り、思うことです。
最近は仕事で、よりシビアな側面に関わることが多くなりました。例えば個人のレベルで言えば「手術法をどう選択するか」、政策の面で言えば「エネルギーの未来についてみんなで考えて決めていくにはどうしたらよいか」など。そうしたところでの科学コミュニケーションの取り組みは、現状では、中途半端です。熟議はしても「そこで決めること」をしてこなかったからだと思います。
なぜ決めることができなかったのか。社会の中の重大な決定を、誰がどこでしているのか見えづらいという状況があり、そのことが、コミュニケーションを深めていけない要因の一つになっています。例えば、原子力発電所の再稼動を決めたのは誰か? 原子力規制委員会が言ったから決まったのか? いや、そうではなく、規制委員会は、決める、決めないは政治の責任だと言っている。その決定プロセスは、非常に不透明ですよね。そこが見えやすくなれば、どこに対して何をコミュニケーションした、あるいはできなかった結果としてその決定が行われたのだ、と分かる。
セグメント化するインターネットのコミュニティ
今はインターネットのおかげもあって、データを白日の下に晒し、目に見えるものにするテクニックは進化しました。ある事案について、「データを示す」という視点を持って取り組む人は、おそらくは増えたのでしょう。それは明らかに進歩です。また、ネット上の意思を、サーベイして大づかみに把握する技術も進んでいます。大づかみされた意思は、東浩紀(あづま ひろき)氏の言う「一般意志2.0」※に近いと思いますが、一生懸命やれば、その一般意志が取り出せるようになってきています。しかし現時点では、ネット上でのこの件に関する空気はこうだった、というレベルで終わってしまい、それを基にした課題の設定にも解決にも向かっていないように見えます。
※ 一般意志2.0/思想家の東浩紀氏が、ジャン=ジャック・ルソーの「一般意志」の概念を情報科学技術の発達した現代のネット社会に照らし出し、現代の民主主義と合意形成のあり方として表した概念。東氏の著書『一般意志2.0 ルソー、フロイト、グーグル』(講談社、2011年)に詳しい。
一方で、最近のネットのコミュニティは、いわば「セグメント化」しています。特定のコミュニティの中や、考え方が似通った人たちの間ではコミュニケーションができていても、他のコミュニティ、つまり異なるセグメント間では、ほとんどバトルのようになってしまう。示されたデータの解釈をめぐり、ただ不毛な争いになって、結局、コミュニケーションが成立しません。データを出す人たちはいるけれど、それを針小棒大に解釈する人や、ねじ曲げて解釈する人など、データの解釈にスペクトラム(連続する分布領域)ができ、そのスペクトラムの両端の間ではほとんどコミュニケーションも成り立たないという状況です。
ネットがこうなる前は、課題を話し合うための場が閉じていた代わりに、そこにあがる情報は一定のルールや精査を通ったものでした。しかし、今は、ネット上にどんな情報もオープンにあがってくる代わりに、その情報を適当に切り取る土俵もたくさんできてしまいました。また、多様で細分化されたセグメントの主体が、アジェンダを設定しています。すると、アジェンダを設定する手前の段階で争いが起き、データはオープンでも、データに基づいたコミュニケーションが行われない、という問題が生じています。
ネット社会は中心軸を欠いています。細分化されたアジェンダが、意思決定に関与できるのかというとできておらず、関与の仕方はむしろ見えづらい。そして、そのことに対する不満が高まり、「関与したつもりになる装置」が発達し、仲間内でのセクト化が不満を吸収する手段になっていたりもする。
科学的なデータを含めいろいろなものが見えやすくなったけれど、悲観的に考えると、見えるようになったもの同士がより対立を鮮明化させて、科学コミュニケーションについて言えば、科学的知見のセクト化のようなことにつながる可能性もある状況なのではないでしょうか。ネットが普及して、課題のフェーズは移ったけれど、結局のところ科学コミュニケーションが前進しているかどうか分からないのです。



伝統的な決定プロセスには"腑に落ちる対話"のヒントがある
最近、仕事で行政や地方自治体を相手にすることも多く、その手続きの大切さと、長い時間がかかるものだということを実感しています。伝統的な決定プロセスでは、面倒な書類の処理をして、多くの確認を踏んでいきます。その長いプロセスの中で、担当者は、いろんなステークホルダーの立場や考えをシミュレーションしていくわけですが、そのプロセスを通して、いつのまにかさまざまな人の言葉を代弁するようになっていくんですね。
また、書類や口頭で交わされる情報が無意識のうちに周囲に染み出し、説明会を開くころにはもう多くの関係者たちの間で共有されていたりします。つまり、伝統的なプロセスそのものが、根回しとネゴシエーションのプロセスになっているわけです。
例えば、コホート研究を進めるための健康調査について話すために、まず保健福祉課に行くとします。「何をしに来たのか?」と聞かれるので、担当者を探す過程で説明をして"情報が染み出す"。「町長に通しください」と言われ、秘書課に行く。その過程で書類を書いて突き返されたり相談したりしていくうちに、また情報が染み出し、説明する相手も増える...。そしていつの間にかみんなが知っていて、俺は聞いていない、という人がいなくなる。それは伝統的な、例えば村に道路をつくる場合と同じ決定のためのシステムなのでしょう。そこでは"ちゃんと挨拶する"というような、良し悪しはありますがそんな些細な過程が大事だったりするわけです。
伝統的な決定プロセスは、ネットなどの新たなコミュニケーションに比べて一見面倒くさい、因習に囚われたカビが生えたようなものに見えますが、そこには意味があり、それを通して"周知"と"理解"と"納得"がなされていきます。周知や理解は分かりやすいのですが、納得は難しくて曖昧なものです。
僕ら東北大学の人間が、仙台から車で3時間かかる漁師さんのところへ行って、靴を脱いで頭を下げている。それを見て、「あいつら一生懸命やっているから」と、それが納得につながることがあります。でもそれは、理解とは全く関係なかったりもします。またこれは、最初に述べた通り、決定が見えにくいものの象徴的な一例でもあります。多くの方々が納得するまでの一連の流れは、当事者以外には見えにくいものです。
サイエンスだからとカフェやシンポジウムをしても、興味のない人は来てくれません。そもそも僕らは科学を構えすぎてしまっているんじゃないかな、と感じます。結局地方では、地べたに座っておやじさんたちと一緒にお茶を飲んでコミュニケーションできた文脈の上にしか、科学のことも乗っからない。そんな話の中で、「科学なんて、難しっからわっかんねっぺ」と言われるんですが、そのわりには、実はけっこう理解してくれていたりもする。
僕がコミュニケーションの手法で参考にするのは、例えばNHKのテレビ番組「鶴瓶の家族に乾杯」です。あの鶴瓶さんの声のかけ方は、本当に参考になります。相手の何かをつかまえて話をし、信頼させる。敵意がないことを示して、「しょうがないから話を聞いてみてあげよう」という気分にさせる。悪意がない、布教に来たのではない、開拓団ではないことを、アピールする話術なんです。
悪ノリをして科学のあり方を展望する
今後、情報科学技術がもっと進化していくと、日常と非日常の境目や、科学者と一般の人の境目がよく分からなくなっていくと思います。例えば、ミクロの世界から大型望遠鏡で見ているような世界まで、これまで科学者しか見ることができなかった世界を、誰もが日常的に見ることができるようになっていくでしょう。シミュレーション研究には、大型研究であってもアマチュアが参画できるようになるかもしれません。
研究者と一般の人がフラットな関係になっていく世の中で、科学を伝えるときに「すごいだろう」という見せ方が難しくなり、より本質的なことが求められるようになるでしょう。しかし、それが何かはまだ分かりません。科学的知見によって得られる非日常的な経験の何が、どのくらい残るのか、本質的に研究者にしかできないことがどこに残されるのかもよく分かりません。一方で、科学が日常化することを利用してできる何かも生まれてくるのだろうと思います。
これからの科学と社会の対話ということで言うと、前に高校生に行なった生命倫理の授業が面白かったので紹介します。まず生徒たちに紙を配り、これから5~10年後に実現していそうな技術を書いてもらいました。その後で、「さあ、今日は倫理の授業です。その科学技術を応用して可能な、"想像しうる一番悪いこと"を考えてみましょう」と問いかけました。すると、生徒たちは、悪魔的なことをいろいろと言い出しました。サイエンスの楽しさは、実はその中にもあります。その負の面に気づき、隣の人間のアイデアなどについて話し合うことで、未来の方向をみんなで考えることができるでしょう。
授業では、悪ノリをすればするほど面白くなっていきました。生徒たちは、影の面を考えることを意外と楽しみます。最初、100人に聞いても手が挙がらないのですが、無理やりマイクを向けたりしながら3割ぐらいが話した段階になると、一斉にスイッチが入る。そこで、科学技術の良い、悪いという単純な切り分けだけでなく、複雑な有り様についても展望してみるのです。そんな場が持てると、みんながリアルに集まる意味が生まれるのではないでしょうか。

長神風二(ながみ ふうじ)
1974年生まれ。2002年東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程満期退学。日本科学未来館、科学技術振興機構、東北大学脳科学グローバルCOE特任准教授を経て、12年東北メディカル・メガバンク機構准教授。13年より東北メディカル・メガバンク機構特任教授。現在、副部門長も兼任。専門は、サイエンスコミュニケーション、科学広報。著書に、『予定不調和-サイエンスがひらく、もう一つの世界』ディスカヴァー・トゥエンティワン。