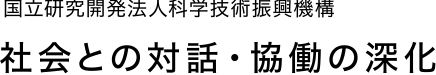科学コミュニケーションについて知りたい
インタビューシリーズ「科学と社会の関係深化のために」
Vol.03
科学と社会の関係深化のために
「科学する」を分け合うために
村山 斉
東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU) 機構長
世界トップレベルの研究拠点のひとつとして、数学と物理、天文学の最先端の知をつなげながら宇宙の謎を探求するカブリ数物連携宇宙研究機構。その立ち上げ時から「若き機構長」を務めてきた村山 斉さんは、素粒子理論における世界的リーダーの一人であるだけでなく、基礎科学分野の指導者としても活躍している。子供の頃から国内外で学び、暮らしてきた村山さんの目は、日本の中にある科学と社会の課題をどう見ているのだろうか。その視線は教育のあり方にも向けられている。

科学的とは何か
科学と社会の関係を深める上で、どうしても乗り越えねばならない課題、その「課題」という言葉を「障害」に置き換えるなら、一つに「科学が持つスタンス」を理解してもらえないという障害があります。科学というものがどのような問いを立て、どうやって答えを見つけようとしているのかを理解してもらえない。そこが大きな障壁になっているのではないでしょうか。
例えば、原発事故による放射能の話で言えば、一般の人はそれが「安全」なのか、「危険」なのか、白黒はっきりさせた答えを望むでしょう。しかし、科学者に聞くと、可能性や確率の話が始まり、結局、はっきりと断言しない。でもそれにはちゃんと理由があります。
どのくらい放射能を浴びたら人体にとって危険なのかのデータが少ないのです。原発事故で私たちが浴びる可能性のある放射線量は、広島や長崎の原爆で犠牲になられた方々が浴びた線量と比べるとはるかに少ない。その量で、どの程度人体に影響があるのか、まだ誰も知らないのです。
この状況で、「安全か危険か」と聞かれると、科学者はまず前提条件から説明しなくてはいけません。前提となる考え方と導かれる結論を論理的に説明しないと「科学」ではありませんから。それでようやく科学の専門家はちゃんと「説明した」と思うわけです。しかし、聞いている一般の人にとってはなんだかごまかされているような雰囲気に受け取られてしまう。「前置きはどうでもいいから答えを言ってくれ」と思われてしまうんです。

日本の新聞に思うこと
例えば、世論調査に関する新聞記事で、「内閣の支持率が2%下がった」と言うためには少なくとも1万人くらいの調査をしなければならないはずです。しかし、実際には数百人に聞いただけで「支持率が下がった」と書く記事もあります。こういう記事を見るたびに、新聞記者は"伝える専門家"のはずなのに、統計の意味や誤差を知らずに書いてるんだな、と思うわけです。
一般に、データや統計には必ず誤差があって、その誤差をはるかに越えるくらいの差が無い限り、変化を言うことはできません。ですから、本来であれば新聞は、「何人に調査をして、誤差はどれだけある」と明記しなければなりません。メディアがそういう努力をすると、記事を読む一般の人は、「世論調査には誤差が存在する」ということを毎回目にするわけですから、データの見方も慣れてくると思うんです。
アメリカの新聞には、しっかりと誤差を示してくれる記事が多い。でも日本には少ない。この状況が続けば「誤解が誤解を」生んだり、「科学に対して疑心暗鬼」になったり、果ては「信頼を失って」しまうのではないでしょうか。科学の持つ「スタンス」を一般の方になかなか分かってもらえない状況になる。そこに障壁があると考えます。
そもそも、科学の考え方や説明の仕方を理解できるようになること自体が、とても難しいと思うのですが、理想としては、子どもの頃から「科学的なものの見方や考え方」をもっとうまく教えることができれば、状況も変わるかもしれません。しかし、そう簡単ではありませんよね。
「科学する」を教えたい
これまでいくつか本を書かせていただきましたが、自分なりに伝えようと努力したことが2つあります。1つは、「科学者はパーフェクトではない」ということでした。例えば、かの有名なアインシュタインですら、自分の書いた理論から導かれた宇宙に始まりがあることを認めることができませんでした。
2つめは、「科学者は潔く捨てる」ということです。実験や観測によって事実がだんだん積み重なると、科学者はどんな思い込みや偏見をも捨てることができます。これは科学者の使命ですね。科学的なものの見方をしていくと、間違っているものを本当に「間違っている」と納得できる。例えば、天動説が地動説に変わるなんていうのはその例です。科学には、何かが「正しい」と証明することは決してできません。ある理論と合う答えが一つ出たとしたら、「その理論と合っている」とは言えても、その理論が「正しい」とは決して言えないのです。
日本では、学校の理科の時間にそうしたことに触れる機会があると思います。科学には仮説があり、それをテストして本当かどうかを調べ、間違っていたら仮説を修正して、またテストを繰り返すのだと知るのですが、今思い返すと、日本の学校教育では、理科の時間に、「こういう事実が分かっています」ということをたくさん詰め込まれますが、なぜその事実が分かったのかという、そこに至るプロセスをあまり教えてくれません。科学を学習する時間に科学の内容は学んでいるけれども、「科学する」という行動は学んでいないのです。
教育の場を変えるのは非常に難しいですよね。その理由の一つに、先生たち自身が「科学する」経験が少ないからだと思います。小中高等学校の先生になる人は、自分で「最先端の研究をした」経験がある人は少ないんじゃないでしょうか。小学校の先生の約8割が、理系科目を苦手と感じているという統計を見たことがあります。先生がこの状況だとすると、「科学する」ことを子どもに伝えるのはほぼ不可能ですよね。
アメリカの公立学校の先生は、夏の3カ月間は学校に雇われておらず、給料もありません。その間に志の高い先生は、いろんな研修を受けて勉強をしたり、あるいは全く違うことに挑戦する。アメリカでは、全地域の国立研究所が、そうした先生、特に高校の先生に向けて研修を行っています。
先生に最先端の研究の話を聞いてもらい、研究者が今挑戦していることや、「こうしたらこんなことができる」という思いを伝えます。その話を先生たちは自分たちの学校に持ち帰り、学生にシェアするのはもちろん、場合によっては授業で問題にしてぶつけてみたりします。実際の研究データを渡して、それを学生が解析してみたりするんですね。さすがに本物の研究者と同じことはできないけれども、先生自身がある程度経験したものを学校に持ち帰り、次に生徒が体験する。こうした取り組みは、2つの点で有効だと思います。
1つは、「伝わる相手の多さ」です。研修にはせいぜい30人くらいの先生しかいないわけですが、それぞれの先生が学校に帰って1000人の生徒に伝えたら、30人に対して1000倍の効果が生まれます。もう1つは、「体験する時期の早さ」です。高校生などまだ頭が柔軟なうちに経験する機会が得られます。大人になってからでは遅いかもしれない経験を、早くに体験できるのです。
伝えるためのトレーニング
受け手側だけでなく、送り手である科学者の側にも課題はあります。例えば、自分がやっていることを「分かるように」話すというトレーニングを受けていない。特に日本では、学生時代に、自分の意見を人前で発表する練習や、議論を戦わせるディベートをあまりやりません。ディベートの面白いところは、自分が本当に思っていることを語るとは限らない点です。与えられたテーマに対して、本心でなくても主張するようにと課題を与えられます。その課題に対して自分でいくつか論拠を考えることで、相手を説得する訓練をさせられる。これには良い点があります。
1つめは、自分の主張を「説得力があるように」話せるようになる点、2つめは、自分の考え方を「相対化」できるようになる点です。アメリカでは、それを小さいときから学んでいて、日本とすごく違うなあ、と思うんです。私の経験した日本の歴史の授業は、先生が黒板に延々と歴史上の事実や年号、人の名前を書いて、それをみんながノートに取って暗記します。しかしアメリカでは、歴史上の事実に対して「なぜこういうことになったんだろう?」と授業で議論するんです。ここにも「科学する」のと同じで、プロセスやその原因・結果があって、論理的なつながりがある。授業はそれをみんなで考える機会になっているんですね。
科学者のコミュニティの中で見ても、残念ながら、日本の科学者はすごくコミュニケーションが下手に見えます。例えば国際会議での日本人研究者の話は、すごくテクニカルで、同じ分野の人ですら分かりにくいとよく話題にされます。アメリカの研究者は、会議に参加している人の層を把握した上で、その層に伝わる言い方を考えて、ちょっと大げさにジョークをまじえながらコミュニケーションできる。
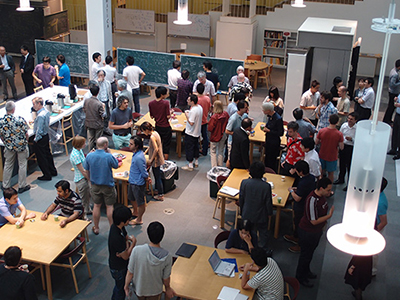
世界の科学者のコミュニティの中ですら日本人は損をしているのですが、だからといって「アウトリーチのために」とコミュニケーションを促しても、「忙しいから」と敬遠されるかもしれません。でも、「あなたの研究結果が、世界でより受け入れられるようになるために、トレーニングになりますよ」とアプローチすれば、結構前向きになる人がいるのではないかと思います。日本の研究者に比べてアメリカの研究者の方がアウトリーチに熱心かと言えば、それほどでもありません。ただ、人と話す訓練を受けているため、コミュニケーションが上手、慣れているんだと思います。
「科学コミュニケーション」を、最初から「一般向けに」と大上段に構えるのではなく、自分の研究発表をもっと上手に行うためのトレーニングということでプログラムして参加者を増やしていけば、徐々に浸透していくのではないでしょうか。そしたら次に、「一般の人の前で話すときにはこうしてみようかな」という考えも自然に出てくるようになる気がします。

村山 斉(むらやま・ひとし)
1964年生まれ。75年西独デュッセルドルフに転居し、ドイツで教育を受ける。79年帰国して日本の高校に進学後、東京大学に入学。90年日本学術振興会特別研究員。91年東京大学博士取得、93年米ローレンス・バークレー国立研究所ポスドク、95年カリフォルニア大学バークレー校助教授、97年准教授、2000年教授。07年10月に数物連携宇宙研究機構 (現:カブリ数物連携宇宙研究機構) 初代機構長着任。著書に、『宇宙は何でできているのか』(幻冬舎新書)、『宇宙は本当にひとつなのか』(講談社ブルーバックス)、『宇宙はなぜこんなにうまくできているのか』(集英社)、『村山さん、宇宙はどこまでわかったんですか?』(朝日新書)、『宇宙を創る実験』(集英社新書)。
■ 関連ウェブサイト
Kavli IPMU東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構