| ■ 研究領域「活性炭素クラスター」の概要 |
19世紀初頭のファラディによるベンゼンの発見で始まった芳香族化合物の化学は、ベンゼンと様々な元素との複合化が可能という性質から、20世紀に入り大発展を遂げ、現代科学・技術を支える基幹分野となった。この歴史に鑑みれば、ベンゼンの集積体と言うべきフラーレンやカーボンナノチューブなどの炭素クラスターに各種元素を複合化するための有効な化学的手法を編み出すことによって、炭素クラスターに内在する性質を完全に引き出し、さらにそれらに新しい性質を付与できるであろうことが予測出来るが、未だ十分に活用できていない。炭素クラスターをもとに作り出されるナノサイズの多元素複合化合物群は、21世紀の科学・技術を変革する可能性を秘めている。
本研究領域では、炭素クラスターに内在する活性に着目し、様々な元素を有する高活性・高機能な炭素クラスター新物質を作り出し、それらの性質の多様性を活用して、物質科学、ナノ科学や生命科学の学術や技術の基礎に貢献する発見を目指すと同時に、単分子エレクトニクス、ナノバイオロジーなどの未来技術の萌芽を探求する。具体的には,炭素クラスターと金属元素、生物活性物質の複合化手法の開拓、本手法により合成した物質群の形成する1次元から3次元の高次複合体の化学・物理的性質の探求、さらには生命体に対する作用を重層的に探求する。合成した様々な活性炭素クラスターおよびそれらの集合体の構造と機能の分析手法の開発は、現在の科学的分析手段の限界を越えるナノ構造解析にとっての挑戦的課題となる。
我が国のお家芸である精密合成化学と,我が国で育った炭素クラスターの科学や高度の分析技術を有機的に結合することによって炭素クラスターを中心とする高活性多元素クラスターに関する研究分野を新しい次元に導くことができる。
本研究領域では、ナノサイズ炭素クラスターを有機物質・無機物質等と結合し、さらにそれらの組織・構造の制御を行うことによって革新的な物性、機能を有する新物質創製を目指すものであり、戦略目標「環境負荷を最大限に低減する環境保全・エネルギー高度利用の実現のためのナノ材料・システムの創製」に資するものと期待される。 |
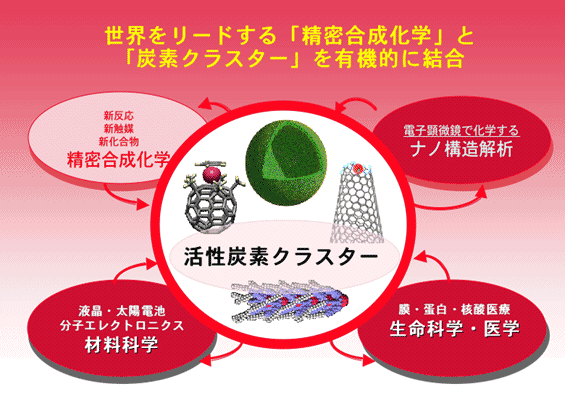 |
| ■ 研究総括 中村栄一氏の略歴等 |
| 1. |
氏名(現職) 中村 栄一(なかむら えいいち)
(東京大学大学院理学系研究科 教授/日本学術振興会学術システム研究センター 主任研究員)53歳 |
|
| 2. |
略歴
| 昭和44年 4月 | 東京工業大学理工学部入学 |
| 昭和48年 3月 | 同理学部化学科卒業 |
| 昭和48年 4月 | 東京工業大学理工学専攻科化学専攻入学 |
| 昭和53年 3月 | 同博士課程卒業(理学博士) |
| 昭和53年 4月 | 米国コロンビア大学化学科博士研究員 |
| 昭和55年 4月 | 東京工業大学理学部化学科化学第4講座助手 |
| 昭和59年12月 | 東京工業大学理学部化学科化学有機化学講座助教授 |
| 平成 5年12月 | 東京工業大学理学部化学科化学有機化学講座教授 |
| 平成 7年 4月 | 東京大学大学院理学系研究科理学部化学専攻有機化学講座教授 |
この間
| 平成 元年4月~ 3年3月 |
国立分子科学研究所相関領域部門客員助教授併任 |
| 平成15年9月~18年3月 |
日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員併任 |
| 平成13~16年度 |
文部科学省科学研究費補助金特別推進研究「炭素クラスター複合体の精密有機合成化学」代表者 |
|
| 3. |
研究分野
有機化学(物理有機化学,合成化学,有機金属化学,生物有機化学),理論化学
|
| 4. |
学会活動等
| 昭和61年~63年 |
有機合成協会誌編集委員 |
| 平成3年 |
第37回IUPAC General Assembly (Hamburg), Physical Organic Commission,日本派遣オブザーバー |
| 平成 4年~ 9年 |
Chemistry Letters 編集委員(日本化学会) |
| 平成 4年~ 5年 |
有機合成協会関東支部常任幹事 |
| 平成 4年~ 9年 |
Journal of Molecular Catalysis (Elsevier), Editorial Board |
| 平成 4年~15年 |
Ultrasonics Sonochemistry, Editorial Board |
| 平成 8年~ |
Topics in Stereochemistry (Wiley), Editorial Board |
| 平成10年~12年 |
文部省学術審議会専門委員 |
| 平成10年~12年 |
有機合成協会誌編集委員 |
| 平成10年~12年 |
Novartis財団研究助成審査委員 |
| 平成10年~12年 |
化学技術戦略推進機構物質・プロセス委員会委員 |
| 平成12年~ |
Organic Letters Associate Editor(アメリカ化学会) |
| 平成12年~16年 |
蓼科有機化学会議創設者および組織委員長 |
| 平成13年~16年 |
中央研究院(台湾)化学研究所学術諮詢委員会委員 |
| 平成14年 |
第16回国際物理有機化学会議国際委員 |
| 平成14年~16年 |
Journal of Organometallic Chemistry (Elsevier), Editorial Board |
| 平成13年~14年 |
日本化学会将来計画委員会国際交流WG主査 |
| 平成14年~16年 |
筑波大学付属駒場高等学校スーパーサイエンススクール運営指導委員 |
| 平成15年~18年 |
Organic and Biological Chemistry (王立化学会) International Editorial Board |
| 平成16年 |
科学技術振興機構・科学技術未来戦略ワークショップコーディネーター |
|
| 5. |
業績等
様々な化合物の化学反応性を通して元素の性質を理解し,その知識を総合して未知の化学反応を発見し,新しい化合物を作り出し,人類の福祉に役立つ新しい現象を見いだしていくことは,化学者の夢であり,責務である。1980,90年代を通して銅や亜鉛などの金属の触媒作用を活かした様々な触媒反応を開発する中で,半世紀前からブラックボックスだった銅触媒有機合成反応での多元素協働触媒サイクルや,ロジウムやコバルトなどの遷移金属触媒反応の反応経路を理論および実験を駆使して解明した(J. Am. Chem. Soc., 1997; Angew. Chem., 2000)。そして,これらの純正化学的知見を駆使して,フラーレンの化学修飾反応において新境地を開いた。世界に先駆けて水溶性フラーレンの生理活性の発見や放射性元素ラベルによる体内動態解明(J. Am. Chem. Soc., 1993)を成し遂げ,フラーレンを用いた遺伝子導入法を開発した(Angew. Chem., 2001)。一方,活性フラーレン誘導体の100%収率・100%選択的な大規模合成法の開発に成功(J. Am. Chem. Soc., 1996),さらにフラーレン・フェロセン複合体・バッキーフェロセンの合成(J. Am. Chem. Soc., 2000),両親媒性フラーレンのつくる二重膜ベシクルの創製 (Chem. Lett., 2000; Science, 2001),世界初のシャトルコック液晶分子の合成 (Nature, 2002)など,複合化フラーレンの応用の将来性を提示した。また半世紀にわたる化学者の夢であったベルト状環状芳香族化合物の合成にも初めて成功した (J. Am. Chem. Soc., 2003)。ここで培った手法をカーボンナノチューブ類の金属複合化に展開して,カーボンナノホーン内部に金属原子を捕捉する方法を発見した (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2004)。
受賞等
| 昭和59年 | 日本化学会進歩賞「新しい反応性中間体を活用する高選択有機合成反応に関する研究」 |
| 平成 3年 | 有機合成化学協会山之内研究企画賞「超音波照射下の熱的非平衡系でのラジカル連鎖反応の高次制御」 |
| 平成 4年 | 手島工業教育資金団記念研究賞 "New Tools in Synthetic Organocopper Chemistry" |
| 平成 4年 | 日本IBM科学賞「新しい反応活性種の合理的設計と実用的応用」 |
| 平成10年 | Fellow of The American Association for the Advancement of Science(アメリカ科学振興協会フェロー)"Fundamental studies in synthetic methodology and the applications of organic synthesis to preparations of useful materials" |
| 平成13年 | 名古屋メダル「Synthetic organic chemistry of carbon cluster complexes」 |
| 平成14年 | 日本化学会賞「新規炭素共有結合形成に基づく機能性分子の創製」 |
|
|
|