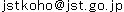大越 慎一 教授(東京大学 大学院理学系研究科 化学専攻)らの研究グループは、光を当てると非磁石の状態(常磁性注1)状態)から磁石の状態 (強磁性注2)状態)へと変化する新種の光スイッチング磁石の開発に成功しました。この物質は、鉄イオンと有機分子を組み合わせた固体物質で、光照射によりスピンクロスオーバー現象 (遷移金属イオンのスピン状態が、低スピン状態注3)と高スピン状態注4)の間で変化する現象)を起こすことにより、磁石の状態に変換する新しいメカニズムの光磁石です。光磁石の磁気相転移温度(Tc)注5)は、20K(ケルビン、摂氏-253度)で、加熱処理により元の非磁石の状態に戻ります。スピンクロスオーバー分子が三次元的に連結した物質では、光によって磁石の状態に変換できるであろうという予想に基づき、今回、大越教授らは、スピンクロスオーバーを示す鉄イオンを、スピンを持つオクタシアノニオブ酸イオンを介して三次元的に架橋することにより、新種の光スイッチング磁石の合成に成功しました。スピンクロスオーバー光磁性体は有機分子を多量に含むことが可能であり、将来、構造的に柔軟性があるフレキシブル光磁性材料への第一歩であるといえます。
本研究成果は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 チーム型研究(CREST)「プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出」研究領域(研究総括:入江 正浩 立教大学 理学部 教授)における研究課題「磁気化学を基盤とした新機能ナノ構造物質のボトムアップ創成」(研究代表者:大越 慎一)によって得られ、2011年6月5日(英国時間)に英国科学雑誌「Nature Chemistry」のオンライン速報版で公開される予定です。
オプトエレクトロニクス用材料として、光で変化する物質(光相転移材料・光変換材料)の研究開発が現在、活発に進められています。光によって直接的に磁性をスイッチングできる光磁性材料は、光による直接的な書き込みが可能であるため、光メモリーや光コンピューターなどの光磁気メモリー媒体などへの応用が期待されています。
大越教授らは、スピンクロスオーバーを光で誘起するという機構で光強磁性を引き起こすことを目的に研究を行ってきました。代表的なスピンクロスオーバー現象として、鉄(II)イオンにおける高スピン状態FeII(S=2)と低スピン状態FeII(S=0)間の熱的な転移が知られています。もし、スピンクロスオーバー分子を無数に連結した結晶固体ができれば、光により磁石の状態へ相転移させることができるようになると期待されます(図1)。これを実現するため、今回、オクタシアノニオブ酸鉄(II)ピリジンアルドキシム(Fe2[Nb(CN)8]・(4-CHNOH-C6H5N)8・2H2O)という三次元構造物質を合成しました(図2)。この物質はスピンクロスオーバー物質であることが実験の結果から確認されると共に(図3)、473nmの青色光を17 mWcm-2の光強度で5分間照射すると、Tcが20K、保磁力(Hc)注6)が240Oe(エルステッド)の強磁性相に光誘起相転移することを観測しました(図4)。各種分光測定より、光を当てる前はFeII低スピン状態(S=0)ですが、光照射後は、FeII高スピン状態(S=2)へと変化し、強磁性状態になることが明らかになりました(図5)。このような光誘起スピンクロスオーバーによる光強磁性の観察は、本研究例が初めてです。本研究においてスピンクロスオーバー光磁性体が実現した理由は、スピンクロスオーバーを示す鉄(II)イオンとシアノ基を介して連結しているニオブイオン(NbIV、S=1/2)との間に強い磁気的相互作用が働いたことなどが挙げられます。
スピンクロスオーバー光磁性体は、有機分子を多量に含むことが可能であるため(今回の物質では有機分子の含有量が体積分率で80%以上)、将来、構造的に柔軟性があるフレキシブル光磁性材料の開発に向けた第一歩であると考えています。
<参考図>
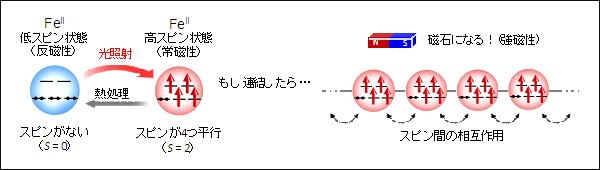
図1 スピンクロスオーバー現象およびスピンクロスオーバー光磁性体のコンセプト図
鉄(II)イオンにおけるスピンクロスオーバー現象では、高スピン状態FeII(S=2)と低スピン状態FeII(S=0)の間を熱や光によって変化する。もし無数の高スピンサイトが連結した場合、それらのスピンが配列して磁石になると期待される。
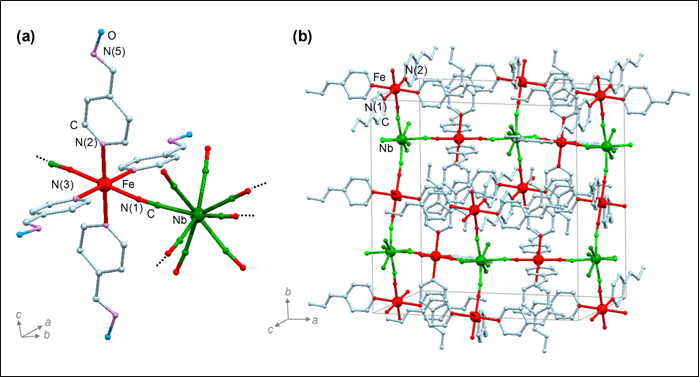
図2 Fe2[Nb(CN)8]・(4-CHNOH-C6H5N)8・2H2Oの結晶構造
- (a)鉄およびニオブ原子の配位環境。
- (b)c軸方向からの結晶構造投影図。
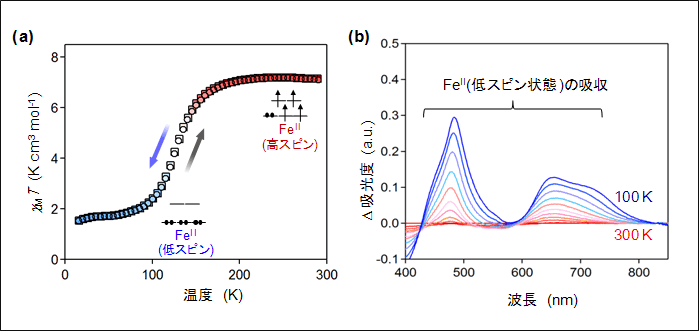
図3 Fe2[Nb(CN)8]・(4-CHNOH-C6H5N)8・2H2Oのスピンクロスオーバー現象
- (a) 化率(χM)×温度(T)の温度依存性。χMTの値は温度低下とともに減少し、スピンクロスオーバーによるFeII(高スピン状態)(S=2)からFeII(低スピン状態)(S=0)への転移が観測された。□および○はそれぞれ、冷却プロセスおよび加温プロセスを表す(挿入図は、FeII(高スピン状態)とFeII(低スピン状態)の電子配置)。
- (b) 視吸収スペクトルの温度依存性。300Kを基準とした時の、300Kと100Kの間の差分スペクトルを示す。
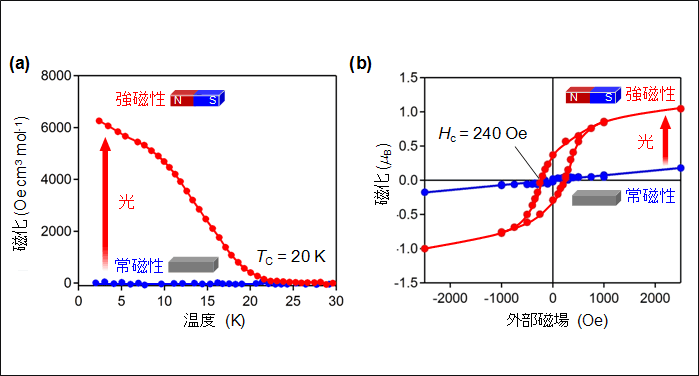
図4 Fe2[Nb(CN)8]・(4-CHNOH-C6H5N)8・2H2Oにおける光誘起強磁性
- (a)473nm光照射前後の磁化-温度曲線;(
 )光照射前、(
)光照射前、( )光照射後。
)光照射後。
- (b)473nm光照射前後の磁化-磁場曲線;(
 )光照射前、(
)光照射前、( )光照射後(Tc:キュリー温度;Hc:保磁力)。
)光照射後(Tc:キュリー温度;Hc:保磁力)。
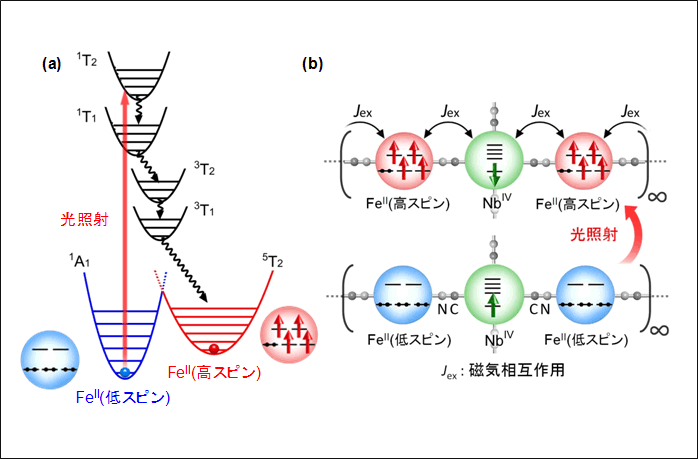
図5 スピンクロスオーバー光磁性のメカニズム
- (a) 光誘起の概念図。FeII(低スピン)状態(1A1状態)が光照射によって励起一重項状態(1T2あるいは1T1状態)に励起され、励起三重項状態(3T2および3T1状態)を経てFeII(高スピン)状態(5T2状態)へと転換する。
- (b) 光誘起スピンクロスオーバー現象による磁気秩序化の機構。光照射により生じたFeII(高スピン)(S=2)と隣接したNbIV(S=1/2)がスピンクロスオーバー大きな磁気相互作用(超交換相互作用:Jex)によって反平行にスピンが配列し磁石となる(本物質はフェリ磁性体である)。矢印はスピンを表している。
<用語解説>
- 注1) 常磁性
- 熱ゆらぎによりスピンの向きが乱れており、自発的な磁化を持たない磁性。
- 注2) 強磁性
- いわゆる磁石のこと。スピンの方向が整列しており、全体として大きな磁気モーメントを持つ磁性。外部磁場がなくても自発磁化を持つことができる。スピンが平行に並んだフェロ磁性と、反平行に並んだフェリ磁性がある。
- 注3) 低スピン状態
- d電子が、パウリ則により電子対を形成し、不対電子スピンが少ない状態。
- 注4) 高スピン状態
- d電子が、フント則により孤立しており、不対電子スピンが多い状態。
- 注5) 磁気相転移温度(Tc)
- スピンの方向がばらばらな常磁性状態からスピンが整列した強磁性状態に相転移する温度。強磁性相転移温度あるいはキュリー温度ともいう。
- 注6) 保磁力(Hc)
- ある方向に磁化された磁石を、磁化されていない状態に戻すために必要な反対向きの外部磁場の大きさ。
<論文名および著者名>
“Light-induced Spin-crossover Magnet”
(スピンクロスオーバー光磁性体)
doi: 10.1038/nchem.1067
Shin-ichi Ohkoshi, Kenta Imoto, Yoshihide Tsunobuchi, Shinjiro Takano, and Hiroko Tokoro
<お問い合わせ先>
<研究に関すること>
大越 慎一(オオコシ シンイチ)
東京大学 大学院理学系研究科 化学専攻 教授
Tel:03-5841-4331、03-5841-4637 Fax:03-3812-1896
E-mail: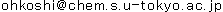
<JSTの事業に関すること>
石井 哲也(イシイ テツヤ)
科学技術振興機構 イノベーション推進本部 研究領域総合運営部
Tel:03-3512-3524 Fax:03-3222-2066
E-mail: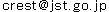
<報道担当>
横山 広美(ヨコヤマ ヒロミ)
東京大学 大学院理学系研究科 広報・科学コミュニケーション 准教授
Tel:03-5841-7585
E-mail: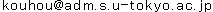
科学技術振興機構 広報ポータル部
Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432
E-mail: