|
|

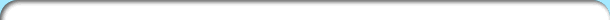 |
 |
- 小松雅明研究者(2期生)
赤血球産生に関与する新しい細胞内酵素に関する研究成果が英国オンライン科学雑誌Nature Communicationsに発表されました。(2011年2月8日)
[掲載誌]
Nature Communications, published online: February 8, 2011; | doi: 10.1038/ncomms1182
[発表テーマ]
The Ufm1-activating enzyme Uba5 is indispensable for erythroid differentiation in mice
[発表概要]
赤血球は体内の細胞に酸素を運び込み、二酸化炭素を運び出す働きをしています。成人では約20億個もの赤血球が体中を巡回しており、赤血球の減少や機能異常は生命を脅かします。赤血球の寿命はおよそ120日間であることから、私たちは毎日大量の赤血球を産生する必要があります。従来、赤血球の産生は造血幹細胞の増殖・分化を促進するサイトカインの働きと、それに呼応し遺伝子発現を制御する転写因子の働きにより厳密に制御されていると考えられてきました。実際、赤血球の分化を促進するサイトカインであるエリスロポエチンの受容体や赤血球の分化を制御する転写因子GATA1の遺伝子を欠損させたマウスは、赤血球の欠乏により重篤な貧血を呈し、胎生期に死亡します。
今回、小松研究者らは、たんぱく質修飾因子Ufm1を活性化する酵素Uba5を全身で欠損させたマウスが、赤血球産生に関与するエリスロポエチン受容体やGATA1を欠いたマウスと同様に重篤に貧血を呈して胎生期に死亡することを明らかにしました。重要なことに、このUba5欠損マウスの血液前駆細胞だけでUba5酵素を発現するようにした遺伝子改変マウスを作出したところ、Uba5欠損マウスで見られた貧血が大幅に改善し、延命することが判明しました。この結果は、たんぱく質修飾活性化酵素Uba5が赤血球産生に直接関与するということを意味します。
赤血球は生命活動に必須であり、絶えず産生され体内に供給され続ける必要があります。造血の異常は生命を脅かす脳貧血や骨髄異形成症候群といった病気を引き起こします。今回の発見は、既知であったサイトカインや転写因子に加えて、血液産生に直接働く新しい細胞内酵素の発見であり、こうした病気の治療法開発につながる発見です。
- 村上誠研究者(1期生)
分泌性ホスホリパーゼA2 の生理機能に関する研究成果が米国科学雑誌J. Biol. Chem.オンライン速報版に連報で発表されました。(2011年1月25日)
[掲載誌]
J. Biol. Chem., published online: January 25, 2011; | doi:10.1074/jbc.M110.206714
[発表テーマ]
Hair Follicular Expression and Function of Group X Secreted Phospholipase A2 in Mouse Skin
[発表概要]
村上誠研究者らは、分泌性ホスホリパーゼA2 (sPLA2) のひとつであるX型sPLA2 (sPLA2-X)が、皮膚の限局したコンパートメント、すなわち毛包(hair follicle)の最外層細胞(外根鞘:ORS)に、毛周期の増殖期に対応して一過的に発現することを見出しました。sPLA2-X過剰発現マウスは第一毛周期に脱毛するとともに、顕著な表皮過形成と皮脂腺肥大を呈しました。皮膚のリピドミクス解析により、sPLA2-Xはホスファチジルエタノールアミンからアラキドン酸などの高度不飽和脂肪酸を遊離し、このアラキドン酸は主にPGE2に代謝されることがわかりました。更に、sPLA2-X欠損マウスの皮膚では体毛関連遺伝子群が一括的に減少しており、超微細形態観察の結果、毛包ORS細胞の増殖遅延が生じていました。本論文は、体毛の形成を制御するsPLA2アイソザイムを同定した初めての報告です。
[掲載誌]
J. Biol. Chem., published online: January 25, 2011; | doi:10.1074/jbc.M110.206755
[発表テーマ]
Physiological Roles of Group X Secreted Phospholipase A2 in Reproduction, Gastrointestinal Phospholipid Digestion, and Neuronal Function
[発表概要]
分泌性ホスホリパーゼA2 (sPLA2) のひとつであるX型sPLA2 (sPLA2-X) が高発現しているマウス組織は生殖器と消化管、および末梢組織の神経繊維ですが、これらの発現部位における本酵素の機能は不明でした。本研究では、sPLA2-X欠損マウスと過剰発現マウスを用いて、これらの組織における本酵素の機能を解析しました。その結果、sPLA2-Xが (1) 精子の受精能を制御するが雌の生殖には関わらないこと、(2) 食餌リン脂質の消化とそれに起因する脂肪組織への脂肪沈着に関与しており、欠損マウスでは恒常的な脂質の消化吸収の低下により加齢に伴い体重と脂肪沈着の減少が起こること、(3) 脊髄後根神経節神経の突起伸長と末梢性痛覚応答の持続性に関わること、を明らかにしました。従来、sPLA2-Xはアラキドン酸代謝を介して炎症や動脈硬化に関わることが強調されてきましたが、本研究は本酵素が本質的に発現している組織における生理機能を解明した初めての報告です。
- 川島博人研究者(2期生)
抗糖鎖抗体の作製に関する研究成果が米国科学雑誌J. Biol. Chem.に発表され、JBC Papers of the Weekに選ばれました。(2010年12月24日)
[掲載誌]
J. Biol. Chem., vol. 285, 40864-40878 (2010)
[発表テーマ]
Novel anti-carbohydrate antibodies reveal the cooperative function of sulfated N- and O-glycans in lymphocyte homing
[発表概要]
糖鎖は、分化・発生、免疫、癌化、タンパク質品質管理などにおいて様々な役割を果たし、近年、第三の生命鎖として注目されています。糖鎖の機能解明には、生体において、いつ・どこで・どのような糖鎖が発現するのかを明らかにする必要があります。そのためには、特定の糖鎖に特異的な抗糖鎖抗体は極めて有用なツールとなりますが、その作製は一般的に困難です。
川島研究者らは、特定の糖鎖生合成酵素を欠損するマウスをその糖鎖の強制発現株で免疫することにより効率よく抗糖鎖抗体を得る新しい方法論の開発を行いました。具体的には、硫酸基転移酵素二重遺伝子欠損マウスを硫酸基転移酵素強制発現株で免疫し、二種類の抗硫酸化糖鎖モノクローナル抗体S1およびS2を新たに樹立しました。さらにこれらの抗体を用いて、リンパ球のリンパ組織への移行と接触性皮膚炎の惹起において、血管内皮細胞に発現する硫酸化されたN-及びO-型糖鎖が協調的に機能することを明らかにしました。
本研究成果は、抗糖鎖抗体を抗体医薬品として用いたアレルギー性疾患の治療法の開発につながることが期待されます。また、本研究で開発した新しい方法論は、他の糖鎖生合成酵素の産物に対しても特異的抗体を効率よく作製するために広く応用しうる汎用性の高いものであり、糖鎖生命科学の発展に広く貢献することが期待されます。
- 有田誠研究者(2期生)
炎症収束の分子機構に関する研究成果が米国科学雑誌The FASEB Journalオンライン速報版に発表されました。(2010年10月19日)
[掲載誌]
The FASEB Journal, published online: October 19, 2010; | doi: 10.1096/fj.10-170027.
[発表テーマ]
Eosinophils promote resolution of acute peritonitis by producing pro-resolving mediators in mice
[発表概要]
炎症反応は微生物感染や外傷に対する重要な生体防御システムです。一方で、一度誘発された炎症は適切に収束する必要があり、この制御が破綻すると慢性炎症や組織傷害を伴う病態につながります。従って、炎症が適切に収束するための分子機構の解明は、医学薬学領域における重要課題です。
有田研究者らは、マウスの急性腹膜炎モデルを用い、ある特定の細胞が炎症の収束期に出現することを見いだし、これが好酸球であることを明らかにしました。さらに好酸球を除去すると急性腹膜炎の収束が遅延することを見いだしました。炎症を制御する脂肪酸代謝物の包括的メタボローム解析の結果、好酸球がプロテクチンD1(PD1)というドコサヘキサエン酸(DHA)由来の抗炎症性代謝物を効率よく産生する細胞であることが分かりました。また、好酸球の除去による収束の遅延は、外から好酸球を補うことで回復しましたが、この効果はPD1の産生酵素である12/15-リポキシゲナーゼを欠損した好酸球では認められませんでした。さらにPD1の直接投与でも炎症の収束は回復しました。以上の結果から、炎症収束期の好酸球および好酸球から産生されるPD1などの脂質メディエーターが、一度誘発された炎症を速やかに収束させる機能を有することが明らかになりました。
本研究成果は、一旦起こった炎症を速やかに収束させるという新たな治療標的として期待されます。さらに「治らない炎症」を基盤病態とする慢性疾患の病態解明につながる可能性が期待されます。
- 村上誠研究者(1期生)
分泌性ホスホリパーゼA2 による精子機能制御に関する研究成果が米国科学雑誌J. Clin. Invest. オンライン速報版に連報で発表されました。(2010年4月26日)
[発表テーマ、掲載誌]
1. Group III Secreted Phospholipase A2 Regulates Epididymal Sperm Maturation and Fertility, J. Clin. Invest., published online: April 26, 2010; | doi:10.1172/JCI40493.
2. Group X phospholipase A2 is released during sperm acrosome reaction and controls fertility outcome in mice, J. Clin. Invest., published online: April 26, 2010; | doi:10.1172/JCI40494.
[発表概要]
生命の発生は、精子と卵子の融合(受精)から始まります。精子は①精巣での精子形成によって産生され、②精巣上体での精子成熟を経て受精能を獲得し、③射精された後に子宮内で活性化し、④卵管で卵子と受精してその生涯を遂げます。しかしながら、これらの諸過程でリン脂質代謝が如何に制御されているかについては殆ど未解明でした。村上研究者らは、2種の異なる分泌性ホスホリパーゼA2 (sPLA2) サブタイプが②および③の各過程に関わることを見出しました。
村上研究者らが作出したsPLA2-III 欠損マウスは精巣上体の精子が未成熟で、精子鞭毛の構造異常による運動性低下のため受精率が著減し、雄性不妊の表現型を示しました。精巣で作られた未熟な精子は精巣上体を通過する際に膜リン脂質の脂肪酸リモデリングが起こり、オレイン酸やアラキドン酸などのϖ-6/ϖ-9系列の不飽和脂肪酸からドコサヘキサエン酸などのϖ-3系列の高度不飽和脂肪酸に置き換わります。sPLA2-IIIは精巣上体の管腔上皮細胞に発現しており、欠損マウスは精巣上体における精子膜リン脂質の脂肪酸リモデリングが著しく損なわれるために精子成熟不全をきたすことがわかりました。村上研究者らは更に、精子のアクロソーム尖端部にsPLA2-Xが発現しており、アクロソーム反応により分泌されることを発見しました。sPLA2-X 欠損マウスの精子は、精巣での精子形成から精巣上体での精子成熟までは正常でしたが、活性化(アクロソーム反応)が起こりにくく、そのため受精率が低下することがわかりました。
以上の結果より、精巣で作られた精子は、(1) sPLA2-IIIによる精巣上体での成熟、(2) sPLA2-Xによる雌性生殖器内での活性化、の2段階制御を受け、卵子との受精が可能になることが初めて明らかとなりました。
- 榎本和生研究者(2期生)
神経回路の再編の分子メカニズムに関する研究成果が米国科学雑誌Developmental Cellに掲載されました。(2010年4月20日)
[掲載誌]
Developmental Cell, vol. 18, 621-632 (2010)
[発表テーマ]
Dendrite reshaping of adult Drosophila sensory neurons requires matrix metalloproteinase-mediated modification of the basement membranes
[プレス発表]
http://www.jst.go.jp/pr/info/info729/index.html
[発表概要]
人間の脳内の神経細胞は、胎児の後期から生後にかけて、神経突起を介した神経回路網を作り上げます。その後、幼児期に音や光などの外部情報を感受し始めると、神経回路の配線の組み替えが頻繁に起こり、言語や音感の学習成立や外環境への適応が行われると考えられています。従って、決まった期間に脳内の適当な場所で神経回路の再編が起こらなければ、さまざまな精神疾患につながると予想されますが、このような神経回路の再編がどのようにして制御されているのかについては、これまで、ほとんど明らかにされていませんでした。
榎本研究者らは、神経回路の構造が人間と類似しているショウジョウバエを研究モデルとし、神経回路の再編を簡便に解析することができるシステムを確立してきました。そして、そのシステムを用いて、神経回路の再編について詳細な解析を行いました。その結果、たんぱく質分解酵素の一種、マトリックス・メタロプロテアーゼ(Mmp)が神経回路の再編に必須であり、神経回路の足場となっている物質を部分的に分解していることを明らかにしました。さらに、分解されずに残存した足場に依存して神経回路が「再配置」されるという現象が起こることを突き止め、この「再配置」の繰り返しにより神経回路の再編が引き起こされることを明らかにしました。
Mmp遺伝子は人間の脳にも存在し、脳神経系で発現していることが知られています。今後、Mmpの機能に着目した研究を行うことにより、人間の脳内における神経回路の再編メカニズムや、精神遅滞疾患などの精神疾患の発症機序の解明、その診断・予防に役立つことが期待されます。
- 南野徹研究者
心不全とインスリンシグナルに関する研究成果が米国科学雑誌J. Clin. Invest. オンライン速報版に発表されました。(2010年4月19日)
[掲載誌]
J. Clin. Invest., published online: April 19, 2010; | doi: 10.1172/JCI40096.
[発表テーマ]
Excessive cardiac insulin signaling exacerbates systolic dysfunction induced by pressure overload in rodents
[発表概要]
南野徹研究者らは、過剰なインスリンシグナルは圧負荷によって誘導される心不全を増悪させることを発見しました。
これまでインスリンシグナルは、生理的な心肥大を誘導し、心臓保護的に働くと考えられていました。しかし多くの臨床研究の結果は、インスリナルが心不全の増悪因子であることを示唆しています。
今回の研究は、過剰なインスリンシグナルが、心筋細胞肥大と血管密度のミスマッチを誘導し、圧負荷によってもたらされる心不全を悪化させることを明らかにしました。インスリンシグナルの適度な抑制は、圧負荷による相対的な血管密度の低下を改善することによって、心不全の進行を阻害しました。圧負荷によって心臓におけるインスリンシグナルは活性化していましたが、全身性にはインスリン抵抗性と高インスリン血症を示しており、それらが心不全の進行に関与していました。本研究によって、インスリンシグナル制御による心不全治療の必要性が示唆されました。
- 宮本健史研究者
破骨細胞分化の制御機構に関する研究成果が米国科学雑誌The Journal of Experimental Medicineオンライン速報版に発表されました。(2010年4月5日)
[掲載誌]
The Journal of Experimental Medicine, published online: April 5, 2010; | doi: 10.1084/jem.20091957
[発表テーマ]
The Blimp1-Bcl6 axis is critical to regulate osteoclast differentiation and bone homeostasis
[発表概要]
破骨細胞は骨の恒常性を保つためのリモデリングを担う中心的な細胞です。破骨細胞分化においては、転写因子であるNFATc1が分化を進めるマスター転写因子であると考えられてきました。しかし、逆に破骨細胞分化をネガティブに制御する転写抑制機構については、まだあまり明らかにされてはいませんでした。
宮本研究者らは、転写抑制因子であるBcl6が、破骨細胞に特徴的な遺伝子群の転写を負に制御すること、Bcl6欠損マウスではこれらの分子の抑制がきかず、破骨細胞分化の亢進から骨量減少をきたすことを見いだしました。また、このBcl6はやはり転写抑制因子であるBlimp1によって発現が抑制されること、破骨細胞特異的Blimp1欠損マウスではBcl6の発現抑制がきかず、破骨細胞分化抑制から骨量増加を示すことを見いだしました。以上の結果は、RANKL-Blimp1-Bcl6 axisが正常に働くことが破骨細胞分化ならびに骨の恒常性維持に必須であることを示しています。
本研究成果は、骨粗鬆症などにおける病態解明や、その治療において新たな治療標的開発の道を開くことが期待されます。
- 重信秀治研究者
アブラムシのゲノム解読に関する研究成果が米国オンライン科学雑誌PLoS Biologyに掲載されました。さらに、英国科学雑誌Insect Molecular Biologyに多数の関連論文が掲載されます。(2010年2月23日)
[掲載誌]
PLoS Biol, published online: February 23, 2010; |doi:10.1371/journal.pbio.1000313
[発表テーマ]
Genome Sequence of the Pea Aphid Acyrthosiphon pisum
[プレス発表]
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20100223-2/index.html
[発表概要]
国際アブラムシゲノム解析コンソーシアムは、昆虫アブラムシのゲノムを解読したことを発表しました。重信研究者はこの国際プロジェクトにおいて日米両国で中心的役割を果たしました。
重信研究者は、アブラムシと共生細菌との間に見られる協調的な代謝制御機構について、さきがけ研究を進めてきましたが、今回の研究で、アブラムシAcyrthosiphon pisumゲノムからおよそ3万5千個の遺伝子を見つけました。重信研究者が既に発表済みの共生細菌のゲノムと比較すると、共生細菌との栄養共生は、アミノ酸やヌクレオチド代謝の経路を構成する遺伝子セットの相補的な関係という形でゲノムに反映されていました。また、アブラムシは免疫関連の遺伝子を大幅に失っていることがわかりました。アブラムシが微生物への攻撃能力を放棄することにより、そうした生物の受け入れや維持を容易にし、細菌との共生を成功させたと解釈できます。また、10種類以上の遺伝子が細菌からアブラムシの核ゲノムに水平転移しており、共生に深く関わっている可能性が示唆されました。
本研究成果は、共生を担う遺伝子基盤の理解につながるものです。特に、アブラムシは様々なタイプの異種間相互作用すなわちエコロジーについて詳しく研究されていることから、ゲノム情報を用いたエコロジー研究が可能な新たなモデル生物として期待されます。
- 小松雅明研究者
小松雅明研究者と東北大学大学院医学系研究科の山本雅之教授らは、オートファジーに関する研究成果を英国科学雑誌Nature Cell Biologyオンライン速報版に発表しました。(2010年2月21日)
[掲載誌]
Nature Cell Biology, published online: 21 February 2010 | doi: 10.1038/ncb2021
[発表テーマ]
The selective autophagy substrate p62 activates the stress responsive transcription factor Nrf2 through Keap1-inactivation
[プレス発表]
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20100222/index.html
[発表概要]
細胞内の自己たんぱく質を分解するオートファジー(自食作用)の障害は、細胞内凝集体の構成成分であるp62たんぱく質の異常な蓄積・凝集化を伴って、防御作用に関係する抗酸化たんぱく質群の遺伝子発現を誘導します。これらの現象は、肝細胞がんやグリオーマなどの悪性腫瘍の病態特性とよく似ています。しかし、その詳しい仕組みや病態生理学的意義は不明のままでした。
今回の研究は、p62たんぱく質が、細胞内の酸化ストレスを巧みに制御していることを分子レベルで新たに見つけたものです。つまりp62たんぱく質が、細胞の酸化ストレスを感知するたんぱく質に直接相互作用することを発見しました。この相互作用により、抗酸化たんぱく質群の遺伝子発現を促す転写因子の分解が阻害されていることを確かめました。その結果、p62が細胞内に過剰に蓄積すると、間接的に、抗酸化たんぱく質群の遺伝子発現が誘導されるというストレス防御システムがあることが分かりました。この仕組みは今まで知られていませんでした。
肝細胞がんやグリオーマなどでは、オートファジーの障害ないしはp62遺伝子の発現上昇によりp62たんぱく質が過剰に蓄積されます。それを起因に、新しく知られたストレス防御システムを恒常的に活性化させ、自身を酸化ストレスから守るという生存戦略がとられていると考えられます。したがって、p62たんぱく質の発現を制御する化合物が新しい抗がん剤の創薬候補になることが期待されます。
- 南野徹研究者
血管新生障害の原因分子に関する研究成果が米国科学雑誌Circulation Researchに掲載されました。(2010年2月5日)
[掲載誌] Circulation Research, vol. 106, 391-398 (2010)
[発表テーマ]
Inhibition of semaphorin as a novel strategy for therapeutic angiogenesis
[発表概要]
南野徹研究者らは、セマフォリンという神経軸索のガイダンス分子が、新規の血管新生治療の標的となりうることを発見しました。
セマフォリンは糖尿病状態で老化分子p53によって誘導されていました。糖尿病状態では、虚血組織における血管新生が障害されていることが知られていますが、本分子の活性を抑制すると、血管新生が著明に改善することがわかりました。逆にセマフォリンを活性化すると、非糖尿病状態でも血管新生は抑制されていました。
今回の研究成果より、セマフォリンは、糖尿病やメタボリックシンドロームなど老化分子の活性化している状態における血管新生障害の原因分子であり、新規の治療標的となりうると考えられます。
- 田中元雅研究者(1期生)
プリオン凝集体の生成機構に関する研究成果が米国科学雑誌Nature Chemical Biologyオンライン速報版に発表されました。(2010年1月17日)
[掲載誌]
Nature Chemical Biology, published online: January 17, 2010 | doi 10.1038/nchembio.306
[発表テーマ]
Differences in prion strain conformations result from non-native interactions in a nucleus
[発表概要]
プリオン病は、孤発性、遺伝性、感染性に分類され、精神機能の低下を伴う神経変性疾患です。その発症機構は、いまだ十分に理解されておらず、治療薬も確立されていません。プリオン病の特徴として、原因となるプリオンタンパク質が脳内で凝集すること、また、プリオンタンパク質のアミノ酸配列が同じでも異なる症状を示すこと(プリオン株の存在)が挙げられます。これまで田中研究者らは、異なる症状が、プリオンタンパク質の凝集体(アミロイド)の構造の違いに由来することを、酵母プリオンの系を用いて明らかにしてきました。しかし、その異なるアミロイド構造が、まったく同じプリオンタンパク質からどのように生成するのかは不明でした。
今回の研究では、大型放射光施設SPring-8を用いて、酵母プリオンのSup35NMタンパク質が凝集する初期段階に形成する核(オリゴマー)の構造が、アミロイドの最終的な構造や、ひいてはプリオン株の表現型(感染強度など)を決定する重要な因子になっていることを見いだしました。さらに、Sup35NMタンパク質が、アミロイド内には存在しない、“非天然相互作用”をオリゴマー形成時に巧みに利用して、感染性の高い脆弱なアミロイド構造を導くことを発見しました。
この成果は、プリオン病だけでなく、疾患原因タンパク質がアミロイドを生成する多くの神経変性疾患の病態解明や、新たな治療法の開発に道を開く、と期待できます。
- 池ノ内順一研究者
上皮細胞の膜分離機構に関する研究成果が米国科学雑誌PNASオンライン速報版に発表されました。(2009年12月22日)
[掲載誌]
PNAS, published online: December 22, 2009 | doi 10.1073/pnas.0908423107
[発表テーマ]
FRMD4A regulates epithelial polarity by connecting Arf6 activation with the PAR complex
[発表概要]
私たちの体を構成する上皮細胞には、アピカル膜やバソラテラル膜などの機能の異なる細胞膜領域(膜ドメイン)が存在しています。このような秩序だった構造は、細胞が様々な機能を発揮する上で必須です。それぞれの膜ドメインを構成する膜タンパク質や脂質代謝物は異なり、ドメイン間を自由に拡散しないと考えられています。しかしながら、そのような細胞膜上の仕切りを作るメカニズムについては、ほとんど明らかになっていません。
池ノ内研究者らは、上皮細胞同士が接着する過程に着目して、接着の初期段階から細胞接着領域に集積する遺伝子の探索を行いました。研究の結果、アピカル膜とバソラテラル膜の分離に必要な新しい遺伝子「FRMD4A」を発見しました。更に、FRMD4A遺伝子から作られるタンパク質は、細胞骨格の再編成や細胞内輸送の調節において重要な働きをするArf6と呼ばれるタンパク質の活性を細胞接着部位において制御することにより、アピカル膜とバソラテラル膜の分離に寄与していることを明らかにしました。
人間の悪性腫瘍の90%以上は上皮細胞に由来し、浸潤性の癌細胞ではアピカル膜とバソラテラル膜を分離する仕組み(細胞極性)が破綻している例が多く認められます。今回の発見は、浸潤性癌細胞の発症メカニズムの解明やその予防につながると考えられます。
- 中野雄司研究者
葉緑体活性化の調節機構に関する研究成果が英国科学雑誌The Plant Journalオンライン速報版に発表されました。(2009年12月)
[掲載誌]
The Plant Journal, published online: December 2009 | doi: 10.1111/j.1365-313X.2009.04077.x
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20091214-2/index.html
[発表テーマ]
The chloroplast protein BPG2 functions in brassinosteroid-mediated posttranscriptional accumulation of chloroplast rRNA
[発表概要]
植物にはブラシノステロイドと呼ぶステロイドホルモンが存在します。その増加は、茎を長くしたり、葉を大きくするなど「体の形作り」を促進し、その減少は、光合成を行う重要な器官である葉緑体を活性化します。つまりブラシノステロイドは、体の形作りと光合成の調節という植物の成長に大変重要な役割を担っています。
中野研究者らは、このブラシノステロイドの生合成を阻害する薬剤「ブラシナゾール(Brz)」を用いて、シロイヌナズナの葉緑体を過剰に発達させ、CO2(二酸化炭素)の吸収で重要な働きを担うタンパク質を、通常の150%の量に増加させることなどに成功しました。また、ブラシノステロイドが葉緑体の活性化を抑制する機構の解明のため、ケミカルバイオロジー研究法を駆使し、シロイヌナズナの変異体種子8,000種の中から、Brz存在下(ブラシノステロイドの抑制下)でも双葉の緑色が薄い変異体を探索しました。その結果、1つの変異体bpg2を発見し、その原因遺伝子「BPG2」を同定することに成功しました。実際、このBPG2を破壊するだけで、葉緑体の中のリボゾームRNAに異常が生じ、その結果、多種類のタンパク質合成の激減や、葉緑体の内部構造や双葉の緑色が薄く見える異常が起きることを確認しました。ブラシノステロイドによる葉緑体活性化の調節機構で、このような「司令塔役」となる遺伝子を発見したのは世界で初めてのことです。
将来、葉緑体の機能増強で大気中CO2を削減し、「低炭素社会」実現へ貢献することが期待できます。
- 小松雅明研究者
小松雅明研究者とNew Jersey-Robert Wood Johnson Medical SchoolのDr. Shengkan Jinらのオートファジーに関する研究成果が、米国科学雑誌PNASに掲載され、同誌の表紙に採択されました。(2009年11月24日)
[掲載誌]
PNAS, vol. 106, 19860-19865 (2009)
[発表テーマ]
Adipose-specific deletion of autophagy-related gene 7 (atg7) in mice reveals a role in adipogenesis
[発表概要]
オートファジーは、細胞質に膜が出現することで開始されます。膜は伸張しながら自身の細胞質構成成分を取り囲んで閉口し、その結果、二重膜からなる構造体、オートファゴソームが形成されます。次に、オートファゴソームの外膜がリソソーム膜と融合することで、内膜とそれに内包された細胞質構成成分がリソソームに局在する種々の分解酵素の働きで壊されます。つまり、オートファジーは、細胞小器官などの巨大分子をも丸ごと壊すことができる特徴を有しており、飢餓時の栄養供給だけでなく、細胞質に凝集した変性タンパクの除去や細胞のリモデリング(細胞小器官等の再構成)にも必要とされます。小松研究者らは条件付きオートファジーノックアウトマウスを作出し、様々な組織におけるオートファジーの生理的役割を解析してきました。
脂肪細胞は細胞質の大部分を脂肪滴が占める特殊な細胞であり、分化の過程において細胞質の再編成がなされます。以前より、この課程にオートファジーが関与することが示唆されてきましたが、培養細胞を用いた形態学的解析に留まり遺伝学的解析はなされていませんでした。今回、小松研究者らは脂肪細胞特異的にオートファジーが不能となるマウスを作製し、解析しました。この変異マウスは脂肪組織が激減し、その脂肪細胞は野生型に比して小さく、細胞質中の脂肪滴の減少およびミトコンドリアの増加が確認されました。また、その脂肪細胞においてβ酸化の亢進やホルモン誘導性の脂肪分解の低下が見られ、結果として血漿中の脂肪酸の減少やインスリン感受性の亢進が起こっていました。さらに、変異マウスは、血漿中のレプチン、トリグリセリド並びにコレステロールレベルの低下を呈し、重要なことに高脂肪食誘導性の肥満に抵抗性を示しました。
今回の研究成果は、オートファジーが脂肪細胞発生に必須であることに加えて、肥満治療の新たなターゲットとなることを示唆するものです。
- 稲田利文研究者 (1期生)
異常タンパク質の分解促進機構に関する研究成果がヨーロッパ分子生物学会誌EMBO reports オンライン速報版に発表されました。(2009年10月2日)
[掲載誌]
EMBO reports (2009), 10, 1265 - 1271, doi:10.1038/embor.2009.200
[発表テーマ]
Upf1 stimulates degradation of the product derived from aberrant messenger RNA containing a specific nonsense mutation by the proteasome
[発表概要]
稲田研究者らは、ナンセンス変異を持ったmRNA由来のタンパク質のプロテアソームよる分解をUpf1が促進することを発見しました。
多様性を獲得する段階のエラーによって合成される異常mRNAやDNA変異等に起因する異常mRNAは、遺伝子発現の正確性を保証する「mRNA品質管理機構」によって認識され分解されます。例えば、遺伝病の主要な原因変異であるナンセンス変異を持ったmRNAは、NMD(nonsense-mediated mRNA decay pathway;ナンセンス変異依存分解系)によって速やかに分解されます。しかしながら、細胞内に存在する様々な異常mRNA由来の遺伝子産物の発現抑制機構は全く明らかでありませんでした。
今回の研究では、ナンセンス変異を持ったmRNAから合成される短い異常タンパク質の安定性を解析しました。その結果、ナンセンス変異を持ったmRNA の分解機構であるNMDに必須なUpf複合体が、プロテアソームによる異常タンパク質の分解を促進することをみいだしました。この結果により、「異常タンパク質の分解促進」というUpf複合体の新規機能が初めて明らかになりました。
- 山口英樹研究者
山口英樹研究者と当領域アドバイザー深見希代子教授らは、浸潤突起形成とヒト乳癌細胞に関する研究成果を米国科学雑誌Cancer Researchオンライン速報版に発表しました。(2009年11月3日)
[掲載誌]
Cancer Research, published online: November 3, 2009 | doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-2305
[発表テーマ]
Lipid rafts and caveolin-1 are required for invadopodia formation and extracellular matrix degradation by human breast cancer cells
[発表概要]
浸潤突起は生理的な基質上で培養された癌細胞の底部に観察される特殊な細胞膜構造です。この構造は細胞外基質を分解する活性を持つことから、癌浸潤転移において重要な働きをしていると考えられています。しかし、その生体内での機能や形成の分子機構は未だほとんど明らかになっていません。
脂質ラフトはコレステロールやスフィンゴ糖脂質に富む細胞膜ドメイン構造であり、局所的なシグナル伝達や膜輸送に関与しています。山口研究者らは脂質ラフトが浸潤突起に局在し、脂質ラフト形成がヒト転移性乳癌細胞による浸潤突起形成と浸潤活性に必要であることを明らかにしました。また、脂質ラフトの構成タンパク質であるCaveolin-1が浸潤突起形成に必要であり、細胞外基質分解酵素であるMT1-MMPの機能制御を行い癌細胞の浸潤活性に関与することを報告しました。さらに、ヒト乳癌細胞の浸潤突起形成能とCaveolin-1及びMT1-MMPの発現に相関があることを示しました。
今回の研究成果は、癌浸潤転移を標的とした新たな治療法開発に寄与するものと期待されます。
- 榎本和生研究者
感覚ニューロンの受容領域形成を制御する基本メカニズムに関する研究成果がヨーロッパ分子生物学会学会誌The EMBO Journalオンライン速報版に発表されました。(2009年10月29日)
[掲載誌]
The EMBO Journal, published online: October 29, 2009 | doi:10.1038/emboj.2009.312
[発表テーマ]
The target of rapamycin complex 2 controls dendritic tiling of Drosophila sensory neurons through the Tricornered kinase signaling pathway
[発表概要]
榎本研究者らは、細胞内エネルギー・センサーとして知られる TOR(target of rapamycin)キナーゼが、感覚ニューロンでは樹状突起のタイル構造を構築する為の必須因子として働くことを発見しました。
視覚・触覚・温度感知などに携わる感覚ニューロンは、外部情報を正確 に受容する為に、入力突起である樹状突起を適切な空間へと配置しなければなりません。たとえば視神経は、網膜上において樹状突起をタイル状に配置することにより正確な視覚情報の入力を実現しています。しかし樹状突起のタイル化を制御する基本メカニズムに関してはほとんど理解されていません。榎本研究者は、TORキナーゼがショウジョウバエ感覚ニューロンに発現することに着目して機能解析を行なったところ、TORがニューロン受容領域のタイル構造構築に必須であることが分かりました。
以前より、TORキナーゼの異常と一部精神疾患との関連が指摘されていました。本研究は、TORキナーゼの機能異常が樹状突起の形成異常につながることを初めて示した知見であり、精神疾患の発病メカニズム解明や予防法の開発に繋がると考えられます。
- 初谷紀幸研究者(1期生)
細菌感染に対する植物免疫機構に関する研究成果が米国科学雑誌Genes & Developmentオンライン速報版に発表されました。(2009年10月15日)
[掲載誌]
Genes & Development, published online: October 15, 2009 | doi:10.1101/gad.1825209
[発表テーマ]
A novel membrane fusion-mediated plant immunity against bacterial pathogens
[発表概要]
初谷研究者らは細菌に感染した植物が誘導する新しい防御メカニズムを発見しました。
私達ヒトは病原菌やウイルスに感染すると、体内の免疫細胞がこれらの外敵を攻撃しくれます。植物も様々な外敵にさらされながら生きていますが、動物にみられる免疫細胞のような特殊部隊をもっていません。そのため、植物は外敵である細菌やウイルスの感染に対して、感染を受けた細胞を犠牲にして死滅させることにより、病原体が全身に拡散することを防いでいます。この生体防御のための細胞死のメカニズムについては、同グループが2004年に米国サイエンス誌にウイルス感染に対する細胞死の実行因子を明らかにしてきましたが(Science, 2004)、細菌に対するメカニズムは不明のままでした。
植物細胞は、内部に発達した液胞をもち、液胞の中に細菌を攻撃するための抗菌物質や分解酵素を多量に蓄積しています。一方、細菌は細胞の外で増殖し植物を危機にさらします。しかし、植物が、細胞外の細菌を死滅させるために、どのようにして細胞内の抗菌物質を使っているかということは長らく謎のままでした。本研究グループは今回、細菌に感染した植物の細胞が、細胞の内側にある液胞と外部とをつなぐトンネルをつくることにより、液胞内部の抗菌タンパク質を外部に放出して細菌を攻撃すると同時に、自らの細胞を死に至らしめるという防御メカニズムを見出しました。
病虫害による食糧損失の軽減は、21世紀の食糧危機を救う重要課題となっています。薬剤防除技術に頼らない環境に調和した新たな病害防除技術の開発が求められている中、本研究の成果は、植物が本来もつ自己防衛能力を強化させるための技術開発に貢献することが期待されます。
- 佐野元昭研究者
ミトコンドリア酸化ストレスと心筋代謝に関する研究成果が米国科学雑誌Circulation Researchオンライン速報版に発表されました。(2009年10月8日)
[掲載誌]
Circulation Research, published online: October 8, 2009; | doi: 10.1161/CIRCRESAHA.109.206607
[発表テーマ]
Metabolic remodeling induced by mitochondrial aldehyde stress stimulates tolerance to oxidative stress in the heart
[発表概要]
ミトコンドリア由来の活性酸素による脂質過酸化とアルデヒドの産生は、酸化的高分子機能障害を介して心臓の病的リモデリングを促進します。一方で低用量のアルデヒドはシグナル伝達分子として働き抗酸化ストレス応答機構を誘導する働きをもつことも知られていました。
佐野研究者らはミトコンドリアのアルデヒド脱水素酵素活性を阻害したトランスジェニックマウスを作製しました。このマウスの心筋ミトコンドリアには期待した通りアルデヒドが蓄積し、マトリックスは酸化状態に傾き、内膜構造の障害と異常な沈着物の出現を認めました。予想外にもこのトランスジェニックマウスの心臓の収縮機能は野生型マウスと変わらず、冠動脈結紮(虚血)・再灌流障害による心筋細胞壊死に対しては野生型マウスよりも耐性を示しました。この適応現象は酸化的障害を受けたミトコンドリアから核への逆行性シグナル( eIF2a-ATF4経路)の恒常的活性化よってグルタチオンレドックスサイクルを活性化させるように心筋代謝のリモデリングがおこり、ミトコンドリア酸化障害と共存する形で心筋細胞全体のレドックスホメオスターシスを維持することによって達成されることを証明しました。
このようなホルメシスストレス応答は、ミトコンドリアの酸化障害が進行している高齢者の心疾患治療に対する新しい治療標的になると考えられます。
- 今井浩孝研究者
男性不妊症と抗酸化酵素GPx4との関連に関する研究成果が米国科学雑誌J. Biol. Chem.オンライン速報版に発表されました。(2009年9月25日)
[掲載誌]
J. Biol. Chem., published online: September 25, 2009; | doi: 10.1074/jbc.M109.016139
[発表テーマ]
Depletion of selenoprotein GPx4 in spermatocytes causes male infertility in mice
[発表概要]
今井浩孝研究者らは以前の研究で、ヒト男性不妊症の中で、特に重度の乏精子症患者における精子において、抗酸化酵素 リン脂質ヒドロペルオキシドグルタチオンペルオキシダーゼ(GPx4)の著しい発現低下症をはじめて報告していました。今回、GPx4の精子での発現低下が本当に男性不妊症の原因となるのかを明らかにする目的で、精巣内の精母細胞特異的なGPx4欠損マウスを作成したところ、精子でのGPx4が欠損し、雄マウスが不妊症となることを見出しました。
精母細胞特異的GPx4欠損マウスは、精巣内の精母細胞が脱落し、著しい総精子数の減少が見られることが明らかになりました。またGPx4は精子のミトコンドリアに多く存在しますが、GPx4が欠損した精子は、ミトコンドリア部分おいてヘアピン様に折れ曲がった構造になること、精子ミトコンドリアの膜電位の維持が、採取後速やかに減少し、クリステ構造が破壊され、精子の運動能が著しく低下すること、GPx4欠損精子ではin vitroでの受精能が欠損することが明らかとなりました。これらのフェノタイプは正常のGPx4ゲノム遺伝子を戻すことにより回復されました。
本研究成果より、GPx4の精巣、精子での欠損は男性不妊症の原因となることが明らかになり、本欠損マウスはGPx4欠損によるヒト男性不妊症の詳細な病態解明や治療薬の開発にも役立つと考えられます。
- 岩脇隆夫研究者
小胞体ストレス応答に関する研究成果が米国科学雑誌PNASオンライン速報版に発表されました。(2009年9月15日)
[掲載誌]
PNAS, published online: September 15, 2009; | doi:10.1073/pnas.0903775106
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20090915/index.html
[発表テーマ]
Function of IRE1 alpha in the placenta is essential for placental development and embryonic viability
[発表概要]
岩脇研究者らは、難病との関連性が指摘されている、小胞体ストレスの軽減にかかわる分子の1つである「IRE1α」が、妊娠中の胎盤で胎児の生死を左右する重要な機能を持つことを世界で初めて発見しました。
ストレスは精神的なものを連想しがちですが、実は小さな細胞の世界にもストレスは存在します。小胞体ストレスは、細胞小器官の1つである小胞体への機能的な負担や障害により生じます。そもそも小胞体は、分泌タンパク質や膜タンパク質の加工工場として機能しています。それらタンパク質には生物が生きていくのに重要なものが数多く含まれるため、小胞体がうまく機能しない場合には、生命活動に大きな支障が生じます。これまでにアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患や糖尿病といった難病と、小胞体ストレスとの関連性が報告されてきました。しかしその一方、健康な生物で小胞体ストレスがどのような生命現象に関与するのかはよく分かっていませんでした。
今回の研究では、小胞体ストレスをマウス生体レベルで可視化する技術と、遺伝子欠損技術を利用して、妊娠中の胎盤が軽度な小胞体ストレス状態にあること、そして小胞体ストレスを軽減するために働くとされているIRE1αが、胎盤の発達や機能に必須であることを明らかにしました。これは健全な繁殖・成長過程でのほ乳動物体内における小胞体ストレスの実態や、それを解消するための反応「小胞体ストレス応答」にかかわる分子の存在意義に迫る発見です。さらに、妊娠中の過度な小胞体ストレスと流産の危険性との関連性を解明する研究へ発展する可能性を持ち、医学的な立場から人間社会への貢献が期待できます。同時に、家畜動物の繁殖が重要な畜産などの産業にも影響を及ぼすと注目されます。
- 新藤隆行研究者
アドレノメデュリンとその受容体活性調節システムに関する研究に対して第13回日本心血管内分泌代謝学会高峰譲吉研究奨励賞の授賞が決定しました。
[授賞式] 2009年10月23日(さいたま市大宮ソニックシティ)
[受賞講演]
アドレノメデュリンとその受容体活性調節システムの病態生理学的意義の解明
[発表概要]
アドレノメデュリン(AM)は、全身の組織で広範に産生される生理活性ペプチドです。AMは強力な血管拡張作用を有する降圧物質として発見されましたが、その後の研究から、体液量調節作用、抗酸化作用、抗炎症作用、抗血栓作用など多彩な生理活性を有することが明らかとなってきました。AMと生活習慣病を中心とした多くの病態との関連も示唆されています。一方、AMとそのファミリー因子は、受容体CRLRを共用しています。CRLRは、もう一つ別の1回膜貫通型タンパクである、RAMP1、2、3のいずれかと重合することが報告されています。
新藤研究者らは、AMノックアウトマウスが致死となる直前の胎生中期の血管において、RAMPサブアイソフォームの中でも、特にRAMP2の発現が亢進している事に着目しました。 新藤研究者らはRAMP2ノックアウトマウス(RAMP2-/-)を樹立し、RAMP2-/-では、AMノックアウトマウス(AM-/-)の血管の異常が再現され、胎生中期に著明な全身性浮腫を生じて致死となることを見いだしました。これに対し、その他のRAMPについては発現変化を認めず、RAMPサブアイソフォームの間には相補性がないことを初めて明らかとしました。またRAMP2発現が半減しているヘテロノックアウトマウス(RAMP2+/-)の成体では、虚血時の血管新生低下が確認されました。更に、血管内皮細胞特異的RAMP2ノックアウトマウス(E-RAMP2-/-)は、殆どが胎生致死でしたが、一部生存したE-RAMP2-/-では、全身の血管炎様の変化や、腎障害などの自然発症が認められました。
以上の結果は、AMの発生における血管新生作用が、RAMP2によって規定されていること、成体においても、AMによる血管新生作用、血管保護作用、臓器保護作用がRAMP2によって制御されていることを示すものです。現在、各RAMPサブアイソフォームのコンディショナルターゲティングなどから発生や各種病態におけるAM-RAMPシステムの役割を多角的に検討しており、それらの知見を将来的に新たな治療法開発へと展開することが期待されます。
- 尾池雄一研究者(1期生)
炎症とメタボリックシンドローム・糖尿病に関する研究成果が米国科学雑誌Cell Metabolismに掲載されました。(2009年9月2日)
[掲載誌]
Cell Metabolism, vol. 10, 178-188 (2009)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20090902/index.html
[発表テーマ]
Angiopoietin-like protein 2 promotes chronic adipose tissue inflammation and obesity-related systemic insulin resistance
[発表概要]
肥満は世界規模で増加の一途をたどっており、肥満に伴う糖尿病や心血管疾患の罹患率、死亡率の増加は社会的な問題となっています。これまでの研究により肥満の際の脂肪組織では慢性炎症が生じており、そのことが糖尿病や全身の代謝異常などの原因となることが明らかになってきていますが、脂肪組織に慢性炎症が生じる機構については不明な点が多く残されていました。
尾池研究者らは今回、肥満の脂肪組織ではアンジオポエチン様たんぱく質2(Angptl2)が多く発現していることに着目し、このたんぱく質の機能について研究を行いました。その結果、Angptl2は肥満の内臓脂肪組織で発現が増加しており、炎症の発症・維持で重要な役割を果たす「単球細胞」を病変部に呼び込んで、脂肪組織の慢性炎症を引き起こすこと、それにより全身でのインスリン抵抗性が生じ、糖尿病の発症につながっていることが分かりました。また、Angptl2の増加が、動脈硬化症の前病変として考えられている血管内皮細胞の炎症性病変を引き起こすことも分かりました。
今後、Angptl2の量や作用を抑えることによって新たなメタボリックシンドローム・糖尿病治療薬の開発につながるものと期待されます。
- 今村博臣研究者
今村博臣研究者と大阪大学産業科学研究所の野地博行教授、北海道大学電子科学研究所の永井健治教授らは、生きた細胞内のATP濃度の可視化に関する研究成果を米国科学雑誌PNASオンライン速報版に発表しました。(2009年8月31日)
[掲載誌] PNAS, published online: August 31, 2009; | doi:10.1073/pnas.0904764106
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20090901/index.html
[発表テーマ]
Visualization of ATP levels inside single living cells with fluorescence resonance energy transfer-based genetically encoded indicators
[発表概要]
ATPは、全ての生物に共通する「細胞のエネルギー通貨」と呼ばれる化合物です。私たちが食べた食物のエネルギーは、いったんATPを合成するために消費されます。そして、ATPに蓄えられたエネルギーは、たんぱく質合成・神経細胞の活動・筋肉の収縮などエネルギーを必要とする反応のために消費されます。このように、細胞はエネルギーをATPというかたちでやりとしていることから「細胞のエネルギー通貨」と呼ばれています。
今村研究者らは、ATPを特異的に結合するたんぱく質の両末端に水色および黄色蛍光たんぱく質をつなげることで、ATP濃度に応じて蛍光色が変化するたんぱく質「ATeam」を作成しました。そして、ATeamの遺伝子を細胞に導入することで、ATeamたんぱく質が細胞内で合成され、その蛍光色から生きた細胞のATP濃度をリアルタイムで観察することに成功しました。この観察の結果、細胞内部のATP濃度は均一ではなく、たとえばミトコンドリアは細胞質と比べてATP濃度が低く保たれていることを新たに発見しました。また、ATeamを改造することで、いろいろなATP濃度での計測に適した改変型ATeamを作成することにも成功しました。
これにより、生きた細胞1個1個のATP濃度を知ることが可能となり、ATPの新しい役割が解明されると期待されます。
- 南野徹研究者
脂肪の老化と糖尿病に関する研究成果が英国科学雑誌Nature Medicineオンライン速報版に掲載されました。(2009年8月30日)
[掲載誌] Nature Medicine, published online: 30 August, 2009; | doi: 10.1038/nm.2014
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20090831/index.html
[発表テーマ]
A crucial role for adipose tissue p53 in the regulation of insulin resistance
[発表概要]
細胞は分裂を繰り返すと、染色体の両端にあるテロメアが短縮することによって染色体の不安定化がひき起こされて老化します。また、細胞は活性酸素による染色体の傷害によっても老化します。これら細胞の老化の過程においては、がん抑制遺伝子として知られているp53の活性化が重要であること、加齢に伴って老化した細胞が体内に蓄積していくことが示されており、これらの老化細胞の蓄積が個体の寿命や加齢に伴う疾患の発症に関与しているのではないかと推測されていました。
南野研究者らは今回、テロメアの短縮しているマウスモデルでは、糖尿病やメタボリック症候群の発症に重要な病態であるインスリン抵抗性をひき起こしており、その機序に脂肪組織の老化が関与していることを明らかにしました。また、2型糖尿病マウスでも脂肪組織が老化しており、その老化を抑制することによって2型糖尿病の発症が抑制され、逆に脂肪老化を促進するとインスリン抵抗性がひき起こされることを明らかにしました。
さらに、2型糖尿病患者の内臓脂肪も老化していたことから、ヒトの糖尿病においても脂肪の老化がその病態に関与している可能性があります。
本研究成果は、2型糖尿病やメタボリック症候群に対して、脂肪の老化制御による新たな治療戦略の開発につながるばかりでなく、加齢に伴うこれらの疾患の発症機構を知る上で重要な知見となりうるものと考えられます。
- 眞鍋一郎研究者
眞鍋一郎研究者と当領域アドバイザー永井良三教授らは、内臓脂肪の炎症に関する研究成果を英国科学雑誌Nature Medicineオンライン速報版に発表しました。(2009年7月26日)
[掲載誌] Nature Medicine, published online: 26 July 2009 | doi:10.1038/nm.1964
[発表テーマ]
CD8+ effector T cells contribute to macrophage recruitment and adipose tissue inflammation in obesity
[発表概要]
眞鍋研究者らは以前の研究で内臓脂肪組織が肥満する際に慢性炎症と捉えることができるダイナミックな変化が生じていることを報告してきました。今回、どのようなメカニズムで炎症が誘導されるかを検討し、CD8+ T細胞が脂肪組織炎症の誘導と維持に必須であることを見いだしました。
マウスに高脂肪食を与えると、内臓脂肪である精巣上体脂肪組織の間質に、まずCD8+ T細胞が増えます。これに続いてマクロファージが集積します。CD8+ T細胞を除去すると、脂肪組織の炎症が著明に抑制され、全身のインスリン感受性も改善します。逆にCD8+ T細胞の存在しないマウスにCD8+ T細胞を補充すると、脂肪組織で炎症が惹起され、インスリン感受性が悪化します。いったん脂肪組織の肥満と炎症が完成したマウスでも、CD8+ T細胞の除去により炎症の抑制とインスリン感受性の改善が見られることから、CD8+ T細胞は炎症の惹起と維持の療法に重要なことが明らかとなりました。脂肪細胞、CD8+ T細胞、マクロファージの間には様々な相互作用があり、肥満ではこれらの細胞の相互作用によって脂肪組織の炎症と全身のインスリン抵抗性が生じると考えられます。
今回の研究成果は、脂肪組織の炎症を標的とする新しい治療法開発の可能性を強く示唆するものです。
- 中戸川仁研究者
オートファジーの分子メカニズムに関する総説が英国科学雑誌Nature Reviews Molecular Cell Biologyに掲載されました。(2009年7月)
[掲載誌] Nature Reviews Molecular Cell Biology, vol. 10, 458-467 (2009)
[発表テーマ]
Dynamics and diversity in autophagy mechanisms: lessons from yeast
[発表概要]
オートファジーは、酵母からヒトまで、真核生物に共通して備わる細胞質成分の大規模な分解系です。その最たる特徴は、リソソームや液胞といった分解の場に分解すべきもの(積み荷)を包み込んで運ぶための二枚重ねの脂質膜のふくろ(オートファゴソーム)の形成にあります。酵母におけるオートファジーの発見とその遺伝学的研究から、オートファゴソームの形成に必須のATG遺伝子群が同定されました。ATG遺伝子は、哺乳動物にも保存されており、そのノックアウト細胞・個体の研究から、オートファジーは栄養飢餓に対する応答機構として重要な役割を果たすだけでなく、発生や分化、老化、細胞死、免疫等、多彩な生命現象や、神経変性疾患や肝疾患等の病気とも深い関連があることが明らかになりつつあります。
本総説では、ATG遺伝子がコードするAtgタンパク質のオートファゴソーム形成における機能やダイナミクスについて、中戸川研究者らの最近の知見も含めて概観しました。また、積み荷の種類や膜の形成様式の違い等、オートファジーの多様性について、分子レベルでの理解を深めるために議論しました。
- 深田正紀研究者(1期生)
パルミトイル化酵素群によるシナプス伝達の制御機構に関する研究成果が米国科学雑誌The Journal of Cell Biologyオンライン速報版に掲載されました。(2009年7月13日)
[掲載誌] The Journal of Cell Biology, vol. 186, 147-160 (2009). Published online: July 13, 2009; | doi:10.1083/jcb.200903101.
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20090713/index.html
[発表テーマ]
Mobile DHHC palmitoylating enzyme mediates activity-sensitive synaptic targeting of PSD-95
[発表概要]
認知症、統合失調症やてんかんなどの脳神経疾患発症の重要な原因は、神経細胞同士のつなぎ目である神経シナプス間の情報伝達の精密性や可塑性が失われることが原因であると考えられています。シナプスではイオンチャネルなどの蛋白質が集まって整然と配置され、かつ神経活動に応じてその数が精密に制御されています。たとえば、神経細胞は自身の活動(発火)が低下すると、シナプス伝達に関わるイオンチャネル(AMPA受容体)のシナプスにおける数を増やそうとする恒常性を示します。深田研究者はこれらの仕組みに、蛋白質にパルミチン酸を結合させる「パルミトイル化脂質修飾」が関わっていると推測して研究を進めてきました。
深田研究者らはこれまでに23種類のパルミトイル化脂質修飾酵素を同定していましたが、今回、このうちのDHHC2とDHHC3の働きを、AMPA受容体のシナプス足場蛋白質でパルミトイル化されるPSD-95をライブ動画にとらえることで明らかにしました。興味深いことに、神経活動の低下に伴い、PSD-95のパルミトイル化レベルが大きく上昇することが分かりました。樹状突起内やスパイン近傍に小胞状に存在するDHHC2が、神経活動の低下に伴い、シナプス後部膜近傍にダイナミックに移動してPSD-95のパルミトイル化レベルを増加させ、その結果、シナプスにおけるAMPA受容体の数を増加させることが分かりました。一方、DHHC3は神経細胞の細胞体内のゴルジ装置に限局して存在し、神経活動とは無関係にPSD-95を含む様々な基質蛋白質をパルミトイル化すると考えられました。このように、パルミトイル化酵素が1)外界刺激の下流で分子種により異なる制御をうけていること、2)シナプス機能(AMPA受容体の発現量)を一定に保つ恒常性維持という現象を制御していることが明らかになりました。
23種類のパルミトイル化酵素は遺伝学的に精神発達遅滞、統合失調症およびがんと関連することから、この発見は、シナプス伝達に異常がみられる難治性神経疾患の病態解明や治療薬の開発にも役立つと考えられます。
- 田中元雅研究者(1期生)
蛋白質凝集構造に基づくハンチントン病の発症機構に関する研究成果が米国科学雑誌PNASオンライン速報版に発表されました。(2009年6月1日)
[掲載誌] PNAS, published online: June 1, 2009; | doi:10.1073/pnas.0812083106
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20090526/index.html
[発表テーマ]
Distinct conformations of in vitro and in vivo amyloids of huntingtin-exon1 show different cytotoxicity
[発表概要]
田中研究者らは、神経変性疾患の1つであるハンチントン病の原因タンパク質「ハンチンチン」がさまざまな構造形態の凝集体を形成し、それぞれ異なる細胞毒性を示すことを世界で初めて発見しました。
ハンチントン病は、不随意運動、認知力低下を伴う神経変性疾患で、その発症機構はいまだ十分に理解されておらず、治療薬も確立されていません。ハンチントン病の特徴として、原因タンパク質のハンチンチンが、脳内で不溶性の線維状凝集体「アミロイド」を形成することが挙げられます。しかし、そのアミロイド構造が、ハンチントン病の病態にどのように関与しているかは不明でした。田中研究者らは、同じアミノ酸配列を持つハンチンチン断片が、異なるアミロイド構造を形成することや、その各々が異なる細胞毒性を持つことを見いだしました。また、ハンチントン病モデルマウスの脳内でも、アミロイド構造の多様性を確認し、その多様性が、ハンチントン病における神経細胞の脱落や変性の部位特異性を決定している1つの要因である可能性が高まりました。
本研究成果は、ハンチントン病だけでなく、疾患原因タンパク質がアミロイドを形成する多くの神経変性疾患の病態解明や、新たな治療法の開発に道を開くものです。
- 佐野元昭研究者
グルココルチコイドの心筋細胞保護効果に関する研究成果が米国科学雑誌J. Clin. Invest. オンライン速報版に発表されました。(2009年5月18日)
[掲載誌] J. Clin. Invest., published online: May 18, 2009; | doi: 10.1172/JCI37413
[発表テーマ]
Glucocorticoid protects rodent hearts from ischemia/reperfusion injury by activating lipocalin-type prostaglandin D synthase-derived PGD2 biosynthesis
[発表概要]
ステロイドホルモンであるグルココルチコイドの心疾患(心筋梗塞や心筋炎)に対する治療効果はグルココルチコイドの持つ抗炎症・免疫抑制作用に基づくものであると考えられてきました。佐野研究者らは、齧歯類の心臓においてグルココルチコイドが心筋細胞におけるprostaglandin D2 (PGD2 ) 合成 を活性化させることによって虚血・再灌流障害を減弱させる効果を発揮することを見出しました。
ラット培養心筋細胞においてグルココルチコイドはglucocorticoid receptor (GR) を活性化させてPGD2 合成に関与するcytosolic phospholipase A2 (PLA2)、cyclooxygenase-2 (COX-2)、lipocalin-type prostaglandin D synthase (L-PGDS) の遺伝子発現をすべて誘導しました。ラット培養心筋細胞をグルココルチコイドで刺激したときの培養上清中や、成獣マウスにグルココルチコイドを腹腔内投与したときの心臓組織中でPGD2 濃度が増加していることを確認しました。グルココルチコイドはランゲンドルフ摘出灌流心や in vivo の心臓において虚血・再灌流障害による心筋梗塞サイズを減少させました。一方、L-PGDSノックアウトマウスではグルココルチコイドによる心筋保護作用は減弱していました。
本研究成果より、グルココルチコイドは投与方法を工夫すればヒトにおいても心筋梗塞サイズを縮小させ予後を改善する効果が期待されます。
- 深田正紀研究者
パルミトイル脂質修飾に関するさきがけ研究成果の総説がProgress in Lipid Researchに発表されました。(2009年2月20日)
[掲載誌] Progress in Lipid Research, published online: 20 February 2009; | doi: 10.1016/j.plipres.2009.02.001
[発表テーマ]
Dynamic protein palmitoylation in cellular signaling
[発表概要]
蛋白質はリン酸化、糖鎖修飾、ユビキチン化あるいは脂質修飾など、いわゆる「翻訳後修飾」によって遺伝情報を超えて動的な機能や制御機構が付加され、複雑な細胞機能を制御します。中でもパルミトイル化に代表されるS-アシル化修飾は多くの機能蛋白質にみられる脂質修飾であり、蛋白質を特定の膜ドメインに輸送し、その機能をダイナミックに制御します。パルミトイル化は他の脂質修飾とは異なり細胞内で可逆性を示し、外界刺激に反応して基質蛋白質の局在・機能を動的に制御することから古くから注目を浴びてきました。最近、酵母遺伝学からDHHCファミリー蛋白質がパルミトイル化酵素群として見出され、蛋白質パルミトイル化の全容解明が一気に加速しています。深田研究者はさきがけ研究を通じて、独自に同定したほ乳類のDHHCファミリー蛋白質群を手がかりに、パルミトイル化動態の測定/可視化技術の開発とパルミトイル化酵素ファミリーの制御機構の解析を進めてきました。本総説では自身の最近の成果をまじえ、パルミトイル化研究分野の最近の進展および今後の展開、残された疑問についてまとめました。
- 小松雅明研究者
小松雅明研究者と順天堂大学医学部の綿田裕孝准教授、藤谷与士夫准教授らのオートファジーに関する論文が、米国科学雑誌Cell Metabolismに掲載され、同誌の表紙に採択されました。(2008年10月8日)
[掲載誌] (1) Cell Metabolism, vol. 8, 325-332 (2008) (2) Cell Metabolism, vol. 8, 318-324 (2008)
[発表テーマ]
(1) Autophagy Is Important in Islet Homeostasis and Compensatory Increase of Beta Cell Mass in Response to High-Fat Diet
(2) Loss of Autophagy Diminishes Pancreatic β Cell Mass and Function with Resultant Hyperglycemia
[発表概要]
オートファジーは栄養飢餓により誘導される細胞内タンパク質分解経路です。栄養枯渇に対応し自己タンパク質を分解し、結果として生じるアミノ酸等を栄養源として利用し死を逃れる究極の生存戦略と考えられてきました。
今回の研究では、インスリンを産生する膵β(ベータ)細胞におけるオートファジーの生理的意義を検討しました。その結果、ベータ細胞においてオートファジーは栄養が十分な環境でも定常的に起こっていること、さらに高脂肪食を摂ることにより激しく誘導されることが判明しました。さらに、ベータ細胞特異的にオートファジーを欠損させたマウスを作製した結果、このマウスはベータ細胞の週齢依存性の変性と、ブドウ糖に応答してインスリンを分泌するというベータ細胞の最も重要な働きの低下をきたすことが明らかになりました。また、このマウスに高脂肪食を与えると、ベータ細胞のアポトーシス死の誘導がおこるのと同時に、代償性のベータ細胞増殖の不全をきたし、結果として糖尿病を発症しました。
これらのことは、ベータ細胞の恒常性維持におけるオートファジーの重要性を示すとともに、高脂肪食摂取や肥満によりインスリン抵抗性が増した場合に、これに対応するためにベータ細胞の数が代償的に増加するという、健康なベータ細胞ならば本来もっているしくみに、オートファジーが欠くべからざる役割を担っていることを示しています。食べ過ぎても、ベータ細胞の予備能が十分あれば、ヒトは簡単には糖尿病にはならないと考えられていますが、その一方で、すぐにインスリン分泌が枯渇してしまい、糖尿病になりやすいヒトがいるのも事実です。その違いを説明するメカニズムはこれまでよくわかっていませんでした。オートファジーがうまく働くことはこのようなベータ細胞の予備能や強さを規定している可能性があります。これらの新知見は今後、糖尿病の新しい予防法・治療法開発に役立つものと考えられます。
- 前田裕輔研究者
前田裕輔研究者と木下タロウ教授(当領域アドバイザー、CREST「糖鎖の生物機能の解明と利用技術」研究代表者)らは、ゴルジ装置の機能に関する研究成果を英国科学雑誌Nature Cell Biologyオンライン速報版に発表しました。(2008年9月14日)
[掲載誌] Nature Cell Biology, published online: 14 September 2008; | doi:10.1038/ncb1773
[発表テーマ]
GPHR is a novel anion channel critical for acidification and functions of the Golgi apparatus
[発表概要]
前田研究者らは、細胞内でタンパク質・脂質の輸送(物流)や修飾(加工)が正しく行われるためには、その物流加工センターであるゴルジ装置と呼ばれる細胞内小器官のpH(酸性度)が正しく維持調節されていることが必要であることを示し、同時に、新しく発見しGPHRと命名したタンパク質がイオンチャンネルとして機能し、この物流加工センターのpHを調節していることを解明しました。
細胞内で新しく作られたタンパク質と脂質は細胞表面や細胞外に運ばれる時に物流加工センターであるゴルジ装置で加工され正しい目的地に向かって仕分け搬送されます。この物流加工センターがうまく機能しないとタンパク質の機能が損なわれ輸送が滞り、糖鎖修飾不全症といった疾患がおこります。
本研究は、細胞の基本的な営みといえる物流加工機能がどのように調節されているかという仕組みを場の環境という観点から解明したものであり、今後、pHによる物流加工のより詳細な調節機構の解明や、その機能障害によって起こる一群の病気の発症予防に役立つものであると考えられます。
- 眞鍋一郎研究者
眞鍋一郎研究者と当領域アドバイザー永井良三教授らは、肥満・メタボリックシンドロームに関する研究成果を英国科学雑誌Nature Medicineオンライン速報版に発表しました。(2008年5月25日)
[掲載誌] Nature Medicine, published online: 25 May 2008; | doi:10.1038/nm1756
[発表テーマ]
SUMOylation of Krüppel-like transcription factor 5 acts as a molecular switch in transcriptional programs of lipid metabolism involving PPAR-δ
[発表概要]
眞鍋研究者らは、転写因子KLF5が骨格筋における脂肪酸燃焼・エネルギー代謝に重要であることを報告しました。
KLF5ヘテロ接合体ノックアウトマウスは高脂肪食負荷を与えても太りにくく、耐糖能障害も軽度であり、メタボリックシンドロームを呈しにくい形質を示します。KLF5ヘテロノックアウトマウスでは酸素消費量や体温が上昇しており、エネルギー消費が亢進していることがこのような代謝系の形質を示す上で重要と考えられました。この分子機構を解析し、翻訳後修飾の一種であるSUMO化を受けたKLF5が脂肪酸燃焼や脱共役に関わる遺伝子群の発現を抑制していること、一方で脱SUMO化されたKLF5はこれらの遺伝子の発現を正に調整することを明らかとしました。また、PPARδアゴニストによってKLF5は脱SUMO化されて転写が活性化されることも示しました。つまり、KLF5のSUMO化はエネルギー燃焼に関わる遺伝子の分子スイッチのように働くことを示しました。また、今回の研究はPPARδおよびそのアゴニストの作用にKLF5が必須であることも示しています。
本研究成果は、肥満を背景とするメタボリックシンドロームと動脈硬化の治療法の開発に結びつくものと期待されます。
- 村山明子研究者
細胞内エネルギー代謝に関する研究成果が米国科学雑誌Cellに発表されました。(2008年5月16日)
[掲載誌] Cell, vol. 133, 627-639 (2008)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20080517/index.html
[発表テーマ]
Epigenetic control of rDNA loci in response to intracellular energy status
[発表概要]
正常な細胞機能を維持するためには、「ATP産生系」と「ATP消費系」から成るATP代謝のバランスが保たれる必要があります。両者のバランスが崩れると、生活習慣病などの種々の疾患が発症したり、細胞エネルギーが枯渇し、細胞死が誘導されます。しかしながら、エネルギーバランスの制御機構の分子メカニズムについてはこれまで不明でした。
村山研究者は、ATPの消費系を制御する新たなタンパク質Nucleomethylin(NML)を見つけました。NMLは細胞内エネルギーセンサーとして知られるSIRT1と複合体を形成し、細胞内のエネルギー状態を感知します。そして、核小体のrDNAのクロマチン状態を制御することによって、rRNA転写を抑制し、もっともATP消費量の高いタンパク合成をコントロールし、細胞内のATP収支のバランスを制御することが明らかになりました。さらに、NMLが低グルコース状態(飢餓状態)での細胞内のATP収支のバランスを制御することによって、細胞死の回避に働いていることも明らかになりました。
本研究の成果を利用して、がん細胞の代謝バランスを壊すことによって、がん細胞を死滅させることができると考えられます。また、糖尿病などの疾患においても代謝異常を標的とした治療への応用が考えられ、新たな治療薬や治療法の開発が期待されます。
- 尾池雄一研究者
白血病発症抑制機構に関する研究成果が米国科学雑誌Genes and Development, Advance Online Articlesに発表されました。
[掲載誌]
Genes and Development, published online March 26, 2008, DOI: 10.1101/gad.1621808
[発表テーマ]
Fbxw7 acts as a critical fail-safe against premature loss of hematopoietic stem cells and development T-ALL
[発表概要]
ペニシリンの発見を代表として自然科学における発見には「セレンディピティ」を活かしたものが少なくありません。本研究成果も「肥満症」におけるエネルギー・脂質代謝制御と血管新生制御との連関の解明」という研究課題の中で、尾池雄一研究者が現在社会的問題になっているメタボリックシンドロームの中心病態である内臓肥満症における脂肪組織での骨髄由来の血液細胞、血管細胞の役割を明らかにするためにユビキチンリガーゼFbxw7の遺伝子を骨髄細胞特異的に欠損したマウスを作製し検討から始まっています。Fbxw7の遺伝子を骨髄細胞特異的に欠損したマウスは、対照コントロールマウスに比較し肥満になりにくいことを見出しましたが、解析の途中で多くのマウスが死亡していくことを見出し、その原因解明の解析の中からFbwx7が白血病発症を阻止する安全弁として機能するとともに、造血幹細胞を細胞周期の静止期にとどめ、過剰な細胞分裂に伴う造血幹細胞の枯渇を未然に防いでいることを見出しました。
本研究成果は、Fbwx7が造血幹細胞の枯渇と白血病発症阻止に重要な役割を果たしていることを示すと同時に、造血幹細胞に影響を与えることなく白血病幹細胞を特異的に障害する治療法を開発するための大きな手がかりになると考えられます。
- 新藤隆行研究者
血管再生に関する研究成果が米国科学雑誌The Journal of Clinical Investigationに掲載されました。(2007年12月21日)
[掲載誌] J. Clin. Invest., published on line December 20, 2007, doi:10.1172/JCI33022
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/info/info452/index.html
[発表テーマ]
The GPCR modulator protein RAMP2 is essential for angiogenesis and vascular integrity
[発表概要]
最近、心筋梗塞や脳梗塞をはじめとした虚血性疾患の新しい治療法として人工的に新しい血管を再生させる血管再生療法が試みられています。しかし、再生された血管は非常にもろく、すぐに退縮する、血管から水分が漏れ出して浮腫を起こすといった問題が起こります。このため、本来の血管に近い、構造的・機能的に安定した血管を作り出す手法の開発が待たれています。
本研究では、血管から分泌されるアドレノメデュリン(AM) という物質に注目し、RAMP2遺伝子を人工的に欠損させたノックアウトマウスを用いることにより、AMの受容体活性調節たんぱく質であるRAMP2が血管再生や血管構造を安定化させる上で必須の役割を持つことを突き止めました。
AM-RAMP2を標的とすることで、構造的・機能的に安定した血管を作り出す、新たな血管再生療法への応用が期待されます。さらに、AM-RAMP2の浮腫抑制作用を応用することにより、これまで良い治療法がなかった脳浮腫など難治性浮腫の治療法開発にもつながるものと期待されます。
- 小松雅明研究者
細胞内封入体に関する研究成果が米国科学雑誌Cellに掲載されました。(2007年12月14日)
[掲載誌] Cell, vol. 131, 1149-1163 (2007)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20071214/index.html
[発表テーマ]
Homeostatic levels of p62 control cytoplasmic inclusion body formation in autophagy-deficient mice
[発表概要]
細胞内封入体は、さまざまな病気において観察される特殊なたんぱく質構造体です。この構造体の構成成分には、一部の例外を除いてユビキチン化たんぱく質が含まれることから、これまで封入体形成は選択的たんぱく質分解経路を担っているユビキチン・プロテアソーム系の破綻による変性たんぱく質の凝集・蓄積に起因すると考えられてきました。一方、本研究グループはオートファジーのマウス遺伝学的研究から、オートファジーの不全がユビキチン陽性封入体の形成を伴った肝障害、神経変性疾患を引き起こすことを世界で最初に明らかにしました。しかし、どのようなメカニズムでユビキチン陽性封入体が形成されるのか、どのようにして疾病発症に至るのかは、今日まで全く不明でした。
今回の研究では、オートファジーによるユビキチン結合たんぱく質p62の選択的な代謝障害が、ユビキチン陽性・p62陽性の封入体形成を引き起こすことを発見しました。さらに、p62遺伝子を欠損したマウスでは、オートファジー欠損に伴う封入体形成がほぼ完全に抑制されることを見出しました。一方、ユビキチンとp62を含む封入体は、アルツハイマー病やパーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症などの神経変性疾患、アルコール性肝炎、脂肪肝、肝細胞癌などの肝疾患で集中的に見出されています。
今回の研究の成果は、封入体形成がオートファジーの減弱に起因しうること、そしてp62が封入体形成の責任分子であることを強く示唆するものであり、神経変性疾患や肝疾患の新しい予防法・治療法開発に役立つと考えられます。
- 豊島文子研究者
細胞の分裂方向に関する研究成果が米国科学雑誌Developmental Cellに掲載されました。(2007年12月4日)
[掲載誌] Developmental Cell, vol. 13, 796-811 (2007)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/info/info446/index.html
[発表テーマ]
Ptd(3,4,5)P3 Regulates Spindle Orientation in Adherent Cells
[発表概要]
通常の細胞を基質の上に接着させた状態で培養すると、細胞は基質面に対して平行な軸に沿って分裂を繰り返し、基質上に一層のシート構造を形成します。つまり、分裂後別れた2つの娘細胞は共に基質に接着することになります。細胞は、分裂装置である紡錘体を基質面に対して平行に配置することで分裂の方向を決めますが、この紡錘体軸の方向を決める仕組みは不明でした。
豊島研究者らは哺乳類培養細胞を用いた研究で、細胞膜の脂質成分であるホスファチジルイノシトール3,4,5-三リン酸〔PI(3,4,5)P3〕が、この仕組みの鍵となることを明らかにしました。PI(3,4,5)P3は分裂期の細胞の中央表層に局在し、モーターたんぱく質であるダイニン・ダイナクチン複合体を中央表層へ濃縮させます。その結果、ダイニンによる紡錘体の牽引力が細胞中央領域で平衡化するため、紡錘体が基質面に対して平行に配置されることが分かりました。本研究は、細胞分裂する方向の決定に細胞膜脂質が関わることを世界で初めて明らかにしたものです。
最近、分裂方向の異常が、腫瘍や多発性嚢胞腎病などの疾患に関わることが明らかとなってきています。本研究は、これらの疾患の発症のメカニズムの解明や早期診断法の開発につながる可能性を秘めています。
- 南野徹研究者
心血管老化に関する研究に対して第11回日本心血管内分泌代謝学会高峰譲吉研究奨励賞の授賞が決定しました。
[授与式] 2007年11月16日(東京コンファレンスセンター品川)
[受賞講演]
老化シグナルによって制御される心血管代謝ネットワークの解明
[発表概要]
南野研究者はこれまで老化研究を「細胞レベルの老化が個体老化の一部の形質、特に病的な形質を担う」という仮説に基づいて進め、テロメアシグナルやAngiotensin II/Ras/ERKシグナル、インスリン/Aktシグナルが細胞レベルの老化に重要であることを報告し、さらにこれらのシグナルが血管老化・動脈硬化だけではなく、心不全や糖尿病などの生活習慣病の病態生理に関与することを示唆してきました。このような老化形質は、老化シグナルによって制御される全身の心血管代謝ネットワークの変化によって引き起こされるのではないかと考え、現在さらに研究を進めています。
- 西野邦彦研究者
薬剤排出ポンプに関する研究に対して第9回日本抗生物質学術協議会奨励賞の授賞が決定しました。
[授賞式] 2007年11月8日(東京・虎ノ門パストラル)
[受賞講演]
細菌多剤耐性化と病原性発現における薬剤排出ポンプの役割に関する研究 -多剤耐性化と病原性を軽減させる新薬ターゲットの解析-
[発表概要]
日本抗生物質学術協議会奨励賞は、「抗生物質及び関連医薬品の領域における主として臨床に関連した優れた研究」に対して、日本抗生物質学術協議会より贈呈されるものです。西野邦彦研究者が、2007年度の受賞者(1名)として選出されました。細菌薬剤耐性化に関与している数多くの薬剤排出ポンプを世界にさきがけて発見したこと、さらに、薬剤排出ポンプによる細菌病原性調節の新機構を発見したことが高く評価されました。薬剤排出ポンプは、細菌薬剤耐性化と病原性を軽減させることのできる新薬のターゲットとして注目されています。
- 小松雅明研究者
オートファジーに関する研究成果が米国科学雑誌Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), online Early Edition に発表されました。
[掲載誌] PNAS, in press
[発表テーマ]
Essential role for autophagy protein Atg7 in the maintenance of axonal homeostasis and the prevention of axonal degeneration
[発表概要]
オートファジー(自食作用)は、大規模な膜形成を伴う細胞内分解システムです。オートファジーは栄養飢餓時に激しく誘導されることから、自己を食べて飢えを凌ぐ究極の生存戦略であると考えられてきました。一方、小松研究者はマウスの遺伝学的研究からオートファジーは低いレベルではありますが恒常的に起こっていること、この恒常的オートファジーの破綻が神経変性を引き起こすことを明らかにしてきました。しかしながら、オートファジーが止まってしまうとどのようにして神経細胞が脱落するのかは依然として不明のままでした。
今回、小松研究者は小脳プルキンエ細胞特異的にオートファジーが不能となるマウスを作製・解析し、このマウスはまずプルキンエ細胞軸索終末の膨大・変性が起こり、その後プルキンエ細胞脱落、最終的に運動障害が起こること見いだしました。膨大化した軸索内には変形したオルガネラが多数詰まっているのに対し、変異マウスのプルキンエ細胞の樹上突起や細胞体において異常はほとんど確認されませんでした。これらのことは、軸索内のオートファジー(局所的オートファジー)が、神経細胞の恒常性維持に特に重要な役割を担っていることを強く示唆します。このマウスで確認された神経細胞の軸索肥大は、複数の神経変性疾患において観察されることから、さらにオートファジーによる病態発症予防が注目されると思われます。
- 中戸川仁研究者
オートファジーに関する研究成果が米国科学雑誌Cellに掲載されました。(2007年7月13日)
[掲載誌] Cell, vol. 130, 165-178 (2007)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/announce/20070713/index.html
[発表テーマ]
Atg8, a ubiquitin-like protein required for autophagosome formation, mediates membrane tethering and hemifusion
[発表概要]
オートファジーとは、細胞が持つタンパク質や構造体を大規模に分解/リサイクルするための仕組みのことです。オートファジーは細胞内の新陳代謝を高めたり、飢餓時には分解産物からエネルギーを得るなど、様々な生命活動において重要な働きをしています。オートファジーには、分解すべきものを取り囲んで隔離する特殊なふくろ(オートファゴソーム)が必要ですが、このふくろを作り上げる仕組みはこれまで謎に包まれていました。
中戸川研究者らは、オートファゴソームの形成に必要な「Atg8」という小さなタンパク質に、ふくろの材料となりうる脂質膜同士をつなぎ合わせ、特殊な融合状態(ヘミフュージョン)にする機能があることを明らかにしました。さらに、このAtg8の機能は、オートファゴソームの膜を大きく伸ばす段階に重要であることを発見しました。本発見は全く新しい生体膜形成メカニズムを示しており、オートファジーのメカニズム全容解明のための突破口となると期待されます。また最近、オートファジーは細胞内の浄化メカニズムとして、パーキンソン病やハンチントン病といった神経変性疾患等の原因となる異常タンパク質の蓄積を防ぐことで、これらの発症に対して抑制的に働くことが明らかとなってきました。本研究は、これら病気の予防法や治療法の開発につながる可能性も秘めています。
- 青木淳賢研究者
2007 FASEB Summer Research Conferences, "Lysophospholipid Mediators in Health and Disease" (Tucson, Arizona, USA) で会議のCo-chairを務められると同時に、招待講演を行います。(2007年6月9 - 14日)
[発表テーマ] Patho-physiological role of autotaxin
[発表概要]
生理活性脂質リゾホスファチジン酸は多彩な機能を持つ生理活性脂質です。青木研究者は、生体内のリゾホスファチジン酸産生を担う酵素を世界で初めて同定しました。会議では、青木研究者が発見したリゾホスファチジン酸産生酵素オートタキシンに関して、(1) ノックアウトマウスの表現型解析 (2) ヒト病態時におけるオートタキシンの変動解析 (3) オートタキシンの血管形成における役割について発表します。
- 阿部郁朗研究者
植物ポリケタイド合成酵素に関する研究成果が米国科学雑誌Chemistry & Biologyに掲載されました。(2007年4月30日)
[掲載誌] Chemistry & Biology, vol. 14, 359-369 (2007)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/info/info395/index.html
[発表テーマ]
Structural insight into chain length control and product specificity of pentaketide chromone synthase from Aloe arborescens
[発表概要]
阿部研究者らは、天然物の分子多様性を生み出す酵素タンパク質の立体構造を解明しました。医薬資源として重要な天然物の基本骨格を構築する酵素の中には、活性部位の微妙な構造の違いで基質特異性や反応様式が大きく変化するものがあり、これが天然物の分子多様性を生み出す大きな要因となっています。本研究では、人為的な機能の制御と分子多様性創出の格好の材料ともいえる、高等植物由来新規III型ポリケタイド合成酵素の結晶構造と分子多様性創出のメカニズムの解明に成功しました。今回得られた結晶構造に基づき、酵素機能を人為的に制御、物質生産を行うことにより、医薬品開発などが可能になります。
- 稲田利文研究者
品質管理機構に関する研究成果が米国科学雑誌Genes & Developmentに掲載されました。(2007年3月1日)
[掲載誌] Genes & Development, vol. 21, 519-524 (2007)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/info/info381/index.html
[発表テーマ]
Translation of the poly(A) tail plays crucial roles in nonstop mRNA surveillance via translation repression and protein destabilization by proteasome in yeast
[発表概要]
ヒトの遺伝子病の原因となる変異の多くは、間違った位置でタンパク合成が終了する変異です。このような異常を持った遺伝子由来のタンパク質が通常の量で発現されると、細胞に様々な異常をもたらす可能性があります。しかしながら、このような異常な遺伝子産物の合成は、細胞の保持する厳密な品質管理機構によって抑制されています。今回、稲田らは、細胞の持つ品質管理機構において、真核生物のmRNAに普遍的に存在するポリ(A)鎖が重要な役割を果たしていることを、世界で初めて明らかにしました。
ヒトの遺伝子病のほとんどは、両方の染色体に変異を持つホモの場合のみ、重篤な症状を呈します。これは、片方の染色体のみに変異を持つ場合には、異常なタンパク質の合成が抑制されることで、正しいタンパク質の活性が阻害されない為と考えられます。今回の実験結果は、細胞における異常タンパク質の合成が抑制される新たな仕組みが明らかになっただけでなく、遺伝病発症のメカニズムやその治療法の開発につながる成果と考えられます。
- 西野邦彦研究者
10th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases (Fukuoka, Japan) で招待講演を行います。(2006年12月5日)
[発表テーマ]
Biological functions of bacterial multidrug efflux pumps
[発表概要]
本招待講演では、「多剤排出ポンプの生理的役割」について概説します。これまで多剤排出ポンプは構造的に関連性の無い多くの抗菌薬を排出することで、細菌多剤耐性化に関与していることが知られていました。一方、西野研究者は多剤排出ポンプが多剤耐性化のみならず、細菌病原性発現に関与していることを発見しました。この事実から、多剤排出ポンプは細菌病原性に関わる何らかの生理的基質を排出していると考えられます。研究を進める中で、AcrDとMdtABC多剤排出ポンプが鉄キレーターであるシデロフォアを排出していることを見出しました。この二つのポンプは通常、発現していませんが、鉄欠乏条件下で発現誘導が起こり、菌体外にある鉄を回収するためにシデロフォアを排出しているというポンプの新しい生理機能を明らかにしました。鉄は細菌病原性発現に必要な因子であることから、多剤排出ポンプによるシデロフォア排出が細菌病原性発現に関与していることが強く示唆されます。
- 深田正紀研究者
シナプス伝達に関する研究成果が米国科学雑誌Scienceに掲載されました。(2006年9月22日)
[掲載誌] Science, vol. 313, 1792-1795 (2006)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/info/info341/index.html
[発表テーマ]
Epilepsy-related ligand/receptor complex LGI1 and ADAM22 regulates synaptic transmission
[発表概要]
深田正紀研究者は、脳神経機能を制御する新しい蛋白質であるリガンドとその受容体を発見しました。
アルツハイマー病を初めとする認知症、精神神経疾患、およびてんかんなどの脳神経疾患発症の重要な原因は、神経細胞同士が接続する部位である神経シナプス間の情報伝達の破綻だと考えられています。各国の研究者によりシナプス伝達機構の分子メカニズムの解明が試みられていますが、全容が明らかになるには現在至っていません。
本研究では、ラットの脳からシナプスに存在する蛋白質複合体を生化学的手法により精製し、分泌蛋白質LGI1(リガンド)が、ADAM22という膜蛋白質を受容体として機能することを世界で初めて発見しました。さらに、このリガンド・受容体が脳内の主要な興奮性シナプス伝達を制御することを、電気生理学的手法により明らかにしました。
LGI1およびADAM22のいずれもがてんかんあるいはけいれんの発症と関連する遺伝子であることから、この発見は、記憶や学習の分子メカニズムを明らかにするだけでなく、てんかんなどシナプス伝達に異常がみられる難治性神経疾患の病態解明や治療薬の開発に役立つと考えられます。
- 田中元雅研究者
プリオン研究の成果が英国科学雑誌「ネイチャー」オンライン版に掲載されました。(2006年6月28日)
[プレス発表] http://www.jst.go.jp/pr/info/info304/index.html
[発表テーマ]
The Physical Basis of How Prion Conformations Determine Strain Phenotypes
[発表概要]
プリオン病は、ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病やウシの海綿状脳症(BSE、狂牛病)など、プリオン蛋白質がその病因に関与する神経変性疾患の一群ですが、これまで原因となるプリオン蛋白質が様々な症状を示す分子メカニズムは不明でした。今回解明した分子メカニズムは他の神経変性疾患の発症メカニズムの解明にもつながるものです。
プリオン蛋白質を原因とするプリオン病では様々な脳の症状が表れますが、その分子メカニズムはこれまで大きな謎でした。
本研究では、まず酵母プリオンの系を用いて、様々な細胞表現型を示すプリオン株が出現する分子メカニズムに関して、プリオン凝集体(アミロイド)の物理的特性に基づく理論モデルを構築しました。次に、そのモデルを実験的に検証し、アミロイドの分割速度がプリオン蛋白質に感染した細胞の表現型を決定する主要因子であることを世界で初めて明らかにしました。本研究は、アミロイドの分割速度を制御することがプリオン病の治療に重要であることを示したものです。
- 村上誠研究者
2006 FASEB Summer Research Conferences (Saxtons River, Vermont, USA) で招待講演を行います。(2006年7月11日)
[発表テーマ]
Diverse functions of sPLA2 isozymes: insights from transgenic mice
[発表概要]
リン脂質代謝酵素ホスホリパーゼA2 (PLA2) には20種類以上の分子種が存在し、細胞内に分布するcPLA2群とiPLA2群、および「細胞外に分泌される」sPLA2群に大別される。sPLA2群には組織細胞分布の異なる10種の分子種が知られるが、それぞれの分子種が生体内で如何なるリン脂質分子を標的とし、その結果として如何なる生体内機能を発揮するのかについては、古典的なsPLA2であるIB型の食餌中のリン脂質消化作用、IIA型の抗細菌作用以外は殆ど未解明である。村上研究者は、各sPLA2分子種の生体内基質を探索するために、培養細胞系において比較的強い細胞膜リン脂質分解作用を示す3種の分子種(III, V, X型)を全身性に過剰発現させたトランスジェニックマウスを作出した。興味深いことに、樹立したマウスは分子種に固有の表現型を示し、各酵素が生体内では異なるリン脂質分子を標的とすることが強く示唆された。本講演では、各sPLA2トランスジェニックマウスの表現型とそれに附随するリン脂質代謝の異常を紹介するとともに、同時に解析中である各酵素のノックアウトマウスについても発表する。
- 阿部郁朗研究者
植物科学研究プロジェクトシンポジウムで招待講演を行いました。(2005年12月2日)
[発表テーマ]
二次代謝酵素の機能開拓と新規生物活性物質の創製
[発表概要]
今後の天然物化学研究の展開について考えた場合、多様な化学構造と生物活性を有するポリケタイドなど、医薬品として重要な天然物の基本骨格生合成に関わる酵素をとりあげ、これを利用、改変することにより、超天然型新規有用物質の生産に結びつけていく試みは大変魅力的である。本シンポジウムでは、マロニルCoAとの縮合及び芳香環形成反応により、カルコンやスチルベンをはじめとして、カンナビノイド、クロモン、キサントン、フロログルシノールなど、一連の植物二次代謝産物の基本骨格を構築するIII型ポリケタイド合成酵素をとりあげ、最近の研究成果について概説した。
- 木下俊則研究者
植物科学研究プロジェクトシンポジウムで招待講演を行いました。(2005年12月2日)
[発表テーマ]
気孔開閉と細胞膜 H+-ATPaseの活性調節機構の解明
[発表概要]
植物の表皮に存在する気孔は、植物固有の代謝反応である光合成に必要な二酸化炭素の唯一の取り入れ口で、気孔を構成する一対の孔辺細胞は、光、特にシグナルとして作用する青色光に応答して気孔を開口させる。私たちは、青色光による気孔開口を植物の環境応答のモデル材料として、その分子機構について研究を進めてきた。その結果、青色光は孔辺細胞の細胞膜H+-ATPaseのリン酸化と14-3-3蛋白質の結合を引き起こすことにより細胞膜H+-ATPaseを活性化し、気孔開口の駆動力を形成していること。また、孔辺細胞に発現する青色光受容体フォトトロピンが青色光に応答してリン酸化されることを見出し、さらに、モデル植物シロイヌナズナのフォトトロピン変異体(phot1 phot2)を用いた解析により、phot1とphot2が重複して細胞膜H+-ATPaseの活性化・気孔開口の青色光受容体として機能していることを明らかにした。今後は、フォトトロピンに受容された青色光シグナルがどのようにして細胞膜H+-ATPaseの活性化を引き起こしているのか、生理・生化学・分子遺伝学的手法を駆使して解明を目指したい。
- 初谷紀幸研究者
植物科学研究プロジェクトシンポジウムで招待講演を行いました。(2005年12月2日)
[発表テーマ]
液胞プロセシング酵素が制御するプログラム細胞死機構の解明
[発表概要]
植物の代表的な生体防御機構として、感染細胞における過敏感細胞死があげられる。過敏感細胞死は感染を受けた細胞が急速に細胞死を起こすことにより、病原体を細胞内に封じ込め、隣接する健全細胞へ病原体が拡がるのを防ぐための植物独自の仕組みである。過敏感細胞死は偶発的な死ではなく、細胞自らの遺伝子発現によって自己を消去するシステム、すなわち植物自身に予めプログラムされた細胞死である。植物の様々なプログラム細胞死で見出されていた動物のcaspase様活性の正体が、caspaseホモログではなく、液胞に局在する液胞プロセシング酵素(vacuolar processing enzyme; VPE)であることがわかった。しかし、植物のプログラム細胞死に関しては、まだ不明な点が多く存在し、VPEを中心に解析を進め、植物の細胞死カスケードで機能する分子を一つずつ明らかにしていくことが今後の課題である。
|
 |
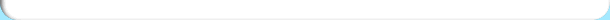 |
|
 |