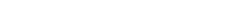01 大学が生み出した成果の特許化をサポート
就職活動をしていた時、同じ研究室の先輩が国の研究機関に就職していたのを知り、興味を抱いて調べていく中で出会ったのがJSTでした。そして、JSTが資金配分機関として大学などで行われているさまざまな研究や生まれた技術を世に出すための実用化支援等を行い、産学連携を促進することで、世の中を変えていくという役割を担っている点に魅力を感じて、入職を決めました。私が現在担当しているのが権利化支援です。大学ではさまざまな研究や技術開発が行われていますが、せっかく優れた技術を生み出しても、外国特許を取得するための費用や海外展開に向けたノウハウが十分ではない大学も少なくありません。そこで、実用化の可能性が高い研究について、資金面での支援を行うだけではなく、特許の取得やビジネス展開に向けたサポートも行っていくのが権利化支援です。私は大学からの申請対応や、有識者委員会で審査を行うための準備のほか、委員会での議論を踏まえたレポート作成などを日々行っています。また社会環境の変化や利用者のニーズに対応し、制度そのものを常に改善しながら業務を行います。申請される特許の中には将来性を感じさせる研究も非常に多く、強い興味を抱きながら仕事に携わっています。