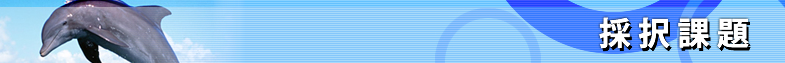
○2024年度 実装支援(返済型)
実装支援(返済型) 採択課題1件(2025年5月30日発表)
| 開発課題名 | 技術シーズを創出した大学等の研究者 | 開発実施企業 | 概要 |
| 長鎖DNA合成技術の開発 |
東京科学大学 生命理工学院 准教授 相澤 康則 助教 金子 真也 |
株式会社Logomix |
近年、COVID-19ワクチンの迅速な開発をはじめ、健康や医療への対応、食料やエネルギーの確保などさまざまな分野において、バイオテクノロジーに対する期待が急速に高まっている。また、各国の政策においても、カーボンニュートラルなど各種社会課題の解決と持続的な経済成長の両立を目指すバイオものづくり分野の推進が図られている。 このような背景の中、ゲノム編集技術を含むゲノム改変技術の進化と、ゲノム塩基配列やmRNA発現、たんぱく質発現などの情報を解析するバイオインフォマティクス技術などの高度化も進んでいる。しかしながら、これらの技術を生かして社会課題の解決に資する有用な細胞株を作製するためには、より多くの遺伝子の細胞内導入を必要とすることが多く、結果として、合成する配列のDNA長は大きくなり、長鎖DNAとなる傾向がある。また、ノーベル賞を受賞したCRISPR-Cas9など従来のゲノム編集技術は特定の塩基配列のみを選択的に改変することに優れているが、この技術単独でゲノム全体を大規模に改変し、より優れた細胞株を創出するといった用途には限界があり、コストや時間の面でも課題が残る。このような技術的制約を克服し、さらなるバイオテクノロジーの発展を実現するための大規模ゲノム改変技術が求められている。 株式会社Logomix(以下、「Logomix」という。)は、東京科学大学の相澤 康則 准教授が創出した複数の技術シーズ(ゲノムの設計、合成、大規模改変)からなる独自ゲノム構築技術「Geno-Writing™ Platform」をパートナー企業との協業において提供している。この大規模ゲノム改変技術により、さまざまな細胞種の機能が改変され、高機能化細胞の作製が期待される。Logomixは、大規模ゲノム改変する細胞株構築サービスの事業化を推進し、多くの産業が抱えるコスト削減や機能改善、新薬探索など多岐にわたる課題解決への貢献を目指している。 本事業支援により、Logomixは大規模ゲノム改変に必須となる長鎖DNA合成をハイスループットに行う技術の確立とその開発環境の構築を行う。このことにより、広いゲノム領域での改変を必要とする疾患モデル細胞の作製、物質生産や創薬に有用な細胞・微生物の作製をより効率的に行うことが可能となり、最適な細胞製品の早期実用化に資する取り組みを加速させる。 |
実装支援(返済型) 採択課題1件(2025年5月1日発表)
| 開発課題名 | 技術シーズを創出した大学等の研究者 | 開発実施企業 | 概要 |
| 診断評価・学習支援向け会話AIエージェントプラットフォームの開発 |
早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構 知覚情報システム研究所 主任研究員(研究院 准教授) 松山 洋一 |
株式会社エキュメノポリス | 近年、マルチモーダルAIの進展が著しく、音声、テキスト、映像、視線といった複数の情報源を統合し、診断や評価を行う技術が急速に発展している。従来、単一モーダルのデータ(音声のみやテキストのみ)を用いたAI技術が主流であったが、異なるモーダルを同時に処理できるマルチモーダルモデルが登場したことで、AIによる言語理解や対話の精度が飛躍的に向上している。 教育分野においても、マルチモーダルAIの導入が進んでおり、英語スピーキング試験や面接評価において、音声、表情、ジェスチャーを含む包括的な点数化が試みられている。しかし、現行の技術は依然として単一モーダルに依存する部分が大きく、発話内容の正確性や流暢性などを評価するテストは存在するものの、相互作用の質(やりとりの力)までは測定できていない。 株式会社エキュメノポリス(以下、EQU社)の会話AIエージェント技術は、AIエージェントとの会話を通じてユーザーの潜在能力や潜在ニーズを自然に引き出す対話戦略を有し、会話により得られたマルチモーダルなデータを統合的に解析することで、より精緻な会話能力の診断を可能としており、単なる発話の正確性だけではなく、会話における「やりとりの力」を測定することができる。また、診断結果に基づいて、個人ごとに最適化された対話シナリオやカリキュラムを生成し、効果的な学習を提供できる。 EQU社は現在、英会話能力の診断・自己学習アプリケーション「LANGX Speaking(ラングエックス・スピーキング)」を提供している。今後、同社は対話型診断・学習支援技術を基盤として、英会話以外の言語教育や対人スキルの評価、カウンセリングや会話を通じた高度な診断など多様な分野で会話AIエージェントの活用を目指している。 EQU社は本事業の支援により、会話AIエージェントを大規模、高品質、高信頼かつ低コストで開発、運用可能なプラットフォーム「EQU AI Platform」を構築する。このプラットフォームを用いて、AIエージェントとの会話を通じた能力診断とトレーニングを高度化するアプリケーションの開発を行うユーザーを支援し、多様なニーズにあった会話AIエージェントアプリケーションをエンドユーザーへ提供可能とする。これにより、英会話にとどまらない言語教育のDXを推進するとともに、実社会で求められるコミュニケーション能力の向上へ貢献する。 |
実装支援(返済型) 採択課題1件(2024年11月29日発表)
| 開発課題名 | 技術シーズを創出した大学等の研究者 | 開発実施企業 | 概要 |
| 普及型超音波霧化分離®装置の開発 |
徳島大学 生物資源産業学部 准教授 佐々木 千鶴 |
ナノミストテクノロジーズ株式会社 | さまざまな分野の製造プロセスにおいて、液体混合物(対象溶液)の分離や濃縮の工程がある。その分離や濃縮の処理の1つの方法として行われてきたのが蒸発・蒸留である。この方法は対象溶液を加熱・加圧し、沸点の差を利用して対象溶液を分離、濃縮する。しかしながら、この方法は加熱・加圧する必要があるため、多くの化石燃料が消費されCO2が排出されるとともに、消費エネルギー量の多さによって高コストになる。そのため、高い環境負荷と高いコストを解決する新たな処理方法が求められてきた。 このような課題を受け、ナノミストテクノロジーズ株式会社は世界に先駆けて独自の超音波霧化分離技術を開発した。この方法は、超音波振動子への通電により発生させた超音波が液体を霧化することで数マイクロメートル以下のミストを効率よく生成させ、このミストを粒子径に応じて送風で分離するもので、分離された微細なミストを冷却回収することができる。超音波霧化分離法では加熱・加圧が不要であるため、環境負荷とコストを抑えることが可能となる。 同社は、この技術を用いた霧化分離装置の販売を開始しているが、現状では顧客ニーズ・仕様に合わせた完全個別受注生産で高い生産コストでの製造を余儀なくされている。 一方で、徳島大学の佐々木 准教授は、同社と共に、超音波振動子の劣化を遠隔で検出可能な超音波霧化システムを開発した。これにより、霧化効率を一定に維持させるために重要な超音波振動子を最適な時期に交換でき、装置の安定な稼働を実現した。 そこで同社は、本制度の支援により、今後超音波霧化分離装置の量産化を視野に、徳島大学の技術を組み込んだ霧化分離装置に関する生産技術の開発を行う。具体的には、装置構成部品の金型などによる製造方法の確立、電子制御系の基板化・ⅠoT化を行い、それらを一体化させた超音波霧化分離装置を作製し、正常稼働を確認する。 本開発により、超音波霧化分離装置の工期短縮およびコストの削減につながり、部品の安定的な生産が可能となり、半導体等の製造プロセスにおける溶剤の再利用に向けた回収、産業廃液やメタン発酵消化液などからの有価物の回収、排水処理における減容と不要物除去など、幅広い業界・用途への導入が見込まれる。将来的には微細ミストへのCO2吸着によるCO2回収も期待され、これらを通じてカーボンニュートラル・脱炭素社会に貢献する。 |