インタビュー「開発しながら協議する、生体分子ロボット」
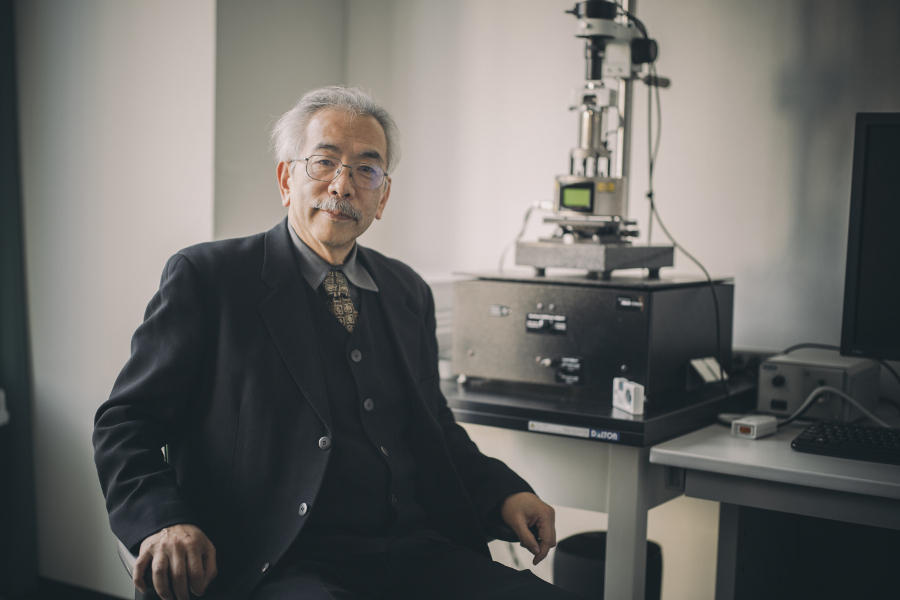
写真:小長谷 明彦(平成28年度 HITE採択プロジェクト企画調査「分子ロボット技術に対する法律・倫理・経済・教育からの接近法に関する調査」代表者。東京工業大学情報理工学院教授。専門は情報学と生命科学を融合する分子ロボティクス、知能情報学)
ナノ・バイオ技術とAI・ロボット技術とが融合しながら開発が進む、知能と感覚を備えた生体分子ロボットがいま、未知への扉を開けようとしています。この技術を社会に浸透させるため、倫理、法律、経済、教育の観点から適切な議論を進めるプラットフォームを立ち上げた小長谷明彦先生に話を伺いました。
生物の体内で動く分子ロボットに知能を与える
小長谷先生が専門とする分子ロボティクスとは、どんなものなのでしょうか。
ひと言でいえば、「感覚と知能を持ち合わせた分子サイズのロボット」です。人間の体内に入り込める分子ロボットに、感覚や知能を与え、自律的にはたらくような仕組みを施すことを目標としています。生物にはもともと生体分子を組み合わせて複雑なシステムを作る能力が備わっています。DNAなどの生体分子は自己集合し、相互作用することで自律的に動く細胞や生体をつくることができます。我々はこうした生物の構造やシステムを学び、分子レベルでの設計原理に基づいて、自己集合した分子ロボットの動きを制御していこうとしているのです。
2016年、私たちのグループはいくつかのアメーバ型の分子ロボットの開発に成功しました。東北大のグループが作成した分子ロボットは細胞よりやや小さい直径20マイクロメートルほどのリポソーム(脂質分子からつくられる二重膜)の中に、微小管と分子モーターとなるタンパク質キネシンを入れ、シグナルを運ぶDNA断片が動力伝達を制御するクラッチを備えています。シグナルを運ぶDNA断片がリポソーム内に存在するとクラッチがオンになり、微小管が動いて全体が変形しますが、存在しなくなるとクラッチがオフになって変形しません。DNA断片を材料とした分子ロボットは2000年台初頭から作られていましたがそれらはランダムにしか動きませんでした。我々のアメーバ型ロボットは動きを制御できる分子ロボットとしては世界で初めてのものです。
分子ロボティクス研究は、現在どのような段階を迎えているのでしょうか。
現在は、さまざまな用途に使える要素技術や方法論が揃った段階です。1990年代前半から、部分的に二重らせんを形成する多数のDNA断片を使って情報処理を行うDNAコンピュータの研究が進められてきました。この技術を使ってコンピュータの論理回路をDNA断片で実現することで、分子ロボットの「知能」として使えるようになったのです。実際に東京工業大学の研究グループは分子ロボットに1つのDNA断片をシグナルとして入力することで、30分間でそのDNA断片の数を1,000倍に増やすことに成功しています。また、1つのDNA断片から異なるDNA断片を時間差で増殖させることができ、コンピュータのクロック信号のような機能を持たせることができます。これからの課題は、同一条件で動作するクラッチや増殖回路のような分子ロボット部品の種類を増やすことです。
今後、がんの診断、抗体医薬、薬物送達システムなどに必要な分子を分子ロボットとして作ることができれば、医療や創薬現場に絶大なインパクトを与えることができるでしょう。いまこの分野を研究する学生たちは、人工免疫として働く分子ロボットや光合成が可能な分子ロボットなど、さまざまな想像を膨らませています。
分子ロボットの社会利用に向けて
かなり高度な技術を伴う分子ロボットですが、今後の社会での活用についてはどのように考えていますか。
研究者たちは分子ロボットの作製や可能性については日々考えているものの、これから開発する、あるいはすでに開発した技術が倫理的、社会的、経済的にどのようなインパクトを与えるのかといった視点はあまり持っていません。特に倫理問題で規制が入るのではないかという恐れから、専門外の人たちとの意見交換には警戒しがちです。
しかし私は、まだ開発段階のうちから倫理規定などを協議していく必要があると考えています。例えば、我々は比較的入手可能なウシの脳から取った微小管を実験に使うことがありますが、これを医薬品に転用しようとした場合、ウシの細胞はBSEの危険性があるとみなされ、せっかくの研究成果が除外されてしまう可能性があります。そうだとすれば、研究は材料選びからやり直しです。また日本のある研究では、がんの表面分子に作用して免疫をアップさせるという画期的な療法薬が開発されましたが、現状では非常に価格が高いため、医療費高騰につながるという意見もあります。こうした問題も、単に技術開発側からの発想だけでは社会にうまく普及しないという一例だと思います。
このように将来的に危ない落とし穴があると予想できるのであれば、研究開発の早い段階でハンドルを切る必要がある。いま、日本は分子ロボットの技術開発で世界のトップを走っています。それだけに、シーズありきではなく、それを使う人間を中心にして、例えば人体に入れたらどうなるか、開発コストや流通、廃棄はどうするかといった視点を最初から取り入れていきたいのです。

それがHITEに応募されたきっかけなのでしょうか。
そうですね。分子ロボティクス研究領域を立ち上げた直後、米国の National Foundation of Science から予算を獲得した「分子プログラミングプロジェクト」の会議に参加しました。そのとき、このプロジェクトには倫理の専門家が参画し、新しい技術が社会に出たときに何が起こるのかを予想し、それを研究にフィードバックさせる仕事をしていることに驚きました。帰国後、我々も倫理の専門家を探したのですがなかなか接点を見つけられませんでした。しかし2016年に日本人工知能学会のAI倫理のセッションで、HITEの立ち上げの情報を聞き、我々の研究と寄り添って走ってくれる倫理や社会的受容、科学コミュニケーションの専門家と出会えることを期待して応募しました。
今後、HITEではどんな活動を進めていきたいと考えられていますか。
HITEでは分子ロボティクスが抱える法律、倫理、経済の観点から課題をあぶりだし、さらにこれらの領域と分子ロボティクスを融合する教育システムを構築したいと考えています。
今、同じHITE内で「リアルタイム・テクノロジーアセスメントのための議題共創プラットフォームの試作」を目指す標葉隆馬さん(成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科専任講師)たちのグループと協働して、「NutShell」と呼ばれる議論のプラットフォームを構築しています。これは、さまざまな分野のステークホルダーが参加し、クローズドで議論を展開できる仕組みです。現在は、分子ロボットに関するヒヤリング、分子ロボット研究会の国際シンポジウムでも倫理や社会受容に関するセッションを持ってもらうなどの地固めを終えた段階で、今後はもっと、分子ロボットと科学コミュニケーションの両方のコミュニティをつなげられると思っています。
また、HITEのプロジェクト全体においても、コミュニティが生まれることで、知識を共有し、情報の発信を促すプラットフォームができていくといいですね。私自身もこれまで、コンピュータネットワークを介して知識を広く共有し、新しい知識を生む源泉とする「knowledge grid(知識の泉)」という考え方を提唱してきました。まさに今、そうした場が生まれることに期待しています。
※本記事は、「人と情報のエコシステム(HITE)」領域冊子vol.01に収録されています。
そのほかの記事、そのほかの号については以下をご確認ください。
HITE領域冊子