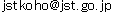概要
-
1.独立行政法人 物質・材料研究機構(理事長 潮田 資勝)光・電子材料ユニットのセラミックス化学グループ 鈴木 拓 主幹研究員、菱田 俊一 グループリーダー、極限計測ユニットスピン計測グループ 山内 泰 グループリーダーは、最表面(表面第一原子層)のスピン・元素組成・原子位置の複合分析に世界で初めて成功した。
-
2.電子は電荷に加え、スピンという磁石のような性質を持っている。電荷とスピンの両方を利用するデバイスはスピントロニクス注1)と呼ばれ、電荷だけを利用する現在のデバイス(エレクトロニクス)に比べて遥かに高い性能が期待されることから、現在、世界中でその開発が進められている。
-
3.スピントロニクス開発で鍵となるのは、最表面(表面第一原子層)の“スピン”と、元素組成や原子位置に関する“構造”の分析である。このうち、スピンに関しては、最先端の分析技術を用いてもその分析は極めて困難であり、この解決がスピントロニクス開発での課題となっていた。
-
4.これに対し、“スピン偏極4He+イオンビーム注2)”と呼ばれる新しいイオンビームは、最表面のスピンとだけ相互作用すると考えられており、この相互作用を利用することで最表面のスピンと構造の複合分析が実現すると期待されている。本研究者らは平成19年に、ビームの性能指標(ビーム偏極率)が世界最高であるスピン偏極4He+イオンビームの開発に成功していた。ただし、その複合分析の実現には、この相互作用(スピン軌道相互作用注3))の解明が課題となっていた。
-
5.本研究では、この新しいイオンビームを用いて偏極4He+イオンと様々な原子を衝突させる実験を系統的に行った。そして得られた実験データの詳細な解析から理論モデルを構築し、この相互作用の解明に成功した。
-
6.本研究によって、比較的小型の装置で、手軽に、最表面のスピンと構造の複合分析が可能になったことから、今後、スピントロニクス開発の飛躍的な進展が期待される。
-
7.本研究成果は、平成23年10月21日(米国東部時間)発行(予定)の米国物理学会の論文誌「Physical Review Letters」に掲載され、オンライン版にて10月18日(米国東部時間)に公開される。また本研究は、独立行政法人 科学技術振興機構 研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)における開発課題「スピン偏極イオン散乱分光」(チームリーダー:鈴木 拓)の一環として行われたものである。
<研究の背景>
現在、電子の持つ電荷のみならずスピンも利用する新しいデバイスとして、スピントロニクスの開発が広く進められている。スピントロニクスの基本動作原理としては、例えば巨大磁気抵抗効果やトンネル磁気抵抗効果がある。これらはいずれも、磁性層/非磁性層の界面で発現するので、スピントロニクスの開発では、表面・界面のスピン分析が不可欠である。とりわけ、最表面に相当する表面第一原子層のスピンの特性は、スピントロニクスに向けた材料開発の指標として、その分析が強く求められてきた。
しかし現在の最先端の分析技術でさえ、最表面のスピンを分析することは極めて困難であり、これがスピントロニクス開発の課題の1つとなってきた。
これに対し、“スピン偏極4He+イオンビーム”と呼ばれる新しいイオンビームは最表面とスピンの双方に極めて敏感というユニークな特徴を有していることから、これを利用することで最表面の「スピン」と原子位置などに関する「構造」の複合分析が実現する可能性がある。具体的には、He+イオンは最表面で電子を受け取りHe原子となる性質(イオン中性化)があるが、これが起こるのはHe+イオンのスピンと最表面の電子のスピンが逆向きの場合に限られる(図1(A))。一方、それらが同じ向きの場合には、イオン中性化は起きない(図1(B))。したがって、He原子とはならずに散乱されたHe+イオンを観測することで、最表面スピンの特性を構成元素ごとに分析することができる。
ただし、He+イオンが最表面の原子で散乱される際、He+イオンの持つスピンによって散乱されやすい方向が異なる性質(スピン軌道相互作用)があり(図2)、この効果は上記のイオン中性化にしばしば重畳する。その結果、散乱イオン強度のスピン依存性(スピン非対称性)がイオン中性化とスピン軌道相互作用のどちらによるものか判別ができず、データの解析に問題が生じてきた。つまり、スピン非対称性の起源としては、最表面スピンを反映するイオン中性化以外に、最表面スピンとは無関係のスピン軌道相互作用があるため、スピン非対称性から最表面スピンに関する情報を抽出するには、イオン中性化とスピン軌道相互作用からの寄与をそれぞれ明らかにする必要がある。しかし、スピン軌道相互作用は未解明であったため、最表面スピンの分析がしばしば困難となってきた。この問題を解決するために、He+イオン散乱注4)におけるスピン軌道相互作用の解明が求められていた。
<今回の研究成果>
本研究者らは、これまでスピン偏極4He+イオンビームの開発を進めてきた。7年前(平成16年)に世界で2番目にスピン偏極4He+イオンビームの発生に成功して以降も、継続して開発を進めており、平成19年にビームの性能指標(ビーム偏極率)が世界最高であるビームの開発に成功するなど、本技術では世界を先導する立場にある。本研究では、この新しいイオンビームを用いて偏極He+イオン-原子衝突実験注5)を行った。具体的には、標的元素で構成される基板を超高真空中に設置し、これに偏極He+イオンの運動エネルギー(入射エネルギー)を揃えて入射し、特定の方向に散乱されるHe+イオン強度のスピン依存度(スピン非対称率)を観測した。そして、このスピン非対称率と散乱角および入射エネルギーとの関係を、様々な標的元素について系統的に調べた。その上で、スピン軌道相互作用の理論モデルを構築し、この理論モデルから計算されるスピン非対称率と実験値との比較を詳細に解析することで、スピン軌道相互作用の解明に成功した。図3で示されるように、スピン非対称率の散乱角に対する依存性(図3(A))と入射イオン速度に対する依存性(図3(B))の実験結果は、今回構築した理論モデルによって良く説明されている。このように、今回の研究でスピン軌道相互作用の解明に成功した背景としては、これまでの開発で蓄積されたスピン偏極4He+イオンビームの発生に関する高い技術がある。そしてこの解明により、スピン非対称率におけるスピン軌道相互作用の寄与分が決定できるようになったため、スピン偏極4He+イオンビームによる最表面のスピン分析が可能になった。
実は、本研究以前では、イオン-原子衝突におけるスピン軌道相互作用の効果はよく分かっておらず、その効果が現れるのは、入射イオンが核スピンを持ち、なおかつ入射エネルギーが1MeV以上の高エネルギーの場合に限られると伝統的に考えられていた。したがって、入射エネルギーが1keV程度のイオン-原子衝突ではスピン軌道相互作用の効果は現れず、その挙動は基本的にはクーロン相互作用(電荷間に働く力)で説明できると考えられてきた。しかし本研究で初めて、入射イオンが電子スピンを持てば、低エネルギーでもスピン軌道相互作用の効果が現れることが明らかとなったことで、クーロン相互作用だけではイオン-原子衝突は説明できないことが明らかとなった。
イオン-原子衝突は、化学反応、放電、プラズマなどの物理・化学で現れる様々な素過程と深く関連するため、これまで広くその実験が行われてきた。そのイオン-原子衝突を規定するのは相互作用ポテンシャルである。今回の発見は、これまでクーロン相互作用のみで構成されていた相互作用ポテンシャルの見直しを求めるもので、物理・化学の広い分野に関係する重要な発見である。
今回、イオン-原子衝突におけるスピン軌道相互作用の効果が発見され、その役割が解明された意義としては、最表面スピン分析が可能になったこと以外に、本発見が偏極イオンビームの新しい発生方法につながる成果であることが挙げられる。すなわち、今回解明されたスピン軌道相互作用を利用することで、偏極イオンビームの発生が可能であることが明らかになった。
これまで、偏極イオンビームの発生には、高価なレーザーが必要であり、それを極めて高い精度で調整する必要であったことから、偏極イオンビームの実験は一般には高度な実験技術が必要であった。しかし、本研究の発見は、散乱イオンは一般にスピン軌道相互作用の結果、スピン偏極していることを示している。つまり、
これまでのような高価なレーザーを使用しなくても、単にスピン軌道相互作用を利用することで、従来の性能を凌駕する偏極イオンビームが発生可能であることが分かった。例えば、図3(A)では、鉛を標的とした散乱角70度の条件で、25%程度のスピン非対称率が観測されている。これはすなわち、1.57keVのエネルギーで無偏極のHe+ビームを鉛標的に衝突させた際、70度方向に散乱されたHe+ビームはスピン軌道相互作用の結果、スピン偏極しており、その偏極率は約25%であることを示している。また、図3(B)で観測されているように、入射イオン速度を上げれば、その偏極率も上がることが分かった。本実験は装置上の制約から、入射イオン速度は3×105m/s以下の条件で行われたが、この結果から、今後入射イオン速度をさらに上げることで、ビーム偏極率の向上が十分に期待できる。
<今後の展開と波及効果>
本研究によって、スピン偏極4He+イオンビームによる最表面スピン分析の実現に目処が立った。最表面のスピンと構造に関する複合分析が可能な手法は、今のところ、本研究で確立されたスピン偏極4He+イオンビームによる手法しかない。また本手法は、大きさが約1m程度と比較的小さいことから、手軽に実験を行うことができる。これらのことから、今後、本手法のスピントロニクス開発への展開が期待される。
<参考図>
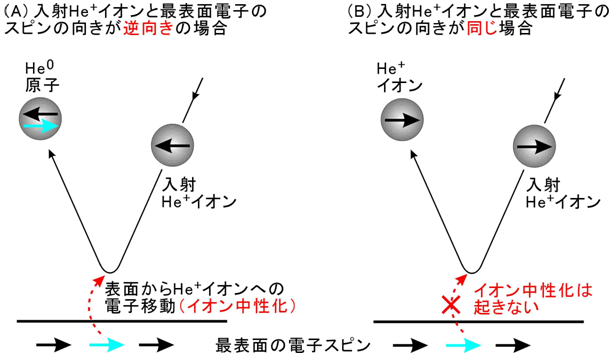
図1 スピン偏極4He+イオンビームによる最表面スピン分析の原理図
He+イオンは表面で散乱される際、最表面で電子を受け取りHe原子となる(イオン中性化)。ただし、中性化が起こるのは、He+イオンのスピンと最表面の電子のスピンの向きが反平行の場合に限られる(パウリの排他原理注6))。したがって、(A)ではHe+イオンは中性化されるのに対し、(B)では中性化が起きない。つまり中性化は最表面電子のスピンに依存するので、イオン中性化を経ずに散乱されたHe+イオンを観測することで、最表面の電子スピンを分析できる。
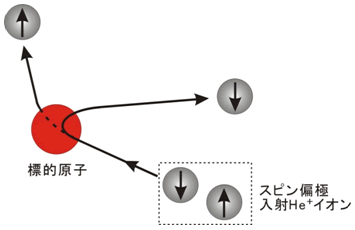
図2 He+イオン散乱におけるスピン軌道相互作用の概念図
He+イオンが最表面の原子で散乱される際、He+イオンの持つスピンによって散乱される方向が異なる性質がある。図では、上向きのスピンを持つHe+イオンが標的原子の前方に散乱される一方で、下向きのスピンを持つHe+イオンが標的原子の後方に散乱される場合を模式的に示している。
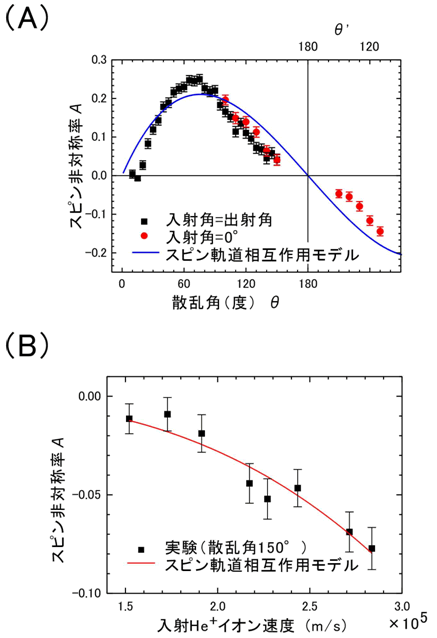
図3 スピン偏極4He+イオン-原子衝突実験における散乱イオンの分光計測注7)から得られたデータと、その解析結果
- (A)は入射イオンのエネルギーが1.57keV、標的原子が鉛の場合の散乱イオン強度のスピン依存度(スピン非対称率)と散乱角との関係。入射イオンビームから見て左に散乱されるとき(散乱角θ)と右に散乱されるとき(散乱角θ’)でスピン非対称率の符合が逆になっており、これは右方向と左方向の散乱では、散乱He+イオンのスピンの向きが逆向きであることを示している。
- (B)は散乱角が150度、標的原子が金の場合のスピン非対称率と入射イオン速度との関係を示している。速度が大きいほどスピン軌道相互作用が強くなりスピン非対称率が増加している。
(A)と(B)の実験データは、スピン軌道相互作用モデルに基づく理論解析の結果と良く一致している。
<用語解説>
- 注1) スピントロニクス
- 電子はスピンと呼ばれる微少な磁石のような性質を持っている。電子の電荷のみならず、このスピンも利用する新しいデバイスのことをスピントロニクスと総称する。
- 注2) スピン偏極4He+イオンビーム
- 4ヘリウム(4He+)イオンのスピンには、上向き、下向きと表現される2種類がある。4He+イオンの集合体であるビームでは、上向きと下向きのスピンを持つ4He+イオンは同数である。これに対して、何らかの人為的な方法で、上向き、または下向きスピンの方へ数分布を偏らせたビームのことをスピン偏極4He+イオンビームと呼ぶ。また、その偏りの程度はビーム偏極率と呼ばれ、ビームの性能指標となる。スピン偏極4He+イオンビームは、2007年に本研究者らによって世界最高のビーム偏極率25%が達成された新しいイオンビームである。
- 注3) スピン軌道相互作用
- 一般的には、スピンを持つ荷電粒子が電場の中で束縛軌道を回っているときに働く、スピン角運動量Sと軌道角運動量Lのベクトル間の角度に依存する相互作用S・L。散乱におけるスピン軌道相互作用は、入射種自身の標的核の周りの過渡的な回転運動の軌道角運動量と入射種のスピンとの相互作用のこと。
- 注4) イオン散乱
- 1keV程度の運動エネルギーを持つ、比較的軽いイオンを固体表面に入射して散乱させることで、固体表面の情報を得る手法。表面で散乱されるイオンをエネルギー分析すれば、表面に存在する元素種とその濃度、表面上の原子配列が決定できる。
- 注5) イオン-原子衝突実験
- 運動エネルギーの揃ったイオンを標的原子に入射して衝突させ、そこから発生する散乱イオンなどを検出することで、衝突における素過程を解明する目的で行われる実験。
- 注6) パウリの排他原理
- 電子は量子状態それぞれに1個しか存在することができない。量子状態では電子が持つ2種のスピン(上向き、下向き)も区別されるので、1つの軌道に2個の電子が入ることができるが2個の電子のスピンは互いに逆向きでなければならない。
- 注7) 散乱イオンの分光計測
- 上記のイオン-原子衝突実験において、特定の方向に出射した散乱イオンの強度をその運動エネルギーの関数として計測すること。
<本件に関するお問い合わせ先>
<研究内容に関すること>
鈴木 拓(スズキ タク)
物質・材料研究機構 光・電子材料ユニット セラミックス化学グループ
〒305-0044 茨城県つくば市並木1-1
Tel:029-859-2825 Fax:029-855-1196
E-mail: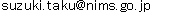
<JSTの事業に関すること>
安藤 利夫(アンドウ トシオ)
科学技術振興機構 イノベーション推進本部 産学基礎基盤推進部(先端計測分析技術・機器開発担当)
〒102-0075 東京都千代田区三番町5 三番町ビル
Tel:03-3512-3529 Fax:03-3222-2067
E-mail: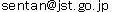
<報道担当>
物質・材料研究機構 企画部門広報室
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1
Tel:029-859-2026 Fax:029-859-2017
科学技術振興機構 広報ポータル部
〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地3
Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432
E-mail: